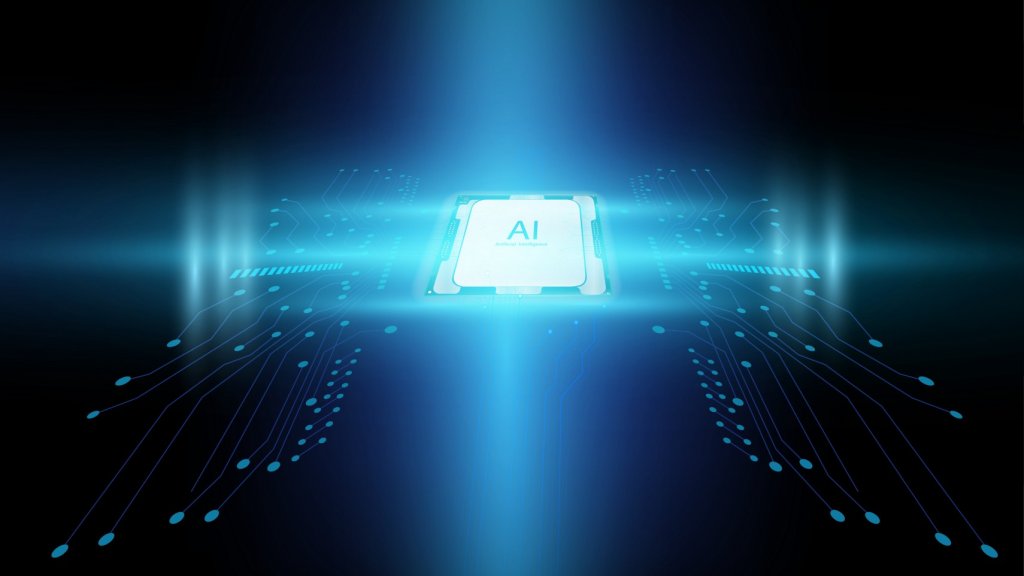BUSINESS
在庫管理の基礎知識と効果的な実践方法

目次
在庫管理は企業の収益性と競争力を左右する重要な経営活動です。この記事では、在庫管理の基本的な定義から最新のAI活用まで、体系的に解説します。
適切な在庫管理により、キャッシュフローの改善、保管コストの削減、機会損失の防止が実現できます。定量発注方式やABC分析などの具体的な手法、システム導入のポイント、効果測定方法まで、実践的な知識を網羅的に習得できます。
▼更に在庫管理について詳しく知るには?
【保存版】在庫管理とは?取り組むメリットや具体的な方法を分かりやすく解説
▼社内のデータをAI化するには?
ノーコードAIツールUMWELT紹介ページ(活用事例あり)
1. 在庫管理とは何か?基本的な定義と重要性

1.1 在庫管理の定義と目的
在庫管理とは、企業が保有する在庫(商品・原材料・仕掛品・完成品など)を最適な状態で維持・管理するための一連の活動を指します。日本工業規格(JIS)では、「必要な資材を、必要なときに、必要な量を、必要な場所へ供給できるように、各種品目の在庫を好ましい水準に維持するための諸活動」と定義されています。
在庫管理の主な目的は以下の通りです。
- 適正在庫の維持:過剰在庫や在庫切れを防ぎ、最適な在庫水準を保つこと
- コスト最適化:在庫保管コストや機会損失を最小限に抑えること
- 顧客満足度の向上:必要な商品を適切なタイミングで提供できるようにすること
- 経営効率の改善:資金繰りの改善や経営資源の有効活用を図ること
- リスク管理:欠品や廃棄による損失を防ぐこと
1.2 適切な在庫管理が企業に与える影響
適切な在庫管理は企業経営に多方面にわたって影響を与えます。その主な影響を以下の表にまとめました。
| 影響分野 | プラスの影響 | マイナスの影響(不適切な場合) |
|---|---|---|
| 財務面 | キャッシュフロー改善、資金効率向上 | 過剰在庫による資金固定化、機会損失 |
| 運営面 | 生産性向上、業務効率化 | 在庫切れによる生産停止、業務混乱 |
| 顧客対応 | 迅速な商品提供、顧客満足度向上 | 欠品による売上機会損失、信頼失墜 |
| 競争力 | コスト削減、市場対応力強化 | 競合他社への顧客流出、価格競争力低下 |
特に財務面では、在庫は貸借対照表上の資産として計上されますが、適切に管理されない場合は「不良資産」となり、企業の財務健全性を損なう要因となります。
一方、適切な在庫管理により在庫回転率が向上すれば、運転資本の効率的な活用が可能となり、ROA(総資産利益率)の改善にも寄与します。
1.3 在庫管理における主要な課題
在庫管理を実践する上で、多くの企業が直面する主要な課題は以下の通りです。
1. 需要予測の困難さ
- 市場の変動や季節要因の影響
- 新商品の需要予測の不確実性
- 外部要因(経済情勢、災害等)による急激な需要変化
2. 在庫情報の精度維持
- 実在庫と帳簿在庫の差異(棚卸差異)
- 入出庫データの入力ミスや遅延
- 複数拠点間での情報共有の課題
3. 多品目・多拠点管理の複雑さ
- SKU(Stock Keeping Unit)数の増加による管理負荷
- 拠点間の在庫移動や配置最適化
- 商品特性の違いに応じた管理方法の使い分け
4. システム・技術面の課題
- 既存システムの老朽化や機能不足
- 他システムとの連携不備
- リアルタイムでの在庫把握の困難さ
5. 人的リソースの制約
- 在庫管理担当者のスキル不足
- 属人化による業務の標準化困難
- 人手不足による管理精度の低下
これらの課題に対処するため、近年では在庫管理にAIやIoTなどの最新技術を活用する企業が増えています。需要予測の精度向上、リアルタイムでの在庫把握、自動発注システムの導入などにより、従来の課題解決が期待されています。
また、在庫管理は単なる倉庫管理ではなく、調達、生産、販売といったサプライチェーン全体を俯瞰した戦略的な取り組みが必要です。各部門間の連携強化と情報共有により、より効果的な在庫管理体制を構築することが重要となります。
2. 在庫管理の種類と手法

在庫管理には様々な種類と手法があります。企業の規模や業種、取り扱う商品の特性に応じて、最適な管理方法を選択することが重要です。ここでは主な在庫管理の種類と方法について詳しく解説します。
2.1 定量発注方式と定期発注方式
在庫管理の基本的な発注方式として、定量発注方式と定期発注方式があります。これらの方式は企業の在庫戦略の根幹を成す重要な選択肢です。
2.1.1 定量発注方式のメリット・デメリット
定量発注方式は、在庫が一定量を下回った時点で発注を行う方法です。この方式には以下のような特徴があります。
| 項目 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 在庫管理 | 在庫切れのリスクを最小限に抑えられる | 需要の急激な変化に対応しづらい |
| 運用面 | 発注のタイミングが明確で管理がしやすい | 在庫の監視を常に行う必要がある |
| 適用場面 | 需要の変動が少ない商品に適している | 季節性商品や流行商品には不向き |
2.1.2 定期発注方式の特徴と活用場面
定期発注方式は、一定の期間ごとに在庫を確認し、必要な量を発注する方法です。この方式の特徴と活用場面は以下の通りです。
特徴として、発注作業の効率化が図れる点が挙げられます。決められた期間ごとに発注を行うため、作業スケジュールが立てやすく、発注業務の標準化が可能です。また、需要の変動に柔軟に対応できるため、市場の変化に応じた在庫調整が行いやすいという利点があります。
活用場面としては、以下のような場合に適しています。
- 季節変動が大きい商品の管理
- 複数の商品を一括で発注する場合
- サプライヤーとの定期契約がある場合
- 発注コストを削減したい場合
2.2 ABC分析による在庫分類
ABC分析は、商品を重要度に応じてA・B・Cの3つのグループに分類し、効率的な在庫管理を行う手法です。
2.2.1 ABC分析の基本的な考え方
ABC分析は、イタリアの経済学者パレートが提唱した「パレートの法則」に基づいています。この法則では、全体の20%の要素が80%の結果を生み出すとされており、在庫管理においては少数の重要商品が売上の大部分を占めるという考え方です。
一般的な分類基準は以下の通りです。
| 分類 | 重要度 | 全体に占める割合 | 管理方針 |
|---|---|---|---|
| Aランク品 | 最重要管理品目 | 約70% | 厳密な在庫管理、頻繁な発注 |
| Bランク品 | 重要管理品目 | 約20% | 定期的な見直し、適度な在庫 |
| Cランク品 | 一般管理品目 | 約10% | 簡易管理、まとめ発注 |
2.2.2 効果的な分類方法と活用事例
ABC分析を効果的に実施するためには、以下のような分類方法を用いることが重要です。
まず、売上金額による分類が最も一般的です。各商品の年間売上金額を算出し、売上金額の多い順に並べて累積比率を計算します。累積比率が70%までをAランク、70%から90%までをBランク、90%以上をCランクとして分類します。
活用事例として、製造業での部品管理が挙げられます。自動車部品メーカーでは、エンジン関連部品をAランクに分類し、毎日の在庫確認と週2回の発注を実施しています。一方、消耗品類をCランクに分類し、月1回のまとめ発注で効率化を図っています。
小売業においても、季節商品や流行商品をAランクに分類し、リアルタイムでの在庫管理を行う一方で、定番商品をBランクに分類し、週単位での発注管理を実施している事例があります。
2.3 JIT(Just In Time)方式
JIT方式は、必要な物を、必要な時に、必要な量だけ生産・調達する方法です。トヨタ自動車が開発したこの方式は、在庫を極限まで削減することを目指しています。
JIT方式の主な特徴は以下の通りです。
- 在庫コストの大幅な削減
- 生産効率の向上
- 品質管理の徹底
- 無駄の排除と継続的改善
実施にあたっては、サプライヤーとの密接な連携が不可欠です。納期の短縮、品質の安定化、小ロット配送などの条件を満たすサプライヤーとの長期的なパートナーシップが成功の鍵となります。
ただし、以下のような課題もあります。
- サプライチェーンの混乱に弱い
- 導入には高度な生産管理システムが必要
- 従業員の意識改革が必要
- 初期投資が大きい
2.4 循環棚卸法の実践
循環棚卸法は、一定期間ごとに特定の商品群の棚卸を行う方法です。全ての在庫を一度に確認する全面棚卸と比べ、業務への影響を最小限に抑えながら在庫精度を向上させることができます。
循環棚卸法の実践手順は以下の通りです。
まず、在庫をABC分析などで分類し、棚卸頻度を決定します。Aランク品は月1回、Bランク品は四半期に1回、Cランク品は半年に1回といった具合に設定します。
次に、棚卸スケジュールを作成し、担当者を決定します。毎日少しずつ棚卸を行うことで、業務の平準化が図れます。
棚卸実施時には、実際の在庫数と帳簿在庫数を比較し、差異がある場合は原因を調査します。差異の原因としては、入出庫の記録漏れ、商品の紛失、システムの不具合などが考えられます。
循環棚卸法のメリットは以下の通りです。
- 日常業務への影響を最小限に抑えられる
- 頻繁な在庫確認により精度が向上する
- 問題の早期発見・対応が可能
- 棚卸作業の標準化ができる
- 従業員の在庫意識向上につながる
効果的な循環棚卸を実施するためには、正確な記録管理と継続的な改善が重要です。差異の原因分析を行い、再発防止策を講じることで、在庫管理の精度向上と業務効率化を同時に実現できます。
3. 在庫管理システムの導入と活用

在庫管理システムの導入は、現代の企業経営において競争力を維持するための重要な戦略となっています。適切なシステムを選択し、効果的に活用することで、在庫管理の精度向上と業務効率化を実現できます。
3.1 在庫管理システムのメリット
在庫管理システムの導入により、企業は以下のようなメリットを享受できます。
リアルタイムでの在庫状況把握により、常に最新の在庫データを確認できるため、過剰在庫や欠品の防止が可能になります。従来の手作業による在庫管理と比較して、データの正確性が格段に向上し、人為的なミスを大幅に削減できます。
作業効率の向上は、在庫管理システム導入の最も大きなメリットの一つです。バーコードやRFIDによる自動認識機能により、入出庫作業の時間を大幅に短縮できます。また、定期的な棚卸作業も効率化され、従業員の労働時間削減につながります。
コスト削減効果も見逃せません。適正在庫の維持により、保管コストの削減と機会損失の防止が可能になります。また、需要予測機能を活用することで、発注の最適化を図れます。
| メリット分類 | 具体的効果 | 期待される改善率 |
|---|---|---|
| 作業効率 | 入出庫作業の時間短縮 | 30~50%削減 |
| 在庫精度 | データの正確性向上 | 95%以上の精度 |
| コスト削減 | 保管コスト・機会損失の軽減 | 10~20%削減 |
3.2 システム導入時の注意点
在庫管理システムの導入を成功させるためには、いくつかの重要な注意点があります。
既存業務プロセスの見直しは必須です。システム導入前に現在の業務フローを詳細に分析し、システムの機能に合わせて最適化する必要があります。無理に既存の業務に合わせようとすると、システムの効果を十分に発揮できません。
従業員への教育とトレーニングも重要な要素です。新しいシステムの操作方法や運用ルールについて、段階的な教育プログラムを実施することで、スムーズな導入が可能になります。特に、システムに不慣れな従業員に対しては、十分なサポート体制を整える必要があります。
データの移行と品質管理にも十分な注意を払う必要があります。既存システムからの데이터 移行時には、データの整合性を保つための検証作業が不可欠です。また、システム稼働後も定期的なデータ品質チェックを実施し、正確性を維持することが重要です。
3.3 システム選定のポイント
在庫管理システムの選定は、企業の将来性を左右する重要な決定です。以下のポイントを総合的に評価して選択することが推奨されます。
3.3.1 機能性と使いやすさの評価
機能の充実度を評価する際は、現在の業務要件だけでなく、将来的な拡張性も考慮する必要があります。在庫管理の基本機能に加えて、需要予測、発注提案、レポート作成機能などの高度な機能が搭載されているかを確認しましょう。
操作性の良さは、システムの定着率に直結します。直感的なユーザーインターフェースを持ち、従業員が短期間で習得できるシステムを選ぶことが重要です。デモンストレーションや試用期間を活用して、実際の操作感を確認することをお勧めします。
3.3.2 他システムとの連携性
現代の企業では、複数のシステムが連携して業務を支えています。在庫管理システムも例外ではなく、ERP(企業資源計画)システム、ECサイト、会計システムなどとの連携機能は必須です。
特に、リアルタイムでのデータ連携が可能なシステムを選ぶことで、業務の効率化と意思決定の迅速化を実現できます。API(アプリケーション・プログラミング・インターフェース)による連携に対応しているシステムは、将来的な拡張性も高く評価されます。
3.4 クラウド型システムの活用
近年、クラウド型の在庫管理システムが注目を集めています。従来のオンプレミス型システムと比較して、多くの利点があります。
初期投資の抑制が可能な点は、特に中小企業にとって魅力的です。サーバーの購入や設置、保守にかかる費用を大幅に削減できます。また、月額料金制により、予算の平準化も図れます。
アクセシビリティの向上も重要な利点です。インターネット接続があれば、どこからでもシステムにアクセスできるため、テレワークや複数拠点での業務にも対応できます。スマートフォンやタブレットからの操作も可能な システムが多く、現場作業の効率化に貢献します。
自動アップデート機能により、常に最新の機能を利用できる点も見逃せません。セキュリティパッチの適用や新機能の追加が自動で行われるため、システム管理の負担を軽減できます。
3.5 AIを活用した在庫管理の最新動向
AI技術の発展により、在庫管理の領域でも革新的な変化が起きています。従来の経験や勘に頼った在庫管理から、データドリブンな意思決定への転換が進んでいます。
需要予測の精度向上は、AI活用の最も顕著な成果です。過去の販売データ、季節変動、市場トレンド、天気予報などの外部要因を総合的に分析し、より正確な需要予測を実現できます。機械学習アルゴリズムの活用により、従来の統計手法では捉えきれない複雑なパターンも発見できるようになりました。
自動発注システムの導入により、人的作業の削減と発注精度の向上が期待できます。AIが需要予測と在庫状況を考慮して最適な発注タイミングと数量を決定し、自動的に発注を実行します。これにより、人為的なミスを防ぎ、機会損失を最小限に抑えることができます。
異常検知機能も注目される機能の一つです。通常とは異なる在庫の動きを自動的に検知し、アラートを発信します。盗難や記録ミス、システム障害などを早期に発見できるため、損失の拡大を防ぐことができます。
| AI活用分野 | 主な機能 | 期待される効果 |
|---|---|---|
| 需要予測 | 多要因分析による精密予測 | 予測精度20~30%向上 |
| 自動発注 | 最適発注タイミング・数量決定 | 発注業務時間50%削減 |
| 異常検知 | 通常パターンからの逸脱検知 | 損失リスク80%削減 |
AI技術の進歩により、在庫管理システムはますます高度化していますが、導入時には自社の規模や業種に適したシステムを選択することが重要です。段階的な導入アプローチを採用し、従業員の習熟度に合わせてシステムを活用していくことで、最大限の効果を得ることができるでしょう。
4. 在庫管理の実践と効果測定
在庫管理の理論や手法を理解した後は、実際の業務において効果的に実践し、その成果を適切に測定することが重要です。本章では、在庫管理を実践するための具体的な手順と、その効果を測定・改善するためのアプローチについて詳しく解説します。
4.1 在庫管理の実践手順
効果的な在庫管理を実現するためには、体系的なアプローチが必要です。以下に、在庫管理の実践における基本的な手順を示します。
4.1.1 現状分析と目標設定
在庫管理の実践は、現在の在庫状況を正確に把握することから始まります。まず、全ての在庫品目について以下の項目を調査します。
| 調査項目 | 内容 | 目的 |
|---|---|---|
| 在庫数量 | 品目別の実際の在庫数量 | 過剰在庫や不足在庫の特定 |
| 在庫金額 | 品目別の在庫評価額 | 資金効率の現状把握 |
| 回転率 | 各品目の在庫回転率 | 売れ筋・死筋商品の識別 |
| 保管状況 | 倉庫の保管効率や品質状態 | 保管コストと品質管理の評価 |
この現状分析に基づいて、適正在庫水準、目標回転率、コスト削減目標などの具体的な目標を設定します。目標設定においては、SMART原則(具体的、測定可能、達成可能、関連性、期限)に従って、明確で実現可能な目標を定めることが重要です。
4.1.2 在庫分類と管理方針の決定
ABC分析を用いて商品を重要度別に分類し、それぞれに適した管理方針を決定します。Aランク品目については厳格な管理を行い、Cランク品目については簡素化された管理手法を適用することで、効率的な在庫管理を実現します。
また、商品の特性に応じて、定量発注方式と定期発注方式のどちらを適用するかを決定します。需要が安定している商品には定量発注方式を、需要変動が大きい商品には定期発注方式を適用することが一般的です。
4.1.3 発注システムの構築
適切な発注点と発注量を設定し、発注業務を標準化します。発注点の設定においては、リードタイム、需要変動、サービスレベルを考慮した計算式を用いて、科学的に決定します。
発注量については、経済的発注量(EOQ)の概念を基に、発注コストと保管コストのバランスを考慮して最適化します。また、季節変動や特別なイベントに対応できる柔軟性も確保します。
4.2 KPI設定と効果測定
在庫管理の効果を客観的に評価するためには、適切なKPI(重要業績評価指標)を設定し、定期的に測定・分析することが不可欠です。
4.2.1 主要なKPI指標
在庫管理において重要なKPI指標は以下の通りです。
| KPI | 計算方法 | 目安 | 改善方向 |
|---|---|---|---|
| 在庫回転率 | 売上原価 ÷ 平均在庫金額 | 業界により異なる | 向上 |
| 在庫回転日数 | 365日 ÷ 在庫回転率 | 業界により異なる | 短縮 |
| 欠品率 | 欠品回数 ÷ 総発注回数 | 1-3%程度 | 低減 |
| 在庫精度 | 正確な在庫品目数 ÷ 全品目数 | 95%以上 | 向上 |
| 充足率 | 即座に出荷できた注文数 ÷ 全注文数 | 95%以上 | 向上 |
4.2.2 効果測定の実施方法
KPIの測定は、定期的かつ継続的に実施することが重要です。月次での基本的な測定に加えて、週次や日次での監視も必要に応じて実施します。特に、季節変動が大きい商品や新商品については、より頻繁な測定が必要です。
測定結果は、グラフやダッシュボードを用いて可視化し、関係者が容易に理解できる形で共有します。また、目標値との比較や前年同期との比較を行い、改善の成果を明確にします。
4.2.3 ベンチマーキングと業界比較
自社のKPIを業界平均や競合他社と比較することで、改善の余地を客観的に評価できます。業界団体が公表するデータや、専門調査機関のレポートを活用して、ベンチマーキングを実施します。
4.3 継続的な改善プロセス
在庫管理は一度設定すれば終わりではなく、継続的な改善が必要です。PDCAサイクルを活用した改善プロセスを構築し、定期的に見直しを実施します。
4.3.1 改善サイクルの構築
継続的改善のためのサイクルは以下の通りです。
- Plan(計画):KPIの分析結果に基づいて改善計画を策定
- Do(実行):改善施策を実際に実施
- Check(評価):実施結果をKPIで評価
- Act(改善):評価結果に基づいて標準化や次の改善計画を策定
このサイクルを月次または四半期ごとに実施し、継続的な改善を図ります。また、大きな市場変化や事業環境の変化があった場合は、臨時での見直しも実施します。
4.3.2 改善施策の例
具体的な改善施策としては、以下のようなものがあります。
- 需要予測精度の向上:過去データの詳細分析や外部要因の考慮
- 発注点の最適化:リードタイムの短縮や安全在庫の見直し
- 在庫配置の最適化:拠点間の在庫移動や集約化
- 廃棄・返品対策:期限管理の強化や販売促進策の実施
- システム改善:自動発注機能の導入や在庫管理システムの高度化
4.3.3 組織的な取り組み
在庫管理の改善は個人の努力だけでは限界があります。組織全体での取り組みが必要であり、以下のような体制を構築します。
- 在庫管理委員会の設置:定期的な会議で改善方針を決定
- 部門間の連携強化:営業、生産、物流部門間の情報共有
- 教育・研修の実施:在庫管理に関する知識とスキルの向上
- インセンティブ制度:在庫管理改善に対する評価と報酬
また、外部専門家の活用や、他社の成功事例の研究も有効です。業界セミナーや研究会への参加を通じて、最新の手法や技術の情報を収集し、自社の改善に活用します。
在庫管理の実践と効果測定は、企業の競争力向上に直結する重要な活動です。適切な手順に従って実践し、継続的な改善を行うことで、コスト削減と顧客満足度の向上を同時に実現できます。
5. まとめ
在庫管理は企業の収益性と競争力を左右する重要な経営活動です。適切な在庫管理により、保管コストの削減、資金繰りの改善、顧客満足度の向上を実現できます。
定量発注方式やABC分析などの手法を組み合わせ、自社の業種や規模に応じた最適な管理システムを構築することが成功の鍵となります。継続的な改善とKPIによる効果測定を通じて、持続可能な在庫管理体制を確立しましょう。
product関連するプロダクト
-

UMWELTウムベルト
UMWELTは、プログラミング不要でかんたんに分析や自動化ができるノーコードツールです。需要予測から生産計画を最適化、人材の最適配置まで課題を解決できます。日々変化する生産数や生産計画、人員配置を自動立案し属人化や作業時間を大幅に削減します。
MWELT

TRYETING
公式
TRYETING公式です。
お知らせやIR情報などを発信します。