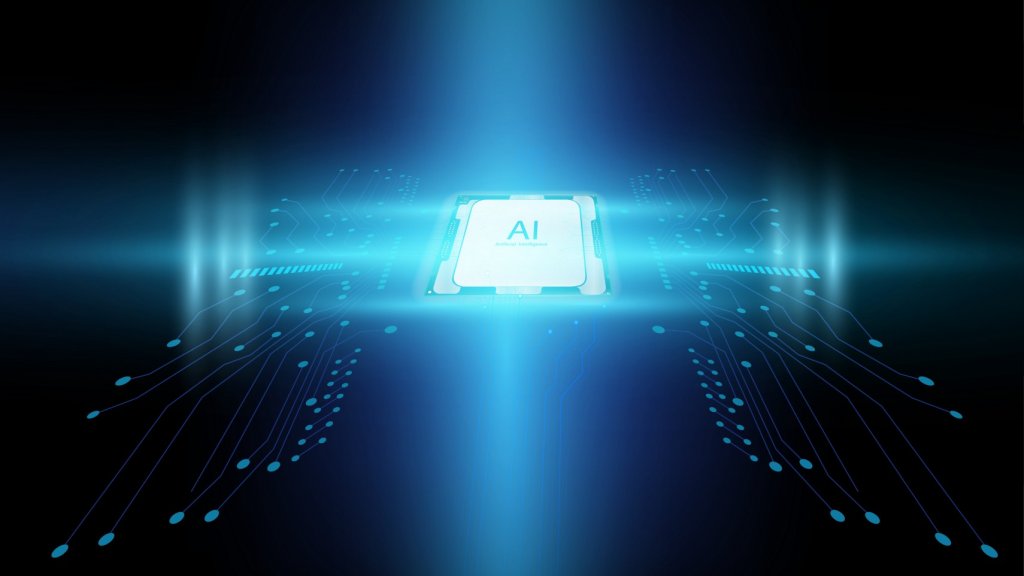BUSINESS
DX成功事例集|業界・目的別に学ぶ推進のポイントと注意点

目次
DX推進のヒントとなる成功事例をお探しではありませんか。
本記事では、国内外のDX事例を業界・目的別に厳選してご紹介します。DX成功の鍵は、単なるツール導入ではなく明確なビジョンに基づく全社的な変革にあります。
各社の取り組みから成功のポイントと注意点を学び、自社のDX推進を加速させるための具体的なヒントを得ましょう。
▼更にDXについて詳しく知るには?
DXとはどのようなもの?導入が求められる理由やメリット・デメリットを解説
▼社内のデータをAI化するには?
ノーコードAIツールUMWELT紹介ページ(活用事例あり)
1. そもそもDX(デジタルトランスフォーメーション)とは?

DX(デジタルトランスフォーメーション)は、今やあらゆる業界・企業で注目される重要な経営課題です。しかし、言葉だけが先行し、その本質的な意味や目的が正しく理解されていないケースも少なくありません。
DXの成功事例を学ぶ前に、まずはその基本的な概念をしっかりと押さえておきましょう。ここでは、DXの正しい定義、混同されがちな関連用語との違い、そしてなぜ今DXがこれほどまでに重要視されているのかを解説します。
1.1 DXの正しい定義と目的
DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、単にデジタルツールを導入することではありません。その本質は「デジタル技術を活用して、ビジネスモデルや組織、企業文化そのものを変革し、競争上の優位性を確立すること」にあります。
この概念は、2004年にスウェーデンのウメオ大学のエリック・ストルターマン教授によって提唱された「ITの浸透が、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させる」という考え方が起源です。ビジネスの文脈においては、経済産業省が「DX推進ガイドライン」で以下のように定義しています。
つまり、DXの最終的な目的は、デジタル化を通じて業務効率を上げることだけではなく、市場の変化に迅速に対応できる体制を築き、新たな価値を創出して企業としての競争力を根本から高めることにあります。既存のビジネスのあり方を見直し、変革を成し遂げてこそ、真のDX推進といえるのです。
1.2 デジタイゼーション・デジタライゼーションとの違い
DXを理解する上で、よく似た言葉である「デジタイゼーション」と「デジタライゼーション」との違いを把握することが不可欠です。これらはDXに至るまでの段階的なプロセスとして捉えることができます。
デジタイゼーションが部分的なアナログ情報のデジタル化、デジタライゼーションが特定の業務プロセスのデジタル化を指すのに対し、DXはそれらの技術を活用して組織全体やビジネスモデルの変革を目指す、より広範で戦略的な取り組みです。それぞれの違いを以下の表にまとめました。
| 段階 | 用語 | 定義 | 具体例 |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | デジタイゼーション(Digitization) | アナログ・物理的な情報をデジタル形式に変換すること。(手段のデジタル化) | ・紙の書類をスキャンしてPDF化する ・会議をオンライン会議ツールに切り替える |
| 第2段階 | デジタライゼーション(Digitalization) | 特定の業務プロセス全体をデジタル技術で最適化・自動化すること。(プロセスのデジタル化) | ・経費精算をクラウドシステムで完結させる ・RPAを導入して定型業務を自動化する |
| 第3段階 | DX(Digital Transformation) | デジタル技術を前提として、ビジネスモデルや組織、企業文化を変革し、新たな価値を創出すること。 | ・収集した顧客データをAIで分析し、新たなサービスを開発する ・製造工程のデータを活用し、生産体制を抜本的に見直す |
このように、デジタイゼーションからデジタライゼーション、そしてDXへと、取り組みの範囲と目的が段階的に進化していくと理解すると良いでしょう。
1.3 なぜ今、DX推進が重要視されるのか
現代において、なぜこれほどまでにDXの推進が叫ばれているのでしょうか。その背景には、私たちのビジネス環境を取り巻く、後戻りのできない大きな変化があります。
1.3.1 ビジネスモデルの変化への対応
デジタル技術の進化は、既存の業界構造を破壊し、全く新しいビジネスモデルを生み出しています。例えば、配車アプリの登場により、人々はタクシー会社に電話せずともスマートフォン一つで車を呼べるようになりました。これにより、従来のタクシー業界はビジネスモデルの変革を迫られています。同様に、動画配信サービスが映像コンテンツの視聴方法を、ECサイトが商品の購買方法を根底から変えました。こうした破壊的な変化に対応し、自らも新たなビジネスモデルを創出していくために、DXは不可欠な戦略となっています。
1.3.2 消費者行動の変化
スマートフォンの普及は、消費者の情報収集や購買における行動を劇的に変化させました。多くの消費者は、商品やサービスを購入する前に、オンラインでレビューや口コミを比較検討します。SNSを通じて情報を収集し、気に入ったものはその場でECサイトから購入することも珍しくありません。
企業は、こうしたデジタル上の顧客接点から得られる膨大なデータを活用し、一人ひとりのニーズに合わせた体験を提供しなければ、顧客から選ばれなくなってしまいます。消費者行動の変化に対応し、顧客との関係性を強化するためにもDXは極めて重要です。
1.3.3 多様な働き方の実現
少子高齢化による労働人口の減少や、新型コロナウイルス感染症の拡大を契機としたテレワークの普及など、企業は多様な働き方への対応を迫られています。
時間や場所にとらわれない柔軟な働き方を実現するためには、業務プロセスの見直しが不可欠です。紙の書類や対面での承認プロセスをデジタル化し、クラウド上で情報共有や共同作業ができる環境を整備しなければなりません。
DXは、こうした働き方改革を推進し、生産性を向上させると同時に、優秀な人材を確保するための鍵ともなっています。
2. 【業界別】国内企業のDX推進事例
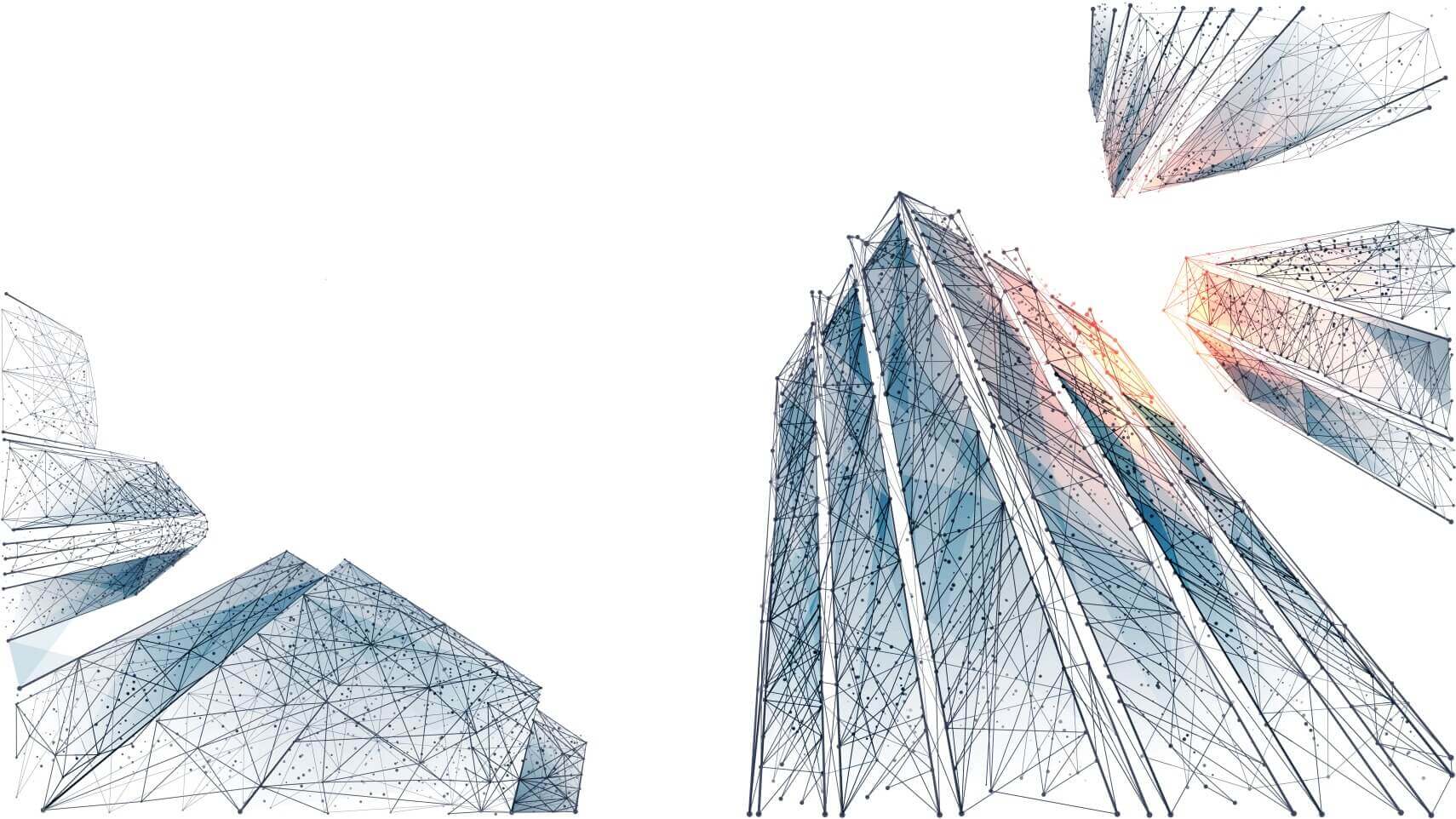
国内でも、業界を問わず多くの企業がDX(デジタルトランスフォーメーション)に積極的に取り組んでいます。それぞれの企業が抱える課題に対し、デジタル技術をいかに活用して新たな価値を創造しているのか、具体的な事例を見ていきましょう。自社の状況と照らし合わせながら、DX推進のヒントを探してみてください。
2.1 製造・製薬業界のDX事例
製造業や製薬業界では、AIやIoTといった先端技術を活用し、研究開発の高速化、生産プロセスの最適化、品質管理の高度化などを実現しています。熟練技術者の知見をデジタル化し、データに基づいた意思決定を行うことで、国際競争力の強化を図っています。
2.1.1 中外製薬株式会社:AI創薬支援によるイノベーション
中外製薬株式会社は、「CHUGAI DIGITAL VISION 2030」を掲げ、デジタル技術を活用してビジネスを革新し、社会を変えるヘルスケアソリューションを提供するトップイノベーターを目指しています。特に創薬分野でのAI活用が注目されています。
機械学習を用いて最適な抗体医薬品の配列を設計するAI創薬支援技術や、深層学習(ディープラーニング)による画像解析を用いた薬理試験の効率化など、これまで膨大な時間とコストを要していた研究開発プロセスを大幅に短縮・効率化。これにより、革新的な新薬をより早く患者に届けることを目指しています。また、RPAによる定型業務の自動化も全社的に進め、生産性向上にもつなげています。
| DXの目的 | 主な取り組み | 期待される成果 |
|---|---|---|
| 革新的な医薬品の創出と提供スピードの向上 | AIによる抗体医薬品の設計・最適化、深層学習による画像解析 | 研究開発期間の短縮、成功確率の向上、創薬コストの削減 |
2.2 不動産業界のDX事例
不動産業界では、従来の「モノ(物件)」を売る・貸すビジネスから、データやデジタル技術を活用して「コト(体験価値)」を提供するビジネスへの転換が進んでいます。顧客接点のデジタル化や、保有する不動産データの活用による新サービスの開発が活発です。
2.2.1 三井不動産株式会社:データプラットフォーム構築による新たな価値創出
三井不動産株式会社は、テクノロジーを活用して不動産業そのものをイノベーションすることを目指しています。その象徴的な取り組みが、街づくりにおけるデータ活用プラットフォームの構築です。
柏の葉スマートシティや日本橋、豊洲などのエリアで、商業施設やオフィス、住宅などから得られる多様なデータを統合・分析。人々の行動やニーズを深く理解し、より快適で質の高いサービス提供や、新たなビジネスの創出に活かしています。例えば、オフィスワーカー向けのアプリを通じて混雑状況を通知したり、パーソナライズされた情報を提供したりすることで、街全体の付加価値向上を図っています。
| DXの目的 | 主な取り組み | 期待される成果 |
|---|---|---|
| 「街づくり」における新たな体験価値の提供 | 各施設から得られるデータを統合・分析するデータ活用プラットフォームの構築 | 顧客満足度の向上、エリアの活性化、データに基づいた街づくり計画の策定 |
2.3 情報通信・IT業界のDX事例
情報通信・IT業界は、自らがDXを牽引する立場として、5GやAI、IoTなどの最先端技術を社会インフラとして提供しています。他産業のDXを支援するソリューションを開発するだけでなく、自社のビジネスモデルも変革し、社会課題の解決に貢献しています。
2.3.1 ソフトバンク株式会社:5G・AIを活用した次世代社会基盤の創造
ソフトバンク株式会社は、「Beyond Carrier」戦略のもと、通信事業者の枠を超え、情報革命で人々の幸せに貢献することを目指しています。5GやAIなどの先端技術を駆使し、多様な産業のDXを支援するとともに、社会課題解決に取り組んでいます。
例えば、ヘルスケア分野では、健康医療相談やオンライン診療などを提供するアプリ「HELPO(へルポ)」を展開。個人の健康増進をサポートするだけでなく、医療アクセスの向上や医療費の適正化といった社会課題にもアプローチしています。また、自動運転やMaaS(Mobility as a Service)分野への投資・開発も積極的に行い、次世代の社会基盤創造をリードしています。
| DXの目的 | 主な取り組み | 期待される成果 |
|---|---|---|
| 先端技術による社会課題の解決と次世代社会基盤の創造 | ヘルスケアアプリ「HELPO」の提供、MaaSプラットフォームの開発 | 新たな収益源の確立、企業の社会的価値の向上、産業のデジタル化支援 |
2.4 【参考】中小企業のDX推進事例
DXは大企業だけのものではありません。限られた経営資源の中で、創意工夫を凝らしてDXを成功させている中小企業も数多く存在します。ここでは特定の企業名ではなく、共通する取り組みのパターンを2つ紹介します。
2.4.1 業務効率化を実現した事例
多くの中小企業が最初に取り組むのが、バックオフィス業務の効率化です。これまで手作業で行っていた請求書発行、経費精算、勤怠管理といった定型業務に、安価なクラウドサービスやRPA(Robotic Process Automation)ツールを導入。これにより、従業員は単純作業から解放され、より創造的な業務に時間を割けるようになります。また、ペーパーレス化が進むことで、コスト削減や情報共有の迅速化にもつながります。
| DXの目的 | 主な取り組み | 期待される成果 |
|---|---|---|
| 生産性の向上と従業員の負担軽減 | クラウド会計・勤怠管理システムの導入、RPAによる定型業務の自動化 | バックオフィス業務の工数削減、ヒューマンエラーの防止、コア業務への集中 |
2.4.2 新たな顧客体験を創出した事例
顧客接点のデジタル化によって、新たなビジネスチャンスを掴んだ事例も増えています。例えば、地域の飲食店がモバイルオーダーシステムを導入し、テイクアウト需要に対応したり、小規模な小売店がECサイトを開設して全国に販路を拡大したりするケースです。MA(マーケティングオートメーション)ツールを活用して顧客情報を一元管理し、個々の顧客に合わせた情報発信を行うことで、顧客満足度とリピート率の向上に成功している例もあります。
| DXの目的 | 主な取り組み | 期待される成果 |
|---|---|---|
| 販路拡大と顧客エンゲージメントの強化 | ECサイトの構築、モバイルオーダーシステムの導入、MAツールの活用 | 新規顧客の獲得、顧客単価の向上、顧客ロイヤルティの醸成 |
3. 【目的別】海外企業のDX推進事例

DX(デジタルトランスフォーメーション)は、国内だけでなく海外でも多くの企業が先進的な取り組みを進めています。特に海外の成功事例は、既存のビジネスの常識を覆すような大胆な発想やテクノロジー活用が多く、日本の企業がDXを推進する上での大きなヒントとなります。ここでは、日本でも馴染み深い海外企業のDX事例を「ビジネスモデル変革」「顧客体験の向上」「迅速な事業展開」という3つの目的別に分類して5つご紹介します。
3.1 ビジネスモデル変革を実現した事例
DXの最も大きなインパクトの一つが、既存の事業領域のルールを根本から変える「ビジネスモデル変革」です。デジタル技術を活用することで、従来は不可能だった価値提供の仕組みを構築し、新たな市場を創造した企業の事例を見ていきましょう。
3.1.1 Netflix:DVDレンタルから動画配信サービスへの転換
今や世界最大の動画配信サービスとなったNetflixは、ビジネスモデル変革によって大成功を収めた代表格です。創業当初はオンラインでのDVD郵送レンタルサービスが主力事業でしたが、インターネット回線の高速化という時代の変化を捉え、定額制の動画ストリーミング配信サービスへと大胆なピボット(事業転換)を行いました。
この変革を支えたのが、膨大なアクセスにも耐えうるスケーラブルなクラウド基盤(AWS)の全面採用と、視聴データに基づく高度なレコメンデーションエンジンです。ユーザーの視聴履歴や評価をAIが分析し、一人ひとりの好みに合った作品を提案することで、ユーザーをサービスに惹きつけました。さらに、そのデータを活用してヒットが期待できるオリジナルコンテンツを制作するという、データドリブンなコンテンツ戦略も確立。映像業界の構造そのものを変革しました。
| 課題 | DXによる施策 | 成果 |
|---|---|---|
| DVDレンタル事業の物理的制約(店舗、在庫、返却の手間)と市場の頭打ち。 | ・事業の主軸をDVDレンタルから動画ストリーミング配信へ転換。 ・クラウド技術を活用し、グローバルで安定した配信インフラを構築。 ・AIによる視聴データの分析と、パーソナライズされたレコメンデーション機能の実装。 ・データに基づいたオリジナルコンテンツの制作。 |
映像業界のビジネスモデルを「都度レンタル」から「サブスクリプション」へと変革し、世界的なメディア企業へと成長。 |
3.1.2 Uber:配車サービスのプラットフォーム化
Uberは、デジタル技術を用いて「移動」の概念を変革した企業です。従来のタクシー業界が抱えていた「電話で呼ぶ手間」「料金の不透明さ」「需給のミスマッチ」といった課題を、スマートフォンアプリを基盤としたプラットフォームを構築することで解決しました。
アプリ上で乗客と、空き時間を利用したい一般ドライバーを直接マッチング。GPSによるリアルタイムな車両追跡、事前に行き先を指定することによる料金の明確化、アプリ内でのキャッシュレス決済、ドライバーと乗客の相互評価システムなど、テクノロジーによって安全で利便性の高い乗車体験を実現しました。これにより、自動車を「所有」するものから「利用」するものへと消費者の意識を変え、「MaaS(Mobility as a Service)」という巨大な市場を創出しました。
| 課題 | DXによる施策 | 成果 |
|---|---|---|
| 既存のタクシー業界が抱える配車手配の煩雑さ、料金の不透明性、非効率なマッチング。 | ・ドライバーと乗客を直接つなぐプラットフォーム型ビジネスモデルの構築。 ・スマートフォンアプリによる配車、リアルタイム追跡、キャッシュレス決済の実現。 ・需要に応じて価格が変動するダイナミックプライシングの導入。 |
配車サービスの仕組みを根底から変革し、MaaS市場を創出。ギグエコノミーを代表する企業へと成長。 |
3.2 顧客体験の向上を実現した事例
デジタル技術は、顧客一人ひとりとの接点を深化させ、これまでにない優れた顧客体験(CX)を提供する強力な武器となります。データを活用して顧客を深く理解し、パーソナライズされたサービスで高い満足度とロイヤルティを獲得した事例を紹介します。
3.2.1 Amazon.com:データ活用によるパーソナライズ
世界最大のECサイトであるAmazon.comは、顧客体験向上のためのデータ活用における先駆者です。同社は、顧客の購買履歴や閲覧履歴、検索キーワードといった膨大なデータを収集・分析し、それをサービスのあらゆる側面に活かしています。
特に有名なのが、協調フィルタリングなどのアルゴリズムを用いたレコメンデーション機能です。「この商品を買った人はこんな商品も買っています」といった形で、顧客の潜在的なニーズを掘り起こし、新たな購買へとつなげます。
このパーソナライズされた体験は、顧客が広大な商品群の中から欲しいものを簡単に見つける手助けとなり、顧客満足度を飛躍的に向上させました。ワンクリック注文や迅速な配送サービスと組み合わせることで、オンラインショッピングにおけるストレスを徹底的に排除し、圧倒的な競争優位性を築いています。
| 課題 | DXによる施策 | 成果 |
|---|---|---|
| 膨大な商品の中から、顧客が求める商品を効率的に見つけ、購入につなげること。 | ・購買履歴や閲覧履歴などの膨大な顧客データを収集・分析。 ・AIを活用した高度なレコメンデーションエンジンの開発と実装。 ・ワンクリック注文やPrime会員向けサービスなど、購入プロセスの利便性を追求。 |
データ活用によるパーソナライズで優れた顧客体験を実現し、高い顧客ロイヤルティと圧倒的な市場シェアを獲得。 |
3.2.2 Shake Shack:モバイルオーダーによるシームレスな体験提供
ニューヨーク発の人気ハンバーガーチェーンShake Shackは、飲食業界におけるDXで顧客体験を向上させた好例です。同社は人気店ゆえの長い行列が顧客満足度を低下させる一因となっていました。
この課題を解決するために、事前注文・決済が可能なモバイルアプリと、店舗に設置したセルフオーダー用のキオスク端末を導入。これにより、顧客は行列に並ぶことなくスムーズに商品を受け取れるようになり、待ち時間のストレスが大幅に軽減されました。店舗側も注文受付業務の負荷が減り、スタッフは調理や質の高い接客に集中できるため、生産性の向上にもつながりました。アプリやキオスクから得られる注文データは、メニュー開発やマーケティング施策にも活用され、さらなる顧客体験の向上と売上増加の好循環を生み出しています。
| 課題 | DXによる施策 | 成果 |
|---|---|---|
| 人気店ゆえの長い行列による顧客体験の低下と、店舗オペレーションの負荷増大。 | ・モバイルオーダー&ペイアプリの開発・導入。 ・店舗へのセルフオーダー用キオスク端末の設置。 ・注文データの収集・分析によるメニュー開発やプロモーションへの活用。 |
行列を緩和し、シームレスな注文体験を提供することで顧客満足度を向上。店舗の生産性向上と顧客単価の上昇にも貢献。 |
3.3 迅速な事業展開を実現した事例
変化の激しい現代の市場において、新たなビジネスチャンスを逃さず、迅速に事業を立ち上げる能力は企業の競争力を大きく左右します。ここでは、既存の資産とアジャイルな開発体制を活かして、新規事業へのスピーディな参入を成功させた事例を見ていきます。
3.3.1 Careem:アジャイル開発によるフードデリバリー参入
ドバイを拠点とする配車サービス企業Careemは、DXによって迅速な事業多角化を実現しました。同社は配車サービスで培ったプラットフォーム技術と広大なドライバーネットワークという資産を活かし、フードデリバリー市場への参入を計画しました。
その際、完璧なサービスを時間をかけて開発するのではなく、必要最小限の機能を持つ製品を短期間で開発し、素早く市場に投入。フードデリバリーサービス「Careem Now」をスピーディに立ち上げました。市場投入後は、ユーザーからのフィードバックを迅速にサービス改善に反映させるサイクルを回すことで、サービスの質を継続的に向上させ、中東の主要なフードデリバリーサービスの一つとしての地位を確立しました。
| 課題 | DXによる施策 | 成果 |
|---|---|---|
| 配車サービスで築いた資産を活用し、新たな収益源となる事業を迅速に立ち上げること。 | ・アジャイル開発手法を採用し、MVPを短期間で開発・市場投入。 ・既存の配車サービス基盤を応用し、フードデリバリー事業を迅速にローンチ。 ・市場のフィードバックを素早く取り入れ、継続的にサービスを改善。 |
競争の激しいフードデリバリー市場への迅速な参入に成功し、事業の多角化を実現。スーパーアプリ化への足がかりを築いた。 |
4. 事例から学ぶDX推進を成功させる5つの鍵
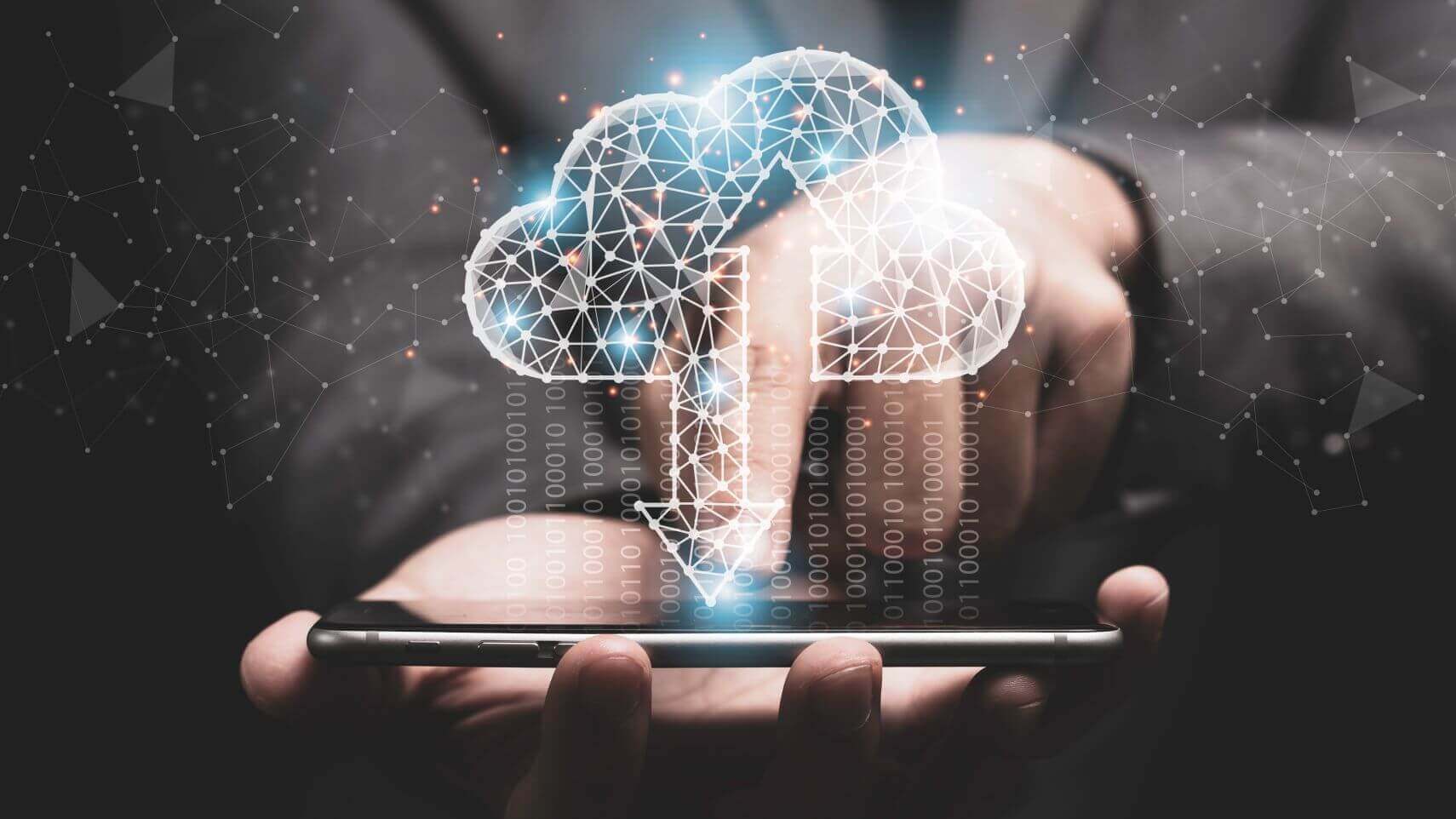
国内外の先進的なDX事例を見てきましたが、成功した企業にはいくつかの共通点が見られます。単に最新のデジタルツールを導入するだけでは、DXは成功しません。ここでは、数々の事例から見えてくるDX推進を成功に導くための「5つの鍵」を具体的に解説します。自社の状況と照らし合わせながら、取り組みのヒントを見つけてください。
4.1 明確なビジョンと経営層のコミットメント
DX推進における最も重要な鍵は、経営層が明確なビジョンを掲げ、強力なリーダーシップを発揮することです。DXは単なる業務改善ではなく、企業全体のビジネスモデルや組織文化を変革する大きな取り組みです。そのため、向かうべき方向を示す羅針盤となるビジョンがなければ、部門ごとの取り組みがバラバラになったり、目先の課題解決に終始してしまったりします。
例えば、事例で紹介した中外製薬は「社会を変えるヘルスケアソリューションを提供するトップイノベーターになる」という明確なビジョンを掲げ、全社一丸となって創薬プロセスの革新に取り組んでいます。
経営層は、このビジョンを社内外に繰り返し発信し、実現に向けた投資や権限移譲を惜しまない「コミットメント(約束)」を示す必要があります。これにより、現場の従業員は安心して新しい挑戦に取り組むことができ、変革の推進力が高まります。
4.2 全社的な協力体制と企業文化の変革
DXは、IT部門や特定の事業部だけで完結するものではありません。成功のためには、部門の壁を越えた全社的な協力体制が不可欠です。従来の縦割り組織では、部門間でデータが分断された「サイロ化」が起こりがちで、これがDXの大きな障壁となります。部門横断型のプロジェクトチームを組成し、各部門の知見やデータを共有しながら進めることが成功の秘訣です。
さらに、協力体制を円滑に機能させるためには、挑戦を奨励し、失敗から学ぶことを許容する「企業文化の変革」が求められます。DXの道のりには試行錯誤がつきものです。一度の失敗で担当者を責めるような文化では、従業員は萎縮してしまい、新たなアイデアは生まれません。変化に柔軟に対応できる、風通しの良い組織文化を醸成することが、持続的なイノベーションの土台となります。
| DX推進を阻む従来の文化 | DX推進を促進する新たな文化 |
|---|---|
| 前例踏襲主義・減点主義 | 挑戦を奨励し、失敗から学ぶ文化 |
| 部門間の縦割り・情報のサイロ化 | 部門横断での連携・オープンな情報共有 |
| 勘と経験に頼る意思決定 | データに基づいた客観的な意思決定 |
| 完璧を目指すウォーターフォール型開発 | 迅速な試行錯誤を繰り返すアジャイルな開発 |
4.3 データに基づいた意思決定サイクールの確立
DXの本質は、デジタル技術を活用してデータを収集・分析し、そこから得られる洞察をビジネスの意思決定に活かすことにあります。Amazonが顧客の購買データから最適な商品を推薦(レコメンド)するように、データに基づいた客観的な判断は、顧客体験の向上や業務効率化に直結します。これを実現するためには、データに基づいた仮説検証のサイクルを組織に定着させることが重要です。
代表的なフレームワークが「PDCAサイクル(Plan-Do-Check-Action)」です。まず、データに基づいて目標(KGI/KPI)と計画(Plan)を立て、それを実行(Do)します。次に、得られた結果をデータで評価(Check)し、改善策を考えて次の行動(Action)につなげます。このサイクルを高速で回すことで、施策の精度が継続的に向上し、データドリブンな組織文化が根付いていきます。
4.4 DXを推進するデジタル人材の確保・育成
DXを具体的に推進するには、デジタル技術やデータ分析に関する専門知識を持つ人材が不可欠です。しかし、こうした人材は多くの企業で不足しており、獲得競争が激化しています。そのため、外部からの採用活動と並行して、社内人材の育成(リスキリング)に計画的に取り組む必要があります。
4.4.1 DXを担う主要な人材像
DXプロジェクトでは、多様なスキルを持つ人材が連携して役割を担います。以下に代表的な職種とその役割を示します。
| 職種 | 主な役割 |
|---|---|
| プロダクトマネージャー | DXプロジェクト全体の責任者。ビジネス要件を定義し、開発チームを率いてビジョンの実現を目指す。 |
| データサイエンティスト | 事業課題を解決するために、AIや統計学を用いて膨大なデータを分析し、ビジネスに有益な知見を導き出す。 |
| UI/UXデザイナー | 顧客視点でサービスやシステムの使いやすさを設計し、最適な顧客体験(CX)を創出する。 |
| DXエンジニア | クラウド、AI、IoTなどのデジタル技術を駆使して、必要なシステムやアプリケーションを設計・開発する。 |
4.4.2 人材育成(リスキリング)の重要性
全社員を専門家にする必要はありませんが、全社でDXを推進するためには、社員一人ひとりがデジタル技術の基礎知識を持つことが望まれます。自社のビジネスを深く理解している既存社員が、研修やe-ラーニングを通じて新たなデジタルスキルを習得する「リスキリング」は、DX人材不足を解消する上で非常に有効な手段です。
4.5 外部パートナーやツールの積極的な活用
DXに必要な専門知識や開発リソースをすべて自社でまかなうことは、特に中小企業にとっては困難な場合が多いでしょう。そのような場合は、無理に内製化にこだわらず、外部の専門家や便利なツールを積極的に活用することが成功への近道です。専門的な知見を持つコンサルティングファームや開発会社といった外部パートナーと連携することで、自社にないノウハウを取り入れ、スピーディにプロジェクトを進めることができます。
また、近年は専門知識がなくてもAIによる需要予測や業務自動化を実現できる「ノーコード・ローコードツール」や、必要な機能を月額料金で利用できる「SaaS(Software as a Service)」も充実しています。こうしたツールをうまく活用すれば、開発コストや時間を大幅に削減し、素早く成果を出すことが可能です。自社の目的や課題に合わせて、最適なパートナーやツールを選定する視点が重要になります。
5. DX推進でよくある失敗例と注意点
多くの企業がDX推進の重要性を認識し、取り組みを開始していますが、すべての企業が成功を収めているわけではありません。むしろ、計画が途中で頓挫したり、期待した成果が得られなかったりするケースも少なくありません。
ここでは、DX推進において企業が陥りがちな典型的な失敗例と、それらを回避するための注意点を解説します。成功事例から学ぶと同時に、失敗事例から教訓を得ることで、自社のDXを成功へと導きましょう。
5.1 目的が「ツールの導入」になってしまう
DX推進における最も典型的な失敗例が、「目的のすり替え」です。本来、DXとはデジタル技術を活用してビジネスモデルや組織文化を変革し、新たな価値を創出して競争上の優位性を確立することです。しかし、いつの間にか「新しいSaaSを導入する」「AIツールを導入する」といった手段そのものが目的になってしまうことがあります。
この状態に陥ると、高額なツールを導入したにもかかわらず、現場では十分に活用されず、部分的な業務効率化に留まってしまいます。結果として、投資対効果(ROI)が見合わず、「DXは失敗だった」という誤った結論に至りかねません。
このような失敗を避けるためには、ツール導入の前に「DXによって何を成し遂げたいのか」という明確なビジョンと戦略を経営層が主体となって策定し、全社で共有することが不可欠です。目的を明確にすることで、導入すべきツールや取るべき施策が自ずと見えてきます。
5.2 レガシーシステムが足かせになる「2025年の崖」問題
多くの日本企業が長年にわたって使用してきた基幹システム、いわゆる「レガシーシステム」がDX推進の大きな障壁となるケースも後を絶ちません。
経済産業省が2018年に公表した「DXレポート」では、この問題が「2025年の崖」として警鐘を鳴らされています。レガシーシステムは、長年の改修によって複雑化・ブラックボックス化しており、最新のデジタル技術との連携が困難です。また、システムの維持管理に多くのコストと人材が割かれ、新たなデジタル投資への足かせとなります。
この問題を放置した場合、2025年以降、最大で年間12兆円もの経済損失が生じる可能性があると試算されています。これは、個々の企業の競争力低下に留まらず、日本の国際競争力にも影響を及ぼす深刻な課題です。
| リスクの種類 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 技術的負債の増大 | システムの複雑化・ブラックボックス化により、改修やメンテナンスが困難になる。障害発生時の復旧も遅れる。 |
| データ活用の阻害 | データが各システムに分散・サイロ化し、全社横断でのデータ収集・分析ができず、データドリブンな経営判断ができない。 |
| セキュリティリスク | 古いシステムは最新のセキュリティ脅威に対応できず、サイバー攻撃や情報漏洩のリスクが高まる。 |
| 人材確保の困難化 | 古いプログラミング言語(COBOLなど)を扱える技術者が減少し、システムの維持・運用が困難になる。 |
「2025年の崖」を乗り越えるためには、自社のシステムを棚卸しし、刷新に向けた具体的な計画を立て、段階的にモダナイゼーション(近代化)を進めていく必要があります。
5.3 現場の理解や協力が得られない
DXは経営層や情報システム部門だけでは決して成功しません。実際に日々の業務を行っている現場の従業員の理解と協力が不可欠です。しかし、トップダウンでDXを推進しようとするあまり、現場の意見を聞かずに進めてしまい、反発を招くケースがよく見られます。
現場の協力が得られない主な原因は以下の通りです。
- コミュニケーション不足:なぜDXが必要なのか、導入によって業務や評価がどう変わるのかが十分に説明されず、現場が「やらされ感」を抱いてしまう。
- 変化への抵抗:長年慣れ親しんだ業務プロセスやツールが変わることへの不安や抵抗感(現状維持バイアス)。
– 業務負荷の増大:通常業務に加えて、新しいシステムの操作方法の習得やデータ移行作業など、一時的な業務負荷が増えることへの懸念。
このような状況では、せっかく導入したシステムが使われなかったり、形骸化してしまったりと、DXは頓挫してしまいます。対策としては、計画の初期段階から現場のキーパーソンを巻き込み、課題や要望をヒアリングすることが重要です。
また、一部の部門でスモールスタートし、成功体験を共有することで、現場のメリットを可視化し、全社展開への機運を高めていくアプローチも有効です。
6. まとめ
本記事では、国内外のDX成功事例を業界・目的別に解説しました。成功企業に共通するのは、経営層の強いリーダーシップのもと、明確なビジョンを掲げている点です。DXは単にツールを導入することではなく、データ活用を通じてビジネスモデルや企業文化そのものを変革する経営戦略です。紹介した成功の鍵や失敗例を参考に、自社の課題解決に向けた第一歩を踏み出しましょう。
product関連するプロダクト
-

UMWELTウムベルト
UMWELTは、プログラミング不要でかんたんに分析や自動化ができるノーコードツールです。需要予測から生産計画を最適化、人材の最適配置まで課題を解決できます。日々変化する生産数や生産計画、人員配置を自動立案し属人化や作業時間を大幅に削減します。
MWELT

TRYETING
公式
TRYETING公式です。
お知らせやIR情報などを発信します。