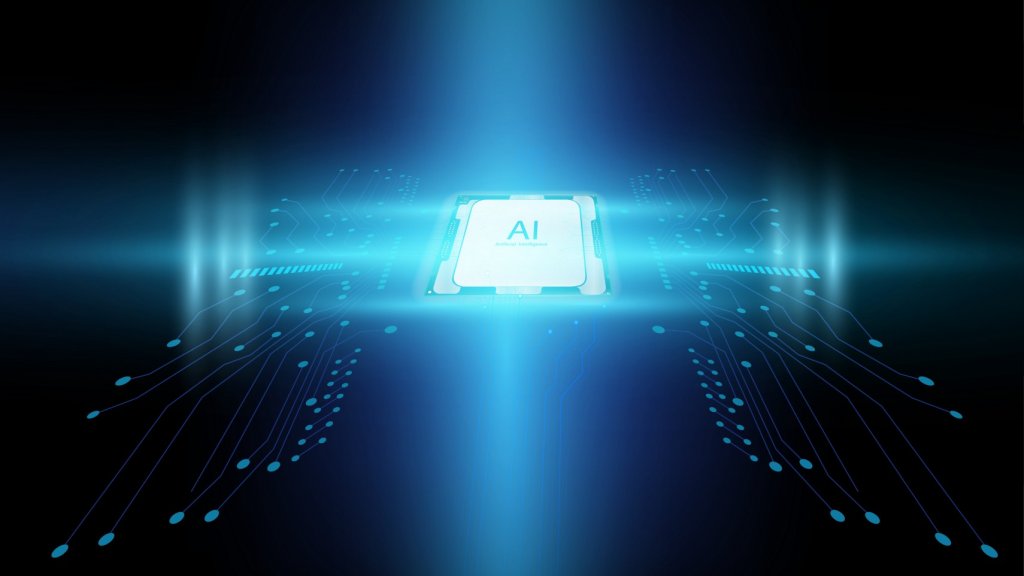BUSINESS
製造業のDXとは?成功へのロードマップ|メリット・課題・事例を徹底解説

目次
製造業が直面する人手不足や「2025年の崖」といった課題を乗り越え、持続的に成長するためにDXは不可欠です。
本記事では、DX推進のメリット・課題から、成功への具体的なロードマップ、目的別の最新事例、活用できる補助金までを網羅的に解説します。この記事を読めば、自社のDXを成功に導くための具体的な手順と、未来へのビジョンが明確になります。
▼更にDXについて詳しく知るには?
DXとはどのようなもの?導入が求められる理由やメリット・デメリットを解説
▼社内のデータをAI化するには?
ノーコードAIツールUMWELT紹介ページ(活用事例あり)
1. 製造業でDX(デジタルトランスフォーメーション)が急務な理由

近年、グローバル競争の激化や深刻化する人手不足、顧客ニーズの多様化など、日本の製造業を取り巻く環境は大きな変革期を迎えています。このような厳しい状況下で企業が競争力を維持し、持続的に成長していくためには、DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進が不可欠です。
しかし、なぜ今、製造業にとってDXが「急務」なのでしょうか。本章では、その背景にある3つの重要な理由を深掘りして解説します。
1.1 DXとは?IT化・デジタル化との違いを解説
DXの推進を語る前に、まず「DX」そのものを正しく理解することが重要です。DXは、単にITツールを導入する「IT化」や、業務プロセスを部分的に電子化する「デジタル化」とは一線を画します。
経済産業省は、DXを「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」と定義しています。つまり、DXとはデジタル技術を手段として、ビジネスの根幹から変革を起こし、新たな価値を創造する経営戦略なのです。
IT化、デジタル化、そしてDXの違いを以下の表にまとめました。
| 用語 | 段階 | 目的・内容 | 製造業における具体例 |
|---|---|---|---|
| IT化(デジタイゼーション) | 第1段階 | アナログ・物理データのデジタル化 | 紙の図面をスキャンしてPDF化する、日報をExcelで入力する |
| デジタル化(デジタライゼーション) | 第2段階 | 個別の業務プロセスをデジタル技術で効率化・自動化する | 特定の工程にRPAを導入して定型作業を自動化する、勤怠管理システムを導入する |
| DX(デジタルトランスフォーメーション) | 第3段階 | データとデジタル技術を活用し、ビジネスモデルや組織全体を変革して新たな価値を創出する | 工場全体のデータを収集・分析し、予知保全や生産計画の最適化を実現する(スマートファクトリー)、顧客データから新たなサービスを創出する |
このように、DXはIT化やデジタル化の先にある、より広範で抜本的な変革を指します。この違いを認識することが、DX成功の第一歩となります。
1.2 経済産業省が警鐘を鳴らす「2025年の崖」問題
製造業がDXを急ぐべきもう一つの大きな理由が、経済産業省が指摘する「2025年の崖」問題です。これは、2018年に同省が発表した「DXレポート」で初めて提唱された概念で、多くの企業が抱えるレガシーシステムが引き起こす深刻な問題を指します。
レガシーシステムとは、長年の運用によって複雑化・肥大化・ブラックボックス化した古い基幹システムのことです。製造業においても、生産管理や受発注、在庫管理などに20年以上前のシステムを使い続けているケースは少なくありません。
これらのレガシーシステムを放置し続けると、以下のような問題が発生します。
- システムの維持管理費が高騰し、IT予算の9割以上を占めてしまう
- システムがブラックボックス化し、全体像を把握できる人材が退職してしまう
- 最新のデジタル技術(AI、IoTなど)と連携できず、データ活用が進まない
- セキュリティリスクが増大し、サイバー攻撃や情報漏洩の標的になりやすい
経済産業省は、もし企業がこの課題を克服できなければ、2025年以降、最大で年間12兆円もの経済損失が生じる可能性があると試算しています。この「崖」から落ちないためには、レガシーシステムから脱却し、DXを推進してデータ活用やビジネスモデル変革を行える体制を早急に構築する必要があるのです。
1.3 製造業が直面する人手不足やグローバル競争の激化
国内の構造的な課題と、国外からの競争圧力も、製造業のDXを後押しする大きな要因です。
1.3.1 深刻化する人手不足と技術継承の課題
日本の生産年齢人口は年々減少し続けており、製造業は特に深刻な人手不足に直面しています。加えて、長年にわたり現場を支えてきた熟練技術者の高齢化が進み、彼らが持つ「匠の技」やノウハウといった暗黙知の継承が大きな課題となっています。このままでは、日本のものづくりの品質や競争力の源泉が失われかねません。
DXは、IoTセンサーで熟練者の動きをデータ化したり、AR(拡張現実)を活用して遠隔から技術指導を行ったりすることで、技術継承問題を解決する有効な手段となります。また、ロボットやAIによる自動化は、人手不足そのものを補う切り札としても期待されています。
1.3.2 激化するグローバル競争と顧客ニーズの変化
海外に目を向ければ、ドイツの「インダストリー4.0」やアメリカの「インダストリアル・インターネット」に代表されるように、世界各国が官民一体で製造業のデジタル化を強力に推進しています。海外の競合他社は、スマートファクトリー化によって生産性を飛躍的に向上させ、コスト競争力と開発スピードで日本企業を猛追しています。
さらに、顧客のニーズは「所有から利用へ」とシフトし、製品の機能だけでなく、サービスを含めたトータルな価値提供(コトづくり)が求められるようになりました。こうした環境変化に対応し、国際競争を勝ち抜くためには、データ活用による需要予測の高度化や、サプライチェーンの最適化、新たなビジネスモデルの創出といったDXの取り組みが不可欠なのです。
2. 製造業がDXで得られる5つのメリット

製造業がDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進することは、単なるITツールの導入に留まらず、企業の競争力を根本から強化する多くのメリットをもたらします。生産現場の課題解決から新たなビジネスチャンスの創出まで、DXによって得られる具体的なメリットを5つの視点から詳しく解説します。
2.1 生産性の向上と業務効率化
製造業におけるDXの最も直接的で大きなメリットは、生産性の向上と業務効率化です。これまで人の手や勘に頼っていた作業をデジタル技術で自動化・最適化することで、製造プロセス全体を効率化し、収益性を高めることができます。
例えば、工場内の設備にIoTセンサーを設置すれば、稼働状況をリアルタイムで監視できます。収集したデータをAIが分析し、故障の予兆を検知する「予知保全」を行えば、突然の設備停止による生産ラインのダウンタイムを最小限に抑えられます。また、RPA(Robotic Process Automation)を活用して、受発注処理や伝票作成といった定型的な事務作業を自動化すれば、従業員はより付加価値の高いコア業務に集中できるようになり、人的ミスも削減できます。
このように、デジタル技術の活用は、製造現場から間接部門まで、あらゆる業務の無駄をなくし、企業全体の生産性を飛躍的に向上させます。
| 対象業務 | 活用するDX技術・ツール | 期待される効果 |
|---|---|---|
| 生産計画 | AI搭載の生産スケジューラ、需要予測システム | 計画立案の自動化、リードタイム短縮、欠品・過剰在庫の防止 |
| 設備保全 | IoTセンサー、AI予知保全システム | ダウンタイムの削減、保全コストの最適化、設備の長寿命化 |
| 組立・加工 | 産業用ロボット、協働ロボット | 省人化・自動化、生産スピード向上、作業品質の安定化 |
| 事務・管理業務 | RPA、ペーパーレス化システム、ERP | 定型業務の自動化、人的ミスの削減、情報共有の迅速化 |
2.2 技術・ノウハウの継承と属人化の解消
多くの製造業が直面する深刻な課題が、熟練技術者の高齢化と、それに伴う技術・ノウハウの継承問題です。個人の経験や勘に依存した「暗黙知」は、その人が退職すると失われてしまうリスクがあります。DXは、こうした属人化された技術をデジタルデータとして「形式知」に変換し、組織全体の資産として蓄積・共有することを可能にします。
具体的には、熟練技術者の作業をビデオカメラやセンサーで記録・データ化し、AIで動きのポイントを解析することで、最適な作業手順を標準化できます。作成したデジタルマニュアルやAR(拡張現実)グラスを活用した遠隔作業支援システムを導入すれば、若手や経験の浅い作業者でも、熟練者と同等の品質で作業を行うためのトレーニングが可能です。これにより、教育期間の短縮と品質の安定化を両立できます。
DXを通じて技術継承の仕組みを構築することは、企業の持続的な成長と競争力維持に不可欠です。
2.3 データ活用による需要予測と品質管理の高度化
DXの推進は、企業内に散在していたデータを収集・統合し、それを分析・活用することで、より的確な意思決定を可能にします。特に「需要予測」と「品質管理」の領域で大きな効果を発揮します。
需要予測においては、過去の販売実績や生産データに加え、市場トレンド、天候、SNSの投稿といった外部データもAIで分析することで、予測精度を大幅に向上させることができます。これにより、無駄な在庫を抱えるリスクや、欠品による販売機会の損失を防ぎ、キャッシュフローの改善に繋がります。
品質管理の面では、生産ラインに設置した画像認識AIカメラが、人では見逃しがちな微細な傷や汚れを瞬時に検知し、不良品の流出を未然に防ぎます。また、各工程から収集される温度、圧力、速度といったセンサーデータを分析し、品質低下に繋がる異常の予兆を捉えることで、不良品の発生そのものを抑制することも可能です。これにより、検査コストの削減と顧客満足度の向上を同時に実現します。
2.4 サプライチェーンの最適化とレジリエンス強化
原材料の調達から生産、在庫管理、物流、販売に至るまでの一連の流れであるサプライチェーンは、DXによって全体最適化を図ることができます。各拠点のシステムを連携させ、受注情報、在庫状況、生産進捗、配送状況といったデータをリアルタイムで一元管理・可視化することで、サプライチェーン全体のボトルネックを特定し、解消に向けた的確な施策を打つことが可能になります。
さらに、近年の地政学リスクや自然災害、感染症のパンデミックなど、予測困難な事態によってサプライチェーンが寸断されるリスクが高まっています。DXは、こうした不確実性に対する「レジリエンス(強靭性)」の強化にも貢献します。データを活用してリスクをシミュレーションしたり、有事の際に代替の調達先や輸送ルートを迅速に確保したりするなど、変化に強く、しなやかなサプライチェーンを構築することができるのです。
2.5 新たなビジネスモデルの創出と顧客価値向上
DXは、既存業務の効率化に留まらず、企業のビジネスモデルそのものを変革し、新たな顧客価値を創出する原動力となります。製品を販売して終わりという従来の「モノ売り」から、製品とサービスを組み合わせて継続的な価値を提供する「コト売り(サービス化)」への転換がその代表例です。
例えば、自社製品にIoTセンサーを組み込み、顧客先での稼働状況を遠隔でモニタリング。収集したデータに基づき、故障前にメンテナンスを行う「予知保全サービス」や、稼働時間に応じた従量課金(サブスクリプション)モデルを提供することが可能になります。これにより、企業は顧客との継続的な関係を築き、安定した収益源を確保できます。
また、顧客の製品使用データを分析することで、新たなニーズを発見し、次世代製品の開発やパーソナライズされたサービスの提供に繋げることもできます。このように、DXは顧客との接点を強化し、競争優位性の高い新たなビジネスを創造する大きなチャンスをもたらします。
3. 製造業DX推進における5つの壁(課題)

多くのメリットが期待できる製造業のDXですが、その推進は決して平坦な道のりではありません。多くの企業が、特有の課題や障壁に直面しています。これらの「壁」を事前に理解し、適切な対策を講じることが、DXプロジェクトを成功に導くための第一歩です。ここでは、製造業がDXを推進する上で直面しがちな5つの主要な壁(課題)について詳しく解説します。
3.1 レガシーシステムの存在と刷新コスト
製造業のDX推進における最初の大きな壁が、長年使用されてきた「レガシーシステム」の存在です。基幹システム(ERP)や生産管理システムなど、特定の業務に最適化して構築された古いシステムは、複雑なカスタマイズが繰り返された結果、内部構造が不明瞭な「ブラックボックス」と化しているケースが少なくありません。
このようなレガシーシステムは、最新のデジタル技術との連携が困難であるだけでなく、以下のような問題を引き起こします。
- データのサイロ化:システムが部門ごとに独立しており、全社横断的なデータ活用ができない。
- 維持コストの増大:システムの保守・運用に多額の費用と専門知識を持つ人材が必要となる。
- セキュリティの脆弱性:古い技術基盤のため、近年の高度なサイバー攻撃に対応できないリスクがある。
- 事業継続性の低下:システムの仕様を把握している担当者の退職により、誰も改修・保守ができなくなる。
これらのシステムを刷新するには、新しいシステムの導入費用だけでなく、データ移行や業務プロセスの再設計、従業員へのトレーニングなど、多大なコストと時間が必要となります。しかし、この「技術的負債」を放置すれば、企業の競争力そのものが失われかねません。段階的な移行計画を策定し、経営判断として刷新に取り組むことが不可欠です。
3.2 DXを推進できるデジタル人材の不足
DXを成功させるためには、デジタル技術と自社の業務知識の両方に精通した「DX人材」が不可欠です。しかし、多くの製造業企業では、こうした人材の確保に苦慮しています。特に、以下のような専門スキルを持つ人材は、業界を問わず需要が高く、獲得競争が激化しています。
- DXリーダー/プロデューサー:経営戦略と結びつけてDXの全体像を描き、プロジェクトを牽引する人材。
- データサイエンティスト/AIエンジニア:収集したデータを分析し、AIモデルを構築して新たな価値を創出する人材。
- ブリッジSE/ビジネスアナリスト:現場の課題を深く理解し、それを解決するための適切なITソリューションを企画・設計できる人材。
情報処理推進機構(IPA)が発行した「DX白書2023」によると、事業会社においてDXを推進する人材の「量」も「質」も不足していると回答した企業が大多数を占めています。社内での人材育成(リスキリング)には時間がかかり、外部からの採用も容易ではありません。そのため、自社だけで全てを賄おうとせず、外部の専門家やパートナー企業と協業することも、人材不足を補う有効な手段となります。
3.3 経営層の理解不足と全社的な協力体制の欠如
DXが失敗する最大の要因の一つに、経営層の理解不足が挙げられます。経営層がDXを単なる「ITツールの導入」や「特定の部門の業務改善」と捉えている場合、全社的な変革は進みません。DXは、デジタル技術を活用してビジネスモデルや組織文化そのものを変革し、新たな顧客価値を創造する経営戦略の一環です。
経営層がDXの本質を理解し、「なぜDXに取り組むのか」という明確なビジョンを全社に示し、強力なリーダーシップを発揮しなければ、現場は動きません。また、従来の縦割り組織の壁が、部門間の連携を妨げ、DXの障害となることも多々あります。
例えば、生産部門がスマート工場化を進めても、営業部門の需要予測データや、開発部門の設計データと連携できなければ、その効果は限定的です。DXを成功させるには、経営トップの強いコミットメントのもと、部門の垣根を越えた全社横断的な推進体制を構築し、現場の従業員一人ひとりを巻き込んでいく企業文化の醸成が不可欠です。
3.4 導入コストと投資対効果(ROI)の不明確さ
DX推進には、相応の初期投資が必要です。しかし、その投資に対してどれだけのリターンが見込めるのか、つまり投資対効果(ROI)を事前に正確に算出することは非常に困難です。これが、多くの企業でDXへの投資判断を躊躇させる大きな要因となっています。
DXに関わるコストは多岐にわたります。
| コストの種類 | 具体例 |
|---|---|
| ハードウェア費用 | サーバー、ネットワーク機器、PC、スマートフォン、IoTセンサー、カメラなど |
| ソフトウェア費用 | SaaSのライセンス料、パッケージソフト購入費、システム開発委託費など |
| 人件費 | コンサルティング費用、外部ベンダーへの支払い、社内のDX推進担当者の人件費など |
| 教育・運用費用 | 従業員への研修費用、導入後の運用保守費用、マニュアル作成費用など |
DXの効果は、人件費削減や生産性向上といった直接的な数値で測れるものばかりではありません。「技術継承の促進」「顧客満足度の向上」「新たなビジネス機会の創出」といった、定性的で長期的な視点で評価すべき効果も多く含まれます。ROIを短期的なコスト削減効果だけで判断するのではなく、将来の企業価値向上に繋がる「戦略的投資」として捉える視点が求められます。
3.5 セキュリティリスクの増大と対策の必要性
DX推進のために工場内の機器をインターネットに接続する「スマート工場化」は、生産性を飛躍的に向上させる一方で、新たなセキュリティリスクをもたらします。従来、外部ネットワークから隔離されていた工場内のOT(Operational Technology:制御・運用技術)システムがサイバー攻撃の標的となる危険性が増大するのです。
工場がランサムウェア(身代金要求型ウイルス)に感染し、生産ラインが停止に追い込まれるといった被害は、国内外で実際に発生しており、事業継続に深刻な影響を及ぼします。また、サプライヤーを踏み台にしてターゲット企業を攻撃する「サプライチェーン攻撃」のリスクも高まっており、自社だけでなく取引先を含めたサプライチェーン全体でのセキュリティ対策が不可欠です。
これらの脅威に対抗するためには、ファイアウォールや侵入検知システムといった技術的な対策はもちろんのこと、経済産業省が策定した「サイバーセキュリティ経営ガイドライン」などを参考に、以下のような組織的な対策を講じることが極めて重要です。
- 全社的なセキュリティポリシーの策定と周知徹底
- 従業員に対する継続的なセキュリティ教育
- インシデント発生を想定した対応体制(CSIRT)の構築と訓練
DXによるメリットを最大限に享受するためには、セキュリティを「コスト」ではなく、事業継続のための「投資」と捉え、経営主導で対策を推進していく必要があります。
4. 【5ステップで解説】製造業DXの具体的な進め方

製造業におけるDX推進は、単にデジタルツールを導入すれば成功するわけではありません。明確なビジョンに基づき、計画的かつ段階的に進めることが不可欠です。思い付きで進めてしまうと、現場の混乱を招いたり、期待した効果が得られなかったりするだけでなく、プロジェクト自体が頓挫してしまうリスクもあります。ここでは、製造業のDXを成功に導くための具体的な進め方を5つのステップに分けて、網羅的に解説します。
4.1 ステップ1:経営ビジョンの策定と全社共有
DX推進の最初のステップは、経営層が主導して「DXによって自社をどのような姿に変えたいのか」という明確な経営ビジョンを策定することです。なぜDXに取り組むのか(Why)、何を目指すのか(What)が曖昧なままでは、全社的な協力は得られません。
例えば、「スマートファクトリー化により生産性を30%向上させ、グローバル市場での競争優位性を確立する」「データ活用による新たなサービスを提供し、顧客満足度No.1企業を目指す」といった、具体的で魅力的なビジョンを掲げることが重要です。このビジョンは、経済産業省が公表している「DX推進ガイドライン」などを参考に、自社の状況に合わせて策定すると良いでしょう。
策定したビジョンは、経営層から全従業員に向けて繰り返し発信し、共有を徹底します。DXが一部の部署だけの取り組みではなく、全社一丸となって進めるべき重要な経営戦略であることを理解してもらうことで、変革への意識統一を図ります。
4.2 ステップ2:現状の課題分析とDXで目指すゴールの設定
ビジョンが定まったら、次に行うのは現状(As-Is)の徹底的な分析です。理想の姿(To-Be)と現状とのギャップを正確に把握しなければ、DXで取り組むべき課題は見えてきません。
まずは、設計、調達、製造、品質管理、物流、保守といった各業務プロセスを可視化し、どこに非効率や無駄、属人化といった問題が潜んでいるかを洗い出します。現場の従業員へのヒアリングやワークショップを通じて、日々の業務で感じている課題や改善要望を吸い上げることも不可欠です。
洗い出した課題の中から、ビジョン実現へのインパクトや緊急性を考慮して、優先的に取り組むべき課題を絞り込みます。そして、その課題を解決した先の具体的なゴールを、測定可能な形で設定します。例えば、「熟練技術者のノウハウをデジタル化し、若手への技術継承期間を50%短縮する」「AIによる需要予測を導入し、在庫を20%削減する」といった、誰が見ても達成度がわかる目標(KGI:重要目標達成指標)を定めることが重要です。これにより、後の効果測定が容易になります。
4.3 ステップ3:DX推進体制の構築とロードマップ作成
具体的なゴールが決まったら、DXを確実に実行していくための推進体制を構築します。DXは既存業務と並行して進める必要があるため、専任の推進チームを組成するのが一般的です。メンバーには、IT部門やDX推進室だけでなく、実際に業務を行う製造現場や設計、営業など各部門の担当者を巻き込むことが成功のカギとなります。
また、社内に知見やスキルを持つ人材が不足している場合は、外部のコンサルタントやITベンダーといった専門家の協力を得ることも有効な手段です。客観的な視点からアドバイスを受けることで、より効果的なDX推進が期待できます。
体制が整ったら、ゴール達成までの具体的な道のりを示す「ロードマップ」を作成します。どの課題に、いつまでに、どの技術を使って、どのように取り組むのかを時系列で計画に落とし込みます。予算や人員計画もこの段階で明確にしておきましょう。
4.3.1 スモールスタートで成功体験を積む重要性
ロードマップを策定する上で重要なのが、「スモールスタート」の考え方です。最初から全社規模で大規模なシステムを導入しようとすると、莫大なコストがかかるだけでなく、失敗したときのリスクも大きくなります。まずは特定の生産ラインや一部の業務に絞ってDXを試験的に導入し、効果を検証するアプローチ(PoC:Proof of Concept/概念実証)が有効です。小さな成功体験を積み重ねることで、DXへの効果を社内に示し、本格展開に向けた協力や理解を得やすくなります。
4.4 ステップ4:自社に合ったツール・技術の選定と導入
ロードマップに基づき、いよいよ具体的なデジタルツールや技術の選定・導入フェーズに入ります。市場には多種多様なツールが存在するため、自社の課題解決や目的達成に最も適したものを見極めることが重要です。選定にあたっては、以下の点を総合的に評価しましょう。
- 機能性:自社の課題を解決できる機能が備わっているか。
- 操作性:現場の従業員が直感的に使えるか。専門知識がなくても扱えるか。
- コスト:導入費用(イニシャルコスト)と運用費用(ランニングコスト)は予算内に収まるか。
- サポート体制:導入時や運用開始後のサポートは充実しているか。
- 拡張性・連携性:将来的な機能拡張や、既存システムとの連携は可能か。
ツールを導入する際は、現場の従業員への丁寧な説明とトレーニングが不可欠です。導入によって業務がどう変わるのか、どのようなメリットがあるのかを理解してもらい、スムーズな移行を支援します。
4.4.1 目的別に見るDXツールの種類
製造業のDXで活用される代表的なツールを目的別に整理すると、以下のようになります。自社の課題と照らし合わせ、ツール選定の参考にしてください。
| 目的 | ツールの種類 | 具体的な活用例 |
|---|---|---|
| 生産性の向上・業務効率化 | IoT、AI、RPA、MES(製造実行システム) | 設備の稼働状況をリアルタイムで監視・分析、単純な事務作業の自動化、生産進捗の可視化 |
| 技術・ノウハウの継承 | AR/VR、AI、動画マニュアル | ARグラスによる遠隔作業支援、熟練者の動きをAIで解析・マニュアル化、VRによる安全教育 |
| 需要予測・品質管理の高度化 | AI、BIツール、画像認識システム | 過去の販売実績や市場データに基づく高精度な需要予測、AIによる外観検査の自動化 |
| サプライチェーンの最適化 | ERP(統合基幹業務システム)、SCMシステム | 受発注、生産、在庫、物流までの一連の情報を一元管理し、全体の最適化を図る |
| 設計・開発の迅速化 | デジタルツイン、3D-CAD、PLM(製品ライフサイクル管理) | 仮想空間での試作品シミュレーション、製品の企画から廃棄までの情報を一元管理 |
4.5 ステップ5:効果測定(KPI設定)と改善(PDCA)
DXはツールを導入して終わりではありません。導入後、その効果を定期的に測定し、継続的に改善していくことが最も重要です。「やりっぱなし」にせず、PDCAサイクル(Plan-Do-Check-Action)を回していく仕組みを構築しましょう。
効果測定のためには、ステップ2で設定したゴール(KGI)を達成するための具体的な指標であるKPI(重要業績評価指標)を設定します。例えば、「生産性向上」というゴールに対しては「設備総合効率(OEE)」「単位時間あたりの生産量」「不良品率」などがKPIとなります。
これらのKPIを定期的にモニタリングし、目標値と実績値の差を分析します(Check)。なぜ目標を達成できたのか、あるいはできなかったのか、その要因を深掘りし、次の改善策を立案して実行に移します(Action)。このサイクルを粘り強く回し続けることで、DXの効果を最大化し、企業の持続的な成長につなげることができます。
5. 製造業のDX推進に活用できる補助金・助成金
製造業のDXを推進するには、新たなシステムの導入や設備投資など、多額のコストがかかる場合があります。しかし、国や地方自治体が提供する補助金・助成金を活用することで、企業の資金的な負担を大幅に軽減し、DX化への第一歩を踏み出しやすくなります。ここでは、製造業のDX推進に特に役立つ代表的な3つの補助金について、その概要や対象経費などを詳しく解説します。
なお、補助金の上限などは公募回ごとに変更される可能性があるため、最新の情報は各制度のホームページなどをご参照ください。
5.1 IT導入補助金
IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者が自社の課題やニーズに合ったITツールを導入する経費の一部を補助することで、業務効率化や売上アップをサポートする制度です。製造業においては、生産管理システムや在庫管理システム、CAD/CAMソフトウェア、RPAツールといったDXに直結するソフトウェアの導入に活用できます。
また、インボイス制度への対応を見据えた会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフトの導入も対象となるため、バックオフィス業務のDX化にも有効です。ハードウェアの購入費用は、一部の申請枠や条件を満たした場合にのみ対象となる点に注意が必要です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 目的 | 中小企業・小規模事業者等の労働生産性の向上を目的としたITツールの導入支援 |
| 対象者 | 日本国内で事業を営む中小企業・小規模事業者等 |
| 主な申請枠 | 通常枠、インボイス枠(インボイス対応類型・電子取引類型)、セキュリティ対策推進枠、複数社連携IT導入枠 |
| 対象経費 | ソフトウェア購入費、クラウド利用料(最大2年分)、導入関連費など |
| 補助額・補助率 | 申請枠により異なる。例えば、通常枠では最大450万円(補助率1/2以内)。 |
※公募回や申請枠によって要件が異なります。最新の情報は公式サイトをご確認ください。
参考:IT導入補助金2024
5.2 ものづくり補助金
ものづくり補助金(正式名称:ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金)は、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的な製品・サービス開発や、生産プロセス・サービス提供方法の改善に必要な設備投資等を支援する制度です。製造業との親和性が非常に高く、DXを目的とした大規模な設備投資に適しています。
例えば、IoTセンサーやAIを活用した予知保全システムの構築、産業用ロボットの導入による生産ラインの自動化、デジタルツイン技術を用いた試作品開発の効率化など、幅広い取り組みが対象となります。特に、DXに資する革新的な製品・サービスの開発や、デジタル技術を活用した生産プロセスの改善を行う事業者は、申請枠によっては優遇される場合があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 目的 | 人手不足の解消に向けた、革新的な製品・サービス開発、生産プロセス改善のための設備投資等の支援 |
| 対象者 | 日本国内に本社・事業所を有する中小企業・小規模事業者等 |
| 主な申請枠 | 省力化(オーダーメイド)枠、製品・サービス高付加価値化枠、グローバル枠 |
| 対象経費 | 機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、クラウドサービス利用費など |
| 補助額・補助率 | 申請枠や従業員規模により異なる。例えば、省力化(オーダーメイド)枠では最大8,000万円(補助率1/2、小規模・再生事業者は2/3)。 |
※公募回ごとに制度内容が変更される可能性があります。申請を検討する際は、必ず最新の公募要領をご確認ください。
参考:ものづくり補助金総合サイト
5.3 事業再構築補助金
事業再構築補助金は、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するため、企業の思い切った事業再構築を支援する制度です。単なる業務効率化にとどまらず、DX技術を活用して新たな製品やサービスを開発し、新市場へ進出するなど、ビジネスモデルそのものを変革するような大規模な挑戦に活用できます。
製造業においては、従来の大量生産モデルから、顧客ごとの個別仕様に対応する「マスカスタマイゼーション」へ転換するためのシステム投資や、製品にセンサーを組み込んで稼働データを収集・分析し、保守サービスを提供する「リカーリングモデル」への事業転換などが考えられます。事業計画の策定には高度な専門性が求められるため、認定経営革新等支援機関との連携が成功の鍵となります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 目的 | 新市場進出、事業・業種転換、事業再編など、思い切った事業再構築の支援 |
| 対象者 | 事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業計画を策定している中小企業等 |
| 主な申請枠 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速化枠、サプライチェーン強靱化枠など(公募回により変動) |
| 対象経費 | 建物費、機械装置・システム構築費、技術導入費、外注費、広告宣伝・販売促進費など |
| 補助額・補助率 | 申請枠や従業員規模により大きく異なる。例えば、成長分野進出枠では最大1.5億円(補助率1/2、中小企業の場合)。 |
※事業再構築補助金は公募回ごとに要件が大きく変わる可能性があります。申請を検討する際は、最新の公募要領を熟読するとともに、認定経営革新等支援機関などの専門家への相談をおすすめします。
参考:事業再構築補助金
これらの補助金を効果的に活用することで、製造業のDX推進における初期投資のハードルを下げ、企業の競争力強化と持続的な成長を実現することが可能です。自社の課題と目指すDXの姿に合った補助金制度をリサーチし、積極的に活用を検討しましょう。
6. まとめ
本記事では、製造業におけるDXの重要性から具体的な進め方、成功事例までを解説しました。人手不足や「2025年の崖」といった課題に直面する日本の製造業にとって、DXは競争力を維持・強化するための不可欠な経営戦略です。明確なビジョンを掲げ、スモールスタートで成功体験を重ねることが重要です。IT導入補助金などを活用し、自社の課題解決に向けた第一歩を踏み出しましょう。
product関連するプロダクト
-

UMWELTウムベルト
UMWELTは、プログラミング不要でかんたんに分析や自動化ができるノーコードツールです。需要予測から生産計画を最適化、人材の最適配置まで課題を解決できます。日々変化する生産数や生産計画、人員配置を自動立案し属人化や作業時間を大幅に削減します。
MWELT

TRYETING
公式
TRYETING公式です。
お知らせやIR情報などを発信します。