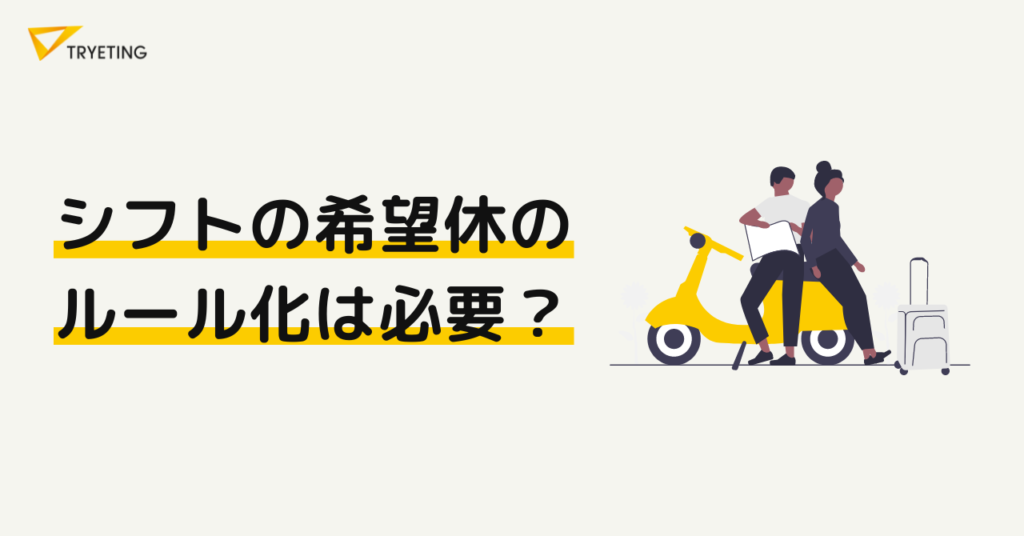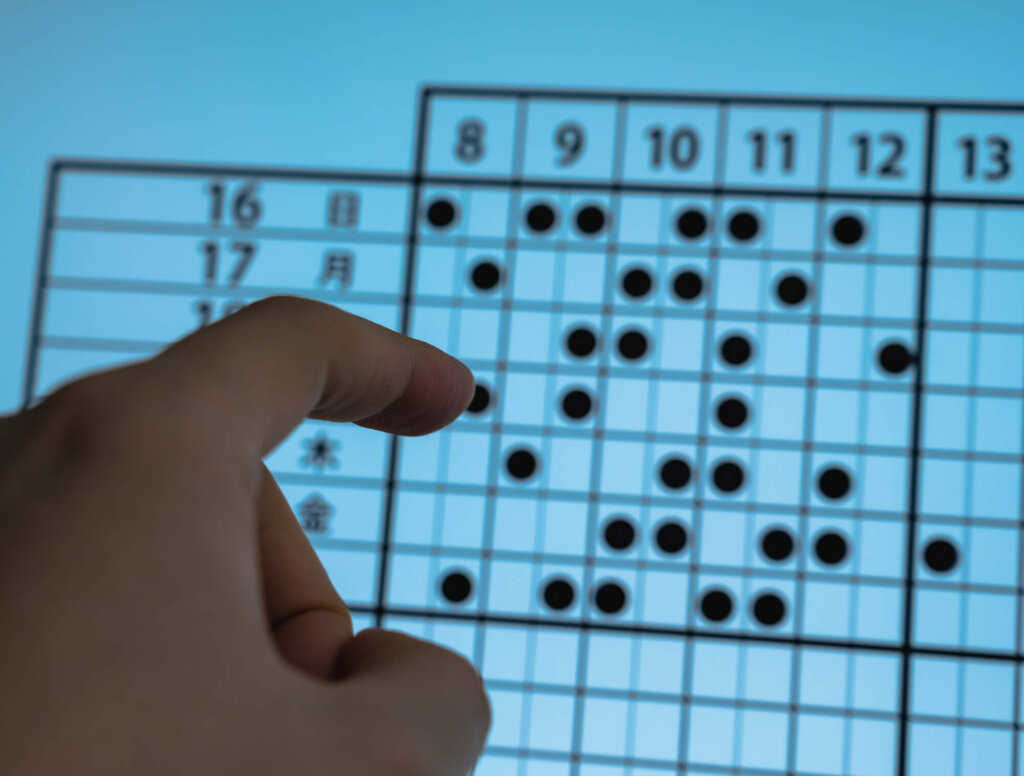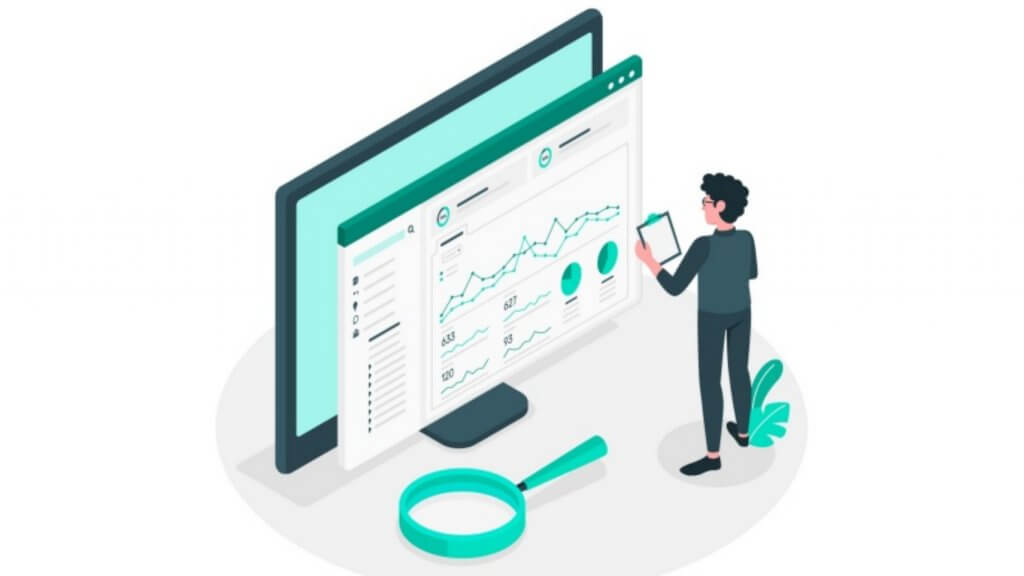WORK
コンビニのシフトの組み方は?管理者のポイントを徹底解説!

目次
コンビニのシフト作成は、人手不足や従業員の希望調整など、多くの店長が頭を悩ませる業務です。この記事では、コンビニのシフト管理における悩みへの対処法から、固定・自由シフトの違い、忙しい時間帯の見極め方までを解説します。円滑な店舗運営の鍵は、事前の準備とツールの活用にあります。具体的なポイントを押さえ、効率的なシフト作成を実現する方法がわかります。
▼更にシフト作成について詳しく知るには?
シフト表作成に役立つツールとは?メリットやおすすめは?
▼面倒なシフト作成をAIで自動化
シフト自動作成AIクラウドHRBEST紹介ページ
1. コンビニのシフトは店長が決めるもの?

結論から言うと、コンビニのシフトは、基本的にその店舗の責任者である店長やオーナーが作成・決定します。 アルバイトやパートのスタッフは、まず自身の希望する勤務日時を提出し、店長やオーナーが全体のバランスを見て調整しながら最終的なシフト表を完成させるのが一般的な流れです。
ただし、同じチェーンのコンビニであっても、店舗が「フランチャイズ店」か「直営店」かによって、シフトのルールや柔軟性に違いが見られることがあります。 そのため、応募する際や働き始める前に、その店舗のシフトがどのように決まるのかを理解しておくことが大切です。
1.1 シフト決定の基本的な流れ
コンビニのシフトは、主に以下のステップで決定されます。このプロセスを理解することで、なぜ希望が通りやすい時と通りにくい時があるのかが見えてきます。
- 従業員からの希望シフト提出
まず、スタッフ一人ひとりが次の期間(多くは月ごとや2週間ごと)で勤務したい曜日や時間帯を申告します。 提出方法は、店内に掲示されたシフト希望表に書き込む、店長に直接伝える、あるいはLINEや専用アプリを利用するなど、店舗によって様々です。 - 店長・オーナーによる調整
次に、集まった希望をもとに、店長やオーナーがシフト表を作成します。 この時、単に希望を並べるだけでなく、以下のような様々な要素を考慮して調整が行われます。- 時間帯ごとの必要人数
- スタッフのスキルや経験(新人ばかりの時間帯ができないようにする、など)
- 人件費の予算
- 労働基準法(休憩時間や連続勤務日数など)の遵守
- スタッフ間の公平性
- シフトの確定と共有
調整が終わると、完成したシフト表がバックヤードなどに掲示され、スタッフ全員に共有されます。確定が遅れるとスタッフが予定を立てにくくなるため、多くの店舗では提出期限を設け、迅速な共有を心がけています。
1.2 コンビニの主なシフト時間帯のパターン
24時間営業のコンビニでは、勤務時間帯がいくつかのパターンに区切られています。店舗の立地(駅前、オフィス街、住宅街など)によって忙しい時間帯は異なりますが、一般的には以下のような分け方がされています。 自身の生活スタイルに合った時間帯を選ぶ参考にしてください。
| 時間帯の名称 | 時間帯の目安 | 主な業務内容・特徴 |
|---|---|---|
| 早朝 | 5:00 or 6:00 ~ 9:00 | 通勤・通学客で混雑するピークタイム。 レジ業務に加え、新聞や朝刊の陳列、淹れたてコーヒーの準備などが中心。短時間で効率よく働きたい人に向いています。 |
| 日中 | 9:00 ~ 17:00 | 昼食のピークを挟み、比較的落ち着いた時間帯。宅配便の受付や公共料金の支払い対応、商品の品出しや前出し(賞味期限が近い商品を前に出す作業)などをじっくり行います。 |
| 夕方 | 17:00 ~ 22:00 | 帰宅ラッシュで再び混雑する時間帯。学生や仕事帰りの客が多く、レジ業務が中心となります。 ホットスナック(揚げ物など)の補充や調理も増えます。 |
| 深夜 | 22:00 ~ 翌5:00 or 6:00 | 客足は減りますが、商品の搬入・検品・品出し、店内の清掃、什器のメンテナンスなど、日中にはできない業務が多くあります。 深夜手当により時給が高くなるのが特徴です。 |
1.3 【ポイント】フランチャイズ店と直営店での違い
シフトの決まり方に影響を与える要素として、店舗の運営形態の違いが挙げられます。コンビニには、個人や法人がオーナーとして経営する「フランチャイズ(FC)店」と、コンビニ本部が直接運営する「直営店」の2種類があります。
1.3.1 フランチャイズ(FC)店の場合
日本のコンビニの多くはフランチャイズ店です。この場合、経営者はオーナーであり、シフトの作成や時給の設定、採用基準など、多くの裁量をオーナーが持っています。 そのため、オーナーの方針によってシフトの融通が利きやすかったり、逆に独自のルールが設けられていたりすることがあります。服装や髪型などの規則が比較的自由な場合もあります。
1.3.2 直営店の場合
直営店は、コンビニ本部が運営している店舗で、店長も本部の社員です。 そのため、シフトのルールや労働条件、福利厚生などが本部のマニュアルに沿って厳格に運用される傾向にあります。 働き方のルールがしっかり決まっている環境を好む人には向いていると言えるでしょう。新商品の研修やオペレーションのテストが先行して行われることもあります。
2. コンビニのシフト管理で良くある悩み
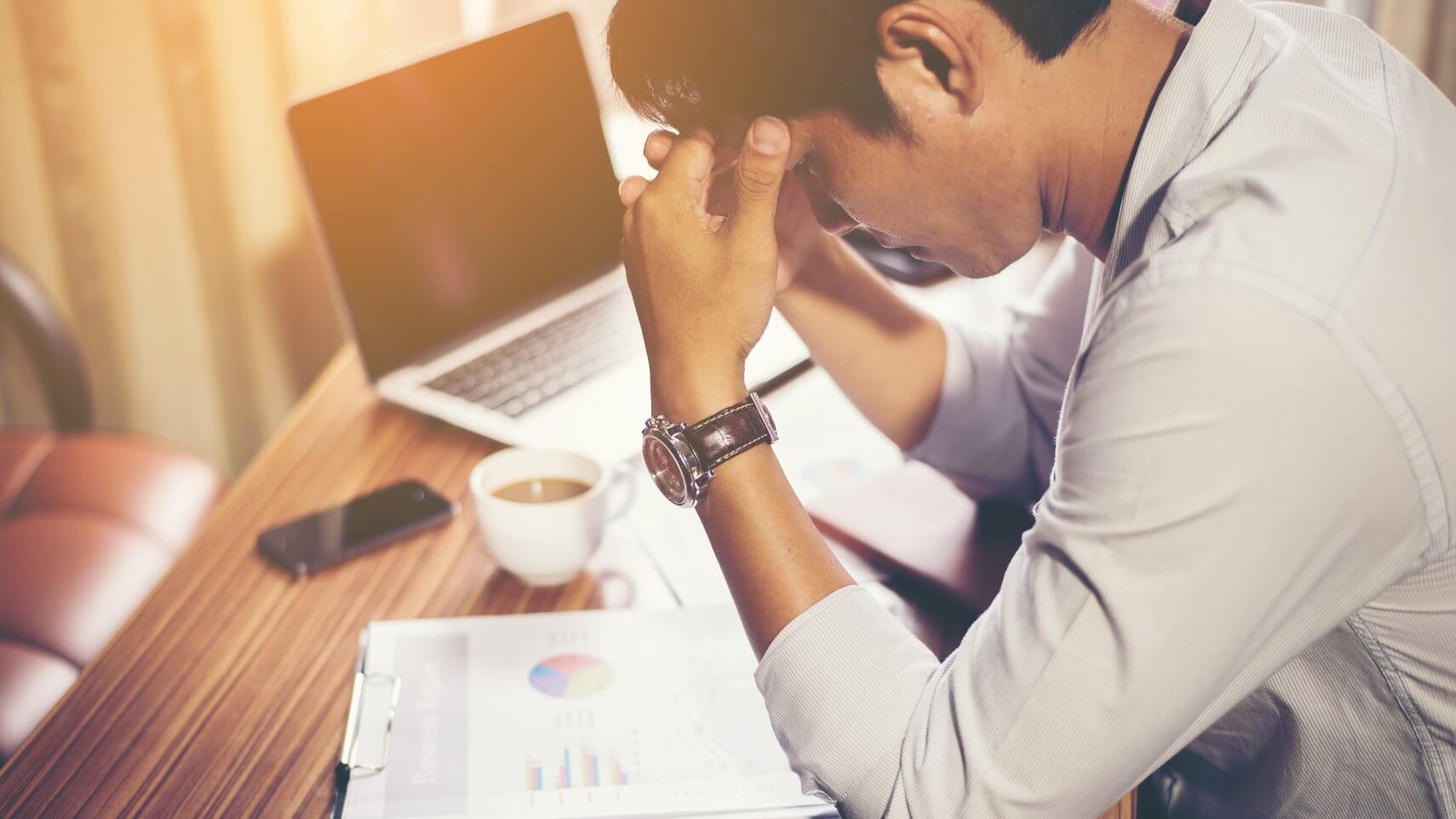
24時間365日営業が基本となるコンビニエンスストアの運営において、シフト管理は売上を左右する重要な業務です。しかし、その特殊な営業形態から、シフト管理には特有の悩みがつきまといます。ここでは、多くのコンビニオーナーや店長が直面する、シフト管理における具体的な悩みについて掘り下げて解説します。
2.1 シフトを組むための人手が足りない
コンビニのシフト管理における最も深刻な悩みが、慢性的な人手不足です。 特に、学生や主婦(夫)といったアルバイト・パートの主力となる層が集まりにくい早朝や深夜の時間帯は、常に人員確保が課題となります。 少人数体制で運営している店舗が多いため、一人のスタッフが退職するだけでシフトに大きな穴が空き、店舗運営に直接的な打撃を与えてしまいます。
人手不足の背景には、以下のような複合的な要因が考えられます。
- 労働人口の減少:少子高齢化により、そもそも働き手となる若年層の人口が減少しています。
- 業務の多様化と複雑化:レジ業務や品出し、清掃だけでなく、公共料金の支払いや宅配便の受付、チケット販売、淹れたてコーヒーの提供など、コンビニの業務は多岐にわたります。 覚えるべき業務が多いことが、働く上でのハードルとなり、人材が定着しにくい一因となっています。
- 待遇の問題:周辺の競合店舗との価格競争や、薄利多売というビジネスモデルから、人件費を上げにくく、給与や待遇の改善が難しい状況があります。
結果として、不足した人員を補うために店長やオーナー自らが長時間労働を強いられるケースも少なくありません。 しかし、店長には発注業務や売上管理といった他の重要な役割もあり、現場の穴埋めだけでは根本的な解決にはならず、経営全体の質を低下させるリスクもはらんでいます。
2.2 従業員の希望通りのシフトを組めない
従業員一人ひとりの希望を尊重したシフトを組むことが難しい点も、大きな悩みの一つです。 学生アルバイトのテスト期間やサークル活動、主婦(夫)パートの子供の学校行事や家庭の事情など、従業員のプライベートな予定は様々です。これらの希望が特定の曜日や時間帯に集中してしまうと、全員の要望に応えることは物理的に不可能になります。
特に人手不足が深刻な店舗では、スタッフに連勤や長時間勤務をお願いせざるを得ない状況も発生しがちです。 このような状況は、従業員の不満や不公平感につながり、結果としてモチベーションの低下や離職を招く悪循環に陥る可能性があります。
| 希望シフトが通らないことによる問題点 | 店舗への具体的な影響 |
|---|---|
| 従業員のモチベーション低下 | 接客態度の悪化、作業効率の低下、お客様からのクレーム増加 |
| スタッフ間の不公平感 | 人間関係の悪化、チームワークの乱れ |
| 離職率の増加 | 慢性的な人手不足の深刻化、採用・教育コストの増大 |
また、スタッフのスキルレベルに差があることも、シフト作成を難しくする要因です。例えば、新人スタッフだけでは対応が難しい時間帯や、特定の業務(発注業務など)を任せられるベテランスタッフが必要な場合など、単純な頭数だけではシフトを組めない現実があります。
2.3 急な遅刻や休みに対応できない
スタッフの急な体調不良や家庭の事情、あるいは寝坊といった予期せぬ欠勤や遅刻への対応も、シフト管理者を悩ませる大きな問題です。 特に、深夜帯など2名体制といった最低限の人数で店舗を運営している時間帯に一人が欠勤すると、残された一人がすべての業務をこなさなければならない「ワンオペ」状態に陥ってしまいます。
そうなると、レジが長蛇の列になったり、品出しや清掃が滞ったりと、店舗のサービス品質が著しく低下します。 防犯上のリスクも高まり、残されたスタッフの身体的・精神的負担は計り知れません。代わりに出勤できるスタッフを探そうにも、休日にはプライベートな予定を入れていることが多く、急なヘルプ依頼に応じてくれるとは限りません。 結局、休日を返上して店長やオーナーが出勤せざるを得ない状況に追い込まれることも少なくないのです。
3. コンビニには固定シフトと自由シフトがある

コンビニのシフトは、店舗のオーナーや店長の方針によって大きく異なり、主に「固定シフト」と「自由シフト」の2種類に分けられます。 店舗によっては、曜日や時間がある程度決まっている固定シフト制を採用している場合もあれば、スタッフの希望に応じて柔軟にシフトを組む自由シフト制(希望シフト制)を導入している場合もあります。 どちらの働き方が自分に合っているか、それぞれの特徴を理解することが重要です。
3.1 曜日や時間を固定する「固定シフト」
固定シフトとは、毎週決まった曜日・時間帯に勤務する働き方です。 例えば、「毎週月曜日と水曜日の9時から17時まで」というように、勤務スケジュールがあらかじめ定められています。多くのコンビニで採用されている一般的な形態です。
3.1.1 固定シフトのメリット
固定シフトには、働く従業員側とシフトを管理する店舗側の双方にメリットがあります。
3.1.1.1 従業員側のメリット
- 収入が安定しやすい:毎月の勤務時間がある程度決まっているため、収入の見通しが立てやすく、安定した給料を得やすいのが大きな利点です。
- 生活リズムが整う:勤務日時が固定されているため、生活リズムを一定に保ちやすく、プライベートの予定も計画的に立てられます。
3.1.1.2 管理者側のメリット
- シフト管理がしやすい:毎回のシフト調整の手間が少なく、人員配置が計画的に行えるため、シフト作成の負担が軽減されます。
- スタッフの教育がしやすい:同じ時間帯に同じメンバーが働くことが多いため、新人スタッフへの教育や業務の引き継ぎがスムーズに行えます。
3.1.2 固定シフトのデメリット
一方で、固定シフトにはデメリットも存在します。
3.1.2.1 従業員側のデメリット
- 急な予定に対応しにくい:勤務日が決まっているため、急な用事や学業の都合などで休みを取りたい場合に、代わりのスタッフを探すなど調整が難しいことがあります。
- 柔軟性に欠ける:テスト期間や家庭の事情などで一時的に勤務時間を変更したい場合でも、融通が利きにくい可能性があります。
3.1.2.2 管理者側のデメリット
- 人材が集まりにくい場合がある:働ける曜日や時間帯が限られている学生や主婦(夫)層は応募しにくく、人材確保の面で不利になることがあります。
- 急な欠員に対応しにくい:スタッフが急に休んだ場合、代わりに入れるスタッフが限られるため、人手不足に陥りやすい側面があります。
3.2 希望に沿ってシフトを組む「自由シフト」
自由シフト(希望シフト制)とは、一定期間ごと(例:1週間ごと、2週間ごと、1ヶ月ごと)にスタッフから勤務可能な日時を提出してもらい、それをもとに店長がシフトを作成する働き方です。
3.2.1 自由シフトのメリット
自由シフトは、特にプライベートを重視したい働き手にとって魅力的な制度です。
3.2.1.1 従業員側のメリット
- プライベートと両立しやすい:自身の予定に合わせて勤務希望を出せるため、学業やサークル活動、家庭の用事、ダブルワークなどとの両立がしやすいのが最大のメリットです。
- 柔軟な働き方が可能:「今月は多めに働きたい」「来月はテスト期間なので少なめに」といった調整がしやすく、自分のペースで働くことができます。
3.2.1.2 管理者側のメリット
- 幅広い人材を確保しやすい:働く時間や曜日に制約がある学生や主婦(夫)なども応募しやすいため、多様な人材を確保できる可能性があります。
- 繁閑に応じて人員を調整しやすい:セール期間やイベント時など、特定の日に多くの人員が必要な場合に、柔軟にスタッフを配置することが可能です。
3.2.2 自由シフトのデメリット
柔軟性が高い一方で、管理の難しさや収入の不安定さといったデメリットもあります。
3.2.2.1 従業員側のデメリット
- 収入が不安定になりやすい:希望通りにシフトに入れない月があると、収入が大きく変動する可能性があります。特に、他のスタッフと希望が重なった場合、勤務時間が削られることがあります。
- 希望が必ず通るとは限らない:応募者が多い時間帯や、逆に希望者が少ない時間帯があるため、必ずしも自分の希望通りにシフトに入れるわけではありません。
3.2.2.2 管理者側のデメリット
- シフト作成の負担が大きい:スタッフ全員の希望を取りまとめ、各時間帯で必要な人数を確保し、スキルのバランスも考慮しながらシフトを組むため、非常に手間と時間がかかります。
- 人手が不足する時間帯が出やすい:人気のない早朝や深夜、あるいは特定の曜日に希望者が集まらず、人手不足が発生しやすくなるリスクがあります。
3.3 【比較表】固定シフトと自由シフト、どちらが向いている?
自分や自分の店舗にどちらのシフト形態が合っているのか、以下の表で比較してみましょう。
| 視点 | 固定シフト | 自由シフト(希望シフト制) |
|---|---|---|
| 従業員のメリット | ・収入や生活リズムが安定する ・先の予定が立てやすい |
・プライベートの予定と両立しやすい ・自分のペースで働ける |
| 従業員のデメリット | ・急な予定変更が難しい ・働き方の柔軟性に欠ける |
・収入が不安定になりやすい ・希望通りにシフトに入れないことがある |
| 管理者のメリット | ・シフト管理の負担が少ない ・計画的な人員配置と教育が可能 |
・幅広い層の人材を確保しやすい ・繁閑に応じた人員調整が可能 |
| 管理者のデメリット | ・特定の層(学生など)が集まりにくい ・急な欠員に対応しにくい |
・シフト作成の手間が大きい ・時間帯によって人手が偏りやすい |
4. シフト作成の前に│コンビニが忙しい時間帯はいつ?
適切なシフトを組むためには、まず店舗がどの時間帯に忙しくなるのかを正確に把握することが不可欠です。コンビニの忙しさは、店舗の立地や周辺環境、さらには曜日やイベントの有無によって大きく変動します。来客数のピークを予測し、必要な人員を配置することで、お客様を待たせることなく、スムーズな店舗運営が可能になります。
4.1 立地別のピークタイムと特徴
コンビニが最も混雑する時間帯は、そのお店がどこにあるかによって大きく異なります。ここでは、代表的な立地ごとのピークタイムと、それに伴う客層や売れ筋商品の特徴を解説します。
4.1.1 ビジネス街・駅ナカの店舗
ビジネス街や駅の構内にある店舗では、人々の通勤・通学や帰宅の動線上に位置するため、平日の朝と夕方が主なピークタイムとなります。 朝の7時から9時にかけては、出勤前の会社員や学生が朝食のおにぎりやパン、コーヒーなどを求めて殺到します。 お昼の12時から13時も、昼食を買い求める人々でレジには長い列ができるでしょう。 そして夕方17時以降は、帰宅途中の人々がお弁当や飲み物、雑誌などを購入していくため、再び混雑します。
4.1.2 住宅街の店舗
住宅街にある店舗は、地域住民の生活リズムに密着した売れ方をします。平日の朝は通勤・通学前の人々で一時的に混み合いますが、日中は比較的落ち着いていることが多いです。夕方になると、仕事帰りの人や夕食の材料を買い足す主婦などで再び客足が増えます。週末や祝日は、家族連れの来店が増え、一日を通して比較的忙しくなる傾向があります。
4.1.3 幹線道路沿いの店舗
トラックや乗用車のドライバーが多く利用する幹線道路沿いの店舗は、他の立地とは異なる特徴を持ちます。特に長距離ドライバーの利用が多いため、深夜から早朝にかけても客足が途絶えにくいです。お弁当や飲料、タバコ、眠気覚ましのガムや栄養ドリンクなどがよく売れます。また、大型駐車場を備えている店舗では、休憩場所としての需要も高まります。
4.1.4 大学・専門学校近くの店舗
学校の近くにある店舗は、学生の行動パターンに大きく左右されます。 講義が始まる前の時間帯、昼休み、そして講義が終わる16時から18時頃が最も忙しくなります。 一方で、夏休みや春休みといった長期休暇中は学生の利用が激減するため、比較的落ち着いた営業になります。
4.2 曜日やイベントによる変動
立地だけでなく、曜日や特定のイベントも来客数に大きく影響します。これらの変動要因を事前に予測し、シフトに反映させることが重要です。
| 曜日・イベント | 主な傾向 | 特に注意すべき業務 |
|---|---|---|
| 平日 | 朝・昼・夕方のピークがはっきりしている。 通勤・通学客が中心。 | ピーク時の迅速なレジ対応、弁当・おにぎりの品出し。 |
| 土日・祝日 | 家族連れやレジャー客が増え、日中の来店が多い。 ピーク時間が長く続く傾向がある。 | お菓子やアイス、飲料の補充。行楽向け商品の管理。 |
| 給料日後(特に週末) | 客単価が上がりやすい。お弁当やお惣菜、スイーツなどの「プチ贅沢」商品の需要が高まる。 | フライヤー商品の調理・補充、デザート類の在庫確認。 |
| 大型連休(GW、お盆、年末年始) | 帰省客や旅行客の利用が増え、年間でも特に忙しい時期となる。 | お土産品の管理、ATM利用者の案内、通常と異なる商品の発注。 |
| 近隣でのイベント開催日 | コンサートやお祭りなどがあると、イベント前後に来客が集中する。 | 飲料や軽食の大量補充、トイレ清掃の頻度増加、店舗周辺の整理。 |
4.3 時間帯別の主な業務内容
来客数の波に合わせて、コンビニでは時間帯ごとに異なる業務が発生します。シフトを組む際は、単に必要な人数だけでなく、「その時間帯に何をするのか」を理解しておくことが、より効率的な人員配置につながります。
4.3.1 早朝(6:00~9:00)
通勤・通学ラッシュに対応するレジ業務がメインです。 それと同時に、配送されたばかりの弁当やおにぎり、サンドイッチなどを急いで品出しする必要があります。 レジ横のホットスナックの準備や新聞の陳列もこの時間帯の重要な業務です。
4.3.2 日中(9:00~17:00)
お昼のピークを過ぎると、客足は一度落ち着きます。 この時間帯は、商品の前出し(奥にある商品を前に出して棚をきれいに見せる作業)や発注業務、店内の清掃など、店舗の基本を維持するための作業が中心となります。 午後には主婦や高齢者のお客様が増え、公共料金の支払いや宅配便の受付といったサービスカウンター業務も多くなります。
4.3.3 夕方~夜(17:00~22:00)
帰宅ラッシュで再び店内は賑わいます。 夕食のおかずとしてフライヤー商品や惣菜がよく売れるため、調理と補充が頻繁に必要です。酒類の販売も増える時間帯であり、年齢確認の徹底が求められます。また、雑誌の発売日には、返本作業と新刊の陳列が重なることもあります。
4.3.4 深夜(22:00~翌6:00)
客足は少なくなりますが、仕事がなくなるわけではありません。 この時間帯は、日中にできない業務を行う貴重な時間です。翌日の朝刊や雑誌の準備、飲料やお菓子などの大量の商品が納品されるため、その検品と品出し作業が主な業務となります。 また、床のモップがけや什器の拭き掃除、フライヤーの油交換など、大掛かりな清掃も深夜に行われます。
5. コンビニのシフト管理のポイントは?
年中無休・24時間営業が基本のコンビニでは、安定的かつ効率的な店舗運営のために、適切なシフト管理が不可欠です。しかし、従業員の希望と店舗の必要人員を両立させるのは容易ではありません。ここでは、コンビニのシフト管理を円滑に進めるための具体的なポイントを、多角的な視点から詳しく解説します。
5.1 早めにシフトを組む
スタッフが抱える不満の中でも特に多いのが「シフトの確定が遅い」ことです。シフトがなかなか決まらないと、プライベートの予定が立てられず、従業員の満足度低下や離職につながる可能性があります。 スムーズな店舗運営のためにも、シフトはできる限り早く作成し、共有することが重要です。
具体的な取り組みとして、以下のようなルールを設けると良いでしょう。
- 希望シフトの提出期限を設ける:「翌月のシフト希望は当月15日まで」のように、明確な期限を設定し、全スタッフに周知徹底します。
- シフトの公開日を約束する:「毎月25日には翌月のシフトを公開する」といった目標を掲げ、それを守ることで、スタッフは安心して予定を組むことができます。
- 未確定部分があってもまずは共有する:すべてのシフトが埋まっていなくても、確定している部分だけでも先行して共有しましょう。 不足している箇所は、その後改めて調整を呼びかけることで、全体の遅延を防ぎます。
5.2 前もって出勤可能な時間帯を聞いておく
急な体調不良や家庭の事情による欠勤は、どの店舗でも起こり得ます。 特に、2名体制など最低限の人数で運営している時間帯に欠員が出ると、店舗運営に大きな支障をきたします。 そんな時、全スタッフに片っ端から連絡するのは非効率です。
こうした事態に備え、通常のシフト希望とは別に「緊急時に出勤可能な曜日や時間帯」を事前にヒアリングしておきましょう。 これにより、ヘルプをお願いできる可能性のあるスタッフに絞って、迅速に連絡を取ることが可能になります。 定期的な面談の際や、アンケート形式で情報を収集し、リスト化しておくと、いざという時に慌てずに対応できます。
5.3 スタッフのスキルを考慮して人員を配置する
円滑な店舗運営のためには、単に必要な人数を配置するだけでなく、各スタッフのスキルレベルを考慮することが極めて重要です。例えば、新人スタッフばかりの時間帯を作ってしまうと、複雑な問い合わせやトラブルに対応できず、お客様に迷惑をかけてしまう可能性があります。また、発注やレジ点検など、特定のスキルが求められる業務もあります。
そこで、スタッフ一人ひとりのスキルを可視化する「スキルマップ」の作成をおすすめします。これにより、各時間帯において必要なスキルを持つスタッフがバランス良く配置されているかを確認できます。
| スタッフ名 | レジ操作 | フライヤー調理 | 商品発注 | 新人教育 |
|---|---|---|---|---|
| Aさん(ベテラン) | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 |
| Bさん(中堅) | ◎ | 〇 | △ | △ |
| Cさん(新人) | 〇 | △ | ✕ | ✕ |
(記号の意味:◎:指導できる、〇:一人でできる、△:補助があればできる、✕:できない)
このようなスキルマップを活用し、ベテランと新人を組み合わせることで、業務の安定化と同時に、新人スタッフのOJT(On-the-Job Training)の機会を創出できます。
5.4 労働基準法を遵守したシフトを作成する
シフトを作成する上で、労働基準法の遵守は絶対条件です。法令違反は、従業員とのトラブルや企業の信頼失墜に繋がります。特に以下の点には注意が必要です。
| 項目 | 規定内容 |
|---|---|
| 法定労働時間 | 原則として、1日8時間、週40時間を超えて労働させてはならない。 |
| 休憩時間 | 労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければならない。 |
| 休日 | 原則として、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない(週休制の原則)。 |
| 深夜労働 | 午後10時から午前5時までの労働には、25%以上の割増賃金(深夜手当)を支払う必要がある。 |
店舗の状況によっては、「変形労働時間制」の導入を検討することも有効ですが、そのためには労使協定の締結など所定の手続きが必要です。 意図せず法令違反とならないよう、正しい知識を持ってシフトを作成することが求められます。
5.5 シフト管理ツールでシフト作成を効率化する
紙やエクセルでのシフト管理は、転記ミスや計算間違いが起こりやすく、作成に多くの時間を要します。 これらの課題を解決し、シフト管理業務を大幅に効率化するのが「シフト管理ツール」です。
シフト管理ツールを導入することで、以下のようなメリットが期待できます。
- 時間と手間の削減:スタッフはスマートフォンアプリなどから直接希望シフトを提出でき、管理者はそれを自動で集約できます。 これにより、転記作業が不要になり、作成時間を大幅に短縮できます。
- ミスの防止:労働時間や人件費の自動計算機能により、手作業によるミスを防ぎます。 法令遵守をサポートするアラート機能を持つツールもあります。
- 円滑なコミュニケーション:急な欠員が出た際に、ヘルプ募集を一斉に通知できる機能など、スタッフとのコミュニケーションを円滑にする仕組みが備わっています。
- リアルタイムでの状況把握:Webシステムを利用するツールなら、店舗外からでも人員の過不足状況やシフトをリアルタイムで確認できます。
様々なシフト管理ツールが存在するため、自店舗の規模やスタッフ数、必要な機能などを考慮し、最適なツールを選ぶことが重要です。
6. まとめ
本記事では、コンビニのシフト管理における悩みと、その解決策を解説しました。人手不足や従業員の希望調整といった課題は、固定・自由シフトの特性を理解し、店舗が忙しい時間帯を把握することで対応しやすくなります。円滑な店舗運営のためには、シフトを早めに組み、事前に希望を聞くことが重要です。また、近年ではシフト管理ツールを導入することで、作成業務を大幅に効率化できます。これらのポイントを押さえ、従業員が働きやすい環境を整えましょう。
product関連するプロダクト
-

HRBESTハーベスト
HRBESTは、「組み合わせ最適化」を用いたアルゴリズムを用いて複雑なシフトを一瞬で作成できるシフト自動作成AIクラウドです。シフト作成時間を77.5%削減(導入ユーザーの平均削減時間)。2か月無料、サポート費用もなしでAI機能がついて月額15,000円からご利用頂けます。

TRYETING
公式
TRYETING公式です。
お知らせやIR情報などを発信します。