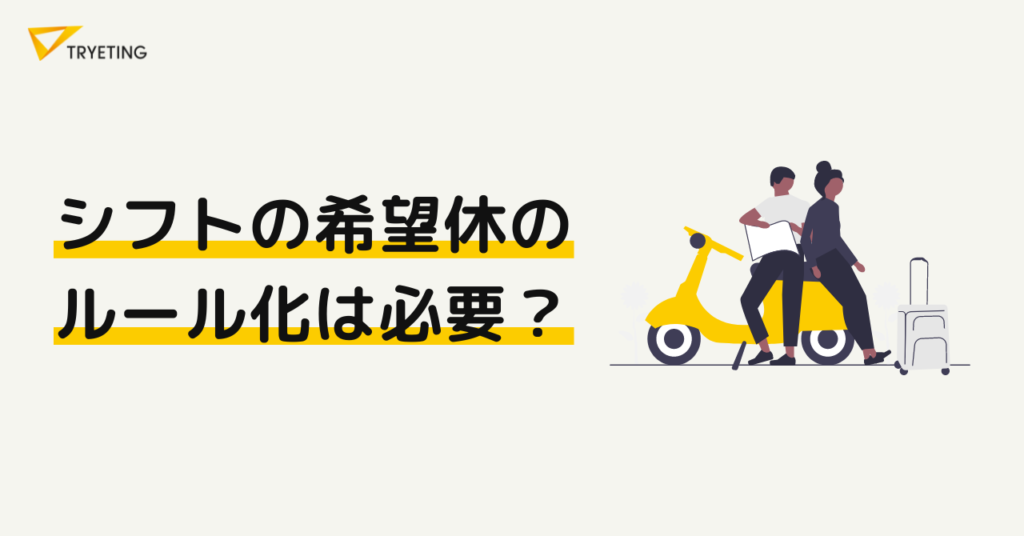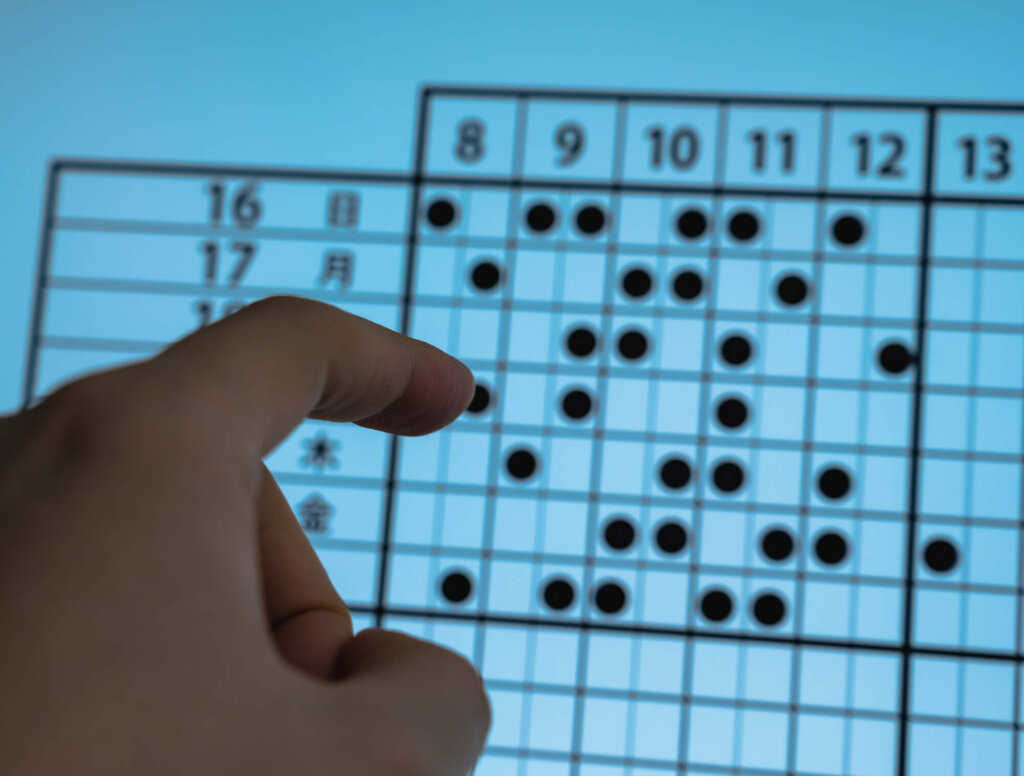WORK
年末調整しないとどうなる?デメリットや罰則、忘れた時の対処法を徹底解説

目次
「年末調整の書類が面倒…」「もし忘れたらどうなるの?」と不安に思っていませんか。年末調整をしないと、払いすぎた所得税が戻ってこないだけでなく、翌年の住民税が高くなるなど、金銭的なデメリットが発生します。この記事では、年末調整をしない場合に起こる5つのデメリットから、忘れた・間に合わなかった場合の対処法、確定申告との違いまでを分かりやすく解説。あなたの疑問や不安をスッキリ解消します。
▼面倒なシフト作成をAIで自動化
シフト自動作成AIクラウドHRBEST紹介ページ
1. そもそも年末調整とは?確定申告との違いをわかりやすく解説
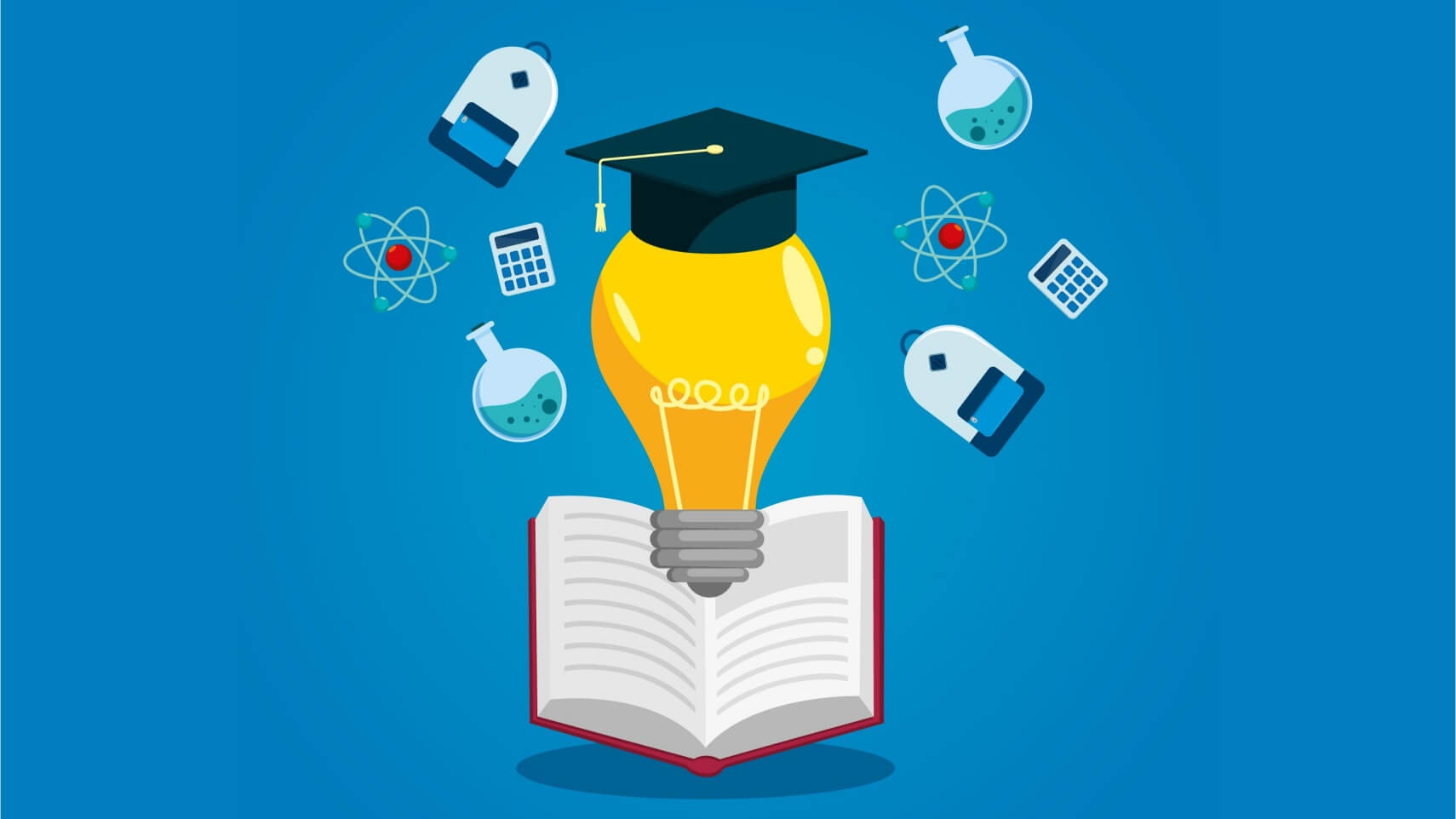
年末調整は、会社員などの給与所得者にとって非常に重要な手続きです。しかし、「毎年なんとなく書類を提出しているけれど、実はよくわかっていない」という方も多いのではないでしょうか。この章では、年末調整の基本的な目的や仕組み、そして混同されがちな確定申告との違いについて、わかりやすく解説します。
1.1 年末調整の目的と仕組み
年末調整の最も大きな目的は、毎月の給与から天引き(源泉徴収)されてきた所得税の1年間の合計額と、その年に納めるべき正しい所得税額(年税額)との差額を精算することです。会社員の場合、毎月の給与や賞与から所得税が天引きされていますが、この金額はあくまで概算です。
そのため、1年間の給与総額が確定する年末のタイミングで、扶養家族の状況や生命保険料の支払いといった個人の事情を反映して正しい税額を計算し直し、過不足を調整する必要があります。これが年末調整です。
この手続きにより、源泉徴収された金額が本来納めるべき税額より多ければ、その差額が「還付金」として戻ってきます。逆に少なければ、追加で徴収されることになります。多くの給与所得者は、年末調整を行うことで納税が完了するため、原則として個人で確定申告を行う手間が省けるという大きなメリットがあります。
年末調整は、具体的に以下のような流れで行われます。
- 従業員が会社から配布された申告書(扶養控除等申告書、保険料控除申告書など)に必要事項を記入し、各種証明書を添付して会社に提出する。
- 会社が提出された書類をもとに、従業員一人ひとりの年間の所得税額を正確に計算する。
- すでに源泉徴収した合計額と、確定した年税額との差額を計算する。
- 差額をその年最後の給与(通常は12月分)で調整(還付または追加徴収)する。
年末調整では、以下のような各種控除が適用されることで、税金の負担が軽減されます。
| 控除の種類 | 概要 |
|---|---|
| 基礎控除 | 合計所得金額に応じて、すべての納税者に適用される控除 |
| 配偶者控除・配偶者特別控除 | 配偶者の所得が一定額以下の場合に適用される控除 |
| 扶養控除 | 生計を同じくする扶養親族がいる場合に適用される控除 |
| 保険料控除 | 生命保険料、地震保険料、社会保険料などを支払った場合に適用される控除 |
| 住宅借入金等特別控除 | 住宅ローンを利用してマイホームを取得した場合に適用される控除(2年目以降) |
これらの控除を正しく申告することで、課税対象となる所得を減らし、結果的に納める税金を少なくすることができます。
1.2 年末調整と確定申告の根本的な違い
年末調整と確定申告は、どちらも1年間の所得に対する税額を確定させる手続きという点では共通していますが、その目的や対象者、手続きの方法に明確な違いがあります。
年末調整は、会社が従業員に代わって所得税の過不足を精算する手続きです。これに対し、確定申告は、納税者本人が自らの所得とそれに対する税額を計算し、税務署に申告・納税する手続きを指します。つまり、手続きを行う主体が「会社」なのか「個人」なのかが大きな違いです。
両者の主な違いを以下の表にまとめました。
| 項目 | 年末調整 | 確定申告 |
|---|---|---|
| 手続きする人 | 勤務先の会社 | 納税者本人 |
| 対象者 | 主に給与所得者(一部例外あり) | 個人事業主、不動産所得がある人、年末調整の対象外の人、特定の控除を受けたい人など |
| 時期 | その年の最後の給与が支払われる時期(11月~翌年1月頃) | 原則、翌年の2月16日~3月15日 |
| 対象となる所得 | その会社から支払われた給与所得のみ | 給与所得、事業所得、不動産所得など、すべての所得が対象 |
| 適用できる主な控除 | 生命保険料控除、扶養控除、住宅ローン控除(2年目以降)など | 年末調整で適用できる控除に加え、医療費控除、寄附金控除(ふるさと納税など)、住宅ローン控除(1年目)など |
会社員であっても、副業の所得が20万円を超える場合や、医療費控除を受けたい場合、住宅ローンを組んだ初年度など、年末調整だけでは手続きが完了しないケースでは、別途確定申告が必要になります。年末調整は、いわば会社員のための簡易的な税額確定手続きと考えると理解しやすいでしょう。
3. 【結論】年末調整をしないと起こる5つのデメリット
年末調整は、会社員にとって1年間の所得税を精算するための重要な手続きです。もし年末調整をしなかった場合、単に「忘れてしまった」では済まされない、金銭的にも手続き的にも大きなデメリットが生じる可能性があります。具体的には、払いすぎた税金が戻ってこない、翌年の住民税が高くなる、確定申告の手間が増えるといった問題が発生します。ここでは、年末調整をしないことで起こりうる5つの具体的なデメリットを詳しく解説します。
3.1 払いすぎた税金が戻ってこない(還付金の喪失)
毎月の給与から天引きされている所得税(源泉徴収税額)は、あくまで概算の金額です。そのため、年間の給与総額が確定した段階で計算し直すと、本来納めるべき税額よりも多く支払っているケースがほとんどです。 年末調整は、この払いすぎた税金(過払い分)を精算し、還付金として受け取るための手続きです。
年末調整を行わないと、生命保険料控除、地震保険料控除、扶養控除、あるいは2年目以降の住宅ローン控除といった、各種控除が適用されません。 これらの控除が適用されないと、課税対象となる所得が減らないため、結果的に払いすぎた税金が戻ってこず、大きな損をしてしまうことになります。 人によっては、数万円から数十万円の還付金を受け取れなくなる可能性もあります。
3.2 翌年の住民税が高くなる可能性がある
住民税は、年末調整の対象ではありませんが、その税額は前年の所得を基に計算されます。 年末調整で申告すべき扶養控除や社会保険料控除、生命保険料控除などが適用されないと、課税所得金額が本来よりも高い金額で市区町村に報告されてしまいます。その結果、翌年6月から徴収される住民税額が、本来よりも高くなってしまう可能性があるのです。 一度決定された住民税額を後から修正するには、別途手続きが必要となり手間がかかります。
3.3 自分で確定申告をする手間が発生する
多くの会社員が自分で確定申告をする必要がないのは、会社が年末調整を行ってくれるためです。 年末調整をしなかった場合、払いすぎた税金を取り戻したり、正しい税額を納めたりするためには、自分自身で確定申告をしなければなりません。
確定申告を行うには、源泉徴収票や各種控除証明書などの必要書類を揃え、自分で申告書を作成し、原則として翌年の2月16日から3月15日までの期間内に税務署へ提出する必要があります。 会社に書類を提出するだけで完了する年末調整に比べ、確定申告は非常に手間と時間がかかる作業です。
3.3.1 確定申告も忘れるとどうなる?
年末調整をせず、さらに確定申告の義務があるにもかかわらず期限内に申告しなかった場合、「無申告」とみなされ、本来納めるべき税金に加えてペナルティとして重い税金が課される可能性があります。
3.3.1.1 無申告加算税や延滞税などのペナルティ
確定申告を期限までに行わなかった場合、以下のようなペナルティが課せられます。
| ペナルティの種類 | 内容 |
|---|---|
| 無申告加算税 | 期限内に申告しなかったことに対する罰金。原則として、納付すべき税額の50万円までは15%、50万円を超える部分は20%が加算されます。 ただし、税務署の調査を受ける前に自主的に申告すれば5%に軽減されます。 |
| 延滞税 | 法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて課される、利息に相当する税金です。 納付が遅れるほど金額は増えていきます。 |
| 重加算税 | 意図的に所得を隠蔽するなど、特に悪質と判断された場合に課される最も重いペナルティ。無申告加算税に代えて、納付すべき税額の40%が課されます。 |
これらの追徴課税は、本来支払う必要のないお金であり、大きな金銭的損失につながります。
3.4 所得証明書・課税証明書の発行が遅れる
所得証明書や課税証明書といった公的な証明書は、市区町村が年末調整や確定申告で報告された所得情報に基づいて発行します。 年末調整が行われないと、あなたの所得情報が市区町村へ正しく連携されず、これらの証明書の発行が遅れたり、すぐに発行できなかったりする場合があります。
これらの証明書は、住宅ローンの審査、賃貸契約、子どもの保育園の入園手続き、奨学金の申請など、生活の様々な場面で必要となります。いざという時に証明書がすぐに取得できないと、手続きが滞ってしまう可能性があります。
3.5 会社に迷惑がかかることも
従業員の年末調整を行うことは、所得税法で定められた会社の義務です。 従業員が必要な書類を提出しないと、経理や人事の担当者は何度も催促する必要があり、担当者の業務負担を増やすことになります。また、会社全体の年末調整スケジュールに遅れが生じ、税務署への法定調書の提出といった会社の義務の履行にも影響を及ぼす可能性があります。 適切な手続きに協力しないことで、会社からの信頼を損なうことにもつながりかねません。
4. 年末調整の対象になる人・ならない人
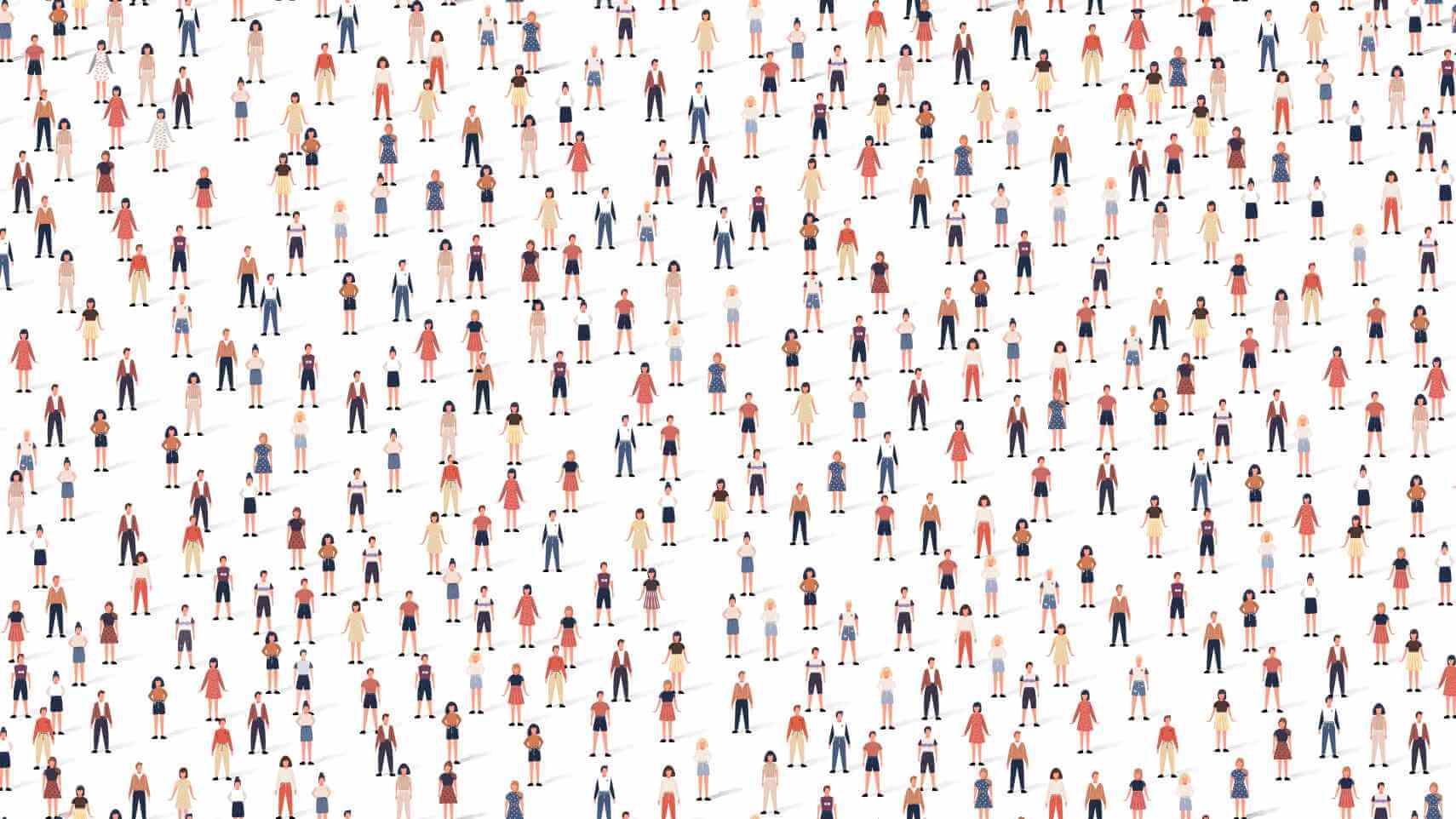
年末調整は、会社員や公務員などの給与所得者であれば誰もが必要な手続きだと思われがちですが、実はすべての人が対象になるわけではありません。ご自身が年末調整の対象者なのか、それとも対象外で確定申告が必要なのかを正しく理解しておくことが重要です。ここでは、年末調整の対象になる人とならない人の具体的な条件について詳しく解説します。
4.1 年末調整が必要な人(対象者)の条件
原則として、勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しており、その年の最後の給与の支払いを受ける日までに在籍している人が年末調整の対象となります。正社員だけでなく、パートやアルバイトといった雇用形態にかかわらず、以下の条件に当てはまる方が該当します。
- 1年を通じて同じ勤務先に勤めている人
- 年の途中で就職し、年末まで同じ勤務先に勤めている人
- 年の途中で海外の支店などから転勤し、年末まで国内の勤務先に勤めている人
また、年の途中で退職した場合でも、死亡によって退職したケースや、著しい心身の障害によって退職し年内の再就職が見込めないケース、12月分の給与を受け取った後に退職したケースなど、特定の条件下では年末調整の対象となります。
4.2 年末調整の対象外となるケース
一方で、特定の条件に当てはまる場合は年末調整の対象外となり、ご自身で確定申告を行う必要があります。主なケースは以下の通りです。
4.2.1 年収2,000万円を超える場合
その年の給与収入の総額が2,000万円を超える人は、年末調整の対象にはなりません。これは所得税法で定められており、高額所得者は医療費控除や寄附金控除(ふるさと納税など)を適用するケースが多く、年末調整では対応できないため、自身で確定申告を行うこととされています。会社からは年末調整が行われていない源泉徴収票が交付されるので、それをもとに確定申告の手続きを進める必要があります。
4.2.2 副業の所得が20万円を超える場合
主たる給与を一つの会社から受け取っている場合でも、副業による所得が年間で20万円を超える場合は確定申告が必要です。ここでいう「所得」とは、収入から必要経費を差し引いた金額を指します。例えば、フリーランスとしての業務委託であれば事業所得や雑所得となります。
ただし、副業がアルバイトやパートの場合は「給与所得」となり、原則として経費は認められません。そのため、給与の「収入」金額が20万円を超える場合に確定申告が必要となります。なお、2か所以上の会社から給与を受け取っている場合、年末調整は主たる給与の支払者である1社でしか行えません。従たる勤務先の給与収入と、その他の所得の合計が20万円を超える場合は、確定申告が必要になるので注意しましょう。
4.2.3 年の途中で退職し、再就職していない場合
その年の途中で会社を退職し、年末までに新しい会社に就職していない場合、年末調整は行われません。この場合、退職時に会社から受け取った源泉徴収票をもとに、自分で確定申告を行う必要があります。多くの場合、毎月の給与から天引きされていた所得税は多めに徴収されているため、確定申告(還付申告)をすることで払いすぎていた税金が戻ってくる可能性があります。この還付申告は、退職した翌年から5年間行うことができます。
もし、年内に再就職した場合は、新しい勤務先に前職の源泉徴収票を提出することで、前職の給与と合算して年末調整を行ってもらえます。
年末調整の対象者と対象外のケースをまとめると、以下のようになります。
| 項目 | 年末調整の対象になる人 | 年末調整の対象外となる人(確定申告が必要な場合あり) |
|---|---|---|
| 年収 | 給与収入が2,000万円以下の人 | 給与収入が2,000万円を超える人 |
| 副業 | 副業の所得が20万円以下の人 | 副業の所得が20万円を超える人 |
| 退職・就職 | 年末時点で会社に在籍している人 | 年の途中で退職し、年末時点で未就職の人 |
| 申告書の提出 | 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人 | 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人 |
5. 【状況別】年末調整を忘れた・間に合わなかった場合の対処法

年末調整の書類提出を忘れたり、期限に間に合わなかったりした場合でも、適切な対処法を知っていれば慌てる必要はありません。状況によって対応方法が異なりますので、ご自身のケースに合わせて最適な手続きを進めましょう。ここでは、3つの状況別に具体的な対処法を解説します。
5.1 会社の提出期限に間に合わなかった場合
まず考えられるのが、会社が定めた年末調整の書類提出期限に遅れてしまったケースです。この場合、すぐに諦めるのではなく、まずは会社の経理や人事の担当者に提出が遅れた旨を正直に伝え、まだ対応が可能かを確認しましょう。
5.1.1 1月末までなら会社での再調整が可能なことも
会社は、全従業員の年末調整の計算を取りまとめ、翌年の1月31日までに税務署へ「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」などを提出する義務があります。この法定の提出期限である1月末までであれば、会社側で年末調整の再計算に応じてもらえる可能性があります。
ただし、これはあくまで会社の厚意による対応であり、義務ではありません。社内での締め切りを過ぎた後の個別対応は、担当者に大きな負担をかけることになります。そのため、再調整を断られてしまうケースも少なくありません。いずれにせよ、期限に遅れたことに気づいた時点で、できるだけ早く担当部署に相談することが重要です。
5.2 会社で年末調整ができなかった場合
会社の担当者に相談したものの再調整が断られてしまった場合や、年の途中で退職して年末時点でどこにも在籍していない場合など、会社で年末調整が行われなかったケースでは、自分で確定申告を行う必要があります。
5.2.1 源泉徴収票をもらい自分で確定申告を行う
確定申告を行うことで、年末調整で受けられるはずだった所得控除(生命保険料控除や扶養控除など)を適用し、払い過ぎた所得税の還付を受けることができます。確定申告の手続きには、その年に勤務していた会社から交付される「源泉徴収票」が必ず必要になります。手元にない場合は、会社に依頼して必ず発行してもらいましょう。
確定申告と聞くと難しく感じるかもしれませんが、現在は国税庁のウェブサイト「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、画面の案内に従って入力するだけで申告書を作成でき、e-Tax(電子申告)で提出まで完結することも可能です。
5.2.1.1 確定申告の期間と必要なもの
確定申告の期間は、原則として所得があった年の翌年2月16日から3月15日までです。手続きには以下のものが必要となるため、事前に準備しておきましょう。
| 必要なもの | 概要・入手先など |
|---|---|
| 源泉徴収票 | その年に給与の支払いを受けた全ての会社から交付してもらいます。 |
| マイナンバーがわかる書類 | マイナンバーカード、または通知カードと運転免許証などの本人確認書類のセット。 |
| 各種控除証明書 | 生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書、iDeCoの掛金払込証明書など、適用したい控除に関する書類。 |
| 住宅ローン控除関係書類 | (該当者のみ)住宅借入金等特別控除申告書、金融機関が発行する年末残高等証明書など。 |
| 還付金の振込先口座情報 | 本人名義の金融機関の口座番号などがわかるもの(通帳やキャッシュカード)。 |
5.3 確定申告の期限も過ぎてしまった場合
「年末調整に間に合わず、うっかり確定申告の期限も過ぎてしまった」という場合でも、まだ税金を取り戻すチャンスは残されています。それが「還付申告」という手続きです。
5.3.1 5年以内なら「還付申告」で税金を取り戻せる
還付申告とは、払い過ぎた所得税を返してもらうための申告手続きのことです。給与から天引きされた源泉徴収税額が、本来納めるべき年間の所得税額よりも多い場合に、この手続きを行うことで差額が還付されます。
この還付申告は、対象となる年の翌年1月1日から5年間行うことができます。例えば、2024年分の所得に関する還付申告であれば、2025年1月1日から2029年12月31日までが提出期間となります。通常の確定申告期間(2月16日~3月15日)とは関係なく、期間内であればいつでも申告が可能です。また、期限後に申告したことによるペナルティ(延滞税など)も一切ありません。過去5年分まで遡って申告できるため、過去に年末調整を忘れた年がないか確認してみるのもよいでしょう。
6. 年末調整に関するよくある質問
年末調整の時期になると、様々な疑問が浮かんでくるものです。ここでは、特に多くの方が疑問に思う点について、具体的なケースを交えながら分かりやすく解説します。
6.1 パートやアルバイトでも年末調整は必要?
はい、パートやアルバイトであっても、一定の条件を満たす場合は年末調整の対象となります。 雇用形態にかかわらず、会社は従業員の年末調整を行う義務があるためです。
ただし、次のようなケースでは年末調整の対象外となることがあります。
- 年の途中で退職し、再就職していない場合
- 年収が2,000万円を超える場合
- 2か所以上から給与を受け取っており、主たる給与以外の方の会社
- 給与の支払期間が2か月を超える場合(例:臨時雇用など)
これらに該当しない限り、パートやアルバイトでも会社が年末調整を行うのが原則です。
6.2 2か所以上で働いている場合はどうすればいい?
2か所以上で働いている、いわゆるダブルワークの場合、年末調整は最も給与が多い「主たる給与」を受け取っている1社でのみ行います。 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は1社にしか提出できません。
そのため、以下のような対応が必要になります。
| 項目 | 主たる給与の勤務先 | 従たる給与の勤務先 |
|---|---|---|
| 扶養控除等申告書の提出 | 提出する | 提出しない |
| 年末調整 | 行われる | 行われない |
| 確定申告 | 原則として、両方の給与を合算して自分で確定申告が必要 | 原則として、両方の給与を合算して自分で確定申告が必要 |
主たる勤務先での年末調整だけでは、従たる勤務先の所得が合算されていないため、正しい税額計算ができません。 従たる給与の収入が年間20万円を超える場合は、必ず確定申告をしましょう。 20万円以下であれば確定申告は原則不要ですが、住民税の申告は別途必要になる場合があります。
万が一、誤って2か所で年末調整を行ってしまった場合は、控除が重複してしまい、本来より納税額が少なくなってしまいます。 この場合、速やかに確定申告を行い、正しい税額を納める必要があります。
6.3 産休・育休中でも年末調整はするべき?
はい、産休・育休中であっても、その年の12月31日時点で会社に在籍していれば年末調整の対象となります。 その年に少しでも給与収入があれば、年末調整を行うことで、源泉徴収された税金が還付される可能性が高いです。
産休・育休中に受け取る以下の手当金や給付金は非課税所得のため、年末調整の計算には含まれません。
- 出産手当金
- 出産育児一時金
- 育児休業給付金
また、産休・育休中は給与収入が減少するため、ご自身の合計所得金額によっては、配偶者が配偶者控除や配偶者特別控除を受けられる場合があります。 忘れずに配偶者の勤務先で手続きをしてもらいましょう。
生命保険料控除や地震保険料控除、住宅ローン控除(2年目以降)なども、産休・育休中にかかわらず適用できるため、忘れずに申告することが大切です。
6.4 会社が年末調整をしてくれない場合は?
給与を支払う会社には、原則として年末調整を行う法的な義務があります。 もし会社が年末調整をしてくれない場合、まずは経理や人事の担当者に理由を確認しましょう。 設立間もない会社などで、担当者が年末調整の必要性を認識していないケースも考えられます。
それでも対応してもらえない場合は、以下の対処法があります。
- 自分で確定申告を行う
- 税務署に相談する
会社から「源泉徴収票」をもらい、自分で確定申告をすれば、年末調整と同様に所得税の精算ができます。 これが最も現実的な解決策です。払い過ぎた税金の還付も受けられます。
会社が源泉徴収票の発行にも応じないなど、悪質な場合は、所轄の税務署に相談しましょう。 税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を提出することで、税務署から会社へ指導が入ることがあります。 相談者の情報が会社に伝わることはありません。
年末調整をしないと、払い過ぎた税金が戻ってこないだけでなく、翌年の住民税が本来より高くなってしまうなどのデメリットがあります。 会社が対応してくれない場合でも、諦めずに適切な手続きを行いましょう。
7. まとめ
年末調整をしないと、払いすぎた所得税が戻ってこないだけでなく、翌年の住民税が高くなる可能性があります。さらに、自分で確定申告を行う手間が発生し、それも怠ると無申告加算税などのペナルティが課されることも。もし会社の期限に間に合わなくても、1月末までなら再調整できる場合や、確定申告で対応できます。確定申告期限後でも5年以内なら還付申告が可能です。損をしないためにも、忘れず手続きを行いましょう。
product関連するプロダクト
-

HRBESTハーベスト
HRBESTは、「組み合わせ最適化」を用いたアルゴリズムを用いて複雑なシフトを一瞬で作成できるシフト自動作成AIクラウドです。シフト作成時間を77.5%削減(導入ユーザーの平均削減時間)。2か月無料、サポート費用もなしでAI機能がついて月額15,000円からご利用頂けます。

TRYETING
公式
TRYETING公式です。
お知らせやIR情報などを発信します。