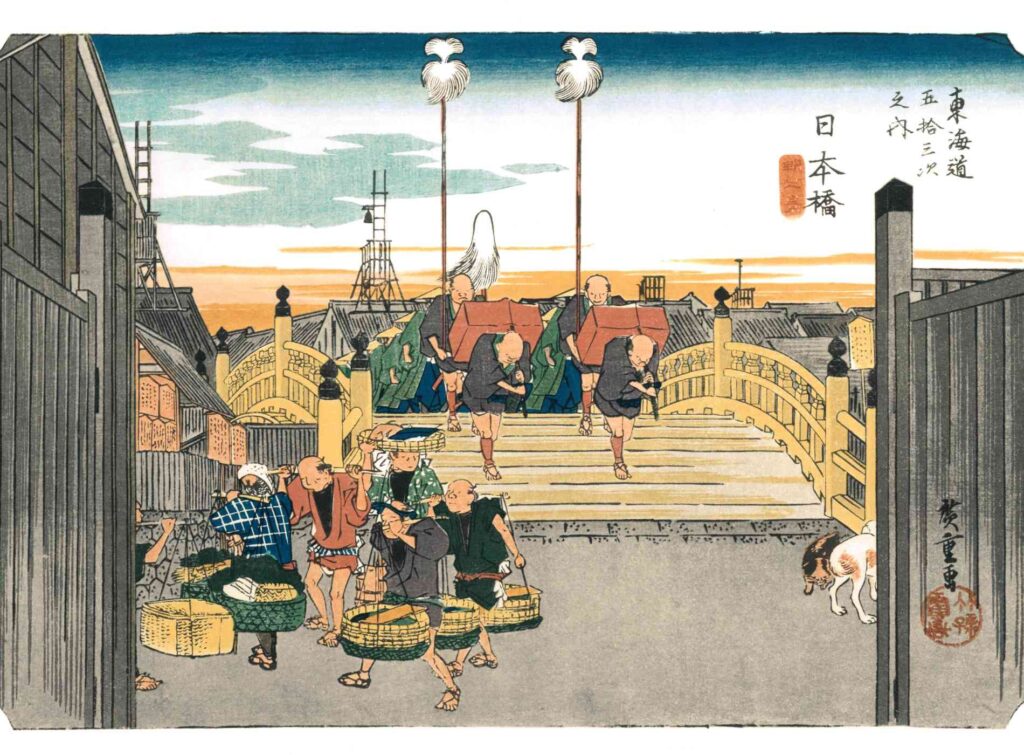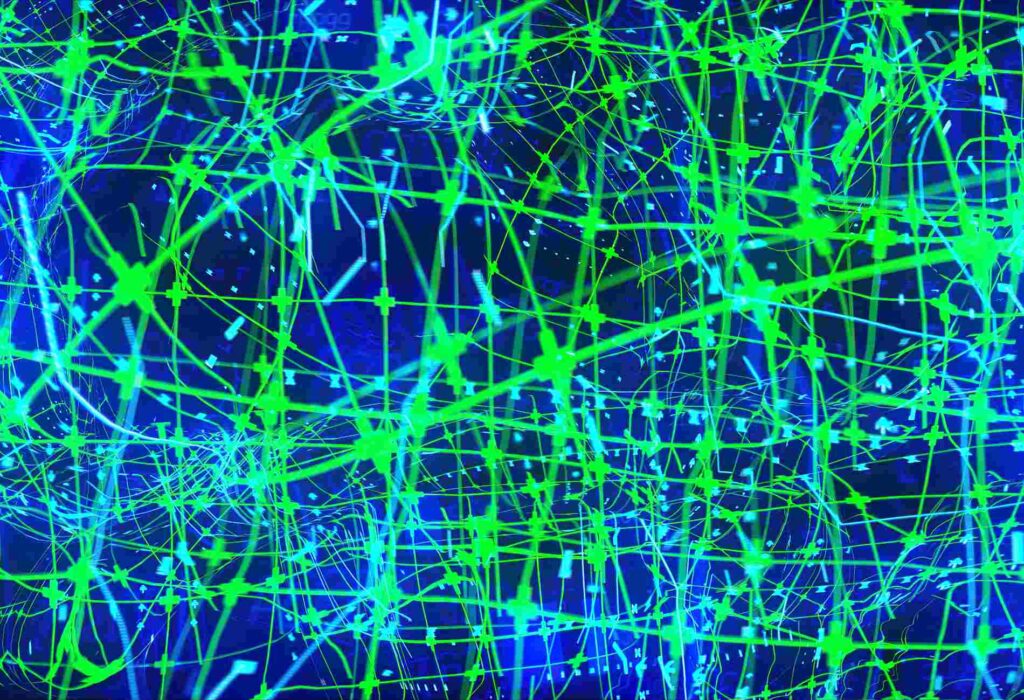BUSINESS
DXレポートとは?2025年の崖から最新版の要点までわかりやすく解説

目次
本記事では、経済産業省が発表した「DXレポート」について、初代から最新版までの要点を時系列でわかりやすく解説します。多くの企業が直面する「2025年の崖」の深刻な問題や、DXが進まない根本原因を明らかにし、課題解決に向けた具体的なアクションプランを提示。自社のDX推進の方向性を見定め、競争力を高めるためのヒントが得られます。
▼更にDXについて詳しく知るには?
DXとはどのようなもの?導入が求められる理由やメリット・デメリットを解説
▼社内のデータをAI化するには?
ノーコードAIツールUMWELT紹介ページ(活用事例あり)
1. DXレポートの概要と目的を理解する

DXレポートとは、経済産業省が日本企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)推進を目的として発表している一連の報告書です。2018年の最初のレポート発表以降、社会情勢やDXの進捗状況に合わせて改訂が重ねられており、多くの企業にとってDX戦略を考える上での重要な指針となっています。この章では、DXレポートがなぜ発表されたのか、その背景から最新版までの変遷と各レポートの要点をわかりやすく解説します。
1.1 経済産業省がDXレポートを発表した背景
経済産業省がDXレポートを発表した背景には、日本企業が直面する深刻な課題への強い危機感があります。グローバル市場では、デジタル技術を駆使した新しいビジネスモデルが次々と生まれ、産業構造そのものが大きく変化しています。しかし、多くの日本企業は既存の事業モデルや業務プロセスに固執し、この変化の波に乗り遅れているのが現状です。
特に、長年にわたって改修を繰り返してきた「レガシーシステム」は、複雑化・ブラックボックス化し、新しいデジタル技術の導入やデータ活用を阻む大きな足かせとなっています。このままでは国際競争力を失い、デジタル時代に取り残されてしまうという懸念から、経済産業省はDXの必要性と具体的な課題、そして解決策を提示するためにDXレポートの発表に至りました。
1.2 初代DXレポート(2018年)の要点
2018年9月に発表された最初のDXレポートは、正式名称を「DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~」といいます。このレポートは、日本企業が抱えるITシステムの課題を「2025年の崖」という衝撃的な言葉で表現し、社会に大きなインパクトを与えました。
レポートの要点は、「多くの企業で老朽化した既存システム(レガシーシステム)がDX推進の障壁となっており、この問題を2025年までに解決できなければ、最大で年間12兆円もの経済損失が生じる可能性がある」という強烈な警鐘です。データ活用の制約、保守運用のコスト増大、セキュリティリスクの高まりといった具体的な問題点を指摘し、企業に対して既存システムの刷新と、経営戦略に基づいたDXの本格的な展開を強く促しました。
1.3 DXレポート2(2020年)で示された新たな課題
初代レポートの発表から2年後の2020年12月、経済産業省は「DXレポート2(中間取りまとめ)」を公表しました。このレポートは、多くの企業がDXの重要性を認識しつつも、実際の変革が思うように進んでいない現状を踏まえて作成されました。
DXレポート2が新たに指摘した最大の課題は、企業におけるDXの本質的な理解不足です。多くの企業が、既存業務のデジタル化やITツールの導入といった部分的な取り組みを「DX」と捉えてしまい、ビジネスモデルや企業文化の変革にまで至っていない「DXごっこ」に陥っていると警鐘を鳴らしました。
成功のためには、経営層の強いリーダーシップのもと、事業部門が主体となって変革を推進する必要があるとし、技術的な課題だけでなく、組織やマインドセットの変革の重要性を強調しています。
1.4 DXレポート2.1・2.2(中間とりまとめ)のポイント
DXレポート2以降も、コロナ禍による社会のデジタル化加速や、DX推進における新たな課題の顕在化を受け、追補版としてレポートが発表されています。これまでのレポートの変遷とポイントを以下にまとめます。
| 発表時期 | レポート名 | 主なポイント |
|---|---|---|
| 2018年9月 | DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~ | 「2025年の崖」を提示し、レガシーシステム刷新の必要性を強調。 |
| 2020年12月 | DXレポート2(中間取りまとめ) | DXの本質的な理解不足と「DXごっこ」への警鐘。企業文化や組織変革の重要性を指摘。 |
| 2021年8月 | DXレポート2.1(DXレポート2追補版) | 個社の取り組みの限界を指摘。企業間連携による価値創出やデジタル産業の構築を提言。 |
| 2022年7月 | DXレポート2.2(概要) | DX推進の鍵となる「デジタル人材」の不足に焦点。人材の育成・確保の重要性を強調。 |
DXレポート2.1では、個々の企業の取り組みだけでは不十分であり、業界や企業間でデータを連携させ、新たな価値を創造していく「デジタル産業」への転換が不可欠であると提言されました。
続くDXレポート2.2では、DXを推進する上で最大のボトルネックとなっている「デジタル人材」の育成と確保に焦点を当て、リスキリングの重要性や人材の流動性を高める必要性を訴えています。このように、DXレポートは時代に合わせてその焦点を変えながら、日本企業が乗り越えるべき課題を継続的に示し続けています。
2. DXレポートが警鐘を鳴らす「2025年の崖」とは?
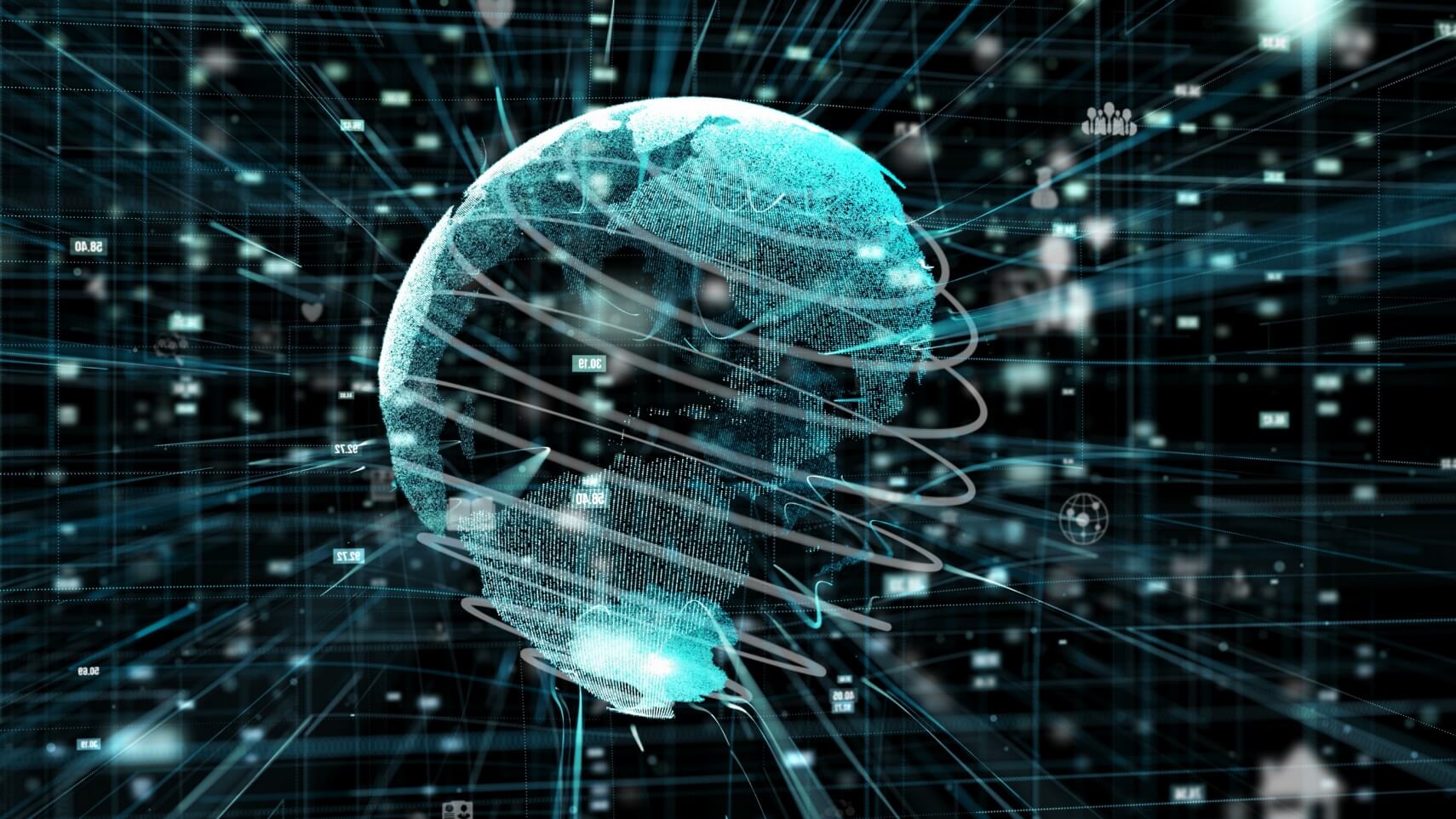
「2025年の崖」とは、2018年に経済産業省が発表した初代DXレポートで初めて提唱された、日本企業が直面する深刻なリスクを指す言葉です。多くの企業が抱える老朽化・複雑化した既存のITシステム(レガシーシステム)を刷新できずに放置した場合、2025年以降、デジタルトランスフォーメーション(DX)が実現できないだけでなく、多大な経済的損失を被る可能性があると警鐘を鳴らしています。
もし企業がこの課題を克服できなければ、市場の変化に追随できず、デジタル競争の敗者となるおそれがあります。この「崖」という強い言葉には、それほどまでに日本の産業界が危機的な状況にあるというメッセージが込められているのです。
2.1 2025年の崖がもたらす深刻な問題
では、具体的に「2025年の崖」はどのような問題を引き起こすのでしょうか。これは単なるITシステムの問題にとどまらず、事業継続そのものを脅かす複合的なリスクを含んでいます。DXレポートでは、主に以下の4つの深刻な問題が指摘されています。
2.1.1 レガシーシステムのブラックボックス化と技術的負債
多くの日本企業では、事業部門ごとのニーズに合わせてシステムを長年にわたり継ぎ足しでカスタマイズしてきた結果、システム全体が極めて複雑化・肥大化しています。このようなレガシーシステムは、当時の開発担当者の退職や関連ドキュメントの紛失などにより、内部構造を誰も把握できない「ブラックボックス」と化しているケースが少なくありません。
ブラックボックス化したシステムは、部分的な改修さえ困難であり、障害発生時の原因究明にも膨大な時間を要します。また、部門ごとにシステムが孤立(サイロ化)しているため、全社横断でのデータ活用や、新しいデジタル技術との連携も阻害されます。
こうした状況は、将来の成長のために投資すべきリソースを過去のシステム維持に費やさざるを得ない「技術的負債」として、企業の経営を圧迫し続けます。
2.1.2 IT人材の不足と保守運用のコスト増大
2025年の崖がもたらす問題は、システムだけでなく「人」にも及びます。レガシーシステムは、COBOLに代表される古いプログラミング言語で構築されていることが多く、これらの技術を扱えるエンジニアは高齢化し、次々と引退しています。その結果、システムの維持・保守ができる人材が枯渇するという深刻な事態が目前に迫っています。
一方で、AIやIoT、データサイエンスといったDX推進に不可欠な先端IT技術を持つ人材も慢性的に不足しています。DXレポートによれば、IT人材の不足は2025年には約43万人に拡大すると試算されています。貴重なIT人材をレガシーシステムの保守・運用に割かざるを得ないため、新しい価値を創造する「攻めのIT投資」にリソースを配分できず、IT予算の9割以上が既存システムの維持管理費(ラン・ザ・ビジネス)に消えていく可能性も指摘されています。
2.1.3 サイバーセキュリティリスクの増大
レガシーシステムを使い続けることは、深刻なサイバーセキュリティリスクを抱え込むことと同義です。古いシステムは、OSやミドルウェア、ハードウェアのメーカーサポートが終了している場合が多く、新たな脆弱性が発見されても修正パッチが提供されません。これは、いわば家の鍵をかけずに外出するようなもので、サイバー攻撃の格好の標的となります。
万が一、ランサムウェア攻撃や不正アクセスを受ければ、機密情報や個人情報の漏洩、工場の生産ラインや基幹システムの停止といった事業継続を揺るがす重大なインシデントに発展しかねません。自社だけでなく、サプライチェーンを構成する取引先にも被害が拡大する可能性があり、企業としての社会的信用を失墜させるリスクもはらんでいます。
2.1.4 国際競争力の低下と最大12兆円の経済損失
DXレポートが社会に最も大きな衝撃を与えたのが、具体的な経済損失額の試算です。レポートでは、もし日本企業がDXを実現できず「2025年の崖」を乗り越えられなかった場合、2025年以降、年間で最大12兆円もの経済損失が生じる可能性があると予測されています。
この損失は、既存システムの維持管理費の増大だけでなく、変化の激しい市場でビジネスチャンスを逃すことによって発生します。革新的なデジタル技術で既存の市場を破壊する「デジタルディスラプター」が登場しても、レガシーシステムに縛られた企業は迅速かつ柔軟な対応ができません。結果として、顧客や市場シェアを奪われ、国際的な競争力を失い、日本経済全体の停滞につながってしまうのです。以下の表は、2025年の崖がもたらす主要なリスクをまとめたものです。
| リスクの種類 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 経済的損失 | 2025年以降、年間最大12兆円の経済損失が発生する可能性。 |
| 競争力低下 | 市場の急激な変化に対応できず、デジタルディスラプターに敗北する。 |
| 技術的負債 | レガシーシステムの維持コストがIT関連費用の9割以上を占める可能性。 |
| 人材問題 | 先端IT人材が不足し、2025年には不足数が約43万人に達する見込み。 |
| セキュリティ | サポート切れのシステムがサイバー攻撃の標的となり、事業継続が困難になる。 |
3. なぜDXが進まないのか?DXレポートが指摘する日本企業の課題

DXレポートでは、「2025年の崖」を回避するためにDXの推進が不可欠であると説く一方で、多くの日本企業がDX推進の途上で壁に直面している実態も明らかにしています。DXが単なるITツールの導入に留まらず、ビジネスモデルや組織文化そのものの変革を求めるものであるからこそ、その障壁は根深く、多岐にわたります。ここでは、DXレポートが指摘する、日本企業が抱える代表的な課題を4つの側面に分けて詳しく解説します。
3.1 経営層のDXに対する理解不足とコミットメントの欠如
DX推進における最大の課題の一つが、経営層の理解不足とコミットメント(主体的な関与)の欠如です。DXレポート2では、多くの経営者がDXの必要性を認識しているものの、それを「やらされごと」として捉え、具体的な変革に繋げられていない実態が指摘されています。
具体的には、DXを単なるコスト削減や業務効率化の手段としか捉えられず、新たなビジネス価値を創出するための「戦略的投資」と認識できていないケースが少なくありません。短期的なROI(投資対効果)を重視するあまり、既存システムの刷新や新しいデジタル技術への投資といった、中長期的な視点が必要な判断を先送りにしてしまうのです。
また、DXの推進を情報システム部門に丸投げし、経営層自らがリーダーシップを発揮して全社的な改革を牽引しようとしない姿勢も大きな問題です。DXは事業部門を横断する全社的な取り組みであり、経営トップの強い意志と継続的なコミットメントがなければ、部門間の壁を乗り越え、企業文化を変革することは極めて困難です。
3.2 事業部門の縦割り意識と協力体制の不備
日本の多くの企業に根付いている「事業部門の縦割り意識」も、DXの推進を阻む大きな壁となっています。各事業部門が自部門の業務効率や目標達成を最優先する「部分最適」を追求した結果、組織全体としての一貫性や連携が失われているのです。
この縦割り構造は、システム面において「サイロ化」という問題を引き起こします。各部門が個別にシステムを導入・カスタマイズしてきたため、部門間でデータ形式や仕様が異なり、全社横断でのデータ収集・分析が困難になります。これでは、データに基づいた迅速な経営判断や、顧客への一貫したサービス提供は望めません。
DXレポートでは、こうした状況を打破するために、部門間の壁を取り払い、全社最適の視点で協力する体制を構築することの重要性が強調されています。しかし、既存の業務プロセスや組織の力学を変えることへの抵抗は大きく、多くの企業で協力体制の構築が進んでいないのが現状です。
3.3 既存システムの複雑化とベンダー企業への依存構造
長年にわたって運用されてきた既存システム(レガシーシステム)の存在も、DXの足かせとなっています。多くの企業では、過去の業務プロセスに合わせてシステムに改修を重ねてきました。その結果、システムは複雑怪奇な「スパゲッティ状態」となり、内部構造を誰も正確に把握できない「ブラックボックス化」が進んでいます。
このようなレガシーシステムは、いわば「技術的負債」となり、以下のような問題を引き起こします。
- 保守・運用コストの増大:システムの維持だけでIT予算の大部分を消費し、新しいデジタル技術への投資(攻めのIT投資)に資金を回せない。
- 柔軟性の欠如:ビジネス環境の変化に対応するための迅速なシステム改修や、新しいサービスとの連携が困難。
- データ活用の阻害:システムがサイロ化しているため、全社的なデータ活用基盤の構築を妨げる。
さらに、システムの構築や運用を特定のITベンダーに丸投げしてきた結果、企業内に技術的な知見やノウハウが蓄積されず、ベンダーに依存しきってしまう「ベンダーロックイン」の状態に陥っている企業も少なくありません。この依存構造は、企業が主体的にDX戦略を立案・実行する上で大きな障壁となります。
3.4 DXを推進する人材の不足と育成の遅れ
DXを実際に推進していく「人材」の不足も深刻な課題です。ここで言う人材とは、単にプログラミングができるITエンジニアだけを指すのではありません。DXレポートが指摘するのは、以下のような多様なスキルを持つ人材の不足です。
- ビジネスの課題を深く理解し、デジタル技術を活用して解決策を構想できる人材
- データ分析を通じて新たなビジネス価値を見出し、事業部門に提案できる人材
- 部門間の利害を調整し、変革プロジェクトを強力に牽引できるリーダー人材
多くの企業では、既存のIT人材はレガシーシステムの保守・運用に追われ、AIやIoTといった最新技術を学ぶ機会がありません。また、DX推進に必要なスキルを定義し、体系的な育成プログラムを整備できている企業もまだ少数です。
外部からの採用も、デジタル人材の獲得競争が激化しているため容易ではありません。結果として、DXを推進したくても「旗を振る人」も「実行する人」もいないという状況に陥ってしまうのです。
これらの課題は互いに複雑に絡み合っており、DXが進まない根本的な原因となっています。以下の表は、ここまで解説した課題を整理したものです。
| 課題の種類 | DXレポートが指摘する具体的な問題点 | 企業にもたらされる弊害 |
|---|---|---|
| 経営・組織 | ・経営層のコミットメント不足 ・DXをIT部門任せにする姿勢 ・縦割り組織による連携不足 |
・全社的な戦略が描けない ・迅速な意思決定ができない ・部門間のデータ活用が進まない |
| システム | ・レガシーシステムのブラックボックス化 ・過剰なカスタマイズによる複雑化 ・ベンダー企業への過度な依存 |
・保守運用コストの高騰 ・新しい技術を導入できない ・データがサイロ化し活用できない |
| 人材 | ・DX推進を担うリーダーの不在 ・ビジネスとITを繋ぐ人材の不足 ・育成体制の不備 |
・変革プロジェクトが頓挫する ・デジタル技術をビジネス価値に繋げられない ・イノベーションが生まれない |
4. 2025年の崖を乗り越えるためのDX推進アクションプラン
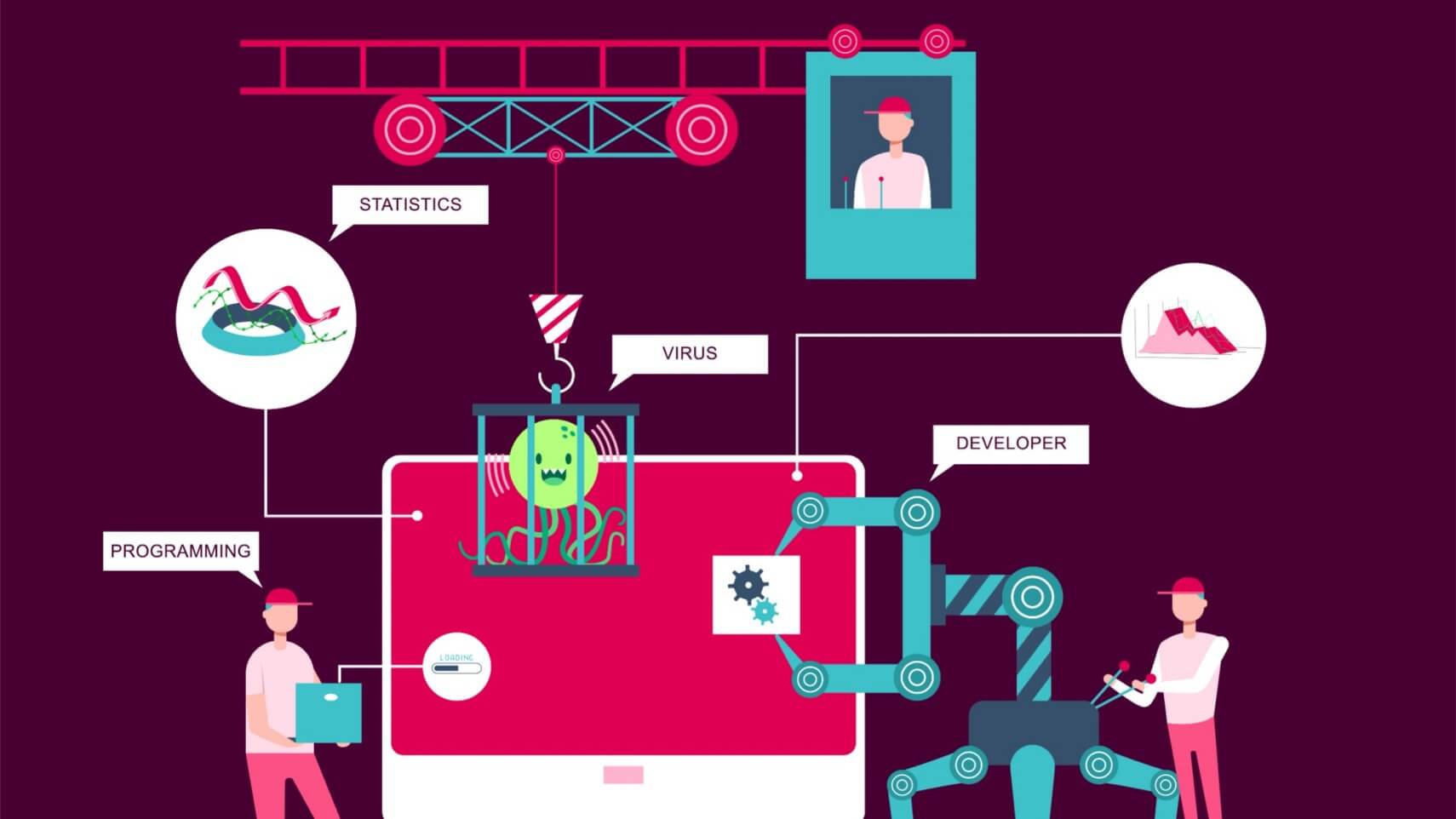
DXレポートが警鐘を鳴らす「2025年の崖」は、ただ待っていれば訪れる未来ではなく、企業が主体的に行動することで乗り越えられる課題です。しかし、やみくもにツールを導入するだけではDXは成功しません。ここでは、経済産業省の提言も踏まえ、企業が具体的に実行すべき4つのアクションプランを段階的に解説します。このプランは、自社の現状を正しく認識し、着実にDXを推進するためのロードマップとなります。
4.1 DX推進指標による現状分析と課題の可視化
DX推進の第一歩は、自社の立ち位置、すなわち「現在地」を客観的に把握することから始まります。そのために極めて有効なツールが、経済産業省が提供する「DX推進指標」です。この指標は、単なるITツールの導入状況を測るものではなく、「経営のあり方・仕組み」と「ITシステムの構築」の両面から、DXの成熟度を自己診断できるように設計されています。
自己診断を通じて、「ビジョン」「戦略」「人材」「組織」「システム」といった多角的な観点から、自社の強みと弱みを可視化します。これにより、DX推進における優先課題が明確になり、具体的なアクションプラン策定の強固な土台を築くことができます。
4.1.1 DX推進指標の主要な診断項目
DX推進指標は大きく9つの項目に分かれており、それぞれについて成熟度を評価します。以下にその一部を抜粋して紹介します。
| 分類 | 診断項目(例) | 診断のポイント |
|---|---|---|
| 経営のあり方、仕組み | ビジョン・ビジネスモデル | DXによってどのような新しい価値を生み出すか、具体的なビジョンが経営トップから明確に示されているか。 |
| 経営のあり方、仕組み | 戦略 | ビジョン実現のための具体的な戦略やロードマップが策定され、組織のKPIにまで落とし込まれているか。 |
| 経営のあり方、仕組み | 人材・組織 | DX推進に必要な人材の定義や育成・確保の計画、挑戦を促す組織文化が醸成されているか。 |
| ITシステムの構築 | 全社的なデータ利活用 | 部門横断でデータを収集・活用できる基盤が整備され、データに基づいた意思決定が行われているか。 |
4.2 経営戦略としてのDXビジョン策定
現状分析で課題が明確になったら、次に「DXによって自社をどのような姿に変革するのか」というビジョンを策定します。DXはIT部門だけの取り組みではなく、企業全体の未来を左右する経営戦略そのものです。そのため、経営トップが強いリーダーシップを発揮し、自社のパーパス(存在意義)と結びついたDXビジョンを打ち出すことが不可欠です。
このビジョンは、変化の激しい市場環境の中で企業が進むべき方向を示す羅針盤の役割を果たします。従業員にとっては、日々の業務が会社の未来にどう貢献するのかを理解する拠り所となり、全社一丸となって変革に取り組むための求心力となります。
4.2.1 ビジョン策定の具体的なステップ
まず、経営層が「なぜ今、我々はDXに取り組むのか」を徹底的に議論し、その覚悟とコミットメントを固めます。
次に、市場の脅威や機会、自社の強み(コアコンピタンス)を踏まえ、3~5年後の理想の姿を描きます。例えば、「データ活用によって顧客一人ひとりに最適な体験を提供し、業界No.1の顧客ロイヤリティを獲得する」「サプライチェーン全体のデータをリアルタイムに連携・最適化し、環境負荷を30%削減する」といった、具体的で測定可能な目標を設定することが重要です。
策定したビジョンは、繰り返し全従業員に伝え、共感を呼び起こし、日々の業務とDXの繋がりを実感させるためのコミュニケーションプランも合わせて実行します。
4.3 全社的なデータ活用基盤の構築
DXビジョンの実現には、社内に散在するデータを統合し、価値あるインサイト(洞察)を引き出すための「データ活用基盤」がエンジンとなります。多くの企業が抱えるレガシーシステムは、長年の改修を経て複雑化・ブラックボックス化し、部門ごとに最適化(サイロ化)されているため、全社横断でのデータ活用を阻害する大きな壁となっています。
この壁を乗り越えるためには、既存システムの刷新(モダナイゼーション)と、クラウド技術を前提とした新たなITアーキテクチャへの移行が求められます。これにより、ビジネスの変化に柔軟かつ迅速に対応できるIT環境を手に入れることができます。
4.3.1 データ活用基盤を構成する主要要素
具体的なアクションとしては、まず各システムに蓄積された生データを一元的に集約する「データレイク」や、分析しやすい形に加工・整理して格納する「データウェアハウス(DWH)」をクラウド上に構築します。その上で、BIツール(TableauやPower BIなど)を導入してデータの可視化を進め、現場の従業員が自らデータを見て気づきを得られる環境を整えます。
さらに、AI・機械学習プラットフォームを活用すれば、需要予測の精度向上や業務プロセスの自動化といった、より高度なデータ活用も可能になります。重要なのは、単にツールを導入するだけでなく、データの品質やセキュリティを担保する「データガバナンス」体制を同時に整備することです。
4.4 アジャイルな開発体制と組織文化の醸成
DXは、一度システムを導入すれば完了するようなゴールのあるプロジェクトではありません。市場や顧客ニーズの不確実な変化に迅速に対応し、継続的にビジネスモデルやサービスを改善していくための「仕組み」と「文化」を根付かせることが本質です。そのために極めて有効なのが「アジャイル」なアプローチです。
従来の大規模な計画を立ててから開発するウォーターフォール型とは異なり、アジャイル開発では、小規模なチームで「計画→設計→実装→テスト」というサイクルを2週間程度の短い期間で繰り返し、素早く価値を提供しながら改善を重ねていきます。これにより、市場投入までの時間を大幅に短縮し、ユーザーからのフィードバックを即座に次の開発に反映させることが可能になります。
4.4.1 挑戦を促す組織文化への変革
アジャイルな開発を成功させるには、技術的な手法だけでなく、組織文化の変革が不可欠です。具体的には、ビジネス部門と開発部門が一体となった「クロスファンクショナルチーム」を編成し、共通の目標に向かって協力する体制を築きます。
また、失敗を責めるのではなく、そこから得られる学びを重視し、新しいアイデアを試すことを奨励する「心理的安全性」の高い環境づくりが求められます。経営層は、短期的な成果だけでなく、学習と挑戦のプロセスそのものを評価する姿勢を示すことが重要です。
このような文化が醸成されることで、従業員一人ひとりが主体的にDXを推進する原動力となり、企業全体の変革スピードが飛躍的に加速します。
5. DX推進を成功させるためのポイント

DXレポートが示す課題を乗り越え、DXを成功に導くためには、戦略的なアプローチが不可欠です。これまでの章でDXの必要性やアクションプランを解説してきましたが、本章では、DXプロジェクトを具体的に推進し、成功確率を高めるための3つの重要なポイントを掘り下げて解説します。
5.1 スモールスタートで成功体験を積む
DXはいきなり全社的な大規模改革を目指すと、関係各所の調整が難航したり、初期投資が膨らんだりして失敗するリスクが高まります。そこで重要になるのが「スモールスタート」です。まずは特定の部門や限定的な業務範囲でDXに着手し、小さな成功体験(クイックウィン)を積み重ねていくアプローチが有効です。
スモールスタートで成功体験を創出し、その効果を社内で共有することで、DXに対するポジティブな雰囲気が醸成されます。経営層や他部門からの理解と協力を得やすくなり、より大きな変革へと繋げるための推進力が生まれます。まずは、以下のような身近な領域から着手するのがおすすめです。
- 定型業務の自動化:RPA(Robotic Process Automation)ツールなどを活用し、経費精算やデータ入力といった定型的なバックオフィス業務を自動化する。
- ペーパーレス化の推進:Web会議システム、ビジネスチャットツール、クラウドストレージなどを導入し、紙媒体での情報共有や申請・承認プロセスをデジタル化する。
- 勤怠管理・経費管理:クラウド型の勤怠管理システムや経費精算システムを導入し、手作業による集計や申請業務の負担を軽減する。
こうした取り組みは比較的成果が見えやすく、従業員がDXのメリットを直接的に実感できるため、全社的なDX推進への第一歩として非常に効果的です。PoC(Proof of Concept:概念実証)を通じて効果を検証しながら、徐々に対象範囲を拡大していくと良いでしょう。
5.2 DX人材の確保と育成戦略
DX推進の成否は、それを担う「人材」にかかっていると言っても過言ではありません。DXレポートでも指摘されている通り、多くの企業でDX人材の不足が深刻な課題となっています。外部のベンダーに依存するだけでなく、自社内に知見を蓄積し、主体的にDXを推進できる体制を構築することが重要です。人材確保・育成には「外部からの採用」と「内部での育成(リスキリング)」の2つのアプローチがあります。
5.2.1 DX人材の確保(中途採用・外部連携)
データサイエンティストやDXプロジェクトマネージャーなど、高度な専門性を持つ人材は、中途採用市場から確保することが即効性のある選択肢です。また、自社に必要なスキルセットを持つフリーランスや副業人材と連携するのも有効な手段です。外部の知見を取り入れることで、自社のDXを加速させることができます。
5.2.2 DX人材の育成(リスキリング)
長期的な視点では、既存社員のリスキリングが不可欠です。自社の業務内容や文化を深く理解している社員がデジタルスキルを習得することで、現場の実情に即したDXが実現しやすくなります。具体的な育成戦略としては、以下のようなものが考えられます。
- 研修・学習プログラムの提供:デジタルリテラシー向上のための基礎研修から、特定のツールや技術に関する専門研修まで、階層や職種に応じたプログラムを用意します。オンライン学習プラットフォームの活用も効果的です。
- 資格取得支援制度:ITストラテジスト、プロジェクトマネージャ試験、AWSやMicrosoft Azureなどのクラウド関連資格の取得を奨励し、費用補助や報奨金制度を設けます。
- OJTによる実践機会の創出:スモールスタートのプロジェクトに若手や中堅社員を積極的にアサインし、実践を通じてスキルを習得する機会を提供します。
DX推進には、多様な役割を担う人材が必要です。自社に必要な人材像を明確にし、戦略的に確保・育成を進めましょう。
| 役割 | 主なミッション | 求められる主なスキル |
|---|---|---|
| ビジネスプロデューサー/DXリーダー | DXの全体戦略を策定し、経営層と現場の橋渡し役を担い、プロジェクト全体を牽引する。 | 経営知識、リーダーシップ、業界知識、プロジェクトマネジメント能力 |
| データサイエンティスト/アナリスト | 事業課題解決のためにデータを収集・分析し、ビジネスに有益な洞察や予測モデルを創出する。 | 統計学、機械学習、プログラミングスキル、データ分析・可視化能力 |
| UI/UXデザイナー | ユーザー視点でデジタルサービスやプロダクトの設計を行い、顧客体験価値を最大化する。 | デザイン思考、情報設計、プロトタイピング、ユーザビリティテスト |
| エンジニア/アーキテクト | DX戦略に基づき、システムの設計、開発、運用を行う。モダンな開発手法や技術に精通する。 | クラウド技術、アジャイル開発、プログラミングスキル、セキュリティ知識 |
5.3 適切なツールやサービスの選定方法
DXを推進する上で、自社の課題や目的に合ったツールやサービスを選定することは極めて重要です。「ツール導入」そのものが目的化してしまい、現場で使われずに形骸化するケースは少なくありません。そうした事態を避けるためにも、慎重な選定プロセスが求められます。
5.3.1 ツール選定のステップ
- 目的と課題の明確化:まず「何のためにDXを行うのか」「どの業務課題を解決したいのか」を明確にします。目的が曖昧なままでは、適切なツールは選べません。
- 要件定義:目的に基づき、ツールに必要な機能、性能、セキュリティレベル、予算などの要件を具体的に定義します。現場の担当者の意見をヒアリングすることも重要です。
- 情報収集と比較検討:定義した要件を基に、複数のツールやサービスをリストアップし、機能、コスト、サポート体制、導入実績などを比較検討します。
- トライアル(試用):可能であれば無料トライアルやPoC(概念実証)を実施し、実際の操作性や自社の業務フローとの親和性を確認します。
5.3.2 ノーコード・ローコードツールの活用
近年、プログラミングの専門知識がなくてもアプリケーションや業務の自動化を実現できる「ノーコード」「ローコード」ツールが注目されています。これらのツールは、IT部門だけでなく事業部門の担当者が主体となって業務改善を進めることを可能にし、スモールスタートやアジャイルな開発と非常に相性が良いです。簡単な業務アプリの開発や定型業務の自動化など、現場主導のDXを加速させる強力な選択肢となります。
5.3.3 SaaSとスクラッチ開発の比較
システムの導入方法には、既存のクラウドサービス(SaaS)を利用する方法と、自社専用にシステムを開発する(スクラッチ開発)方法があります。それぞれにメリット・デメリットがあるため、目的や要件に応じて最適な方法を選択する必要があります。
| 比較項目 | SaaS(Software as a Service) | スクラッチ開発 |
|---|---|---|
| 導入スピード | 速い(契約後すぐに利用可能) | 遅い(要件定義から開発・テストが必要) |
| 初期コスト | 低い(開発費用が不要) | 高い(開発人件費などがかかる) |
| カスタマイズ性 | 低い(提供される機能の範囲内) | 高い(自社の要件に合わせて自由に設計可能) |
| 運用・保守 | ベンダー側で実施(アップデートも自動) | 自社で実施(専門人材やコストが必要) |
| 適した用途 | 業界標準的な業務(経理、人事、顧客管理など) | 自社独自の競争優位性を生むコア業務 |
これらのポイントを踏まえ、自社の状況に最適なツールやサービスを戦略的に選定することが、DXプロジェクトを成功に導く鍵となります。
6. まとめ
本記事では、経済産業省が公表したDXレポートの要点と、それが警鐘を鳴らす「2025年の崖」について解説しました。多くの日本企業が抱えるレガシーシステムや組織体制、人材不足といった課題が、国際競争力の低下を招く大きな要因となっています。
この危機的状況を乗り越えるためには、経営層がDXを経営課題として捉え、明確なビジョンを掲げ全社的に取り組むことが不可欠です。DXレポートを羅針盤とし、自社の現状を分析することから第一歩を踏み出しましょう。
product関連するプロダクト
-

UMWELTウムベルト
UMWELTは、プログラミング不要でかんたんに分析や自動化ができるノーコードツールです。需要予測から生産計画を最適化、人材の最適配置まで課題を解決できます。日々変化する生産数や生産計画、人員配置を自動立案し属人化や作業時間を大幅に削減します。
MWELT

TRYETING
公式
TRYETING公式です。
お知らせやIR情報などを発信します。