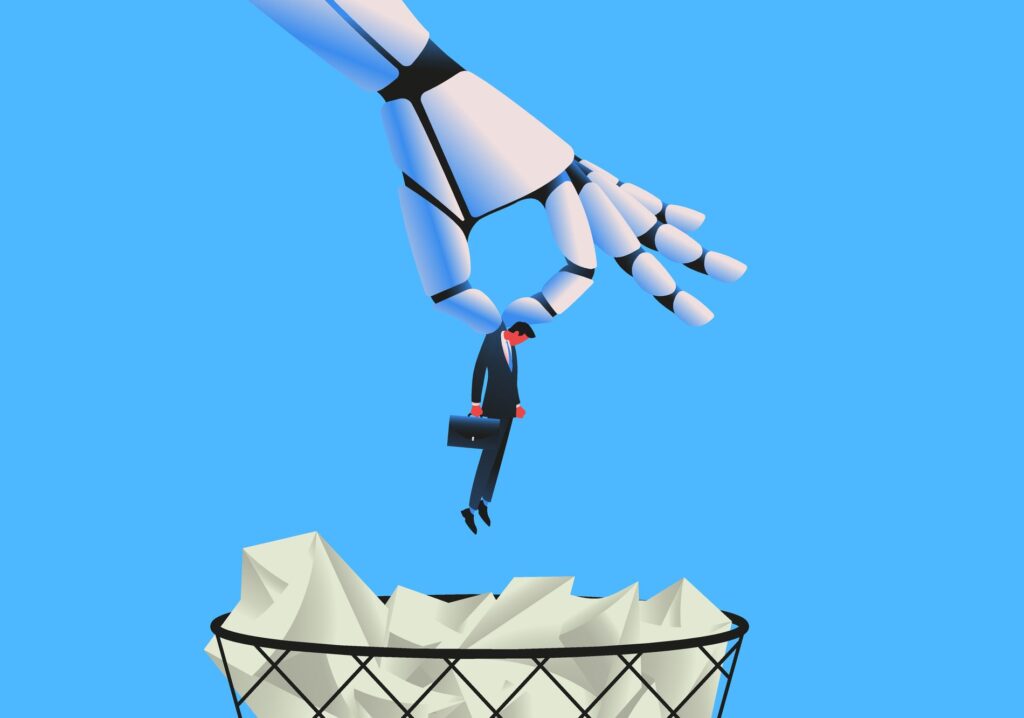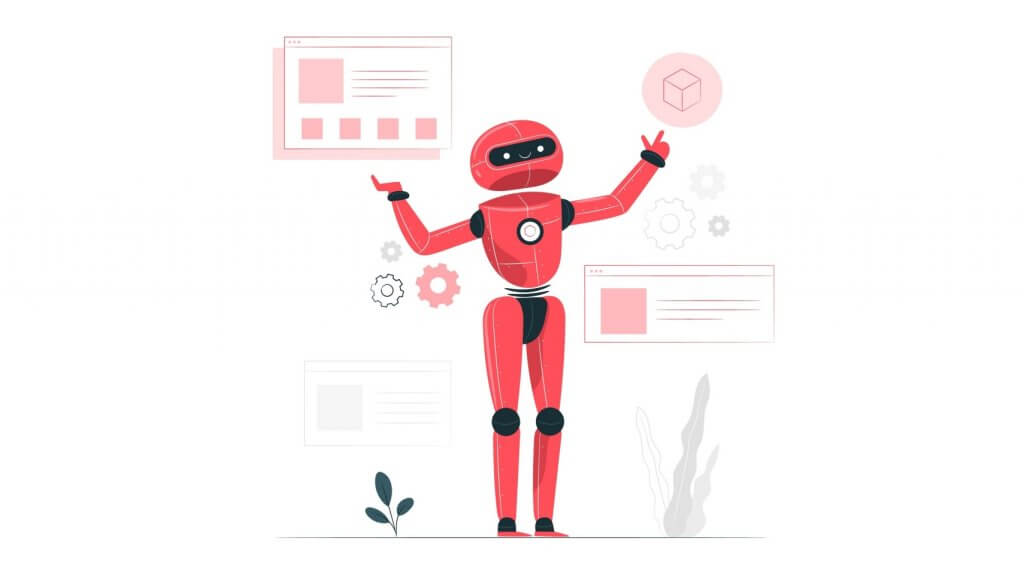BUSINESS
在庫管理のやり方完全ガイド|初心者でもわかる基礎からシステム導入まで

目次
「在庫管理のやり方がわからない」「欠品や過剰在庫をなくしたい」とお悩みではありませんか?
この記事では、在庫管理の目的といった基礎知識から、Excelや在庫管理システムを使った具体的な手順、ABC分析などの効率化テクニックまでを網羅的に解説します。
自社に最適な方法で適正在庫を維持し、キャッシュフロー改善と業務効率化を実現するためのノウハウがわかります。
1. そもそも在庫管理とは?目的と重要性を正しく理解する

「なぜかいつも在庫が合わない」
「必要な時に商品がなくて販売機会を逃してしまった」
「倉庫が不良在庫で溢れ、資金繰りが苦しい」
多くの企業が、このような在庫に関する悩みを抱えています。在庫管理は、単にモノの数を数える地味な作業ではありません。企業の利益とキャッシュフローに直結し、顧客満足度をも左右する、経営の根幹をなす重要な業務です。
この章では、在庫管理の基本的な定義から、なぜそれを行う必要があるのかという目的、そして管理を怠った場合に待ち受けるリスクまでを詳しく解説します。まずはここを正しく理解することが、効果的な在庫管理への第一歩となります。
1.1 在庫管理の基本的な定義
在庫管理とは、企業が保有する商品、製品、原材料、仕掛品などの「在庫」を、最適な量・品質・場所で維持するための活動全般を指します。具体的には、「いつ、どこに、何が、いくつあるのか」という在庫状況を正確に把握し、需要と供給のバランスを取りながら、入庫から出庫、保管、棚卸しに至るまでの一連のプロセスを管理することです。
単に在庫の数量を記録するだけでなく、その価値(金額)や状態(品質、鮮度など)も管理対象に含まれます。最終的な目的は、在庫を企業の資産として最大限に活用し、経営効率を高めることにあります。
1.2 在庫管理を行う3つの目的
在庫管理は、コスト削減といった「守り」の側面だけでなく、売上向上や顧客満足度向上といった「攻め」の側面も持ち合わせています。その主な目的は、以下の3つに大別されます。
1.2.1 目的1:欠品による機会損失の防止
顧客が商品を求めている時に在庫がない「欠品」状態は、企業にとって最も避けたい事態の一つです。欠品は、その瞬間の売上を失う「販売機会の損失」に直結します。それだけでなく、「あそこに行っても欲しいものがない」という印象を与え、顧客が競合他社へ流れてしまう原因にもなりかねません。リピート顧客を失うことは、長期的な売上の減少を意味します。適切な在庫管理によって必要な在庫を確保することは、顧客の期待に応え、満足度と信頼を維持し、安定した売上を確保するために不可欠です。
1.2.2 目的2:過剰在庫によるキャッシュフロー悪化の防止
欠品を恐れるあまり、必要以上に在庫を抱えてしまう「過剰在庫」もまた、経営を圧迫する大きな要因です。在庫は会計上「資産」として扱われますが、それらが売れて現金化されるまでは、企業の資金を固定化させてしまいます。これを「在庫が寝る」と表現することもあります。
過剰在庫は、以下のような問題を引き起こします。
- 保管コストの増大:倉庫の賃料、光熱費、保険料、人件費など、在庫を維持するためのコストが増加します。
- 品質劣化・陳腐化のリスク:長期間保管されることで、商品の品質が落ちたり、流行遅れになったりして価値が下がり、最悪の場合は廃棄せざるを得なくなります。
- キャッシュフローの悪化:仕入れに使った資金が回収できず、運転資金が不足する原因となります。黒字なのに資金繰りが苦しくなる「黒字倒産」のリスクも高まります。
在庫管理は、これらの問題を未然に防ぎ、健全なキャッシュフローを維持する上で極めて重要です。
1.2.3 目的3:管理コストの削減と業務効率化
適切な在庫管理は、日々の業務に潜む無駄をなくし、コスト削減と生産性の向上に貢献します。例えば、在庫の場所が明確でなければ、従業員は商品を探し回るのに多くの時間を費やします。在庫数が不正確であれば、不要な発注をしてしまったり、急な欠品に対応するために緊急で手配したりと、余計な手間とコストが発生します。
在庫管理を徹底し、倉庫内を整理整頓(5Sの徹底)し、誰が見ても在庫状況がわかる仕組みを整えることで、以下のような効果が期待できます。
- 在庫を探す時間や確認作業の削減
- 発注業務の標準化とミスの防止
- 棚卸し作業の負担軽減と時間短縮
- 倉庫スペースの有効活用による保管効率の向上
これらの業務効率化によって生まれた時間や人材を、より付加価値の高いコア業務に振り向けることができ、企業全体の生産性向上につながります。
1.3 在庫管理を怠ると起こる深刻なリスク
これまで述べた目的の裏返しになりますが、在庫管理の重要性を軽視し、その実践を怠ると、企業の経営基盤を揺るがしかねない深刻なリスクに直面します。具体的にどのようなリスクがあるのかを下の表にまとめました。
| リスクの種類 | 具体的な内容 | 企業への影響 |
|---|---|---|
| 財務的リスク | 過剰在庫による保管コストの増大、品質劣化による廃棄損の発生、運転資金の圧迫。 | 利益率の低下、キャッシュフローの悪化、最悪の場合は黒字倒産の可能性。 |
| 販売機会のリスク | 欠品による販売機会の損失、顧客の期待を裏切ることによる信頼の失墜。 | 売上の減少、顧客離れ(スイッチング)、市場シェアの低下。 |
| 業務上のリスク | 在庫を探す無駄な時間、発注ミスや誤出荷の頻発、長時間にわたる棚卸し作業。 | 生産性の低下、従業員の疲弊とモチベーション低下、残業代などの人件費増加。 |
| 信用のリスク | 納期遅延の発生、欠品による顧客満足度の低下、在庫情報の不一致による取引先とのトラブル。 | 企業ブランドイメージの毀損、社会的信用の低下、取引関係の悪化。 |
これらのリスクは互いに連鎖し、気づいた時には手遅れという事態にもなりかねません。安定した企業経営のためにも、在庫管理を経営課題として捉え、組織的に取り組むことが極めて重要です。
2. 在庫管理の基本的なやり方【5つのステップで解説】

在庫管理を成功させるためには、闇雲に始めるのではなく、体系立てられた手順を踏むことが不可欠です。ここでは、初心者の方でも着実に在庫管理の仕組みを構築できる、基本的な5つのステップを具体的に解説します。このステップに沿って進めることで、自社の課題を明確にし、効果的な在庫管理体制を築くことができます。
2.1 ステップ1:現状の在庫を正確に把握する(実地棚卸し)
在庫管理のすべての始まりは、「今、何が、どこに、いくつあるか」という現状を正確に把握することです。帳簿上の在庫数と、実際の在庫数にはズレが生じていることが少なくありません。この差異を解消し、正確な在庫数を把握するために行うのが「実地棚卸し」です。
実地棚卸しは、倉庫や店舗にある在庫を一つひとつ目視で数え、品番、数量、状態などを記録していく作業です。この作業により、以下のことが可能になります。
- 帳簿在庫と実在庫の差異確認:紛失、破損、入力ミスなどによるズレを特定し、原因を究明するきっかけになります。
- 資産の正確な評価:決算時に会社の資産を正しく評価するために不可欠です。
- 滞留・不良在庫の発見:長期間動いていない在庫や、品質が劣化した在庫を見つけ出し、処分や対策を検討できます。
定期的な実地棚卸しを通じて在庫の「数量」「場所」「状態」を正確に把握することが、精度の高い在庫管理に向けた第一歩となります。
2.2 ステップ2:在庫の置き場所とルールを決める(ロケーション管理と5S)
在庫の数を正確に把握したら、次はそれらを効率的かつ安全に保管するためのルールを定めます。ここで重要になるのが「ロケーション管理」と「5S」の徹底です。
ロケーション管理とは、倉庫内のどの場所に何を保管するかを管理する手法です。主な方法として「固定ロケーション」と「フリーロケーション」の2種類があります。
| 管理方式 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 固定ロケーション (商品を常に決まった場所に保管) |
・商品の場所が分かりやすく、担当者が変わっても迷いにくい ・ピッキング作業の習熟が早く、人的ミスが起こりにくい |
・保管スペースに空きが出やすく、スペース効率が悪い ・新商品や季節商品への対応がしにくい |
| フリーロケーション (空いている場所に商品を保管) |
・保管スペースを最大限に活用でき、スペース効率が良い ・新商品などにも柔軟に対応できる |
・在庫の場所をシステムで管理しないと把握が困難 ・ピッキング時に場所を探す手間がかかる可能性がある |
さらに、倉庫内全体の作業効率と安全性を高めるために「5S」を徹底することが重要です。5Sとは、整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもので、職場環境を維持・改善するためのスローガンです。
| 5S項目 | 在庫管理における実施内容 |
|---|---|
| 整理 | 必要なものと不要なもの(滞留在庫、不良在庫など)を区別し、不要なものは処分する。 |
| 整頓 | 必要なものを、決められた場所(ロケーション)に、誰でも分かるように表示して置く。「どこに」「何が」「いくつあるか」が明確な状態を目指す。 |
| 清掃 | 倉庫や棚をきれいに保ち、商品が汚れたり破損したりするのを防ぐ。同時に設備の点検も行う。 |
| 清潔 | 整理・整頓・清掃の状態を維持し、誰が見てもきれいで分かりやすい状態を保つ。 |
| 躾 | 決められたルール(ロケーション管理、入出庫手順など)を全員が守るように習慣づける。 |
これらのルールを定めることで、在庫を探す無駄な時間がなくなり、入出庫作業のスピードと正確性が飛躍的に向上します。
2.3 ステップ3:自社に合った発注方式を選ぶ
在庫を適切に維持するためには、いつ、どれくらいの量を発注するのかという「発注方式」のルールが必要です。自社の商品の特性や需要の変動に合わせて、最適な方式を選択します。代表的な発注方式には「定量発注方式」と「定期発注方式」があります。
2.3.1 定量発注方式のメリット・デメリット
定量発注方式は、在庫があらかじめ設定した「発注点」という数量を下回ったタイミングで、毎回決まった量(定量)を発注する方法です。需要がある程度安定している定番商品などに適しています。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ・発注量が一定のため、発注作業が単純で管理しやすい ・発注点を下回ったら発注するだけなので、需要予測が不要 ・比較的少ない在庫量で運用できる |
・常に在庫量を監視する必要がある ・需要の急増やリードタイムの遅延が起こると欠品しやすい ・複数の商品をまとめて発注しにくく、発注コストが割高になることがある |
2.3.2 定期発注方式のメリット・デメリット
定期発注方式は、毎週、毎月など、あらかじめ決めたタイミング(定期的)に在庫量を確認し、その時点での必要量を発注する方法です。需要の変動が大きい商品や、複数の商品を同じ仕入先からまとめて発注する場合に適しています。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ・発注タイミングが決まっているため、業務計画を立てやすい ・複数の商品をまとめて発注でき、輸送コストなどを削減できる ・需要の変動に合わせて発注量を調整できる |
・次の発注タイミングまで在庫が持つよう、多めに在庫を抱える必要がある(過剰在庫リスク) ・発注の都度、需要を予測して発注量を計算する必要がある ・急な需要増に対応できず、欠品することがある |
どちらか一方に限定する必要はなく、商品の重要度や特性に応じてABC分析などを行い、発注方式を使い分けることも効果的です。
2.4 ステップ4:適正在庫と安全在庫を設定する
最適な発注を行うためには、「どのくらいの在庫量を目指すのか」という基準値の設定が欠かせません。その基準となるのが「適正在庫」と「安全在庫」です。
適正在庫とは、欠品による機会損失を出さず、かつ過剰在庫によるコスト増も招かない、最もバランスの取れた在庫量のことです。一方、安全在庫とは、需要の急増や納品の遅れといった不測の事態に備えるための、最低限のストックを指します。適正在庫は、この安全在庫を含んだ概念です。
2.4.1 適正在庫の計算方法
適正在庫は、日々の消費量に加えて、発注から納品までにかかる日数(リードタイム)と安全在庫を考慮して算出します。基本的な計算式は以下の通りです。
適正在庫 = 一定期間の平均出庫数 + 安全在庫
また、実務では「サイクル在庫(次の発注までに消費される在庫量)」と「安全在庫」の合計で考えることもあります。
適正在庫 = サイクル在庫 + 安全在庫
これらの計算には、過去の出庫データや正確なリードタイムの情報が不可欠です。まずは日々の入出庫データを記録することから始めましょう。
2.4.2 安全在庫の計算方法
安全在庫は、欠品をどの程度許容するかによって変動します。統計的な計算式も存在しますが、ここではより実用的な計算方法を紹介します。
安全在庫 = 安全係数 × 使用量の標準偏差 × √(発注リードタイム+発注間隔)
この式は複雑なため、はじめは「過去の需要の最大値から平均値を引く」といった簡易的な方法で設定し、運用しながら調整していくのが現実的です。
重要なのは、安全在庫は多すぎるとキャッシュフローを圧迫し、少なすぎると欠品リスクを高めるため、自社のサービスレベルに合わせて適切な水準を見極めることです。
2.5 ステップ5:PDCAを回して継続的に改善する
在庫管理は、一度ルールや仕組みを作って終わりではありません。市場の需要、競合の動向、サプライヤーの状況など、ビジネス環境は常に変化します。その変化に対応し、常に最適な状態を維持するためには、継続的な改善活動が不可欠です。そこで有効なのが「PDCAサイクル」です。
- Plan(計画):ステップ1〜4で設定した内容(在庫の保管ルール、発注方式、適正在庫数など)を基に、具体的な目標(例:在庫回転率を〇%向上、欠品率を〇%未満に抑える)を立てます。
- Do(実行):計画に沿って、日々の在庫管理業務を実践します。入出庫の記録、棚卸し、発注などをルール通りに行います。
- Check(評価):一定期間が経過したら、設定した目標が達成できているかを確認します。在庫回転率、欠品率、在庫評価額などのKPI(重要業績評価指標)を分析し、計画と実績の差異や問題点を洗い出します。
- Action(改善):評価結果に基づき、改善策を検討・実行します。「発注点が適切でなかった」「安全在庫が多すぎた」「ロケーションが悪く作業に時間がかかっている」などの問題に対し、設定値の見直しやルールの変更を行います。そして、その改善策を次のPlanに繋げます。
このPDCAサイクルを地道に回し続けることで、在庫管理の精度は着実に向上し、変化に強い強固な経営基盤を築くことができます。
3. 【ツール別】在庫管理の具体的なやり方
在庫管理のやり方は、事業の規模や取り扱う商品の種類、量によって最適なものが異なります。ここでは、代表的な4つの方法を「手書き」「Excel」「在庫管理システム」「最新技術」に分けて、それぞれの具体的なやり方、メリット・デメリットを詳しく解説します。自社に合った方法を見つけるための参考にしてください。
3.1 手書きやノートで行うアナログな方法
最も原始的でシンプルな方法が、ノートや大学ノート、市販の在庫管理台帳などを使って手書きで管理する方法です。商品名、入庫日、出庫日、数量などを項目として設け、在庫の動きがあるたびに手で記入していきます。
この方法は、事業を始めたばかりで商品数が非常に少ない個人商店や、特定の備品管理など、ごく限られた範囲で有効です。導入コストがかからず、誰でもすぐに始められる手軽さが最大のメリットです。しかし、事業規模が拡大し、商品数や取引量が増えるにつれて、以下のような多くのデメリットが顕在化します。
- 記入ミスや計算ミスなどのヒューマンエラーが起こりやすい
- 担当者以外は状況を把握できない「属人化」に陥りやすい
- 在庫数の確認に時間がかかり、リアルタイムでの把握が困難
- 複数拠点での情報共有ができない
- 帳簿の紛失や破損によるデータ消失のリスクがある
これらのデメリットは、欠品や過剰在庫に直結するため、本格的な事業運営においては、早い段階でデジタルツールへの移行を検討することが推奨されます。
3.2 Excel(エクセル)を使った在庫管理のやり方
多くの企業で導入されているMicrosoft Excelは、在庫管理ツールとしても広く活用されています。関数やマクロを駆使することで、アナログ管理のデメリットをある程度解消できます。
3.2.1 メリットとデメリット
Excelでの在庫管理は、手軽さとコストの低さから多くの企業で採用されていますが、メリットとデメリットを正しく理解しておくことが重要です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| メリット |
|
| デメリット |
|
3.2.2 在庫管理表の作り方と無料テンプレート
Excelで在庫管理を始めるには、まず在庫管理表を作成します。基本的な作成手順は以下の通りです。
- 管理項目の決定:在庫管理に必要な項目を洗い出します。最低限、以下の項目は入れておくと良いでしょう。
- 商品コード
- 商品名
- 入庫日/出庫日
- 入庫数
- 出庫数
- 現在庫数
- 保管場所(ロケーション)
- 担当者名
- 備考
- 関数の設定:「現在庫数」のセルに「期首在庫+入庫数-出庫数」の計算式を入れるなど、基本的な関数を設定して入力を自動化します。SUMIF関数やVLOOKUP関数を活用すると、商品別の集計やデータ参照が容易になります。
- 入力ルールの策定:日付の書式や担当者名の入力方法など、複数人で運用する場合のルールを明確に定めます。入力規則機能を活用して、誤入力を防ぐ工夫も有効です。
一から作成するのが難しい場合は、Microsoft公式サイトなどで提供されている無料のテンプレートを活用するのも一つの手です。テンプレートをベースに、自社の運用に合わせてカスタマイズすることで、効率的に在庫管理表を作成できます。
3.3 在庫管理システム(WMS)を活用したやり方
Excelでの管理に限界を感じたら、在庫管理に特化した専門の「在庫管理システム」や「WMS(倉庫管理システム)」の導入を検討する段階です。これらのシステムは、在庫管理業務を大幅に効率化し、精度を高めるための機能が豊富に搭載されています。
3.3.1 システムでできることと導入のメリット
在庫管理システムを導入することで、手作業やExcelでは困難だった高度な管理が実現可能になります。
【システムでできることの例】
- リアルタイムな在庫状況の可視化:いつ、どこに、何が、いくつあるかを即座に把握できます。
- 入出庫・検品作業の効率化:ハンディターミナルやスマートフォンでバーコードを読み取るだけで、正確かつスピーディに作業が完了します。
- ロケーション管理の最適化:固定ロケーション、フリーロケーションに対応し、どこに何があるかをシステムが管理します。
- 賞味期限・ロット管理:食品や医薬品などで必須の先入れ先出し(FIFO)を徹底し、期限切れのリスクを低減します。
- 適正在庫の維持と発注支援:過去のデータから需要を予測し、適切な発注点や発注量を自動でアラートします。
- 棚卸作業の効率化:ハンディターミナルを使うことで、棚卸しにかかる時間と人員を大幅に削減できます。
これらの機能により、「業務効率化」「人的ミスの削減」「欠品・過剰在庫の防止」「属人化の解消」といった多くのメリットがもたらされ、結果としてキャッシュフローの改善や顧客満足度の向上に繋がります。
3.3.2 システムの選び方と注意点
在庫管理システムは多種多様なため、自社に最適なものを選ぶことが重要です。選定時には以下のポイントを確認しましょう。
| 選定ポイント | 確認すべきこと |
|---|---|
| 提供形態 | 初期費用を抑えたいなら「クラウド型」、自社サーバーで厳重に管理したいなら「オンプレミス型」など、自社のIT方針に合ったものを選びます。 |
| 業種・業態との適合性 | EC、小売、製造、アパレルなど、自社の業界特有の商習慣(セット品管理、B品管理など)に対応しているかを確認します。 |
| 機能の過不足 | 必要な機能が揃っているか、逆に不要な機能が多くて複雑になっていないかを見極めます。 |
| 操作性 | 現場の担当者が直感的に使えるか、デモや無料トライアルで必ず確認します。 |
| 外部システム連携 | 販売管理システム、会計ソフト、ECカートシステム、POSレジなど、既存システムと連携できるかは非常に重要です。 |
| サポート体制 | 導入時の設定支援や、運用開始後のトラブル対応など、サポート体制が充実しているかを確認します。 |
導入を成功させるためには、「なぜシステムを導入するのか」という目的を明確にし、現場の課題や意見を十分にヒアリングした上で、複数のシステムを比較検討することが不可欠です。
3.4 バーコード・RFID・AIを活用した最新のやり方
近年、テクノロジーの進化により、在庫管理はさらなる高精度化・自動化が進んでいます。特にバーコード、RFID、AIの活用は、業務を劇的に変えるポテンシャルを秘めています。
バーコード・QRコード
商品やロケーションに貼付したバーコードやQRコードを、ハンディターミナルやスマートフォンで読み取る方法です。在庫管理システムの基本的な機能として広く普及しており、手入力によるミスをなくし、作業時間を大幅に短縮します。導入コストも比較的安価で、費用対効果が高いのが特徴です。
RFID(Radio Frequency Identification)
ICタグと電波を用いて、非接触で複数の商品を一括で読み取る技術です。段ボール箱を開封せずに中身を検品したり、専用ゲートを通過するだけで棚卸しが完了したりと、作業効率を飛躍的に向上させます。アパレル業界の「ユニクロ」などが全商品に導入し、棚卸しやレジ業務を効率化している事例が有名です。ただし、ICタグのコストがバーコードに比べて高いため、高単価な商品や大量の商品を扱う現場での導入が中心です。
AI(人工知能)
AIを在庫管理に活用することで、人間では困難なレベルの最適化が可能になります。過去の販売実績、天候、季節、イベント情報、トレンドなど、あらゆるデータを分析して高精度な「需要予測」を行い、欠品や過剰在庫を最小限に抑えます。これにより、最適な発注量を自動で算出したり、倉庫内の最適な在庫配置を提案したりするなど、より戦略的な在庫管理が実現します。
4. 在庫管理の精度と効率を上げるためのテクニック

在庫管理の基本的なステップを理解したら、次はその精度と効率をさらに高めるための具体的なテクニックを導入しましょう。ここでは、データ分析に基づいた管理手法から、倉庫内の物理的な改善策まで、実践的で効果の高い3つのテクニックを詳しく解説します。
4.1 ABC分析で在庫の優先順位をつける
ABC分析は、数ある在庫品目を重要度に応じてランク分けし、管理の優先順位を明確にするためのフレームワークです。「売上の8割は全商品のうち2割の品目が生み出している」というパレートの法則に基づいた考え方で、在庫管理にメリハリをつけることで、限られたリソースを効果的に配分できます。
具体的には、品目ごとの売上高や出荷金額などを基準に、在庫をA・B・Cの3つのグループに分類します。
- Aランク:最重要品目。売上全体への貢献度が非常に高く、厳密な在庫管理が求められる。
- Bランク:中程度の重要品目。Aランクほどではないが、安定した管理が必要。
- Cランク:重要度が低い品目。管理の手間を簡素化し、コストを抑える対象となる。
この分析を行うことで、どの在庫に注力すべきかが一目瞭然となり、欠品による機会損失や過剰在庫のリスクを戦略的に低減できます。
4.1.1 ABC分析の進め方
ABC分析は以下のステップで進めます。
- データ収集:分析対象期間(例:年間、半期)を定め、品目ごとの「売上高」や「出荷金額」、「出荷数量」などのデータを収集します。
- 計算と集計:各品目の売上高を算出し、全品目の合計売上高に占める「売上構成比」を計算します。
- 累積構成比の算出:品目を売上高の大きい順に並べ替え、上位から順に売上構成比を足し合わせた「累積構成比」を算出します。
- ランク分け:算出した累積構成比を基に、以下の基準でA・B・Cのランクに分類します。
ランク 累積構成比の目安 品目数の目安 Aランク 0%~70% 上位10%~20% Bランク 70%~90% 中位20%~30% Cランク 90%~100% 下位50%~70% ※上記の構成比や品目数の割合はあくまで目安であり、企業の状況や商材の特性に応じて調整することが重要です。
4.1.2 ランク別の管理方針
分類したランクごとに、以下のように管理方針を変えることで、在庫管理を効率化します。
| ランク | 管理方針の例 |
|---|---|
| Aランク (最重要在庫) |
発注方式は需要予測の精度を高め、安全在庫を確保する「定量発注方式」を採用。毎日在庫数をチェックし、欠品を絶対に避ける。実地棚卸しも頻繁に行う。 |
| Bランク (中位在庫) |
定期的に需要の変動を確認し、定量発注方式と定期発注方式を使い分ける。Aランクよりは棚卸しの頻度を落とす。 |
| Cランク (一般在庫) |
管理工数を削減するため、発注サイクルを固定化する「定期発注方式」や、2つの棚(ビン)を用いる「ダブルビン方式」などを採用。在庫切れのリスクをある程度許容し、発注業務を簡素化する。 |
4.2 在庫回転率を算出して滞留在庫を見つける
在庫回転率は、一定期間内に在庫がどれだけ入れ替わったかを示す指標です。この数値を見ることで、在庫が効率的に販売に結びついているか、あるいは長期間倉庫に眠っている「滞留在庫(不動在庫)」になっていないかを判断できます。キャッシュフローの健全性を測る上でも非常に重要な指標です。
在庫回転率が高いほど、商品はスムーズに売れており、資本が効率よく活用されている状態を意味します。逆に低い場合は、過剰在庫や不良在庫を抱えている可能性があり、保管コストの増大や資金繰りの悪化につながります。
4.2.1 在庫回転率の計算方法
在庫回転率は、金額で計算する方法と数量で計算する方法があります。
- 金額で計算する場合:
在庫回転率(回) = 期間中の売上原価 ÷ 平均在庫金額
※平均在庫金額 = (期首在庫金額 + 期末在庫金額) ÷ 2 - 数量で計算する場合:
在庫回転率(回) = 期間中の出庫数 ÷ 平均在庫数
※平均在庫数 = (期首在庫数 + 期末在庫数) ÷ 2
また、在庫が何日で入れ替わるかを示す「在庫回転日数」も併せて算出すると、より具体的に在庫の状況を把握できます。
在庫回転日数(日) = 期間の日数 ÷ 在庫回転率
例えば、在庫回転率が年12回であれば、在庫回転日数は約30日となり、在庫が平均1ヶ月で入れ替わっていることがわかります。
4.2.2 滞留在庫の特定と対策
品目ごとに在庫回転率を算出し、極端に数値が低いものや、長期間動きのないものを滞留在庫としてリストアップします。滞留在庫は、保管スペースを圧迫し、品質劣化のリスクもあるため、早期の対策が必要です。
- セールや値下げ販売:利益が少なくなる、あるいは赤字になるとしても、販売して現金化することを優先します。
- セット販売:人気商品と組み合わせて販売し、在庫の消化を促します。
- 廃棄・処分:販売の見込みが全く立たない場合は、保管コストの発生を止めるために、思い切って廃棄処分を決定することも重要です。
定期的に在庫回転率をモニタリングし、滞留在庫を早期に発見・対策するサイクルを確立することが、健全な在庫管理につながります。
4.3 倉庫内の動線を最適化する
倉庫内の「動線」とは、作業者が入庫から検品、棚入れ、ピッキング、梱包、出庫までの一連の作業で移動する経路のことです。この動線が非効率だと、移動距離が長くなり、作業時間が無駄に増えるだけでなく、作業者の疲労やミスの原因にもなります。動線の最適化は、生産性向上とコスト削減に直結する重要なテクニックです。
4.3.1 動線最適化の基本「5S」と「3定管理」
動線最適化の土台となるのが「5S」の徹底です。
- 整理:必要なものと不要なものを分け、不要なものを処分する。
- 整頓:必要なものを、誰でもわかるように決められた場所に置く。
- 清掃:常にきれいな状態を保ち、異常を発見しやすくする。
- 清潔:整理・整頓・清掃を維持し、習慣化する。
- 躾:決められたルールや手順を全員が守るように徹底する。
特に「整頓」においては、「どこに(定位)」「何を(定品)」「いくつ(定量)」置くかを決める「3定管理」が効果的です。これにより、モノを探す時間を劇的に削減できます。
4.3.2 ロケーション管理とレイアウトの工夫
ABC分析の結果を倉庫内のレイアウトに反映させることで、動線を大幅に改善できます。
- 出荷頻度に応じた配置:Aランクのよく売れる商品は、出入り口に最も近い、取り出しやすい高さの場所に配置します。逆にCランクの商品は、倉庫の奥や上段など、アクセスしにくい場所に置いても影響は少なくなります。
- 関連商品の集約:同時にピッキングされることが多い商品を近くに配置することで、移動距離を短縮します。
- フリーロケーションの活用:在庫管理システムを導入している場合、空いているスペースに効率よく商品を保管する「フリーロケーション」が有効です。スペース効率を最大化し、棚入れ作業の動線を短くできます。
- 一方通行の動線設計:倉庫内の通路を一方通行にすることで、作業者同士の衝突や渋滞を防ぎ、安全でスムーズな流れを作ります。
これらのテクニックを組み合わせることで、ピッキング作業にかかる時間を短縮し、倉庫業務全体の効率を飛躍的に向上させることが可能です。
5. 【業種・業界別】在庫管理のやり方のポイント
在庫管理の基本的なやり方は共通していますが、業種や業界の特性によって抱える課題や管理の重点ポイントは大きく異なります。ここでは主要な4つの業種・業界を例に挙げ、それぞれの在庫管理のやり方のコツを具体的に解説します。
5.1 小売業・店舗の場合
実店舗を持つ小売業では、顧客の目に触れる店頭在庫と、バックヤード在庫の両方を適切に管理する必要があります。欠品は販売機会の損失に、過剰在庫は売り場の圧迫や資金繰りの悪化に直結するため、バランスの取れた在庫管理が求められます。
5.1.1 小売業における主な課題と解決のポイント
小売業の在庫管理を成功させるには、POS(販売時点情報管理)システムのデータをいかに活用するかが鍵となります。
| 課題 | 解決のポイント |
|---|---|
| 欠品・過剰在庫の発生 | POSデータで売れ筋・死に筋商品を把握し、ABC分析を活用して商品ごとの発注点を最適化する。需要予測に基づいた仕入れを行う。 |
| 店舗とバックヤードの在庫不一致 | ハンディターミナルなどを活用し、定期的な棚卸しを効率化する。入荷・検品・品出しのルールを標準化し、全スタッフで共有する。 |
| セールや季節商品の管理 | 過去のセール実績や天候、地域のイベント情報を加味して需要を予測する。セール後の残在庫を速やかに把握し、次の施策(再値下げ、店舗間移動など)を決定する。 |
| 複数店舗間の在庫の偏り | 在庫管理システムを導入し、全店舗の在庫状況をリアルタイムで可視化する。店舗間で在庫を融通し合う仕組みを構築し、販売機会の最大化を図る。 |
特にアパレル業界などトレンドの移り変わりが激しい業種では、在庫回転率を常に意識し、シーズンオフになる前に売り切るための販売戦略と連動した在庫管理が不可欠です。
5.2 EC・ネットショップの場合
EC・ネットショップでは、物理的な店舗がない代わりに、ウェブサイト上の在庫表示と倉庫内の実在庫をリアルタイムで正確に連携させることが最も重要です。受注から発送までのスピードも顧客満足度に大きく影響します。
5.2.1 EC・ネットショップにおける主な課題と解決のポイント
ECの在庫管理では、WMS(倉庫管理システム)の活用が業務効率と精度を飛躍的に向上させます。
| 課題 | 解決のポイント |
|---|---|
| 売り越し(空売り)の発生 | WMSとECカートシステムをAPI連携させ、注文が入ると自動で在庫数が引き落とされる仕組みを構築する。複数のECモールに出店している場合は、在庫連携システムで一元管理する。 |
| 誤出荷や発送遅延 | バーコードやRFIDを用いて商品を管理し、ピッキングや梱包時にスキャンすることで人的ミスを防ぐ。フリーロケーション管理とピッキングリストの自動生成で、倉庫内作業を効率化する。 |
| 返品在庫の管理 | 返品された商品の状態(良品・不良品)を検品し、速やかに在庫に戻す、または廃棄するルールを明確にする。返品処理のステータスをシステム上で管理し、状況を可視化する。 |
| セール時の受注急増への対応 | WMSを導入して出荷能力を向上させるとともに、セール期間中の人員計画を事前に立てる。過去のデータからセール対象商品の需要を予測し、十分な在庫を確保する。 |
また、「ささげ業務(撮影・採寸・原稿作成)」が完了し、ECサイトに商品が掲載されたタイミングで初めて在庫が動くため、入荷からサイト公開までのリードタイムを短縮することも、在庫効率を高める上で重要です。
5.3 製造業の場合
製造業の在庫は、「原材料」「仕掛品(製造途中の製品)」「完成品」の3種類に大別されます。これらの在庫を生産計画と密接に連携させながら管理することが特徴です。部品や原材料の欠品は、生産ライン全体の停止という深刻な事態を引き起こす可能性があります。
5.3.1 製造業における主な課題と解決のポイント
生産管理システムやMRP(資材所要量計画)システムと連携し、サプライチェーン全体を最適化する視点が求められます。
| 課題 | 解決のポイント |
|---|---|
| 原材料・部品の欠品による生産停止 | BOM(部品表)を正確に管理し、生産計画に基づいて必要な資材量を自動算出するMRPを導入する。リードタイムや供給の不安定さを考慮し、品目ごとに適切な安全在庫を設定する。 |
| 仕掛品の滞留 | 各工程の生産能力を把握し、ボトルネック工程を解消する。生産の進捗状況をリアルタイムで可視化し、工程間の連携をスムーズにする。 |
| 完成品の過剰在庫 | 需要予測の精度を高め、見込み生産と受注生産のバランスを最適化する。在庫回転率を算出し、滞留している完成品を特定して対策を講じる。 |
| 品質管理(ロット管理) | 製品や原材料をロット単位で管理し、トレーサビリティを確保する。万が一品質に問題が発生した際に、影響範囲を迅速に特定できる体制を整える。 |
トヨタ生産方式に代表されるJIT(ジャストインタイム)の考え方を取り入れ、必要なものを、必要なときに、必要なだけ生産・調達することで、在庫の極小化を目指すことも重要な取り組みです。
5.4 飲食店の場合
飲食店では、食材という鮮度が命の商品を扱います。賞味期限・消費期限が短く、日々の廃棄(フードロス)が直接的に原価を圧迫するため、きめ細やかな在庫管理が利益確保の生命線となります。
5.4.1 飲食店における主な課題と解決のポイント
日々の発注業務の精度を高め、食材の廃棄ロスをいかに減らすかが最大のテーマです。
| 課題 | 解決のポイント |
|---|---|
| 食材の廃棄ロス(フードロス) | 日次・週次での棚卸しを徹底し、食材の消費ペースを正確に把握する。FIFO(先入れ先出し)を徹底し、古い食材から使用するルールを全員で守る。 |
| 欠品によるメニュー提供不可 | POSデータからメニューごとの出数を分析し、必要な食材量を予測する。天気や曜日、近隣のイベントなどを考慮して発注量を微調整する。 |
| 発注作業の属人化 | 食材ごとに発注点を設定し、誰でも同じ基準で発注できる仕組みを作る。ハンディターミナルや発注システムを導入し、作業を標準化・効率化する。 |
| 歩留まりの管理 | 食材の仕入れ形態(ブロック肉、丸ごとの魚など)と、実際に使用できる可食部分の割合(歩留まり率)を把握し、原価計算と発注量に反映させる。 |
近年では、タブレットPOSレジと連携し、注文が入るとリアルタイムでレシピに基づいた食材在庫が差し引かれる飲食店向けの在庫管理システムも登場しています。こうしたツールを活用することで、より正確で効率的な在庫管理が実現可能です。
6. まとめ
本記事では、在庫管理の基本的なやり方を5つのステップで解説し、Excelや在庫管理システムといったツール別の手法、ABC分析などの改善テクニックまで網羅的に紹介しました。在庫管理は、欠品による機会損失や過剰在庫によるキャッシュフローの悪化を防ぐ、企業の利益に直結する重要な業務です。まずは現状の在庫把握から始め、自社の状況に合った管理方法を導入し、継続的な改善(PDCA)を回していきましょう。

TRYETING
公式
TRYETING公式です。
お知らせやIR情報などを発信します。