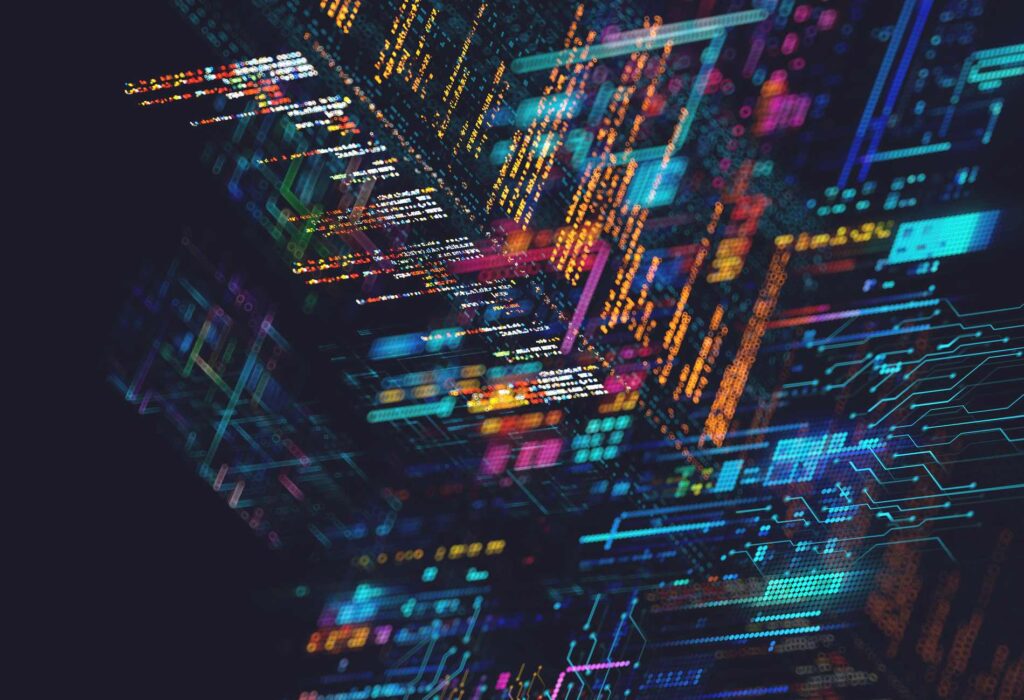BUSINESS
生産計画はどう立てる?最適化のポイントやシステムの選び方を解説

目次
生産計画の最適化は、事業の成長には欠かせない要素です。しかし、生産計画はさまざまな要因から影響を受けるため、計画立案の最適化に悩みを抱える企業様もいるでしょう。
この記事では、生産計画の立案業務と立案が困難な理由を解説し、最適化するためのポイントを紹介します。計画立案を自動化する生産管理システムのメリットや課題、選び方も説明しますので、生産計画の最適化に役立つでしょう。
▼更に生産管理について詳しく知るには?
生産管理の仕組みや役割とは?業務フローでの課題や効率化する方法を解説
▼社内のデータをAI化するには?
ノーコードAIツールUMWELT紹介ページ(活用事例あり)
生産計画はどのような業務?

企業にとって生産計画は、製造ラインのリソース管理や在庫数管理に重要な要素です。業種により生産計画の種類や立て方はさまざまで、自社計画の最適化には定義など基本事項の理解が不可欠です。ここでは、生産計画の定義と種類を解説します。
「いつ」「どのくらい」生産するかを決める
生産計画は、製品をいつまでにどのくらい生産するかを決定する計画です。需要の3要素である「QCD(Quality Cost Delivery)」を適切に管理し、現場業務の作業効率の最大化を目的としています。
生産計画では、部品の発注から納品管理、現場の進捗確認、出荷管理など幅広い計画を統合的に管理します。製造業は、生産計画に基づいて動いているといえるでしょう。
生産計画の種類は2つ
生産計画には「引っ張り方式」と「押し出し方式」の2種類があります。引っ張り方式は、後工程から前工程に物が流れていく生産方法を指し、受注が入った段階で計画に落とします。そのため、過剰在庫が出にくいことが特徴です。
一方の押し出し方式は、生産計画をベースに各工程の作業計画を立て、前工程から後工程に物が流れる生産方法です。計画通りに進めるため、注文が入っても柔軟に対応できます。
しかし、作業計画が注文ベースではないことから、過剰在庫を抱えやすいことが特徴です。
生産計画を立てるのは難しいといわれる4つの理由

生産計画を立てる際には、さまざまな要因への考慮が必要です。製造プロセスが複雑で、事業規模が大きいほど計画に影響する要因も多くなります。予測できない突発的な事態が起こることもあるでしょう。
ここでは、生産計画の立案が難しい主な理由を4つ紹介します。
納期遅れが発生しやすい
1つ目の理由は、必要部品の納期遅れが発生しやすいことです。製造業では、生産計画に基づいて生産に必要な部品を前もって発注します。しかし、市場の状況や社会の情勢によっては部品の供給が予定通りに行われず、納期に遅れが生じます。
生産計画を立てる段階では急な供給不足を予測できないため、正確な生産計画の立案は困難です。
当初の計画から変更がある
2つ目の理由は、生産計画を立てた当初の計画に変更が生じることです。生産計画では、数か月先の予定を立てることが一般的です。そのため、立案当時に予定していた製品以外を製造する可能性も十分にあります。
また、予定していた生産数の変更、生産期間の短縮、製品の優先度の変更などへ柔軟に対応しなければなりません。
原材料や部品の不足が起こる
3つ目の理由は、原材料や部品の不足が起こることです。現場では、投入した部材が正常な状態で次の工程に届くとは限りません。生産の過程では、さまざまな要因から不良品が生まれます。
不良品が多く発生すると発注当初よりも多くの部品が必要となり、予定した製品数を生産できない状況に陥ります。
設備故障
4つ目は、生産用の設備が故障してラインが止まる場合です。製造工程ではさまざまな設備が稼働しており、生産計画は全ての設備が順調に機能している前提で立案します。
各設備には整備担当者が置かれ、定期的なメンテナンスも行いますが、故障リスクを完全に防ぐことは不可能です。突発的に設備故障が生じると生産ラインは停止し、復旧の遅れは納期遅れに直結します。
特に、新規設備導入後は操作経験の浅さから復旧までに時間を要するでしょう。
生産計画の立て方は?流れを紹介

生産計画立案プロセスの全体像を把握すると、計画時に全体の流れや作業量をイメージできます。計画を立てる前に課題を整理し、粒度の異なる「大日程計画」「中日程計画」「小日程計画」の3つの計画を立案します。それぞれの作業内容を詳しく見てみましょう。
1.生産計画の課題をチェック
生産計画を立てる際には、以下の課題を考慮する必要があります。
・販売計画の反映
・在庫計画の反映
・生産に必要なリソースの調節
・資材調達
・納期変更への対応
・不良発生時の対応
必要な数を一度に生産するのではなく、決められたタイミングに必要な数量の生産を行います。
計画からの隔たりは、追加コストの発生や在庫不足による販売機会損失など事業にとって悪影響です。過去の実績なども参考に、生産計画の課題を可能な限り明確にしましょう。
2.大日程計画を作成
はじめに、3か月~1年程度の大日程計画を作成します。大日程計画では、現場レベルの作業計画ではなく企業としての大きな取り組みを扱います。主に以下のような項目です。
・設備の導入計画
・生産能力計画
・新製品開発や新規機能追加に向けた計画
・長期的な人員計画
3.中日程計画を作成
中日程計画は、1か月~3か月程度の粒度で計画を立てます。受注データをベースに作成する計画で、各製品の製造数や製造スピードを決めます。また、各製品の数量を達成するために以下の内容も必要です。
・人員リソースの割り当て
・月間の生産計画
・必要部品の発注管理
・生産能力計画
4.小日程計画を作成
小日程計画は、1週間~1か月間の期間です。これまでの計画と違い、現場では小日程計画を基に実際の作業を実施します。そのため、現場で具体的な行動が取れるよう、詳細な計画にしなければなりません。
例えば、その日に製造する数に加え、現時点での在庫から前工程の在庫数を把握するなどです。他にも、計画策定では以下のような要素も必要です。
・機械や人員の生産能力
・在庫数
・生産ライン
・ロット番号
生産計画を最適化するためのポイント

生産計画の立案は複雑な作業で、規模が大きくなるほど最適化は難しくなります。経験豊富な従業員であっても、膨大な情報の収集から精度の高い計画をすぐには立案できません。ここでは、生産計画を最適化するためのポイントを4つ紹介します。
生産に必要なリソース管理を徹底する
生産に必要なリソースは「人」「設備」「手順」「原材料」の4つを指し、それぞれの英表記の頭文字を取って「4M」と呼びます。各項目のポイントは以下の通りです。
・人:製造ラインで必要となる人員リソースや作業にかかる工数を計画する。計画を基に、シフト作成や人材の確保を進める。
・設備:必要となる設備の洗い出しや、必要となるタイミング・数量・稼働時間を計画する。不足があれば発注する。
・手順:各工程での加工手順や運搬方法を定める。手順次第で作業効率に大きな影響が出る。
・原材料:製品の製造に必要となる部材の種類・数量・規格・業者の手配などを明らかにして準備する。
リソースを最適化するには、4Mがいつどのくらい必要になるのかを明確にする必要があります。
3つのバッファを設定する
バッファとは余裕を意味し、生産計画でもバッファの設定が重要です。バッファを持たせることで、想定外の事態が起きても柔軟に対応できます。ここで指す3つのバッファとは「在庫」「能力」「時間」です。
在庫は、ラインでの不良発生や納期遅れに対応するために、余裕を持つ必要があります。能力は、設備や人員など製造のリソースに余裕を持つことです。
設備は、計画外の時間に稼働する可能性もあるため、バッファを設定する必要があります。
時間は、製造にかかるまでの時間にバッファを持たせるのが効果的です少し長めのリードタイムを想定しましょう。
ローリングプランを立てる
ローリングプランとは、中長期的な計画を定期的に見直しつつ修正を加えることです。ローリングプランを立てることで、計画との隔たりを小さくできます。
例えば、新型コロナウイルス感染症の影響で人々の購買活動が消極的になり、多くの企業がダメージを受けました。ローリングプランで現状を踏まえた計画の見直しを行うと、無駄な生産を回避できるでしょう。
生産計画を自動化する
Excelの機能を使って作業を自動化すれば、業務効率化につながります。Excelを用いる主なメリットは以下の3つです。
・機能や操作に慣れている
・安価で追加費用不要
・マクロで操作を自動化できる
使い慣れたExcelを生産計画に利用すれば、使い方の習得やコストを追加せずとも活用できます。マクロの知識があれば、複雑な操作も自動化できます。しかし、次の点には注意が必要です。
・ファイルのバージョン管理が大変
・データ量が増えると処理が遅くなる
・ファイル管理が属人化する
Excelは、複数の従業員が扱うとデータ量が増え、利便性が低下します。そのため、生産計画作成の自動化には生産管理システムの導入が効果的です。
生産計画を自動化!システムを導入するメリットと課題

生産計画は、さまざまな要因の影響を考慮して作成します。多様なデータを入手して計画に反映するため、複雑で効率化が難しい業務です。生産計画を効率化する手段として、ツールの導入があります。
ここでは、生産管理業務を幅広くサポートする生産管理システムのメリットと課題を紹介します。
メリット
生産管理システムを導入する代表的なメリットは以下の3つです。
・生産計画の精度向上
・生産負荷の平準化
・不良率の低減
販売予測や在庫数、過去の生産実績などのデータを活用し、精度の高い生産計画が立案できます。受注生産と見込み生産の違いにも対応でき、企業の生産方法に合った計画作成が可能です。
製造開始から完成までの全ての工程情報をシステム上で把握し、負荷の偏りを平準化できます。また、工程ごとの不良率を確認できるため、特に不良率の高い工程の作業内容や環境改善に取り組めます。
課題
生産管理システムを導入するには費用がかかります。導入時にかかる初期費用の他に、システムを運用するための維持費も必要です。オンプレミス型やクラウド型など、システムの種類でも費用は変わります。
また、生産管理システムを効果的に活用するには現場の理解が欠かせません。導入目的や達成したいことを丁寧に説明し、積極的に協力してもらう体制を整えることも重要です。
生産計画を最適化する自動化システムの選び方

生産管理システムを導入する際に重要となるのが、自社に適したシステムの選び方です。企業の状況や目的に応じて必要な機能は異なり、生産管理システムの種類もさまざまです。ここでは、システムを選ぶ際のポイントを2つ紹介します。
操作しやすいか
生産管理システムを選ぶ際に大切なのは、操作性です。多くの人がシステムを操作するため、分かりやすく操作しやすいシステムを選びましょう。
操作が複雑なシステムは、導入から運用開始までに時間がかかり、トラブルシューティングも大変です。現場の混乱を招く可能性もあります。
また、システムに搭載している機能も重要です。必要な機能がないばかりか、不要な機能が多いシステムを選ぶと効果は期待できません。業種によって必要な機能は異なるため、導入前に生産計画に必要な機能を明確にしましょう。
自社システムと連携が可能か
生産計画は、在庫数や販売予測のデータを基に作成します。
これらのデータが既存の基幹システムにある場合、新しい生産管理システムと連携できなければ十分に活用できません。関連データを生産計画に活用するには、基幹システムと連携できるシステムが必要です。
また、社内データをリアルタイムで収集し、BIツールなどを用いて意思決定に生かしている企業もあります。この場合も、BIツールが生産管理システムの情報を取り入れられるか事前に確認しましょう。
生産計画の最適化にノーコードAIの『UMWELT』を導入しよう!

システム導入によって生産計画の最適化を実現したい企業様には、TRYETINGの『UMWELT』がおすすめです。
生産管理業務の効率化に役立つ機能を豊富に搭載し、業務の自動化による省力化も可能なAI予測プラットフォームです。ここでは、UMWELTの特徴と導入事例を紹介します。
豊富な機能を備えているから自社システムと連携が可能
UMWELTは、AIによる既存データを活用した高精度な予測ができます。需要予測や在庫管理、安全在庫計算など、生産計画の立案に関連する機能も豊富です。DXやAIに関する専門的な知識は不要で、既存の従業員が操作できます。
また、APIによりさまざまなシステムと連携が可能です。UMWELTで計算した結果はBIツールなどに出力でき、迅速な意思決定にも役立つでしょう。
UMWELTの導入事例をチェック
キング醸造株式会社様では、生産計画の立案時に利用する出荷予測の精度にばらつきがあり、在庫の過不足が発生していました。また、出荷拠点が複数あることから予測する品目数も多く、予測や生産計画の作業に多くの工数が必要でした。
既存の手法で出した予測値とUMWELTで出した予測値を実際の販売値と比較し、トライアルでUMWELTの精度を実感いただけました。
本導入に至ったポイントは、基幹システムや受発注システムのデータのみで予測値が出せること、業務によって柔軟な予測結果を得られることです。
(参考:『【キング醸造株式会社様】UMWELT導入事例|調味料の需要予測を短期間で実現|TRYETING』)
まとめ
生産計画の最適化は、企業の利益向上には欠かせない取り組みです。しかし、実現にはさまざまな課題があり、従来の方法では解決が難しいこともあります。
UMWELTは、生産計画の最適化に役立つ豊富な機能を搭載しています。幅広い業種の生産管理に適用でき、難しい操作も必要ありません。生産計画の改善を目指す企業様は、ぜひTRYETINGにご相談ください。
product関連するプロダクト
-

UMWELTウムベルト
UMWELTは、プログラミング不要でかんたんに分析や自動化ができるノーコードツールです。需要予測から生産計画を最適化、人材の最適配置まで課題を解決できます。日々変化する生産数や生産計画、人員配置を自動立案し属人化や作業時間を大幅に削減します。

TRYETING
公式
TRYETING公式です。
お知らせやIR情報などを発信します。