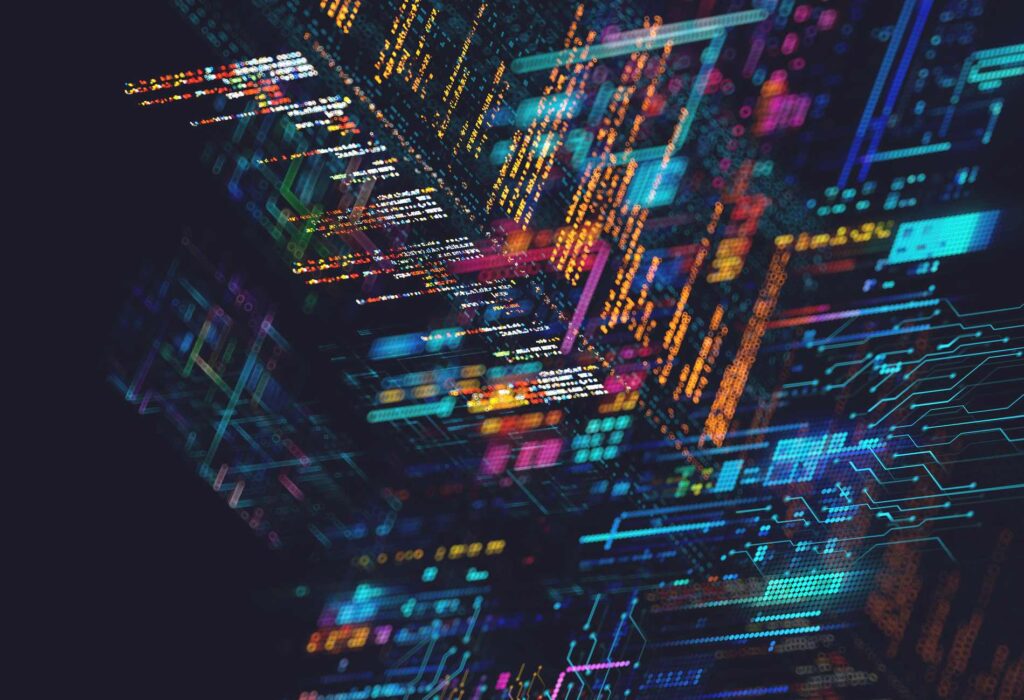BUSINESS
生産管理の役割や業務内容は?課題から効率化する方法まで解説!

目次
本記事では、生産管理の基本から実践的な効率化方法まで、包括的に解説します。生産管理の役割や業務内容を理解し、企業が直面する課題や解決策を学ぶことができます。需要予測、工程管理、品質管理など、生産管理の主要な業務を詳しく説明し、QCDの改善やPDCAサイクルの活用方法も紹介します。
さらに、生産管理システムの導入による効率化や、システム選びのポイントも解説します。特に、TRYETINGの『UMWELT』というシステムが生産管理業務の効率化に有効であることを示します。この記事を読むことで、生産管理の全体像を把握し、効率的な生産活動を実現するための具体的な方策を学ぶことができます。
1. 生産管理の基本

生産管理は製造業において非常に重要な役割を果たしています。製品の企画から製造、出荷までの一連のプロセスを効率的に管理し、品質、コスト、納期を最適化することが目的です。ここでは生産管理の基本的な概念と重要性について解説します。
1.1 生産管理とは生産工程を統合的に管理すること
生産管理とは、製品の受注から出荷までの全工程を統合的に管理することを指します。具体的には以下のような業務が含まれます。
- 需要予測
- 生産計画の立案
- 資材調達
- 製造工程の管理
- 品質管理
- 在庫管理
- 出荷・物流管理
これらの業務を効率的に連携させることで、生産活動全体の最適化を図ります。生産管理の目的は、必要な製品を必要な時に必要な量だけ生産し、無駄なく顧客に届けることです。
1.2 目的はスムーズな生産活動のため
生産管理の主な目的は、生産活動をスムーズに進めることです。具体的には以下の3つの要素(QCD)を最適化することを目指します。
| 要素 | 説明 |
|---|---|
| Quality(品質) | 製品の品質を一定以上に保つこと |
| Cost(コスト) | 生産コストを適切に管理すること |
| Delivery(納期) | 約束した納期を守ること |
これらの要素をバランス良く管理することで、企業の競争力向上につながります。NTTによると、QCDの向上は顧客満足度の向上にもつながるとされています。
1.3 工程管理との相違
生産管理と工程管理は似て非なるものです。主な違いは以下の通りです。
- 生産管理:製品の企画から出荷までの全工程を対象とする
- 工程管理:製造工程のみを対象とする
つまり、工程管理は生産管理の一部であり、生産管理はより広範囲で総合的な管理を行います。生産管理は工程管理を包含する上位概念と言えます。
1.3.1 生産管理システムの重要性
近年の製造業では、生産管理システムの導入が進んでいます。経済産業省の報告によると、生産管理システムの導入により以下のような効果が期待できます。
- 生産性の向上
- 個人のスキルから脱却した管理
- 在庫の適正化
- 品質の安定化
生産管理システムを活用することで、人的ミスの削減や迅速な意思決定が可能となり、企業の競争力強化につながります。
2. 生産管理にはどのような仕事がある?基本業務内容

生産管理には多岐にわたる業務があります。製品の企画から出荷まで、生産活動全体を統括的に管理する重要な役割を担っています。ここでは、生産管理の基本的な業務内容について詳しく解説します。
2.1 需要予測
需要予測は生産管理の出発点となる重要な業務です。以下の要素を考慮しながら、自社製品の将来的な需要を予測します。
- 過去の受注データの分析
- 販売計画との整合性
- 季節変動や時期による需要の変化
- 市場全体のトレンド
- 競合他社の動向
正確な需要予測により、過剰在庫や欠品による機会損失を防ぐことができます。また、日立ソリューションズによると、需要予測の精度向上は企業の利益率に大きく寄与するとされています。
2.2 受注業務管理
受注業務管理は、顧客からの注文情報を適切に把握し管理する業務です。主に以下の情報を管理します。
- 顧客情報
- 製品名・型番
- 注文数量
- 金額
- 納期
これらの情報は生産計画の立案に直結するため、正確かつタイムリーな情報共有が極めて重要です。例えば、営業部門と製造部門の間で受注情報の齟齬があると、生産計画に大きな影響を与える可能性があります。
2.3 生産計画
生産計画は、需要予測と受注情報を基に、具体的な生産スケジュールを立案する業務です。以下の要素を考慮しながら計画を立てます。
- 生産数量と納期
- 必要な人員・設備・資材
- 各工程にかかる時間
- 在庫状況
無理と無駄のない最適な生産計画を立てることが重要です。スケジュールに無理があると品質低下や納期遅延のリスクが高まり、逆に無駄が多いと過剰在庫などによるコスト増大につながります。
2.4 調達(購買)
調達(購買)業務は、生産に必要な原材料や部品、設備などを適切に調達する役割を担います。主な業務内容は以下の通りです:
- 必要な資材の選定
- サプライヤーの選定と価格交渉
- 発注と納期管理
- 在庫管理
コスト削減と安定供給のバランスを取ることが重要です。また、経済産業省が支援する事例によると、調達業務の効率化を行うことで物流業務のリジェリエンス向上が狙いであると紹介されています。
2.5 工程管理
工程管理は、実際の製造工程を監督し、計画通りに生産が進んでいるかを管理する業務です。主な業務内容は以下の通りです。
- 製造工程の設定と最適化
- 進捗管理
- 品質チェック
- 問題発生時の対応
リアルタイムでの状況把握と迅速な対応が求められます。工程管理の質が直接製品の品質や納期に影響するため、高度なスキルと経験が必要とされる業務です。
2.6 品質管理
品質管理は、製品が設定された品質基準を満たしているかを確認する業務です。具体的には以下のような作業を行います。
- 品質基準の設定
- 製造工程での品質チェック
- 完成品の検査
- 不良品の分析と改善策の立案
一定以上の品質を維持することは、顧客満足度と企業ブランドの維持向上につながります。日本科学技術連盟の記事によると、品質管理の徹底は長期的な企業価値の向上に大きく貢献するとされています。
2.7 在庫管理
在庫管理は、原材料から完成品まで、各段階での在庫状況を適切に管理する業務です。主な業務内容は以下の通りです:
- 在庫数量の把握と記録
- 適正在庫量の設定
- 在庫の入出庫管理
- 棚卸し
過剰在庫と在庫切れのバランスを取ることが重要です。適切な在庫管理は、コスト削減と顧客満足度の向上の両立につながります。
2.8 出荷管理
出荷管理は、完成した製品を顧客に届けるまでの過程を管理する業務です。主な業務内容は以下の通りです。
- 出荷計画の立案
- 梱包・ラベリング
- 輸送手段の選択と手配
- 出荷状況の追跡
正確かつ迅速な出荷は顧客満足度に直結します。また、出荷管理の効率化はコスト削減にもつながるため、多くの企業が注力している分野です。
2.9 原価管理
原価管理は、製品の製造にかかる全てのコストを把握し、管理する業務です。主な業務内容は以下の通りです。
- 材料費、労務費、経費の計算
- 原価の分析と削減策の立案
- 予算と実績の比較
- 原価情報の報告
適切な原価管理は企業の収益性向上に直結します。大興電子によると、原価管理の精度向上は企業の粗利改善に大きく寄与するとされています。
| 業務 | 主な内容 | 重要ポイント |
|---|---|---|
| 需要予測 | 将来的な製品需要の予測 | 過去データ、市場動向の分析 |
| 受注業務管理 | 顧客からの注文情報管理 | 正確な情報共有 |
| 生産計画 | 具体的な生産スケジュール立案 | 無理と無駄のない計画 |
| 調達(購買) | 必要資材の調達 | コストと安定供給のバランス |
| 工程管理 | 製造工程の監督と管理 | リアルタイムでの状況把握 |
| 品質管理 | 製品品質の確認と維持 | 一定以上の品質維持 |
| 在庫管理 | 各段階での在庫状況管理 | 過剰在庫と在庫切れの防止 |
| 出荷管理 | 製品の出荷過程管理 | 正確かつ迅速な出荷 |
| 原価管理 | 製造コストの把握と管理 | コスト削減と利益率向上 |
これらの業務を適切に遂行し、相互に連携させることで、効率的な生産管理が実現します。近年では、IoTやAIなどのテクノロジーを活用し、これらの業務をさらに効率化・高度化する取り組みも増えています。生産管理の質を高めることは、企業の競争力向上に直結する重要な課題といえるでしょう。
3. 生産管理の仕事は難しい?企業が抱える課題

生産管理は製造業において非常に重要な役割を担っていますが、多くの企業が様々な課題に直面しています。ここでは、一般的な生産管理の課題について詳しく解説します。
3.1 需要予測の難しさ
需要予測は生産管理において最も重要かつ難しい課題の一つです。正確な需要予測ができないと、過剰生産や在庫不足といった問題が発生し、企業の収益に大きな影響を与えます。
需要予測が難しい主な理由は以下の通りです。
- 市場の変化が激しく、過去のデータだけでは予測が困難
- 季節変動や特殊要因(例:パンデミック、自然災害)の影響を正確に見積もるのが難しい
- 新製品の需要予測には過去データがないため、特に困難
- 競合他社の動向や経済状況など、外部要因の影響を予測するのが難しい
これらの課題に対処するために、多くの企業が高度な需要予測ツールやAIを活用し始めています。経産省によると、AIを活用した需要予測の精度を向上させるためには定期的なモニタリングが必要とのことです。
3.2 業務の平均化が難しい
生産管理において、業務負荷を平準化することは非常に重要ですが、同時に大きな課題でもあります。業務の繁閑の差が大きいと、設備や人員の無駄が生じたり、品質低下や納期遅延のリスクが高まったりします。
業務平準化が難しい主な理由
- 受注の波が不規則で予測が困難
- 製品ごとに必要な工程や作業時間が異なる
- 急な特急注文や仕様変更への対応が必要
- 季節性の強い製品がある場合、年間を通じた平準化が困難
これらの課題に対処するため、多くの企業が以下のような取り組みを行っています。
- 生産計画の最適化ツールの導入
- 多能工化による柔軟な人員配置
- 平準化生産方式(ヘイジュンカ)の導入
- サプライチェーン全体での情報共有と協力体制の構築
3.3 想定外のトラブルリスク
製造現場では様々な予期せぬトラブルが発生する可能性があり、これらへの対応は生産管理の大きな課題となっています。想定外のトラブルは生産計画の遅延や品質問題につながり、顧客満足度の低下や経済的損失を招く恐れがあります。
主な想定外トラブルとその影響
| トラブル | 影響 |
|---|---|
| 設備の突発的な故障 | 生産ラインの停止、納期遅延 |
| 原材料の供給遅延 | 生産計画の変更、在庫不足 |
| 品質不良の発生 | 返品・交換対応、信頼性低下 |
| 自然災害 | 工場の操業停止、サプライチェーンの混乱 |
これらのリスクに対処するため、企業は以下のような取り組みを行っています。
- 予防保全の徹底による設備故障の削減
- 複数のサプライヤーの確保によるリスク分散
- 品質管理システムの強化
- BCP(事業継続計画)の策定と定期的な見直し
3.4 ヒューマンエラーからの損失
生産管理においてヒューマンエラーは避けられない問題であり、多くの企業が課題として認識しています。ヒューマンエラーは品質不良、生産効率の低下、安全性の問題など、様々な形で損失につながる可能性があります。
主なヒューマンエラーの種類と対策
| エラーの種類 | 対策 |
|---|---|
| 操作ミス | マニュアルの整備、定期的な研修 |
| 判断ミス | ダブルチェック体制の構築、意思決定支援システムの導入 |
| 記録ミス | 自動記録システムの導入、データ入力の自動化 |
| コミュニケーションエラー | 情報共有ツールの活用、定期的なミーティングの実施 |
中央大学の資料によると、検査で発見される不良の約75%がヒューマンエラーによるものであり、その削減が重要な課題となっています。
3.5 管理担当の属人化
生産管理業務の属人化は、多くの企業が直面している重要な課題の一つです。特定の個人の経験や勘に頼った管理は、その人物が不在になった際に業務が滞るリスクがあり、また組織全体の生産性向上を妨げる要因にもなります。
属人化がもたらす主な問題点
- 知識やノウハウの共有が困難
- 業務の標準化が進まない
- 人事異動や退職時の引き継ぎが困難
- 業務の効率化やシステム化が進まない
- 組織全体の生産性向上が阻害される
属人化を解消するための取り組み:
- 業務プロセスの可視化と標準化
- ナレッジマネジメントシステムの導入
- 定期的なジョブローテーションの実施
- 生産管理システムの導入によるデータの一元管理
- 継続的な教育・研修プログラムの実施
3.6 部署間の調整が難しい
生産管理は多岐にわたる部署と密接に関わる業務であるため、部署間の調整は大きな課題となっています。営業、製造、購買、物流など、各部署の目標や優先順位が異なることで、全体最適化が困難になる場合があります。
部署間調整の難しさの主な要因
- 部署ごとのKPIや目標の違い
- 情報共有の不足や遅延
- 部署間の意思疎通の問題
- 全体最適よりも部分最適を優先する傾向
- 責任の所在が不明確な領域の存在
部署間調整を改善するための施策:
- クロスファンクショナルチームの編成
- 全社的な目標の設定と共有
- 部署横断的な情報共有プラットフォームの構築
- 定期的な部署間ミーティングの実施
- SCM(サプライチェーンマネジメント)の導入
大興電子の記事によると、部署間の効果的な連携やデータ管理を実現している企業は、リードタイム短縮を実現しているとのことです。
これらの課題に対処することで、企業は生産管理の効率を向上させ、競争力を強化することができます。次章では、これらの課題を解決するための具体的な方法について説明します。
4. 生産管理オペレーションを効率化する方法

生産管理の効率化は企業の競争力向上に欠かせません。ここでは、生産管理オペレーションを効率化するための主な方法を解説します。
4.1 QCDを改善する
QCD(Quality:品質、Cost:コスト、Delivery:納期)の改善は生産管理効率化の基本です。各要素のバランスを取りながら改善を進めることが重要です。
4.1.1 Quality(品質)の改善
品質管理システムの導入や従業員教育の徹底により、製品の品質向上を図ります。具体的な方法として以下が挙げられます。
- 統計的品質管理(SQC)の導入
- 全数検査からサンプリング検査への移行
- 品質マネジメントシステム(ISO 9001など)の取得
4.1.2 Cost(コスト)の削減
原材料費の削減、生産プロセスの効率化、在庫管理の最適化などによりコスト削減を実現します。主な方法は以下の通りです。
- サプライチェーンマネジメントの最適化
- リーン生産方式の導入
- 自動化・ロボット化の推進
4.1.3 Delivery(納期)の短縮
生産リードタイムの短縮、物流の効率化により、納期の短縮と遵守率の向上を図ります。具体的な方法として以下があります。
- 生産スケジューリングの最適化
- ジャストインタイム(JIT)生産の導入
- 物流システムの改善
4.2 PDCAサイクルを回す
PDCAサイクルは、Plan(計画)→Do(実行)→Check(評価)→Act(改善)のサイクルを繰り返すことで、継続的な改善を図る手法です。生産管理においても、このサイクルを効果的に回すことで効率化を実現できます。
4.2.1 Plan(計画)
現状分析を行い、目標を設定し、具体的な実行計画を立てます。例えば、月間生産量の10%増加を目標に、設備稼働率の向上や作業工程の見直しなどの計画を立てます。
4.2.2 Do(実行)
計画に基づいて実際の生産活動を行います。この段階では、計画通りに実行できているか常にモニタリングすることが重要です。
4.2.3 Check(評価)
実行結果を評価し、計画との差異を分析します。例えば、生産量が計画を下回った場合、その原因を特定します。
4.2.4 Act(改善)
評価結果に基づいて改善策を検討し、次のサイクルの計画に反映させます。例えば、ボトルネックとなっている工程の改善策を次の計画に盛り込みます。
PDCAサイクルを効果的に回すためには、各段階でのデータ収集と分析が不可欠です。生産管理システムを活用することで、このプロセスを効率的に進めることができます。
4.3 生産管理システムを導入する
生産管理システムの導入は、生産管理オペレーションの効率化に大きく貢献します。以下に主な利点を示します。
| メリット | 内容 |
|---|---|
| リアルタイムの情報管理 | 生産状況をリアルタイムで把握し、迅速な意思決定が可能になります。 |
| データの一元管理 | 部門間でのデータ共有が容易になり、情報の齟齬を防ぎます。 |
| 業務の自動化 | 日報作成や在庫管理などの定型業務を自動化し、作業効率が向上します。 |
| 精度の高い需要予測 | AIやビッグデータ分析を活用した高精度の需要予測が可能になります。 |
| トレーサビリティの向上 | 製品の生産履歴を詳細に記録し、品質管理や問題発生時の対応が容易になります。 |
生産管理システムの選定には、自社の業務プロセスとの適合性、拡張性、他システムとの連携性などを考慮することが重要です。また、経済産業省のスマートファクトリー推進事業など、政府の資料を活用することも検討に値します。
4.4 IoTとAIの活用
IoT(Internet of Things)とAI(人工知能)の活用は、生産管理の効率化に革新をもたらす可能性を秘めています。具体的な活用例は以下の通りです。
- センサーによる設備稼働状況のリアルタイムモニタリング
- AIによる需要予測と生産計画の最適化
- 機械学習を用いた品質管理システムの高度化
- 画像認識技術を活用した検品作業の自動化
これらの技術を効果的に導入するためには、デジタル人材の育成や既存システムとの連携など、組織全体での取り組みが必要です。
4.5 従業員教育とスキル向上
生産管理の効率化には、システムやツールの導入だけでなく、それらを使いこなす人材の育成も重要です。以下のような取り組みが効果的です。
- 生産管理手法(リーン生産方式、Six Sigmaなど)の研修実施
- データ分析スキルの向上を目的とした教育プログラムの提供
- 現場改善活動(カイゼン)の推進と成果発表会の開催
- 他社や他業界の優良事例の研究と自社への適用検討
従業員のスキル向上と意識改革により、生産管理の効率化を継続的に推進する組織文化を醸成することができます。
以上の方法を総合的に実施することで、生産管理オペレーションの大幅な効率化が期待できます。ただし、各企業の状況に応じて最適な手法を選択し、段階的に導入していくことが成功の鍵となります。
5. 生産管理システムの選び方
生産管理システムを選ぶ際は、以下の3つのポイントを重視することが重要です。
5.1 1. 機能の拡張性
生産管理システムを導入した後、業務フローの変更や新たなニーズが発生することがあります。そのため、将来的な機能拡張が可能なシステムを選ぶことが大切です。以下の点をチェックしましょう。
- カスタマイズ性の高さ
- モジュール追加の容易さ
- アップデートの頻度と内容
5.2 2. 既存システムとの相性
生産管理システムは単独で機能するものではなく、既存の販売管理システムや会計システムなどと連携して効果を発揮します。以下の点を確認しましょう。
- データ連携の容易さ
- APIの提供状況
- 他社システムとの実績
5.3 3. サポート体制の充実度
生産管理システムは複雑な機能を持つため、導入後のサポートが充実しているかどうかは非常に重要です。以下の点を確認しましょう。
- 導入時のトレーニング内容
- 問い合わせ対応の迅速さ
- 定期的なメンテナンスの有無
5.4 導入前の検討事項
システム選定の前に、以下の点を社内で十分に検討することが重要です:
| 検討項目 | 内容 |
|---|---|
| 現状の課題整理 | 現在の生産管理プロセスの問題点を明確化 |
| 必要機能の洗い出し | 解決したい課題に対応する機能を特定 |
| 予算設定 | 初期費用と運用コストを含めた予算計画 |
| 導入スケジュール | システム導入から運用開始までのタイムライン |
5.5 導入効果の測定
システム導入後は、以下のような指標を用いて効果を測定することが重要です。
- 生産リードタイムの短縮率
- 在庫回転率の改善
- 納期遵守率の向上
- 生産性(一人あたりの生産量)の向上
これらの指標を定期的に確認し、生産管理の効率化が実現できているかを評価しましょう。
5.6 注意点
生産管理システムの導入には以下の点に注意が必要です。
- 導入には一定の時間とコストがかかるため、長期的な視点での判断が必要
- 従業員のトレーニングや業務プロセスの変更が伴うため、組織全体での取り組みが重要
- セキュリティ対策を十分に行い、機密情報の保護に努める
適切な生産管理システムを選択し、効果的に運用することで、生産性の向上やコスト削減、品質改善などの大きな効果を得ることができます。自社の特性や課題に合わせて、最適なシステムを選択しましょう。
6. 生産管理業務のシステム化はTRYETINGの『UMWELT』がおすすめ!
生産管理業務のシステム化を検討している企業にとって、TRYETINGの『UMWELT』は非常に魅力的なソリューションです。UMWELTは、データ分析や業務自動化をノーコードで実現できる革新的なサービスです。
6.1 UMWELTの特徴
UMWELTには以下のような特徴があります。
- 約100種類のアルゴリズムを組み合わせた高度なデータ分析
- ドラッグ&ドロップの簡単操作でプログラミング不要
- 既存システムとのAPI連携が可能
- 社内全体でのアルゴリズム共有機能
6.2 生産管理における活用例
UMWELTは生産管理の様々な課題解決に活用できます。
| 課題 | UMWELTの活用方法 |
|---|---|
| 需要予測の精度向上 | 過去の販売データや外部要因を考慮した高精度な需要予測 |
| 在庫の最適化 | 需要予測に基づいた最適な発注量・生産量の算出 |
| 生産計画の効率化 | 各工程の所要時間予測と最適なスケジューリング |
| 品質管理の強化 | 不良品発生の要因分析と予兆検知 |
6.3 導入のメリット
UMWELTを導入することで、以下のようなメリットが期待できます。
- 業務効率の大幅な向上:データ入力や分析作業の自動化により、人的リソースを戦略的な業務に集中できます。
- データドリブンな意思決定:精度の高い予測や分析結果に基づいた客観的な判断が可能になります。
- 部門間連携の強化:データやアルゴリズムの共有により、部門を越えた情報活用が促進されます。
- コスト削減:在庫の最適化や生産効率の向上により、無駄なコストを削減できます。
6.4 導入事例
実際にUMWELTを導入した企業の事例を見てみましょう。
株式会社ニシケンでは、UMWELTを活用して建設機械のレンタル需要予測を実施。過去の実績データや気象情報などを組み合わせた分析により、予測精度が大幅に向上し、在庫の最適化に成功しました。
また、東急不動産株式会社では、UMWELTを用いてリゾート施設の需要予測を行い、収益の最大化と業務効率化を実現しました。
6.5 導入のステップ
UMWELTの導入は以下のステップで進められます。
- 現状の課題分析と目標設定
- 必要なデータの洗い出しと収集
- UMWELTを用いたモデル構築とテスト
- 既存システムとの連携設定
- 運用開始と継続的な改善
TRYETINGのサポートチームが導入から運用まで丁寧にサポートするため、IT知識が豊富でなくても安心して利用を開始できます。
6.6 まとめ
TRYETINGの『UMWELT』は、生産管理業務のシステム化において非常に有効なツールです。高度なデータ分析と業務自動化を簡単に実現でき、企業の生産性向上とコスト削減に大きく貢献します。生産管理の効率化を目指す企業にとって、UMWELTの導入を検討する価値は十分にあるでしょう。
7. まとめ
生産管理は企業の製造活動において非常に重要な役割を担っています。需要予測から出荷管理まで、幅広い業務をカバーし、効率的な生産活動を支えています。
しかし、需要予測の難しさや業務の平準化、想定外のトラブルなど、多くの課題も抱えています。これらの課題を解決するには、QCDの改善やPDCAサイクルの実践、そして生産管理システムの導入が効果的です。
特に、TRYETINGの『UMWELT』のような最新のシステムを活用することで、生産管理業務の効率化と精度向上が図れます。適切な生産管理システムを選択し、運用することで、企業の競争力向上につながります。生産管理の重要性を理解し、継続的な改善を行うことが、製造業の成功への鍵となるでしょう。
product関連するプロダクト
-

UMWELTウムベルト
UMWELTは、プログラミング不要でかんたんに分析や自動化ができるノーコードツールです。需要予測から生産計画を最適化、人材の最適配置まで課題を解決できます。日々変化する生産数や生産計画、人員配置を自動立案し属人化や作業時間を大幅に削減します。

TRYETING
公式
TRYETING公式です。
お知らせやIR情報などを発信します。