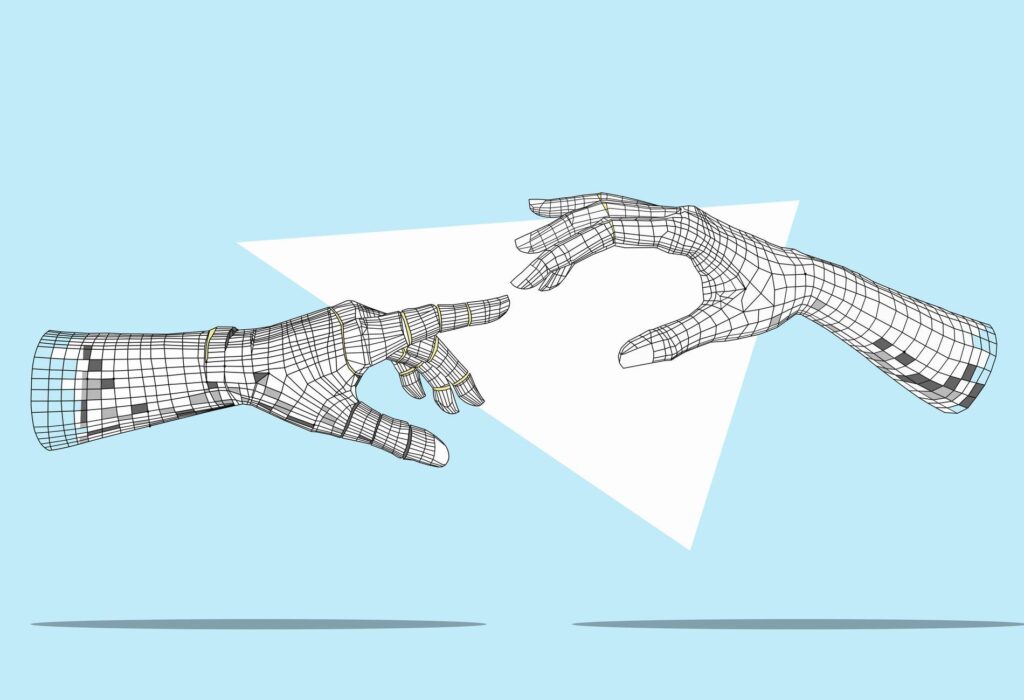PHILOSOPHY
路上の哲人、犬のディオゲネス〜「アテネの学堂」スーパーガイド②〜

目次
マイクロフト・ホームズはかく語りき

コナン・ドイル作シャーロック・ホームズの短編「ギリシャ語通訳」にはこんな不思議な“社交場”の描写がある。
「ディオゲネス・クラブというのはロンドンでもいちばん風変わりなクラブなんだよ。ロンドン中の社交嫌いの男たちを大半網羅している。クラブ員はおたがいにほかのクラブ員に絶対関心をもってはいけないし、外来者室以外では、どんな事情があっても談話することを許されない」
シャーロックの兄マイクロフト・ホームズが創立に資した人嫌いの人々向けの沈黙の社交場であり、このクラブの名前に冠されたのが、古代ギリシアの“狂ったソクラテス”こと哲学者ディオゲネスである。
狂ったソクラテスとはプラトンがディオゲネスを表現した言葉だが、貴族的な他の哲学者たちとは一線を画す、樽甕に住み浮浪者としてアテナイに生き、奴隷として死んだ異色の哲人である。マイクロフトの定めた社交嫌いがディオゲネスに当てはまるかはやや疑問だが、人間社会の制度や規範から一切を捨てて自由になり、1人で生きたと言う点ではあながち間違いでもないかもしれない。
「アテネの学堂」でも装飾的服装に身を包んだ哲人たちの中で、粗末な布一枚をだらしなく着て石段に腰掛け寝そべり、まるで老いた野犬のような風貌で描かれている。実際に古代アテナイの人々はディオゲネスを犬のようだとも形容し嘲笑ったが、同時に人々から愛され一目置かれ、後のストア派に多大な影響を与えた。
彼は何故犬のような暮らしを自ら選んだのか、この異色の哲人の思想に迫ってみたい。
裸の愚者か、最強の賢人か

「アテネの学堂」でラファエロは、ディオゲネスを群衆の中央空間というなんとも大胆な位置に描いている。遠近法の焦点であるプラトンとアリストテレスの次に目がいくのはディオゲネスかもしれない。
他がグループで議論する中、階段で誰とも交わらず腰掛け、体勢は殆ど寝そべっているようなだらしなさである。哲人が集う間にこのような人物が混ざっていたら、少しギョッとしてしまうかもしれない。それほどダイナミックな構図である。
その我関せずな風変わりな姿勢は、同じく対になるように独りで配置されている(ヘラクレイトスとして描かれた)ミケランジェロと共に、彼らの飛び抜けた個性や聡明な変わり者という印象を私たちにも与えてくる。ディオゲネスにモデルがいたとしたらミケランジェロに劣らぬ個性の持ち主だったに違いないがモデルは分かっていない。
ただしディオゲネスの逸話だけを鑑みると、モデルとされることはルネサンス時代でもやや不名誉と考えられたのだろうか、ラファエロが空想で描いたとしても不思議ではない。

服装は粗末な青い布切れ一枚で、殆どはだけていて裸に近い。老齢のディオゲネスの服装としてはあまりに不釣り合いである。上衣なのか寝袋なのかそのどちらにも使われているのか、シワシワの布地を下敷きにくつろぎながら何か紙を読み耽っている(当然紀元前はパピルスの巻物の時代であるから、まだ紙は存在していない)。ディオゲネスの右手傍らには、飲みかけなのか杯がことりと置かれている。
ネズミを模範とし、酒樽を棲家とす

ディオゲネスという人物について、同名の哲学史家ディオゲネス・ラエルティオスが紀元後3世紀頃に書いた『ギリシア哲学者列伝』に詳しく描写している。この著作は今日までギリシャ哲学研究のための重要史料であり、今後も連載の中で度々引用されることになると思われる。紀元前の哲学者たちの生き様をユニークで愉快なエピソードで我々に伝えてくれている。
ディオゲネスは両替商ヒケシアスの息子で現在のトルコのシノペに生まれた。父は市の公金を扱う今で言うところの造幣局の長のような仕事をしていたとされるが、ディオゲネス共々通貨を改鋳した罪で追放されることとなった。一説には父は獄中死し、ディオゲネスのみギリシャ、アテナイへ逃れついたとされている。
この通貨改鋳事件は、ディオゲネスがアポロン神殿に参ったところ、アポロンから「国の中で広く通用しているものを変えることをゆるす(ポリティコン・ノミスマ、つまり制度や習慣のこと)」という神託を受けたとされるが、ディオゲネスがそれをそのままの意味で捉え通貨を粗悪なものに作り変えるに至ったという逸話もある。
アテナイに辿り着いたディオゲネスは、哲学者アンティステネスのところへ身を寄せた。ソクラテスに影響を受けたアンティステネスは、彼独特の姿勢として世界を貴族的に壮麗なものではないとして清貧を重んじた為に、ディオゲネスのような貧しい人々が慕い集まるようになった。アンティステネスに弟子入りを許されたのち、未だ亡命の身であった為、異邦人としてアテナイでの非常に簡素な暮らしを始めた。
ディオゲネスはその当時既に老齢さしかかっていたとされるが、突然に富裕層からホームレスのような暮らしになったことは非常な困難だったに違いない。自分に仕えるマネスという名の奴隷すらそんな境遇の主人を見捨てて去り、人々はディオゲネスを憐れに思いマネスを捜索することを提案したが、「おかしな話だよ」「もし、(奴隷の)マネスはディオゲネスなしにも生きていけるが、ディオゲネスの方はマネスなしには生きていけないだろうとすれば」と応えて捜索はしないこととした。
そんな中、ディオゲネスは鼠を観察し、彼らが寝床を求めず、美味美食とされているものを欲しがりもせずに走り回っているのを見て、自分の置かれた状況を切り抜ける手立てを見出したとされている。
彼は着古した衣服で身を包み眠り、頭陀袋に食べ物を入れて持ち歩いた。どんな場所でも話し合いや食事や寝床に使い、ゼウスの神殿の柱廊や祭の道具をしまう保管庫であるポンペイオンを指差して「アテナイ人は自分のために住みかをしつらえてくれている」と言っていた。その後メートローオンという神殿の公文書保管所にあった大甕(ワイン樽のようなものであるが、当時は酒を甕で作っていた)を住居として用いた。
全てを手放して犬のように生きる

納富信留著『哲学の根源』では、ディオゲネスの師となったアンティステネスは「労苦」を乗り越える鍛錬を重要な要素とみなしたが、それは季節を問わず同じ簡素な服装と裸足で過ごし、困難に立ち向かい死すらを平然と受け入れたソクラテスをモデルとした倫理観であるとしている。
こうした思想は連綿とディオゲネスにも受け継がれ、最低限の持ち物すら手放し、持たないことを選択することで心身共に自由になり、徳だけあれば自足して幸福に暮らせるという“足るを知る”姿勢として実践的に示した。
ある時ディオゲネスは小さな子が両手で水をすくって飲んでいるのを目にし「簡素な暮らしぶりでは、わたしはこの子に負けたよ」と言いながら頭陀袋の中からコップを取り出して投げ捨てた。また別の子供がパンを皿の代わりにスープを注いでいるのを見ると皿も投げ捨ててしまったという。
高貴な生まれや名声は悪徳を目立たせる飾りとして冷笑し、社会的地位や金銭的充足という価値観から脱却し、精神的幸福を鍛錬によって追求した。鍛錬は精神的鍛錬と肉体的鍛錬の二種類があり、どちらも欠けては完全なものとならないと説いた。
プラトンのような、貴族的暮らしをし、自らの学説を絶対真理として人々より高位に立ち“理解できる者のみ”に説いていた他の哲学者を嘲笑うように、彼らの授業などに現れ彼らの論理を堂々と皮肉ったり、突飛な行動をとって注目を集め授業を混乱させたりした。裕福に暮らしながら目に見えないものを論ずるより、1番低いところで生き、人間の暮らしと今目に見えるものを重んじたのだろう。

彼のスタンスはどんな権力者を前にしても変わることなく、それがより人々の好奇と尊敬を集めた。
ある時、ディオゲネスが一向に挨拶に現れないので、アレクサンドロス大王がディオゲネスのほうを訪ねて彼の前に立ちながら「何なりと望みのものを申してみよ」と言った。するとディオゲネスは「どうか、わたしを日陰におかないでいただきたい(あなたが立つと日が遮られるので退いてほしい)」と答えたという。
またアレクサンドロス大王が「お前は、余が恐ろしくないのか」と言ったとき、それに対して「いったい、あなたは何者なのですか。善い者なのですか、それとも、悪い者なのですか」と訊ねた。そこで大王が、「むろん、善い者だ」と答えると、「それでは、誰が善い者を恐れるでしょうか」と彼は言ったとある。
実にディオゲネスらしい、市井の哲人の芯を突いた言葉にアレクサンドロスは感銘を受けたに違いない。後に「私がアレクサンドロスでなければ、ディオゲネスになりたい」と言ったという逸話が残っている。
また異邦人であったがゆえだろうか、人々から「本当は何人なのか」と問われると当時のポリス的国家社会区分に意を唱え「自分はコスモポリテース(世界市民)である」と発言した最初の人物であると記録されている。今でこそ世界全体で人類、人間は独立した存在であるという考え方は一般的であるが、当時は大変奇異な姿勢であったに違いない。
人々はディオゲネスに骨を投げたり「犬」と呼称して嘲笑しながらも、その奇抜な人物像と達観したものの見方は様々な信奉者を生み、アテナイの人々に愛された。
ディオゲネスの様々な逸話は語り継がれ、彼をモデルとして生きる「キュニコス派(犬儒学派)」が誕生した。またキュニコス派のクラテスの弟子としてキプロス島の哲学者ゼノンが説いたストア派にも、その生き様が取り入れられていった。
獣の餌になる程に、私は自由だ

ディオゲネスは老年、奴隷として売りに出されてしまうという困難にまたも見舞われている。しかし買主であるクセニアデスとも対等に渡り合い一目置かれ、彼の息子たちの教育係として大変重宝された。
ディオゲネスの最期は諸説あるが、1番印象深いのは、彼が自分自身で息を止めて(自身を窒息させて)逝去したという逸話だろう。何ものからも自由であった哲人は、死期すらも自らの手で選びとり、自立したまま死んでいったのである。
ディオゲネスは死に際して、死んだ後は埋葬しないで、どんな野獣の餌食にでもするように投げ捨てておくか、イリス河へ投げ込まれることを望んだ。ラエルティオスはこれを、他人に迷惑をかけないために、と記しているが、ここにもディオゲネスの生き様が表れているように思う。
この遺言は2021年に亡くなったノンフィクション作家の立花隆を思い起こさせる。臨死体験を研究し“死後の世界はあるのか”、がん研究を通して“人は何故死ぬのか”という人間の命題に向き合った立花が辿り着いた答えは、「死んだら物質的には、無に返る」ということだった。その答えをもって、彼は「遺体はゴミとして捨ててほしい」と言い残した。
人は1人で生まれて、1人で死に、無に還帰する。それほどまでに自由だということを、ディオゲネスと立花は体現しているのかもしれない。
ディオゲネスは死は悪い者かと訊かれ、「どうして悪いものでありえよう。それがやってきたとき、われわれが知覚することのないものが」と答えた。
紀元前323年、ディオゲネスを敬愛したアレクサンドロス大王がバビロンで滅したのと同じ日に、コリントスで亡くなったと伝えられている。
参考文献
ディオゲネス・ラエルティオス著 加来彰俊訳「ギリシア哲学者列伝(中)」岩波書店、1989年
高畠純夫著「古代ギリシアの思想家たち〜知恵の伝統と闘争〜」山川出版社、2014年
荻野弘之著「哲学の饗宴〜ソクラテス・プラトン・アリストテレス〜」日本放送出版協会、2003年
荻野弘之著「哲学の原風景〜古代ギリシアの知恵のことば〜」日本放送出版協会、1999年
サー・アーサー・コナン・ドイル著 延原謙訳「シャーロック・ホームズの思い出」新潮社、1942年
納富信留著「西洋哲学の根源」放送大学教育振興会、2022年

伊藤 甘露
ライター
人間、哲学、宗教、文化人類学、芸術、自然科学を探索する者