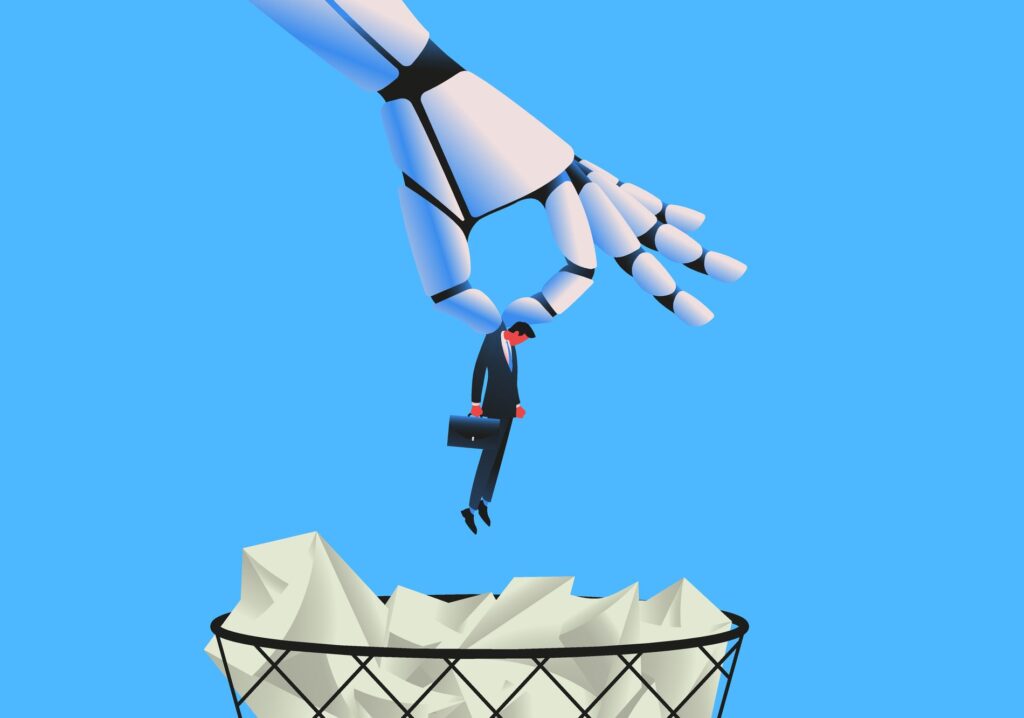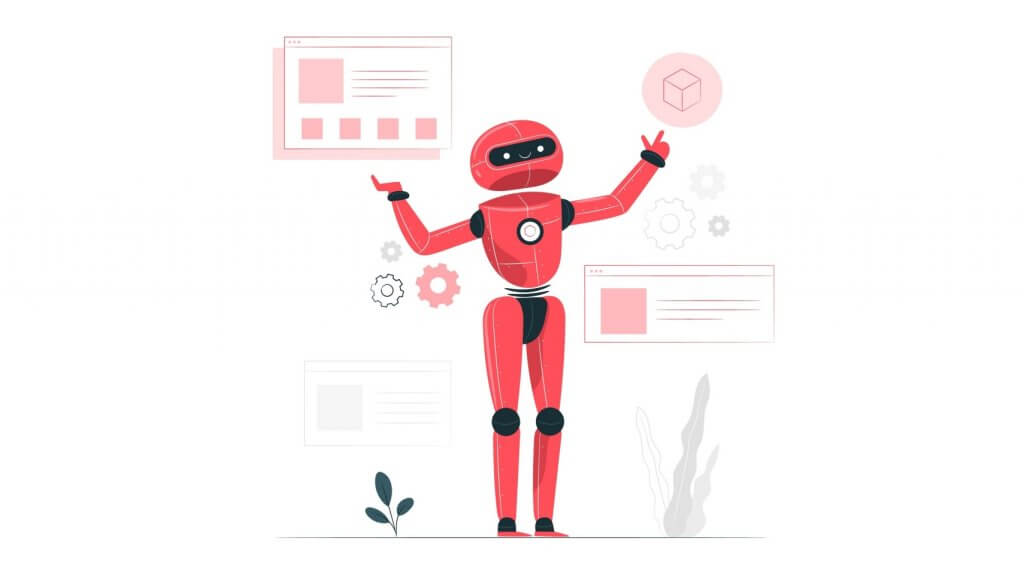BUSINESS
在庫管理システムを自作する方法|Excel・Accessでの作り方から費用、注意点まで解説

目次
在庫管理システムの自作を検討していませんか?本記事では、ExcelやAccess、ノーコードツールを使った具体的な自作方法から、開発費用、失敗しないための5つのステップまで網羅的に解説します。
市販システムとの比較を通じて、自社の規模や目的に最適な在庫管理の方法を見極めるための判断材料を提供。この記事を読めば、自作のメリット・デメリットを理解し、最適な選択ができるようになります。
1. 在庫管理システムの自作は可能?まずはメリット・デメリットを理解しよう

結論から言うと、在庫管理システムの自作は可能です。特にExcelやAccessといった身近なツールを使えば、専門の開発会社に依頼するよりもコストを抑えて、自社独自のシステムを構築できます。
しかし、手軽に始められるからといって、安易に自作に踏み切るのは危険です。自作には大きなメリットがある一方で、専門知識の不足や運用面の課題といったデメリットも存在します。
まずは自作のメリットとデメリットを正しく理解し、市販のシステムを導入する場合と比較検討することが、失敗しない在庫管理システム導入の第一歩です。この章では、自作を判断するために不可欠なメリット・デメリットを詳しく解説します。
1.1 在庫管理システムを自作するメリット
在庫管理システムを自作する最大の魅力は、市販のシステムにはない「自由度の高さ」と「コストパフォーマンス」にあります。具体的にどのようなメリットがあるのか、3つのポイントに分けて見ていきましょう。
1.1.1 コストを抑えて導入できる
自作の最も分かりやすいメリットは、導入コストを大幅に削減できる点です。市販のパッケージ型在庫管理システムや、月額料金が発生するSaaS(クラウド)型システムを導入する場合、初期費用やライセンス料、ランニングコストがかかります。
一方、自作であればこれらの費用は原則として発生しません。特に、多くの企業で既に導入されているMicrosoft OfficeのExcelやAccessを活用すれば、新たなソフトウェア費用をかけることなく開発をスタートできます。開発を内製化することで、外部への発注費用もかからず、予算が限られている中小企業や小規模事業者にとっては大きな魅力となるでしょう。
1.1.2 自社の業務フローに完全に最適化できる
市販のシステムは汎用的に作られているため、自社の特殊な業務フローや管理方法に合わないケースが少なくありません。「この機能は不要なのに消せない」「自社独自の管理項目を追加したいのにできない」といった不満から、結局システムを使わなくなり、Excelでの手管理に戻ってしまうこともあります。
自作であれば、自社の業務内容に合わせてゼロから設計できます。例えば、商品のロット番号管理や使用期限管理、業界特有の在庫評価方法、独自の承認フローなどを自由に組み込むことが可能です。現場の担当者が本当に使いやすい画面設計や操作性を追求できるため、導入後の定着がスムーズに進み、業務効率を最大限に高めることができます。
1.1.3 必要な機能だけを搭載したシンプルな設計にできる
高機能な市販システムは、多機能であるがゆえに操作が複雑になりがちです。使わない機能が多数表示されることで、かえって担当者が混乱し、入力ミスを誘発する原因にもなりかねません。
自作の場合、自社にとって本当に必要な機能(例:入出庫登録、在庫一覧の表示、発注点アラートなど)だけに絞って搭載できます。これにより、誰にとっても直感的で分かりやすい、シンプルなシステムが実現します。操作方法の習得にかかる時間や教育コストを削減できるだけでなく、システムの動作が軽快になるというメリットも期待できます。
1.2 在庫管理システムを自作するデメリット・注意点
多くのメリットがある一方で、自作には相応のスキルや工数が求められ、見過ごせないデメリットも存在します。特に運用開始後に出てくる問題も多いため、開発に着手する前に以下の注意点を必ず確認してください。
1.2.1 開発・保守に専門知識と工数が必要
システムを自作するには、当然ながら開発スキルが必要です。Excelで作成するならVBA(Visual Basic for Applications)、Accessならデータベース設計やクエリの知識が求められます。より本格的なシステムを目指すなら、プログラミング言語やデータベース、サーバーに関する専門知識が不可欠です。
また、問題は開発時だけではありません。完成後も、OSのアップデートに伴う動作不良の修正、新たなバグの発見と対応、業務内容の変更に伴う機能追加など、継続的な保守・メンテナンス作業が発生します。これらの作業にも専門知識と工数が必要であり、「一度作ったら終わり」ではないことを理解しておく必要があります。
1.2.2 セキュリティ対策を自社で行う必要がある
在庫データには、仕入価格や取引先情報など、企業の重要な機密情報が含まれます。万が一、これらの情報が外部に漏洩したり、サイバー攻撃によってデータが改ざん・消失したりすれば、事業に深刻なダメージを与えかねません。
市販のSaaS型システムであれば、提供元のベンダーが高いレベルのセキュリティ対策を講じていますが、自作の場合はすべて自社で責任を負うことになります。アクセス権限の適切な設定、不正アクセスからの防御、データの暗号化、定期的な脆弱性診断など、専門的なセキュリティ対策を自社で設計・実装・運用しなければならない点は、非常に大きな負担でありリスクです。
1.2.3 担当者の異動や退職による属人化リスク
自作システムで最も陥りやすいのが「属人化」の問題です。システムを開発した特定の担当者しか、その詳細な仕様やプログラムの中身を理解していない「ブラックボックス」状態になってしまうケースが後を絶ちません。
この状態で担当者が異動や退職をしてしまうと、簡単な修正やトラブル対応すら誰もできなくなり、最悪の場合、システム自体が利用不能に陥るリスクがあります。
このリスクを避けるためには、詳細な設計書や操作マニュアルを整備し、複数の担当者で情報を共有する体制を構築することが不可欠ですが、そのためのドキュメント作成や引き継ぎにも相応の工数がかかることを忘れてはなりません。
2. 【4つの選択肢】在庫管理システムの自作方法とそれぞれの特徴

在庫管理システムを自作するといっても、その方法は一つではありません。企業の規模、管理する在庫の量、予算、そして社内のITスキルに応じて、最適な選択肢は異なります。
ここでは代表的な4つの自作方法を取り上げ、それぞれのメリット・デメリット、そしてどのようなケースに向いているのかを詳しく解説します。自社の状況と照らし合わせながら、最適な開発方法を見つけましょう。
2.1 Excel(VBA)で自作する
多くの企業で日常的に利用されているMicrosoft Excelは、在庫管理システムを自作する上で最も手軽な選択肢です。関数やVBA(Visual Basic for Applications)というプログラミング機能を活用することで、単なる表計算ソフトを超えた簡易的なシステムを構築できます。
2.1.1 メリット・デメリット
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ・多くのPCに標準インストールされており、追加コストがほぼかからない ・普段から使い慣れているため、操作の習得が容易 ・関数やVBAを使えば、入出庫の自動計算など、ある程度の自動化が可能 ・レイアウトや項目を自由に追加・変更できる |
・複数人での同時編集に不向きで、データ破損のリスクがある ・データ量が増える(数万行を超える)と動作が極端に遅くなる ・高度なセキュリティ設定が難しく、人的ミスによるデータ改ざんや削除が起こりやすい ・作成した担当者に依存しやすく、異動や退職でメンテナンス不能になる「属人化」のリスクが高い |
2.1.2 Excelでの自作に向いているケース
- 管理する品目(SKU)が少なく、在庫の動きが比較的緩やかな小規模事業者
- 在庫管理の担当者が1名、または特定の少数に限定されている場合
- まずはコストをかけずに在庫管理のデジタル化を試してみたいスタートアップ企業
- 複雑な分析や他のシステム(会計ソフトなど)との連携が不要な場合
2.2 Accessで自作する
Microsoft Accessは、Excelと同じくMicrosoft Officeスイートに含まれるデータベース管理ソフトです。Excelが表計算ソフトであるのに対し、Accessはデータベースの構築に特化しており、より大量のデータを効率的に、かつ安全に管理する能力に長けています。Excelでの管理に限界を感じた場合の、次のステップとして有力な選択肢です。
2.2.1 メリット・デメリット
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ・データベース機能により、Excelよりも大量のデータを安定して扱える ・テーブル間の関連付け(リレーションシップ)で、データの整合性を保ちやすい ・入力フォームやレポート(帳票)を直感的に作成できる ・複数人での同時利用にも、Excelより高いレベルで対応可能 |
・データベース設計やSQL、VBAに関する専門知識が必要 ・Office Professionalなど上位エディションにしか含まれず、別途ライセンス費用が必要な場合がある ・クラウド非対応のため、社外からのアクセスやスマートフォンでの利用は基本的に困難 ・ファイルの容量に2GBという上限がある |
2.2.2 Accessでの自作に向いているケース
- 管理品目数が数百〜数千点規模の中小企業
- Excelでの在庫管理に動作の遅さやデータ破損といった問題を感じている企業
- 社内にAccessやデータベースの知識を持つ人材がいる場合
- 入庫伝票や在庫一覧表など、定型的な帳票を印刷する業務が多い場合
* 複数の担当者が同時に在庫情報を更新する必要がある環境
2.3 ノーコード・ローコードツールで自作する
近年、IT専門家でなくても業務アプリケーションを開発できる「ノーコード・ローコード」ツールが注目されています。これらのツールは、プログラミング言語を記述することなく、マウス操作や簡単な設定でシステムを構築できるのが特徴です。代表的なツールには、サイボウズの「kintone(キントーン)」やMicrosoftの「Power Apps」などがあります。
2.3.1 メリット・デメリット
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ・プログラミングが不要なため、開発期間を大幅に短縮できる ・クラウドベースで提供されるため、場所を選ばずアクセス可能 ・スマートフォンやタブレット用のアプリも同時に作成できることが多い ・豊富なテンプレートが用意されており、一から作る手間を省ける |
・月額または年額のライセンス費用(ランニングコスト)が発生する ・プラットフォームの機能に依存するため、デザインや機能のカスタマイズに限界がある ・サービス提供が終了するリスクや、料金改定の影響を受ける可能性がある ・非常に複雑な業務ロジックや外部システムとの特殊な連携は難しい場合がある |
2.3.2 ノーコード・ローコードでの自作に向いているケース
- 社内にIT専門の部署や開発担当者がいない企業
- 現場の担当者が主体となって、業務改善を進めたい場合
- 倉庫や店舗など、現場でスマートフォンを使ってリアルタイムに入出庫を記録したい場合
- 開発にかかる時間を最小限に抑え、スピーディーにシステムを導入したい企業
2.4 プログラミング言語で本格開発する
既存のツールでは実現できない、完全にオリジナルの在庫管理システムを求める場合、プログラミング言語を用いた本格的なスクラッチ開発が選択肢となります。Python、PHP、JavaといったWeb系の言語と、MySQLやPostgreSQLなどのデータベースを組み合わせて、要件に100%合致したシステムを構築します。
2.4.1 メリット・デメリット
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ・自社の特殊な業務フローに合わせて、機能を完全に自由に設計できる ・ECサイトや会計システム、基幹システム(ERP)など、あらゆる外部システムと柔軟に連携できる ・将来の事業拡大に合わせて、自由に機能を拡張していける高いスケーラビリティを持つ ・パフォーマンスやセキュリティ要件を自社の方針に合わせて最適化できる |
・プログラミング、データベース、サーバー、セキュリティなど広範で高度な専門知識が必須 ・開発に数ヶ月から1年以上の期間と、数百万円以上の高額なコストがかかる ・完成後の保守・運用にも専門の担当者と継続的なコストが必要 ・開発を外部に委託する場合、要件定義からベンダー選定、プロジェクト管理まで多くの工数を要する |
2.4.2 本格開発が向いているケース
- 独自の商習慣や複雑な在庫評価方法があり、市販のシステムでは対応できない企業
- 複数のECモールや実店舗の在庫を一元管理し、販売機会の損失を徹底的に防ぎたい企業
- 将来的にAIによる需要予測や自動発注など、高度な機能を実装したいと考えている企業
- 社内に開発部門がある、もしくはシステム開発に十分な予算と時間を投資できる体力のある企業
3. 失敗しない!在庫管理システム自作の5ステップ

在庫管理システムの自作は、思いつきで進めると失敗のリスクが高まります。しかし、計画的にステップを踏んで開発を進めることで、自社の業務に本当にフィットした、価値あるシステムを構築することが可能です。ここでは、システム開発の経験が少ない方でも失敗しないための、具体的な5つのステップを解説します。
3.1 ステップ1:要件定義(目的と必要な機能の洗い出し)
開発に着手する前に、最も重要なのが「要件定義」です。このステップでは、「なぜシステムが必要なのか」「誰が、何のために使うのか」「どのような機能が必要か」を徹底的に明確にします。ここでの定義が曖昧だと、開発の途中で方向性がぶれたり、完成したシステムが使われないといった事態に陥りかねません。
まずは、現在の在庫管理業務の流れを可視化し、課題点を洗い出しましょう。「手入力によるミスが多い」「リアルタイムで在庫数がわからない」「棚卸に時間がかかりすぎる」など、現場の担当者にヒアリングを行い、具体的な問題点をリストアップすることが成功への第一歩です。
3.1.1 実装すべき必須機能リスト
洗い出した課題を解決するために、最低限必要となる機能を定義します。多機能を目指すのではなく、まずは「これがないと業務が回らない」というコアな機能に絞り込むことがポイントです。
| 機能カテゴリ | 具体的な機能内容 | 目的 |
|---|---|---|
| 商品マスタ管理 | 商品コード、商品名、仕入先、単価などの基本情報を登録・更新・削除する機能。 | 商品情報を一元管理し、入力の揺れを防ぐ。 |
| 入出庫管理 | 商品の入庫日、出庫日、数量、担当者などを記録する機能。登録と同時に在庫数が自動で増減する。 | 誰がいつ、何を動かしたかを記録し、在庫数の正確性を保つ。 |
| 在庫照会・検索 | 商品名や商品コードで現在の在庫数を検索・一覧表示する機能。 | 必要な時に、迅速かつ正確に在庫状況を把握する。 |
| アラート機能 | あらかじめ設定した在庫数(発注点)を下回った際に、通知や警告を表示する機能。 | 欠品による販売機会の損失や、生産遅延を防ぐ。 |
3.1.2 あると便利な拡張機能リスト
必須機能が固まったら、次に「あるとさらに業務が効率化する」拡張機能を検討します。これらは初期開発に含めず、運用が安定した後のフェーズ2で追加することも可能です。
| 機能カテゴリ | 具体的な機能内容 | 導入によるメリット |
|---|---|---|
| バーコード・QRコード連携 | バーコードリーダーやスマートフォンのカメラでコードを読み取り、入出庫作業を簡略化する機能。 | 手入力ミスを撲滅し、作業スピードを大幅に向上させる。 |
| 棚卸機能 | 実在庫とデータ上の在庫を照合し、差異を記録・調整するための機能。 | 定期的な棚卸作業の負担を軽減し、在庫精度を高める。 |
| 複数倉庫・ロケーション管理 | 複数の倉庫や、倉庫内の棚番(ロケーション)ごとに在庫を管理する機能。 | どこに何がいくつあるかを正確に把握し、ピッキング作業を効率化する。 |
| ABC分析機能 | 売上や出荷量に応じて商品をA・B・Cのランクに分け、在庫管理の優先度を可視化する機能。 | 重点的に管理すべき商品を明確にし、在庫の最適化を図る。 |
| レポート出力機能 | 期間別の入出庫履歴、在庫推移、在庫回転率などを集計し、CSVやPDF形式で出力する機能。 | データに基づいた経営判断や、業務改善の分析に役立てる。 |
3.2 ステップ2:基本設計(データベースと画面UI)
要件定義で決めた機能を、具体的なシステムの「設計図」に落とし込むフェーズです。ここでシステムの骨格となるデータベースと、利用者が直接触れる画面(ユーザーインターフェース)の設計を丁寧に行うことで、手戻りの少ないスムーズな開発が可能になります。
3.2.1 データベース設計のポイント
データベースはシステムの心臓部です。ここで管理するデータの構造を決めます。Excelで言えば、どのようなシート(テーブル)を作り、各シートにどのような列(項目)を持たせるかを定義する作業に相当します。ポイントは、情報の重複をなくし、後から拡張しやすい構造にすることです。
| テーブル名 | 主な項目(フィールド)の例 | 役割 |
|---|---|---|
| 商品マスタ | 商品コード(主キー)、商品名、カテゴリ、仕入先コード、標準単価、発注点 | 商品の基本情報を管理する台帳。 |
| 在庫テーブル | 商品コード、倉庫コード、ロケーション、現在在庫数、最終更新日時 | リアルタイムの在庫数を場所ごとに管理する。 |
| 入出庫履歴テーブル | 履歴ID(主キー)、処理日、商品コード、入出庫区分、数量、担当者名、備考 | すべての在庫変動の記録を時系列で保存する。 |
| 仕入先マスタ | 仕入先コード(主キー)、仕入先名、住所、電話番号、担当者 | 取引のある仕入先情報を管理する。 |
各テーブルには「主キー」と呼ばれる、データを一意に識別するための項目(例:商品コード)を設定することが重要です。また、データの整合性を保つために「正規化」という考え方を取り入れ、関連するデータを適切にテーブル分割することを意識しましょう。
3.2.2 ユーザーインターフェース(UI)設計のポイント
UIは、システムの使いやすさを直接左右します。どんなに高機能でも、操作が複雑で分かりにくいシステムは現場で使われません。PC操作に不慣れな人でも直感的に使えることを目指し、画面のレイアウト(ワイヤーフレーム)を紙やツールで作成してみましょう。
- 入力画面:入力ミスを防ぐ工夫が重要です。商品名を手入力させるのではなく、商品コードを入力したら自動で表示されるようにしたり、日付はカレンダーから選択できるようにしたり、担当者名はドロップダウンリストから選べるように設計します。
- 一覧画面:必要な情報が一目でわかるように、表示項目や並び順を工夫します。在庫数が少ない商品を赤字で表示するなど、視覚的な分かりやすさも考慮しましょう。
- ボタンの配置:「登録」「更新」「削除」など、よく使うボタンは分かりやすい場所に配置し、誤って押しにくいデザインにします。
3.3 ステップ3:開発・実装
設計書に基づいて、実際にシステムを構築していく工程です。選択したツール(Excel VBA、Access、ノーコードツールなど)を使い、データベースの作成、画面の作成、機能のプログラミング(または設定)を行います。
このステップでのポイントは、一度にすべてを作ろうとしないことです。まずは「商品マスタ管理機能」、次に「入庫機能」というように、機能単位で小さく作り、その都度動作を確認しながら進める「モジュール開発」がおすすめです。これにより、問題が発生した際に原因を特定しやすくなります。
また、開発の過程で行った変更は、必ず記録を残しましょう。ファイル名に日付やバージョンを付けて保存するだけでも、後から「いつの時点のファイルに戻したい」という時に役立ちます。これは簡易的なバージョン管理であり、トラブル発生時のリスクを低減します。
3.4 ステップ4:テストと改善
開発したシステムが、設計書通りに正しく動作するかを検証する、非常に重要な工程です。開発者自身の思い込みや見落としがないか、客観的な視点で厳しくチェックします。
テストは段階的に行うのが効果的です。
| テストの種類 | 確認内容 | 実施者 |
|---|---|---|
| 単体テスト | 個々の機能(例:入庫ボタンを押すと在庫数が増えるか)が単独で正しく動作するかを確認する。 | 開発者 |
| 結合テスト | 複数の機能を連携させた場合(例:入庫登録後、在庫照会画面に正しく反映されるか)に問題がないかを確認する。 | 開発者 |
| 総合テスト | システム全体を通して、要件定義で定めたすべての機能や性能を満たしているかを確認する。 | 開発責任者 |
| 受け入れテスト | 実際の業務担当者が、実際の業務の流れに沿ってシステムを操作し、実用上問題がないか、使いにくい点はないかを確認する。 | 現場の担当者 |
テストで発見された不具合(バグ)や改善点はすべてリストアップし、修正と再テストを繰り返してシステムの品質を高めていきます。特に、受け入れテストで現場担当者から挙がった「もっとこうだったら使いやすい」という意見は、システムの価値を大きく向上させるヒントになります。
3.5 ステップ5:導入と運用ルールの策定
完成したシステムを実際の業務で活用し始める最終ステップです。システムの導入を成功させ、継続的に活用していくためには、事前の準備とルール作りが不可欠です。
まず、既存の在庫データ(Excelファイルなど)を新しいシステムに移行する「データ移行」の計画を立てます。次に、システムの利用者全員が迷わず操作できるよう、分かりやすい「操作マニュアル」を作成します。これが後の属人化を防ぐ重要な資産となります。
そして最も重要なのが「運用ルール」の策定と周知徹底です。ルールが曖昧なまま導入すると、人によって入力方法が異なったり、データ更新がされなかったりして、せっかくのシステムが機能しなくなります。以下のような項目を明確に文書化し、関係者全員で共有しましょう。
- 入力のタイミング:「商品が入荷したら、その日のうちに必ず入庫処理を行う」など、データ入力のタイミングを具体的に決めます。
- 担当者の役割分担:誰がマスタ情報の管理を行い、誰が日々の入出庫を入力するのか、責任の所在を明確にします。
- 棚卸のルール:「毎月末に、〇〇の手順で棚卸を実施し、システム上の在庫と差異があれば責任者に報告する」といった手順を定めます。
- トラブル発生時の対応:システムに不具合が生じた際の報告先や、一時的な代替業務のフローなどを決めておきます。
利用者向けの研修会を開き、操作方法と運用ルールを丁寧に説明することで、スムーズな導入と定着を図ることができます。
4. 自作した在庫管理システムの運用で直面する課題と対策
在庫管理システムは、開発して完成したら終わりではありません。むしろ、安定して運用し続けることこそが重要です。自作したシステムは、市販のパッケージソフトと異なり、運用中に発生する様々な課題に自社で対応していく必要があります。ここでは、運用フェーズで直面しがちな4つの主要な課題と、その具体的な対策について詳しく解説します。
4.1 定期的なデータバックアップと復旧計画
自作システムで最も警戒すべきリスクの一つが、データの消失です。人的な操作ミス、ハードウェアの故障、サイバー攻撃、災害など、様々な原因で在庫データが失われる可能性があります。在庫データは企業の資産そのものであり、これが失われると事業継続に深刻な影響を及ぼしかねません。
対策:バックアップの自動化と復旧テストの実施
データの安全性を確保するためには、定期的かつ自動的なバックアップ体制の構築が不可欠です。バックアップ戦略の基本として「3-2-1ルール」が推奨されています。
- 3つのデータコピーを保持する(本番データ+2つのバックアップ)
- 2種類の異なるメディアに保存する(例:内蔵HDDと外付けHDD)
- 1つはオフサイト(遠隔地)に保管する(例:クラウドストレージ)
具体的なバックアップ方法と推奨頻度は以下の通りです。
| バックアップ方法 | 特徴 | 推奨頻度 |
|---|---|---|
| 自動バックアップ | スクリプトやタスクスケジューラを利用し、深夜など業務時間外に自動でデータを複製・保存する。人為的ミスを防ぎ、確実性が高い。 | 毎日(少なくとも1日1回) |
| 手動バックアップ | システムの大きな変更前や、週次・月次の締め処理後などに、担当者が手動でバックアップを取得する。 | 週に1回以上 |
| オフサイトバックアップ | 物理的に離れた場所(別の事業所やクラウドストレージサービスなど)にデータを保管する。災害対策として極めて重要。 | 毎日または週に1回 |
さらに、バックアップデータがあるだけでは不十分です。「本当にデータを復元できるか」を確認するための復旧テスト(リストア訓練)を定期的に行い、万が一の事態に備えた具体的な復旧手順書(リカバリープラン)を策定しておくことが重要です。
4.2 情報漏洩を防ぐセキュリティ対策
在庫データには、商品の仕入価格や原価、取引先情報といった機密情報が含まれています。これらの情報が外部に漏洩すれば、企業の信用失墜や金銭的損害に直結します。自作システムは、セキュリティ対策も自社の責任で行わなければなりません。
対策:多層的なセキュリティ対策の導入
脆弱性を突かれないよう、複数の観点からセキュリティ対策を講じる必要があります。
- アクセス制御の徹底:ユーザーごとにIDとパスワードを発行し、「閲覧のみ」「編集可能」など、業務に必要な最小限の権限(最小権限の原則)を付与します。退職者や担当変更者のアカウントは速やかに削除・無効化します。
- パスワードポリシーの強化:パスワードの最低文字数、複雑さ(英大文字・小文字・数字・記号の組み合わせ)を定め、定期的な変更を義務付けます。
- ソフトウェアの更新:OS、データベースソフト、Webサーバー、利用しているライブラリやフレームワークに脆弱性が発見された場合、速やかにセキュリティパッチを適用します。
- データの暗号化:データベースに保存する重要なデータ(特に個人情報や価格情報)は暗号化します。また、ネットワーク通信もSSL/TLSで暗号化し、盗聴を防ぎます。
- 操作ログの取得と監視:誰が、いつ、どのデータにアクセスし、何を行ったかのログを記録・保管します。定期的にログを監視し、不審なアクティビティがないかを確認する体制を整えます。
4.3 属人化を防ぐマニュアル作成とメンテナンス体制
自作システムは、開発した担当者にしか仕様やメンテナンス方法が分からない「属人化」に陥りがちです。その担当者が異動や退職をしてしまうと、誰もシステムを改修・保守できなくなり、小さな不具合が大きな問題に発展するリスクがあります。
対策:ドキュメントの整備とチームでの運用体制構築
システムの継続性を担保するため、知識や情報を個人に依存させない仕組み作りが不可欠です。
4.3.1 ドキュメントの作成と更新
以下のドキュメントを作成し、誰でも参照できる場所に保管します。また、システムを改修した際には、必ずドキュメントも更新するルールを徹底します。
| ドキュメントの種類 | 記載すべき内容 |
|---|---|
| 運用マニュアル | 日常の入出庫入力、棚卸処理、レポート出力などの操作手順。エラー発生時の対処法(トラブルシューティング)。 |
| システム設計書 | データベースのテーブル定義、画面レイアウト、機能一覧、処理フローなど、システムの全体像がわかる資料。 |
| ソースコードのコメント | VBAやプログラミング言語で開発した場合、コード内に処理の目的やロジックをコメントとして記述し、可読性を高める。 |
4.3.2 メンテナンス体制の整備
担当者を一人に限定せず、主担当と副担当を置くなど、複数人でシステムを管理する体制を構築します。定期的なミーティングで情報の共有を図り、データベースの最適化やエラーログの確認といった定期メンテナンスの計画を立てて実行します。
4.4 事業拡大に備えたシステムの拡張性
ビジネスの成長に伴い、取り扱う商品数や拠点数、システムを利用する従業員数は増加していきます。初期の小規模な運用を想定して作られたシステムでは、データ量の増加やアクセス集中によってパフォーマンスが著しく低下したり、新しい業務フローに対応できなくなったりする可能性があります。
対策:将来を見据えたスケーラブルな設計
開発の初期段階から、将来の拡張性を意識した設計を心掛けることが重要です。
- パフォーマンスの維持:データ量が増えても検索速度が落ちないよう、データベースに適切なインデックスを設定します。また、サーバーの性能向上(スケールアップ)やサーバー台数の追加(スケールアウト)が容易な構成を検討します。
- 機能追加の容易さ:「入庫管理」「出庫管理」「分析機能」など、機能ごとにプログラムを部品(モジュール)化して開発します。これにより、特定の機能を修正・追加する際に、他の機能への影響を最小限に抑えることができます。
- 外部システムとの連携:将来的に会計システムやECサイト、ハンディターミナルなどと連携する可能性を考慮し、API(Application Programming Interface)でのデータ連携がしやすい設計にしておくと、システムの価値をさらに高めることができます。
これらの運用課題に事前に対策を講じておくことで、自作した在庫管理システムを長期間にわたり安定して活用し、企業の成長を支える強力なツールとすることができます。
5. 自作は難しい?市販・SaaS型在庫管理システムとの比較
在庫管理システムの自作を検討する中で、「本当に自社で開発するのが最善の策だろうか?」という疑問を持つのは当然のことです。自作にはコスト削減や高いカスタマイズ性といった魅力がある一方で、市販のパッケージ型システムやクラウドベースのSaaS型システムにも、それぞれ優れた点があります。
この章では、自作システムと市販・SaaS型システムを「コスト」「機能・カスタマイズ性」「導入スピード・サポート体制」の3つの観点から徹底比較します。それぞれのメリット・デメリットを客観的に把握し、自社の状況に最適な選択をするための判断材料としてご活用ください。
5.1 コスト(初期費用・ランニングコスト)の比較
システムの導入と運用にかかるコストは、最も重要な比較ポイントの一つです。ここでは「自作」「パッケージ型(買い切り)」「SaaS型(月額課金)」の3つの形態に分けて、コスト構造を比較します。
| 形態 | 初期費用 | ランニングコスト | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 自作 | 低い〜非常に高い (人件費、開発環境による) |
低い〜高い (サーバー代、メンテナンス人件費) |
ExcelやAccessで開発すればソフトウェア費用は抑えられますが、開発にかかる人件費(工数)が実質的な初期費用となります。サーバーや保守にも継続的なコストが発生します。 |
| パッケージ型 | 高い (ライセンス購入費) |
中程度 (年間保守費用、アップデート費用) |
ソフトウェアのライセンスを買い取るため、初期費用が高額になる傾向があります。安定した運用には、ベンダーとの年間保守契約が別途必要になることがほとんどです。 |
| SaaS型 | 無料〜低い (初期設定費用) |
中程度〜高い (月額・年額利用料) |
初期費用を抑えて導入できるのが最大の魅力です。利用料はユーザー数やデータ量、機能に応じて変動するプランが多く、事業規模に合わせた柔軟なコスト管理が可能です。 |
自作は一見コストを抑えられるように見えますが、目に見えない人件費やメンテナンス工数を考慮すると、必ずしも最も安価な選択肢とは限りません。トータルコストを長期的な視点で比較検討することが重要です。
5.2 機能・カスタマイズ性の比較
次に、システムの心臓部である機能と、自社の業務に合わせるためのカスタマイズ性について比較します。求める機能レベルと業務の特殊性が、どの形態を選ぶかの大きな分かれ道となります。
| 形態 | 基本機能 | カスタマイズ性 | 拡張性(API連携など) |
|---|---|---|---|
| 自作 | 自社で要件定義した機能のみ | 非常に高い | 設計次第で可能だが、高い技術力が必要 |
| パッケージ型 | 網羅的・汎用的 | 制限あり(追加費用が発生する場合が多い) | 対応範囲は製品による |
| SaaS型 | 豊富(定期的にアップデート) | 提供される範囲内での設定変更が主 | API連携に対応しているサービスが多い |
自作の最大のメリットは、自社のユニークな業務フローに100%合致したシステムを構築できる点です。しかし、ハンディターミナル連携やAIによる需要予測といった高度な機能を実装するには、相応の技術力と開発期間が必要になります。
一方、市販・SaaS型システムは、多くの企業で必要とされる標準機能(入出庫管理、棚卸機能、ABC分析など)が予め網羅されており、すぐに高度な在庫管理を実現できます。特にSaaS型は、外部のECサイトや会計ソフトとのAPI連携が容易なサービスも多く、システム全体の連携をスムーズに行える利点があります。
5.3 導入スピード・サポート体制の比較
「いつから使えるか」という導入スピードと、「困ったときに頼れるか」というサポート体制も重要な選定基準です。特にIT専門の担当者がいない企業にとっては、サポートの有無が運用を左右します。
| 形態 | 導入スピード | サポート体制 | 属人化リスク |
|---|---|---|---|
| 自作 | 遅い(数ヶ月〜1年以上) | なし(すべて自社で対応) | 非常に高い |
| パッケージ型 | 比較的速い(設定・データ移行に時間) | ベンダーによる有償サポート | 低い |
| SaaS型 | 非常に速い(即日利用可能な場合も) | 充実(マニュアル、メール、チャットなど) | 非常に低い |
自作システムは、要件定義から設計、開発、テストという工程を経るため、導入までに長い期間を要します。また、最大の課題は「属人化」です。開発担当者が異動・退職した場合、システムの改修やトラブル対応が困難になるリスクを常に抱えています。
SaaS型であれば、契約後すぐに利用を開始でき、システムのアップデートやセキュリティ対策、サーバー管理はすべてサービス提供事業者に任せられます。マニュアルやFAQ、カスタマーサポートが充実しているため、専門知識がなくても安心して運用できる点が大きなメリットです。
5.4 自社に合うのは自作か市販か?判断のポイント
これまでの比較を踏まえ、自社にはどの選択肢が合っているのかを判断するためのポイントをまとめました。以下の項目をチェックし、自社の状況と照らし合わせてみましょう。
5.4.1 自作システムが向いているケース
- 管理する品目数が少なく、在庫の動きがシンプルである。
- 業務フローが非常に特殊で、市販のシステムでは対応できない部分が多い。
- 社内にシステム開発および継続的な保守・メンテナンスを行える人材がいる。
- 開発にかかる人件費を許容でき、時間をかけてでも完全にフィットするシステムを構築したい。
- セキュリティ対策やデータバックアップを自社の責任で完遂できる。
5.4.2 市販・SaaS型システムが向いているケース
- IT専門の担当者がおらず、システムの保守・運用にリソースを割けない。
- できるだけ早く在庫管理をシステム化し、業務効率を改善したい。
- 複数拠点や店舗間で、リアルタイムに在庫情報を共有する必要がある。
- ハンディターミナルやバーコードリーダーを使った効率的な検品・棚卸を行いたい。
- 将来の事業拡大を見据えて、拡張性や柔軟性の高いシステムを求めている。
- システムのセキュリティや法改正への対応を専門家に任せたい。
近年では、「ロジクラ」や「zaico」といった高機能かつ低コストで始められるSaaS型在庫管理システムが数多く登場しています。まずは無料プランやトライアルでSaaS型システムを試してみて、自社の業務にフィットするかどうかを確認した上で、自作の必要性を再検討するというアプローチも有効です。自社の体力と将来のビジョンに合った、最適な在庫管理の方法を選択しましょう。
6. まとめ
在庫管理システムの自作は、コストを抑えつつ自社業務に最適化できる魅力的な選択肢です。しかし、開発や保守には専門知識と工数が必要で、セキュリティや属人化のリスクも伴います。本記事で解説したExcelやAccess、ノーコードツールといった自作方法のメリット・デメリット、市販システムとの比較を踏まえ、自社の規模やリソースに本当に合っているか慎重に判断することが重要です。まずは目的と必要な機能を明確にすることから始めましょう。

TRYETING
公式
TRYETING公式アカウントです。
お知らせやIR情報などを発信します。