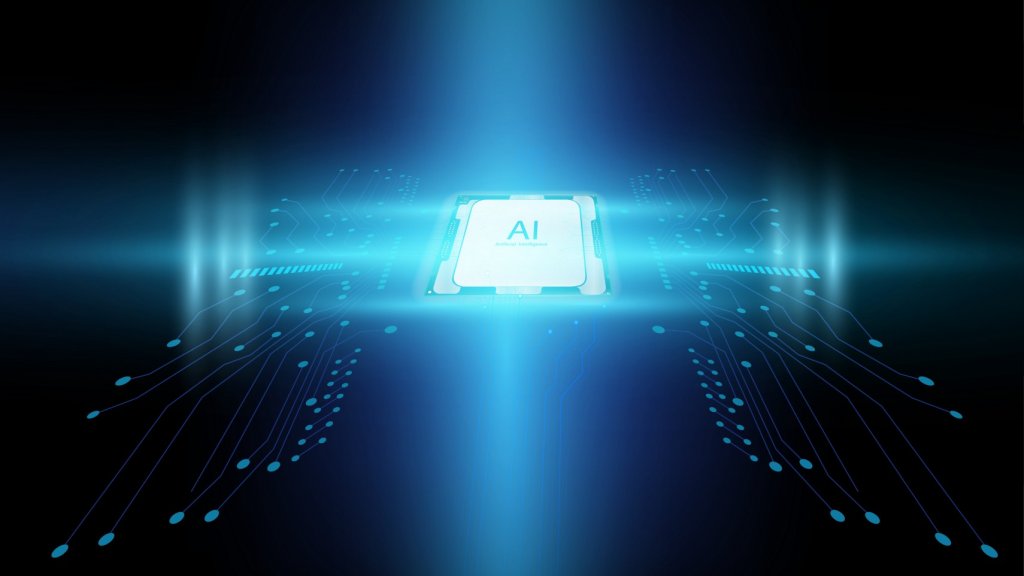BUSINESS
生産管理システムとは?導入するメリットや選び方を分かりやすく解説
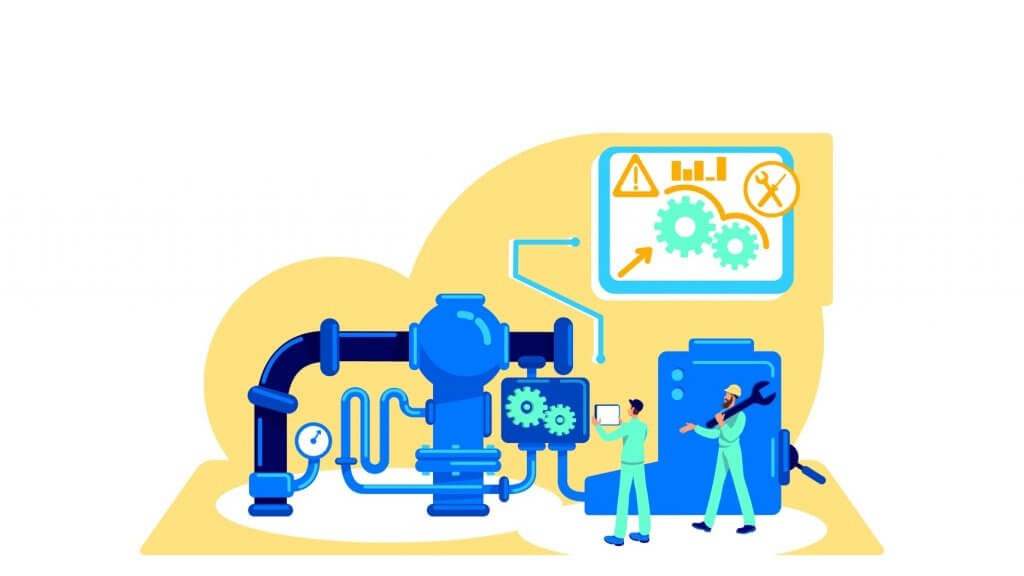
目次
生産管理システムとは?導入するメリットや選び方を分かりやすく解説

この記事では、生産管理システムの基本から導入メリット、選び方まで徹底解説します。生産管理システムとは何か、ERPやMESとの違い、重要な基本機能を理解できます。さらに、在庫管理精度の向上や人的ミスの削減など、導入によるメリットを詳しく説明。最適なシステムを選ぶポイントも、企業規模や業種、生産方式との適合性など、具体的に解説します。トヨタ生産方式のような日本発の生産管理手法にも触れながら、製造業の効率化や競争力強化につながる知識が得られます。導入における課題と対策も紹介し、生産管理システムについて包括的に理解できる内容となっています。
1. 生産管理システムとは何か
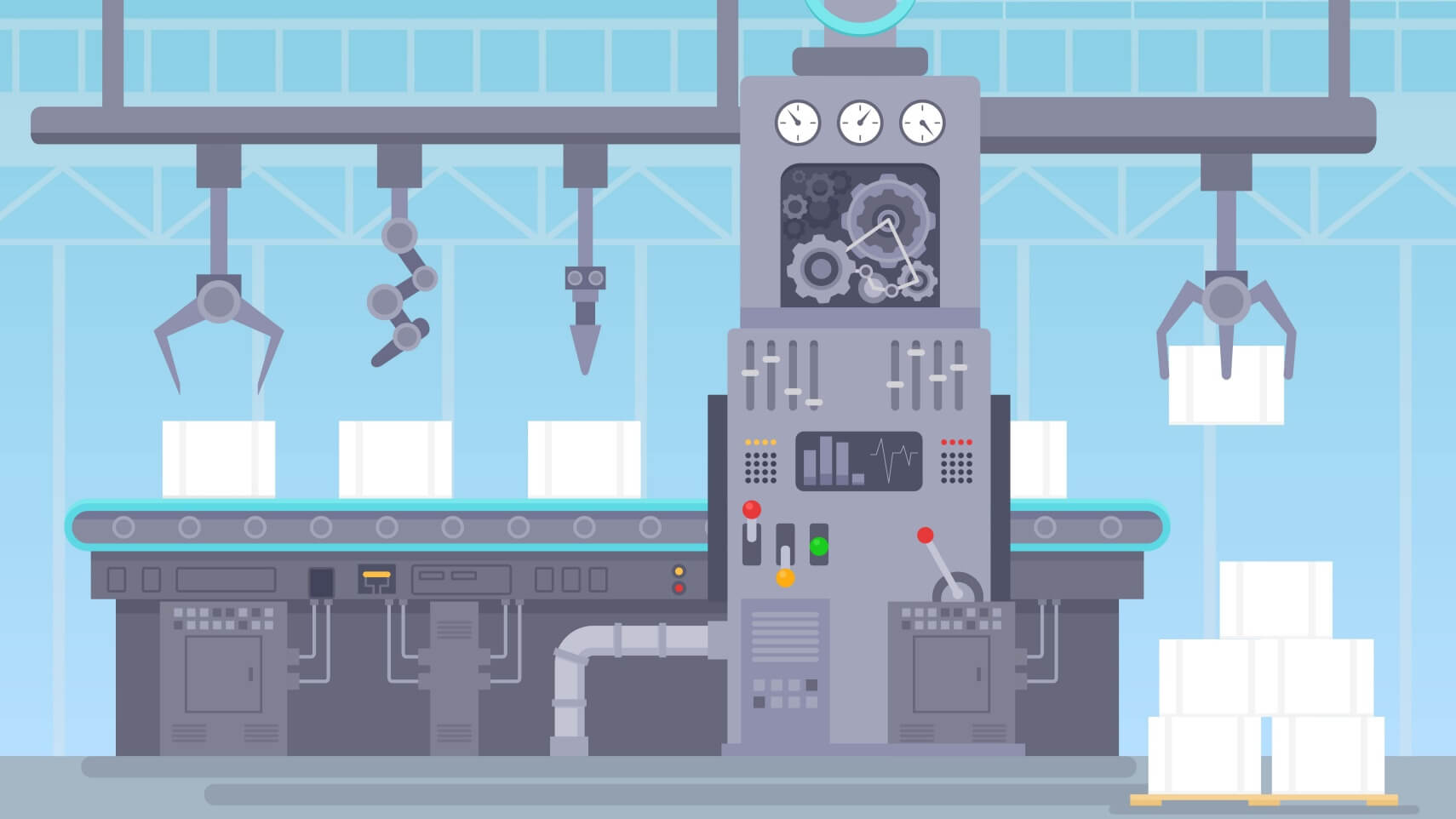
生産管理システムは、製造業において受注から出荷までの一連の業務を一元管理するシステムです。生産計画の立案、資材調達、製造、在庫管理などの業務を統合的に管理することで、業務効率化と生産性向上を実現します。
1.1 生産管理システムの定義と役割
生産管理システムの主な役割は以下の通りです。
- 生産計画の立案と管理
- 資材の調達と在庫管理
- 製造工程の進捗管理
- 品質管理
- コスト管理
- 納期管理
これらの機能を統合することで、製造現場の可視化、リアルタイムでの状況把握、迅速な意思決定が可能となります。例えば、経済産業省の資料によると、生産管理システムの導入により生産リードタイムの短縮や在庫の適正化などの効果が報告されています。
1.2 ERPやMESなど他システムとの違い
生産管理システムは、他の企業システムと以下のような違いがあります。
| システム | 特徴 | 主な対象範囲 |
|---|---|---|
| 生産管理システム | 製造業の生産に特化したシステム | 生産計画、資材調達、製造、在庫管理 |
| ERP (Enterprise Resource Planning) | 企業の経営資源を統合的に管理 | 財務、人事、販売、生産など企業全体 |
| MES (Manufacturing Execution System) | 製造現場のリアルタイム管理に特化 | 製造ラインの稼働状況、品質管理 |
ERPは企業全体の業務を統合的に管理するシステムであり、生産管理はその一部として位置づけられます。一方、MESは製造現場のリアルタイムな情報を収集・管理するシステムで、生産管理システムとの連携により、より詳細な製造プロセスの管理が可能になります。
生産管理システムは、これらのシステムと連携しながら、製造業の中核となる生産活動を効率的に管理する役割を果たします。例えば、経産省の資料では、生産管理システムとERPやMESとの連携による効果について詳しく解説されています。
生産管理システムを導入する際は、自社の業務プロセスや既存のシステム環境を十分に分析し、最適なシステム構成を検討することが重要です。また、導入後も継続的な改善と最適化を行うことで、より効果的な生産管理を実現できるでしょう。
2. 生産管理システムが担う重要な基本機能

生産管理システムは、製造業の生産性向上に欠かせない様々な機能を担っています。ここでは、生産管理システムの8つの基本的な機能について詳しく解説します。
2.1 生産計画
生産計画は、受注した製品を納期までに製造するための計画を立てる機能です。需要予測に基づいて、必要な資材や人員、設備の手配を行います。例えば、「今月は〇〇製品を△△台生産する」といった具合に、生産量と期間を決定します。
生産計画の期間は企業によって異なりますが、一般的には以下のようなものがあります。
- 3か月計画
- 月次計画
- 週次計画
これらの計画は、商品の受注データをベースとして、対象製品の在庫状況や納入時期、製品の原価などを考慮しながら作成されます。
2.2 資材管理
資材管理は、生産に必要な資材の種類と数量を把握し、過不足なく調達する機能です。生産計画と並行して行われ、完成品となる製品から必要となる部品などの量を計算し、納期までに間に合うよう調整します。
効果的な資材管理により、以下のようなメリットが得られます。
- 在庫の最適化
- 生産の遅延防止
- コスト削減
2.3 仕入管理
仕入管理は、仕入に関する情報を一括で管理する機能です。最適な仕入れ先を選定し、適切な価格と納期で調達することが主な役割です。
製造業では、製品完成までに様々な工程があるため、指定の日時までに全ての部品をそろえることが重要です。仕入管理機能により、以下のような確認が可能になります。
- 発注した部品が問題なく納品されているか
- 納品が遅延していないか
- 必要な部品数が納入されているか
2.4 販売管理
販売管理は、受注から出荷までの一連の流れを管理する機能です。この機能により、受注漏れや二重出荷などのミスを防ぎ、顧客満足度の向上につなげることができます。
販売管理機能の主な利点には以下のようなものがあります。
- 販売実績データの分析による需要予測の精度向上
- 効果的な販売戦略の立案
- 在庫回転率の向上
2.5 製造管理
製造管理は、生産計画に基づいて、製造工程の進捗状況を管理する機能です。ものづくりの現場では、製品が完成するまでに多くの工程を経るため、途中の状態となる仕掛品の把握も重要です。
製造管理機能により、以下のようなことが可能になります。
- 仕掛品の状態把握
- 次工程への作業指示
- 作業進捗の把握
- 生産効率の向上
2.6 在庫管理
在庫管理は、原材料や製品の在庫状況をリアルタイムで把握する機能です。適正な在庫量を維持することで、生産計画の立案や資材の発注がスムーズに行えるだけでなく、在庫の過不足を防ぐことで資金の無駄や機会損失を防げます。
在庫管理機能の主なメリットには以下のようなものがあります。
- 在庫の可視化による問題の早期発見・改善
- 適正在庫の維持によるコスト削減
- 欠品リスクの低減
2.7 予算管理
予算管理は、部門別もしくは組織全体における予算編成業務を効率的に行うための機能です。原材料や人件費、設備投資など、さまざまな支出を管理し、予算と実績の差異を分析できます。
予算管理機能により、以下のようなことが可能になります
- 無駄な支出の削減
- 来期以降の予算策定への活用
- 経営判断のためのデータ提供
2.8 原価管理
原価管理は、製品そのものにかかる費用を管理する機能です。正確に原価を把握することで、企業の経営活動に活用できます。
原価管理機能の特徴と利点には以下のようなものがあります。
- 仕入管理との連携による部品原価の正確な把握
- 人の手による原価計算よりも高い精度
- 適切な価格設定への活用
- 収益性の向上
これらの8つの基本機能を効果的に活用することで、生産管理システムは製造業の生産性向上に大きく貢献します。各機能が相互に連携することで、より効率的な生産管理が可能となり、企業の競争力強化につながります。
生産管理システムの導入を検討する際は、自社の業務プロセスや課題を十分に分析し、必要な機能を見極めることが重要です。また、経済産業省のデジタルトランスフォーメーション(DX)推進ガイドラインなども参考にしながら、戦略的にシステム導入を進めることをおすすめします。
3. 生産管理システム導入のメリット
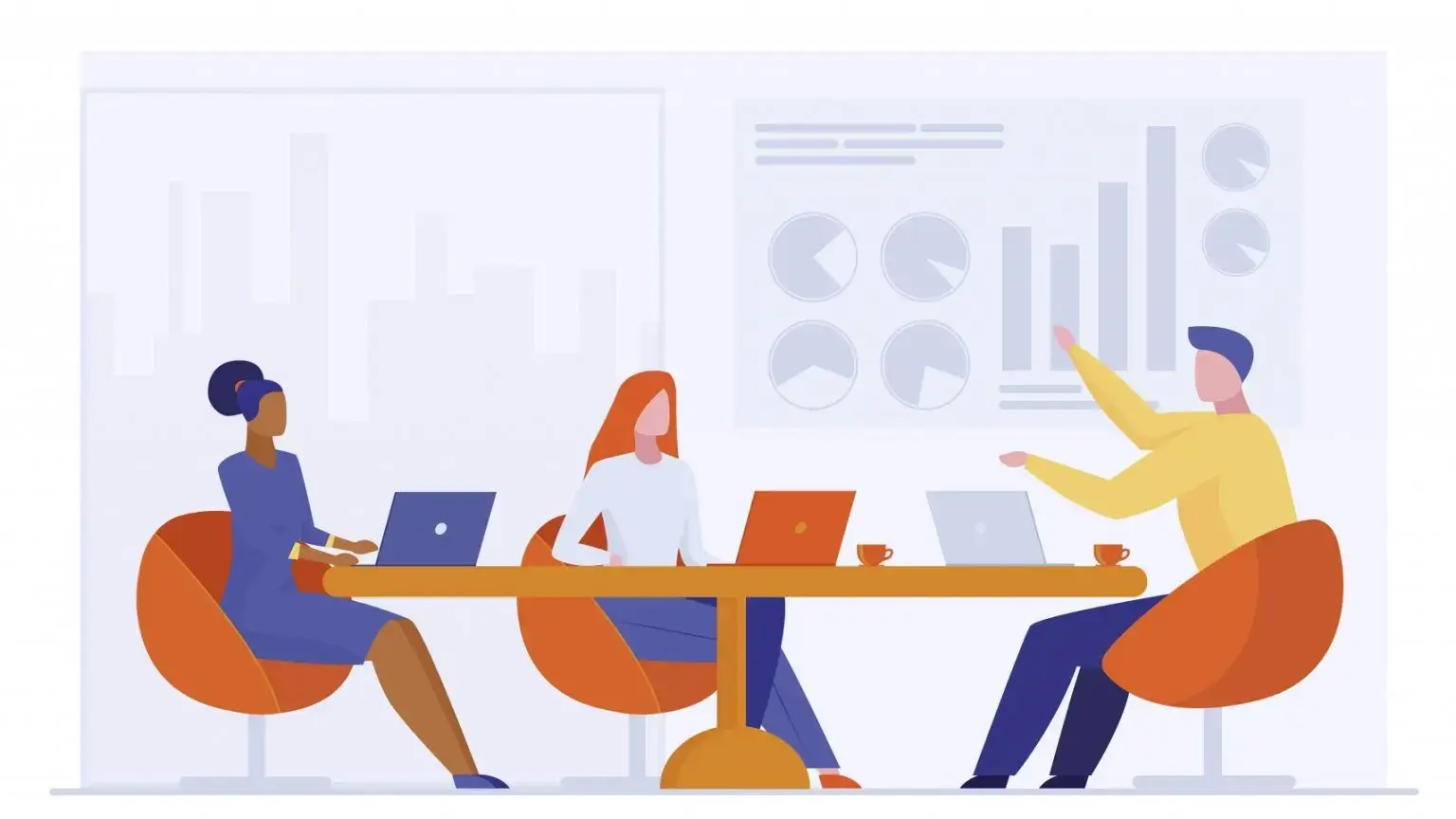
生産管理システムを導入することで、製造業の現場には様々なメリットがもたらされます。ここでは主な4つのメリットについて詳しく解説します。
3.1 在庫管理の精度向上
生産管理システムの導入により、在庫管理の精度が飛躍的に向上します。具体的には以下のようなメリットがあります。
- リアルタイムでの在庫状況把握が可能に
- 過剰在庫や欠品リスクの最小化
- 適正在庫レベルの維持による資金効率の改善
- 在庫回転率の向上
在庫の可視化により、発注のタイミングや量を最適化できるため、在庫関連コストの削減にもつながります。例えば、経済産業省の資料によると、生産管理システム導入企業による在庫管理の実例が掲載されていおり、全体的な生産性向上に貢献しているとのことです。
3.2 人的ミスの削減
手作業での情報入力や伝達が減ることで、人的ミスが大幅に削減されます。
- データ入力ミスの減少
- 情報伝達の正確性向上
- 作業指示の明確化
人的ミスの削減は品質向上だけでなく、業務効率の改善にも直結します。従業員は単純作業から解放され、より付加価値の高い業務に注力できるようになります。
3.3 問題の早期発見
生産管理システムによるデータの一元管理と分析により、以下のような問題の早期発見が可能になります。
- 生産ラインの異常検知
- 品質不良の傾向把握
- 納期遅延のリスク予測
- 原材料の在庫切れ予測
問題を早期に発見し対処することで、大きな損失を未然に防ぐことができます。また、データに基づく意思決定が可能になるため、経営層も現場の状況を正確に把握した上で、戦略的な判断を下せるようになります。
3.4 作業効率や品質の向上
生産管理システムの導入は、作業効率と品質の向上に大きく貢献します。
| 項目 | 効果 |
|---|---|
| 作業効率 |
|
| 品質 |
|
作業効率と品質の向上は、顧客満足度の向上や競争力の強化につながります。内閣府によると、製造業分野において生産管理システム導入企業は生産性向上とともにIoT化を進める必要があるとしています。
これらのメリットは相互に関連しており、総合的に企業の生産性と収益性の向上に寄与します。生産管理システムの導入は、製造業の競争力強化に不可欠な要素といえるでしょう。
4. 最適な生産管理システムの選び方

生産管理システムを選ぶ際は、自社の特性やニーズに合ったものを選択することが重要です。以下に、最適な生産管理システムを選ぶためのポイントを詳しく解説します。
4.1 企業規模・業種・生産方式に適合している
生産管理システムは、企業の規模や業種、生産方式によって最適なものが異なります。大企業向けの複雑なシステムを中小企業に導入しても、機能過多で使いこなせない可能性があります。逆に、シンプルすぎるシステムを大企業に導入すると、必要な機能が不足する恐れがあります。
例えば、経済産業省の報告によると、中小企業向けのシステムでは、基本的な在庫管理や生産計画機能に特化したものが多く、大企業向けのシステムでは、より高度な需要予測や最適化機能が含まれる傾向にあります。
また、業種によっても必要な機能が異なります。例えば、食品製造業では賞味期限管理が重要ですが、自動車部品製造業ではロット管理が重要になるでしょう。
生産方式についても、受注生産と見込み生産では必要な機能が異なります。受注生産の場合は個別の注文に対応できる柔軟性が求められ、見込み生産の場合は需要予測機能が重要になります。
4.2 業務範囲に必要な機能が搭載されている
生産管理システムに求める機能は、企業ごとに異なります。以下の機能が自社の業務範囲に必要かどうかを検討しましょう。
- 受発注管理
- 在庫管理
- 生産計画
- 工程管理
- 品質管理
- 原価管理
- 納期管理
- 資材調達管理
必要な機能が過不足なく搭載されているシステムを選ぶことで、効率的な運用が可能になります。また、将来的な業務拡大も見据えて、拡張性のあるシステムを選ぶことも重要です。
4.3 生産形態に適合性している
生産形態によって、必要とされる生産管理システムの機能は大きく異なります。主な生産形態とそれに適したシステムの特徴は以下の通りです。
| 生産形態 | システムに求められる主な特徴 |
|---|---|
| 受注生産 |
|
| 見込み生産 |
|
| 組立生産 |
|
| プロセス生産 |
|
自社の生産形態に最適化されたシステムを選ぶことで、より効果的な生産管理が可能になります。
4.4 提供形態が利用環境に合っている
生産管理システムの提供形態には、主にオンプレミス型とクラウド型があります。それぞれの特徴は以下の通りです。
| 提供形態 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| オンプレミス型 |
|
|
| クラウド型 |
|
|
独立行政法人情報処理推進機構(IPA)の資料によると、近年はクラウド型システムの採用が増加傾向にあります。特に中小企業では、初期投資の抑制や運用負担の軽減を理由にクラウド型を選択するケースが多いようです。
自社の予算、IT環境、セキュリティポリシーなどを考慮し、最適な提供形態を選択することが重要です。
4.5 サポート体制が充実している
生産管理システムの導入後も、継続的なサポートは不可欠です。以下のようなサポート体制が整っているかどうかを確認しましょう。
- 導入時のトレーニング・研修プログラム
- オンラインヘルプデスクやFAQの充実
- 定期的なメンテナンスやアップデート
- トラブル発生時の迅速な対応
- カスタマイズや機能追加の相談
充実したサポート体制があることで、システム導入後も安心して利用でき、長期的な運用が可能になります。特に、生産管理は企業の根幹に関わる重要な業務であるため、迅速かつ的確なサポートが受けられることは非常に重要です。
また、ベンダーの実績や評判も重要な選定基準となります。同業他社での導入実績や、ユーザーの評価なども参考にしながら、信頼できるベンダーを選ぶことが大切です。
以上の点を考慮しながら、自社に最適な生産管理システムを選択することで、より効果的な生産管理が実現し、企業の競争力向上につながるでしょう。
5. 生産管理システム導入における課題と対策
生産管理システムの導入には多くのメリットがありますが、同時にいくつかの課題も存在します。ここでは、主な課題とその対策について詳しく解説します。
5.1 初期投資とランニングコストの負担
生産管理システムの導入には、ソフトウェア購入費用やハードウェア整備費用、導入時のコンサルティング費用など、多額の初期投資が必要となります。また、システムの保守・運用費用も継続的に発生します。
5.1.1 対策:
- クラウド型システムの選択による初期投資の抑制
- 段階的な導入によるコストの分散
- 補助金や助成金の活用
特に中小企業向けのIT導入補助金などを利用することで、初期費用の負担を軽減できる可能性があります。
5.2 既存業務プロセスとの整合性
新しいシステムの導入により、既存の業務プロセスの変更が必要になる場合があります。これは従業員の抵抗を招く可能性があります。
5.2.1 対策:
- 導入前の十分な現状分析と業務フローの見直し
- 段階的な導入と並行運用期間の設定
- 従業員への丁寧な説明と教育訓練の実施
NTT東日本によると、業務プロセスの再設計(BPR)とシステム導入を並行して行うことが重要とされています。
5.3 データの移行と整備
既存システムや紙ベースの記録からのデータ移行は、時間と労力を要する作業です。また、データの品質や整合性の確保も重要な課題となります。
5.3.1 対策:
- データクレンジングによる不要データの削除と整理
- 段階的なデータ移行計画の策定
- 自動化ツールの活用によるデータ移行の効率化
データの品質管理は、システム導入後の運用効率に大きく影響するため、十分な時間と資源を割り当てることが重要です。
5.4 セキュリティリスクへの対応
生産管理システムには機密性の高い情報が含まれるため、セキュリティ対策は必須です。特にクラウド型システムを採用する場合、データの外部保管に関する懸念が生じる可能性があります。
5.4.1 対策:
- robust暗号化技術の採用
- 多要素認証の導入
- 定期的なセキュリティ監査の実施
- 従業員へのセキュリティ教育の徹底
IPAの中小企業向け情報セキュリティ対策ガイドラインを参考に、適切なセキュリティ対策を講じることが重要です。
5.5 従業員のITリテラシー向上
生産管理システムを効果的に運用するためには、従業員のITスキル向上が不可欠です。特に、高齢の従業員や ITに不慣れな従業員への対応が課題となります。
5.5.1 対策:
- 段階的かつ継続的な教育プログラムの実施
- マニュアルの整備とヘルプデスクの設置
- ユーザーフレンドリーなインターフェースの選択
| 教育内容 | 対象者 | 頻度 |
|---|---|---|
| 基本操作研修 | 全従業員 | 導入時 |
| 応用機能研修 | 管理者・リーダー | 四半期ごと |
| セキュリティ研修 | 全従業員 | 年2回 |
5.6 カスタマイズと拡張性の確保
導入時には想定していなかった業務ニーズが発生した場合、システムのカスタマイズや機能拡張が必要になることがあります。しかし、過度のカスタマイズはコスト増大やバージョンアップの困難さにつながる可能性があります。
5.6.1 対策:
- 将来的なニーズを見据えた柔軟性のあるシステム選択
- APIを活用した他システムとの連携
- ノーコード/ローコードツールの活用による内製化
システムの選定時には、将来の拡張性を考慮し、モジュール構造やオープンAPIを持つシステムを選択することが重要です。
5.7 運用体制の整備
システム導入後の運用体制の整備も重要な課題です。特に、システム管理者の育成や、トラブル発生時の対応体制の構築が必要となります。
5.7.1 対策:
- 社内IT部門の強化またはアウトソーシングの検討
- ベンダーサポート契約の締結
- 定期的なシステム評価と改善プロセスの確立
IPAのITスキル標準(ITSS)を参考に、必要なIT人材のスキルセットを定義し、計画的な人材育成を行うことが重要です。
5.8 ROI(投資対効果)の測定と評価
生産管理システムの導入効果を適切に測定し、投資対効果を評価することは、経営層の理解と継続的な支援を得るために重要です。
5.8.1 対策:
- KPI(重要業績評価指標)の設定と定期的な測定
- 定量的・定性的効果の可視化
- 導入前後の比較分析の実施
| 評価項目 | 測定方法 |
|---|---|
| 生産性向上率 | 単位時間あたりの生産量の変化 |
| 在庫回転率 | 年間売上高÷平均在庫金額 |
| 納期遵守率 | 納期内出荷数÷総出荷数 |
システム導入の成功は、単なる技術的な実装だけでなく、組織全体での変革マネジメントと継続的な改善プロセスの確立にかかっています。
これらの課題に適切に対処することで、生産管理システムの導入を成功に導き、製造業の競争力強化と持続的な成長を実現することができます。導入プロジェクトの各段階で、これらの課題を意識し、適切な対策を講じることが重要です。
6. まとめ
生産管理システムは、企業の製造プロセスを効率化し、生産性を向上させる重要なツールです。本記事では、生産管理システムの定義、基本機能、導入メリット、選び方、そして導入時の課題と対策について詳しく解説しました。
適切な生産管理システムを導入することで、在庫管理の精度向上、人的ミスの削減、問題の早期発見、作業効率や品質の向上などが実現できます。システム選びの際は、企業規模や業種、生産方式との適合性、必要な機能の搭載、サポート体制などを慎重に検討することが重要です。
トヨタ生産方式やカンバン方式などの日本発の生産管理手法と組み合わせることで、さらなる効果が期待できます。適切な生産管理システムの導入と運用により、企業の競争力強化と持続的な成長が可能となるでしょう。
product関連するプロダクト
-

UMWELTウムベルト
UMWELTは、プログラミング不要でかんたんに分析や自動化ができるノーコードツールです。需要予測から生産計画を最適化、人材の最適配置まで課題を解決できます。日々変化する生産数や生産計画、人員配置を自動立案し属人化や作業時間を大幅に削減します。

TRYETING
公式
TRYETING公式です。
お知らせやIR情報などを発信します。