PICK UP
アメリカの若者世代が「ブルーカラーワーク」をキャリアに選ぶ理由とは?
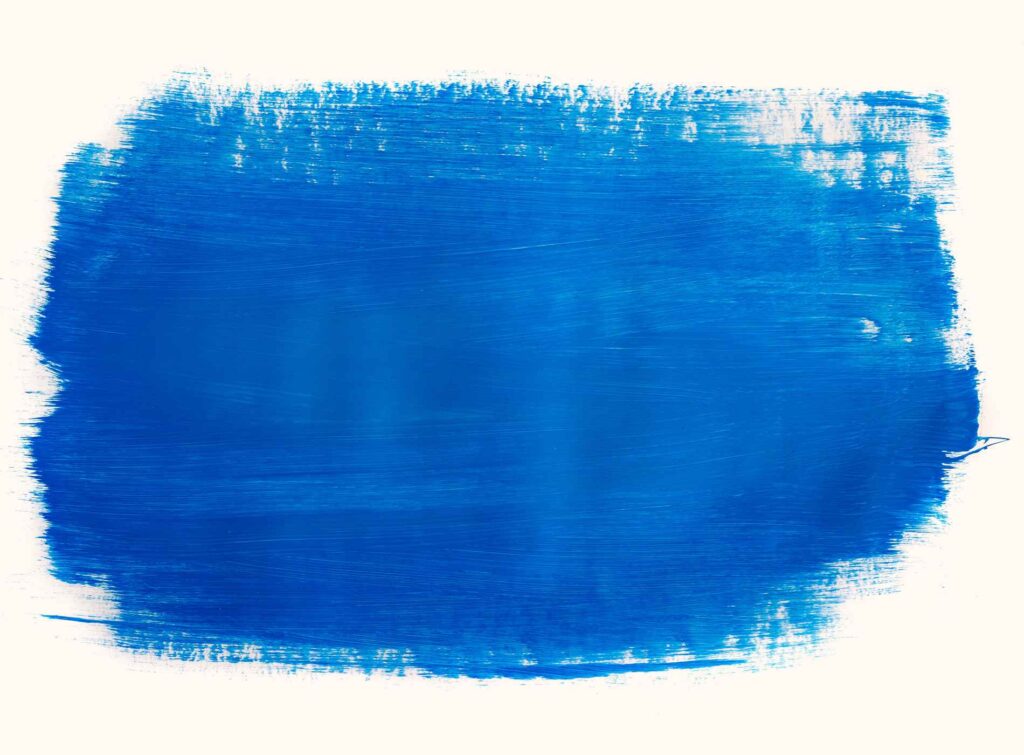
目次
アメリカのジェネレーションZを中心とした若者世代において、いわゆるブルーカラーワークをキャリアに選ぶ動きが広がっている。中でも四年生大学を卒業して学士の資格を得た大学新卒生の多くがブルーカラーワークを選択し、ホワイトカラーワークが中心だったこれまでの労働市場に地殻変動をもたらしている。アメリカの若者がブルーカラーワークを志向するのは何故か、実情をお伝えする。
ジェネレーションZの42%がブルーカラーワークを志向

アメリカのオンライン履歴書作成サイトResume Builderが今年2025年3月に実施した調査によると、調査対象となったZ世代(1997年から2012年生まれの世代)ユーザーのうち、42%がブルーカラーワークをキャリアとして検討しているか、または実際に働いていると答えている。また、37%が四年制大学を卒業して学士の学位を取得しているという。現在13歳から28歳という若い世代の多くがブルーカラーワークを志向しているわけだが、男子に限ると、学士取得者の46%がブルーカラーワークをキャリアに選ぶか、実際に働いていると答えている。
アメリカでは、日本と同様に、四年生大学を卒業して学士の学位を取得した新卒者は、オフィスワークなどのホワイトカラージョブに就くのが長らく「当たり前」とされてきた。ところが、四年生大学新卒者でもブルーカラーワークを志向し、実際にキャリアとして選ぶケースが激増している。アメリカの労働市場は今日、複数の大きな地殻変動に見舞われているが、Z世代の学士取得者によるブルーカラーワーク志向も、そうした地殻変動の震源のひとつになりつつある。しかも、その規模とエネルギーは決して小さくない。
トレードジョブと呼ばれる「手に職を付ける」仕事が人気

Z世代に人気のブルーカラーワークの中でも、とりわけ人気なのがトレードジョブと呼ばれる仕事だ。トレードジョブ(Trade jobs)とは、GoogleのAIによると、「特別なスキルと知識が求められる技術職で、配管工、電気技師、溶接工、暖房換気空調技術工、自動車整備士などが挙げられる。ほとんどは徒弟制度を通じて職務訓練を受けるか、トレードスクールと呼ばれる専門学校で技術などを学んでキャリアを積み始める」類の一連の仕事だ。
アメリカのトレードワーカーの多くは個人事業主で、労働形態的には日本の個人事業主の職人に近い。大手転職情報サイトIndeedによると、アメリカでは配管工の人気が高く、全米平均所得額7万3341ドル(約1100万円)となっている。溶接工、自動車整備工、電気技師なども人気で、全米平均所得がそれぞれ5万7766ドル(約866万円)、6万5329ドル(約980万円)、5万3980ドル(約809万円)となっている。いずれも、都市中心部を避けさえすれば、家族を養って十分に暮らしてゆける水準だ。
もはや現実となったAIによるホワイトカラーワーカーのリプレース
アメリカのZ世代のブルーカラーワーク志向の原因だが、AIによるホワイトカラーワーカーのリプレースは間違いなくその一つだろう。
前に「アメリカでついに始まった、AI普及による『新卒就職氷河期』」という記事で、これまで新卒者が主に担当してきた「エントリーレベルジョブ」とされる仕事の多くがAIに奪われ、新卒者の雇用機会が大きく減少している現状について書いた。法律事務所の「リーガルリサーチ」、ソフト開発企業の「プログラムのバグ探し」、サービス企業の「カスタマーサポート」といったエントリーレベルジョブの多くがAIによってリプレースされ、AIが人間以上のパフォーマンスを上げ始めている。こうしたエントリーレベルジョブが、再び人間の手に戻ってくることはないだろう。
EC大手Amazonは先日、全従業員の10%に相当する従業員3万人のレイオフを発表した。レイオフの対象は、人事部、サービス、オペレーション、AWS(Amazon Web Services)事業部などで働く従業員で、いずれもAIによってリプレースされる可能性が高いと見られている。AmazonはAIの導入に非常に積極的であるとされ、今後も他の多くのホワイトカラージョブがAIに奪われる可能性が高い。
上述のResume Builderの調査でも、Z世代がブルーカラーワークを志向する理由として、調査対象者の25%が「ブルーカラーワークがAIによってリプレースされそうにないから」と答えている。AIによるホワイトカラーワーカーのリプレースは、少なくともZ世代のアメリカ人にとっては、もはや近未来図などではなく、今起きている現実なのだ。
高騰する学費と、得た学位が「割に合わない」?
また、高騰する大学の学費と、大学を卒業して得た学位が「割に合わない」と考えるZ世代が増えているのも理由の一つに挙げられる。
アメリカの大手調査機関ピュー・リサーチ・センター(Pew Research Center)が四年制大学卒業者を対象にした調査を実施、結果を発表している。「大学へ行くことに価値があると思うか?」という質問に対して、「学生ローンを借りてでも大学へ行く価値がある」と答えたのは全体の22%に過ぎず、47%が「学生ローンを借りる必要がなければ大学へ行く価値がある」と答え、29%が「大学へは行く価値がない」と答えている。
大学へ行って学位を取得した10人のうち2人しか「学生ローンを借りてでも大学へ行く価値がある」と考えていない現状には、多くの学生にとってアメリカの大学の学費のレベルが「学費を支払っても回収が難しい」「得た学位が割に合わない」水準に達してしまっていることが背景にあるだろう。
別の記事で、直近のアメリカの大学の平均的な学費が年間38,270ドル(約574万円)に達し、さらに学生ローンの利用残高が1.7兆ドル(約261兆円)に拡大していることについて書いた。アメリカの大学の学費はどう見ても高過ぎであり、多くの学生にとってあまりにも負担が重い。多くの学生は、大学卒業時点で数十万ドル規模の教育ローンを負い、社会人としてキャリアを始める段階からその返済を迫られている。
学費が高騰を続け、学生たちの重荷になる一方で、これまで定番だったホワイトカラージョブがAIによってリプレースされ始めている。大卒者の10人に2人しか「学生ローンを借りてでも大学へ行く価値がある」と答えないとしても不思議でも何でもないだろう。
アメリカと同様のトレンドは日本でも発生するか?
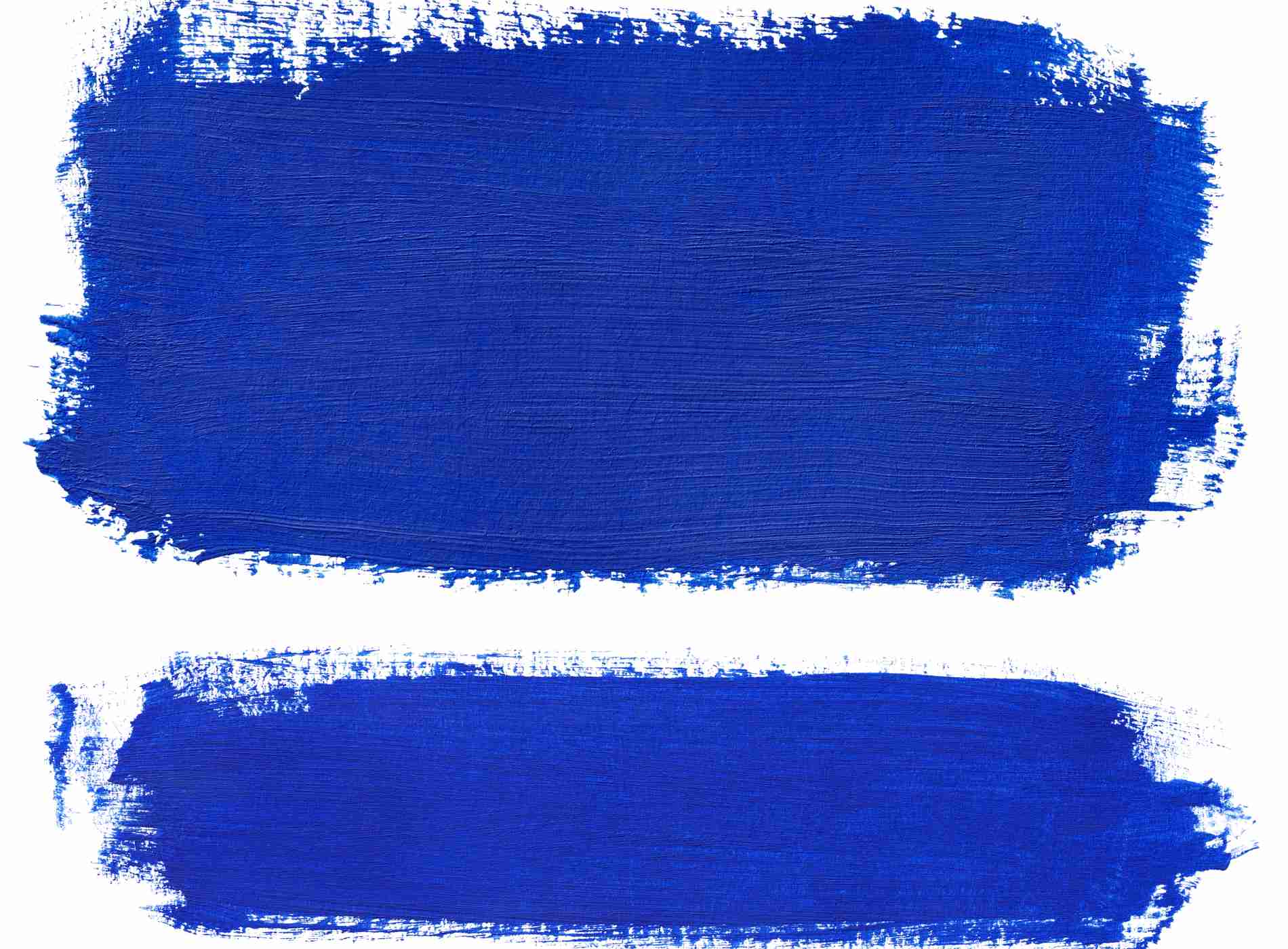
ところで、アメリカと同様のトレンドは日本でも発生するだろうか。幸いなことに、大学の学費については、今のところ日本の大学はアメリカのような状況には陥っていない。国立大学の学費は53万5,800円(2025年度の年間授業料)で、アメリカの若者から見れば垂涎ものの低水準だ。一方、私立大学の学費は四年間で410万7,759円(文系、入学料などを含む)で、アメリカと比較すれば安いものの、一般的な家庭にとってはそれなりの負担になる金額だ。
気になるのは我が国の奨学金利用者割合だ。日本学生支援機構の奨学金(貸与型)は、基本的には借金で、アメリカで一般的な学生ローンと本質的に同類だ。その奨学金の利用者割合が高止まりで推移していて、日本学生支援機構によると、奨学金を利用している大学生(昼間部)の割合は55%に達しており、二人に一人以上が利用していることになる。
例えば、私立大学の四年間の学費を奨学金で賄ったとした場合、利用者は卒業時点で400万円を超える借金を背負うことになる。日本の場合、企業の正社員としてキャリアを始める場合、最低レベルの初任給からのスタートとなる。往々にして乏しい初任給の中から毎月奨学金を返済してゆくことになるわけだが、それなりの数の人が「奨学金を借りて大学へ行ったけれど、割に合わない」と考えたとしても不思議ではない。
また、AIによるホワイトカラーワーカーのリプレースは日本でも始まっている。日本では、アメリカのように、学費高騰のあおりを受けて過度な経済的負担を負わされ、大学進学よりもブルーカラーワークを選ぶ若者が増えているといった事態にはなっていないものの、AIによる労働市場の地殻変動は始まりつつある。筆者の考えでは、日本では労働市場におけるAIの台頭と普及が、今後若者のブルーカラーワーク志向を後押しすると考えているが、実際はどうなるであろうか。今後の動向に注目したい。
参考文献
https://www.resumebuilder.com/4-in-10-gen-z-college-grads-are-turning-to-blue-collar-work-for-job-security/
https://www.indeed.com/career-advice/finding-a-job/types-of-trade-jobs
https://www.reuters.com/business/world-at-work/amazon-targets-many-30000-corporate-job-cuts-sources-say-2025-10-27/
https://www.pewresearch.org/social-trends/2024/05/23/is-college-worth-it-2/
https://www.asahi.com/thinkcampus/ariticle-120763/
https://www.jili.or.jp/lifeplan/lifeevent/761.html

前田 健二
経営コンサルタント・ライター
事業再生・アメリカ市場進出のコンサルティングを提供する一方、経済・ビジネス関連のライターとして活動している。特にアメリカのビジネス事情に詳しい。





