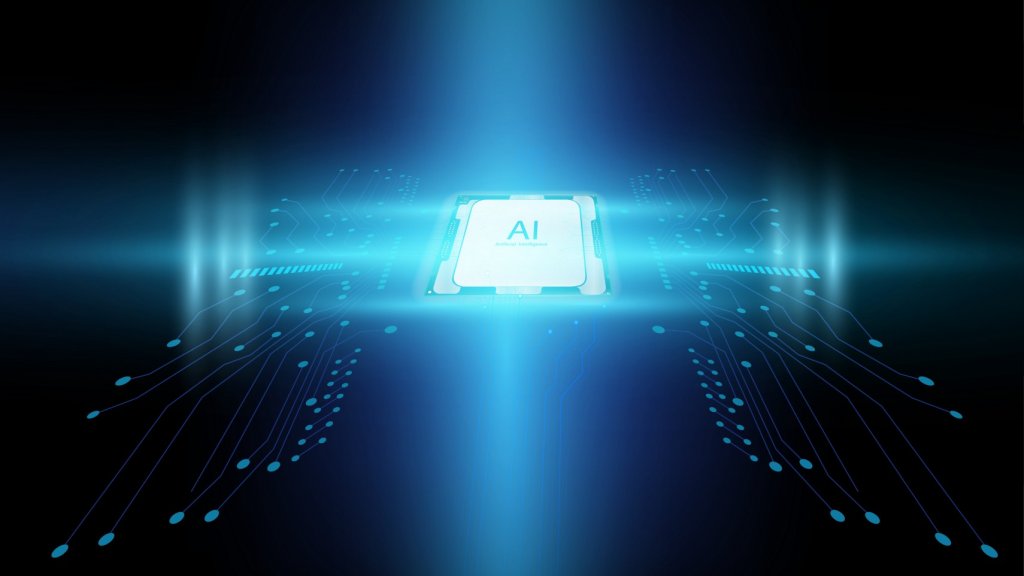BUSINESS
アメリカの中小企業のDXはどこまで進んでいるのか? 高まり続ける生成AIへの期待

目次
DX(デジタル・トランスフォーメーション)が世界的な経営トレンドワードになって久しい。SNSの利用増加、クラウドコンピューティングの普及、AIの台頭など、ニューテクノロジーを震源とする地殻変動が世界規模で進行中だが、日本では未だにDXが多くの企業にとっての名目上の経営課題であり続けている。
一方、アメリカの企業、特にアメリカの中小企業においてDXはどの程度進んでいるのだろうか。アメリカ商工会議所がまとめたレポートをもとに現状をお伝えする。
アメリカ商工会議所のレポート
アメリカ商工会議所が、アメリカの中小企業におけるDXの状況を伝えるレポートを年次ベースで発行している。「アメリカ中小企業へのテクノロジーのインパクト2024年度版」(The Impact of Technology on US Small Business Report 2024) は、アメリカで現在進行中のITテクノロジーによるビジネスの地殻変動について、中小企業への調査結果をまとめたレポートだ。2022年度から毎年発行されていて、特に今日のAIなどのテクノロジー台頭のアメリカ中小企業への影響を現場の観点から報告、その実態をあからさまに伝えている。
なお、同レポートにおける中小企業(Small businesses)の定義は、アメリカ中小企業庁(Small Business Administration)のそれに準拠して、「従業員数500名未満の未上場企業」としている 。
米中小企業の99%が「最低ひとつのテクノロジーを利用」

同レポートは、冒頭から驚くべき数字を紹介している。まず、アメリカの中小企業の実に99%が「最低ひとつのテクノロジーを利用」していると答えている。
ここで言うテクノロジーとは、「FacebookやXなどのSNS」「QuickBooksなどの会計ソフトウェア」「Google広告などのマーケティングツール」「ChatGPTなどのAIツール」「SquareなどのPOSツール」「Slackなどの生産性アップツール」「SalesForceなどのCRMツール」などで構成されているが、「FacebookやXなどのSNS」ではアメリカの中小企業の63%が利用していると答えており、54%が「QuickBooksなどの会計ソフトウェア」を利用していると答えている。また、これらのテクノロジーを同時に二つ以上利用している中小企業が全体の69%と、全体の三分の二以上を占めている。
「給与計算」「マーケティング」「売上処理」などの実務でテクノロジーを利用
テクノロジー利用の目的だが、一位は「給与計算」で全体の49%となっている。次いで「マーケティング・プロモーション」(48%)、「売上処理」(48%)、「会計」(47%)、「顧客とのコミュニケーション」(44%)、「カスタマーリレーションの管理」(39%)となっている。
アメリカの中小企業の約半分はQuickBooksなどの会計ソフトを導入して給与計算や売上処理などを行い、FacebookやXなどのSNSを使ってマーケティングやプロモーションを行う一方で、電子メールやSalesForceなどのCRM(Customer Relationship Management)ツールを使ってカスタマーリレーションを管理している光景がイメージできる。
また「顧客の与信管理」(34%)、「在庫管理」(32%)、「ビジネスパートナーの信用管理」(25%)、「人材の採用」(24%)、「返品処理」(21%)といったニッチな分野でもテクノロジーの活用が広がっている。会計ソフトやSNSといった一般的なテクノロジーの利用が標準になりつつある一方で、これまでテクノロジーの陽があまり当たらなかった領域でも利用が着実に進んでいる。
生成AIの利用が前年から17%ポイント増加

同レポートは、第二部においてアメリカの中小企業のAI活用の実態を紹介している。まず、アメリカの中小企業の40%が生成AIをビジネスに利用していると答えている。前年2023年度では23%だったので、一年間で17%ポイントも増加している。
AI利用の目的だが、最も多いのが「マーケティング・プロモーション」で、全体の51%となっている。次いで「顧客ニーズの把握」(46%)、「顧客および見込み客とのコミュニケーション」(41%)、「カスタマーリレーションの管理」(38%)、「見込み客の識別」(37%)となっている。先にアメリカの中小企業の63%が「FacebookやXなどのSNS」を利用していると書いたが、多くの企業は生成AIを使ってマーケティング・プロモーション用セールスコピーなどを作成し、SNSで発信している。また、SNSのメッセージ機能を使った顧客とのやり取りなどでも、生成AIに応答文などを作成させ、利用している。
実際に、筆者の知人のアメリカ人コンサルタントは、飲食店を経営している彼のクライアントがSNSで寄せられる顧客の声への返信文や、レビューサイトの投稿に対するコメントなどを生成AIに作らせている実態について教えてくれた。そのクライアントの店では、それまでフロアスタッフの一人にSNSでのコミュニケーション業務をまかせていたものの対応が不十分で、顧客との密接なコミュニケーションがとれなかった。
ところが、生成AIを使って対応してみたところ、コメントを返されたユーザーの反応が軒並みよく、SNSでのコメントやフィードバックも目に見えて増えていったという。そのクライアントは、今では新規のメニューやInstagram広告のクリエイティブなども生成AIに作らせているという。
AI利用中小企業の91%が「AIが自社の将来成長に役立つ」と回答
アメリカの中小企業はAIの台頭と将来に関して極めて楽観的だ。AIを利用している中小企業の91%が「AIが自社の将来成長に役立つ」と回答し、前年度から7%ポイントプラスとなっている。また86%が「AIが自分のビジネスの効率性を向上させている」と答えている。一方で、AIを利用していない中小企業においては、「AIが自社の将来成長に役立つ」と回答したのは全体の29%に過ぎない。
AIを利用していない中小企業にその理由をたずねると、「AIが自分のビジネスにどう活かせるのかわからない」(31%)、「AIについて十分理解していない」(31%)、「コンプライアンスや法律上の問題が心配」(25%)、「AIのクオリティが心配」(24%)、「AIの利用コストが心配」(22%)、「AIに関する教育やトレーニングが不十分」(13%)などと答えている。AIを使ったことがないからAIについてわからないのか、あるいはAIについてわからないからAIを使っていないのか、どちらであるか判別しづらいが、多分ほとんどのケースにおいては程度の差はあれ、いずれにも該当している可能性が高いと思われる。
日本の中小企業のDXは?

一方、日本企業、とりわけ日本の中小企業においては、状況はどうなっているのだろうか。デロイトトーマツコンサルティング合同会社のレポート『令和5年度中小企業実態調査事業調査報告書』 によると、調査に回答した中小企業548社のうち、「ファイル共有サービス、WEB会議システム、販売管理システム、会計ソフト、CRMなどのITツール、インターネットバンキング、グループウェアなどのコミュニケーションツール、自社ウェブサイト、SNS、インターネット広告」などの「ITツール」を導入していると答えたのは357社で、全体の65.1%であった。
アメリカの中小企業の99%が何らかのITツールを導入している一方で、日本では未だに三分の一以上の企業が「DX導入前企業」として残されているのが現状だ。
日本の中小企業によるAIの利用状況はさらに厳しい。一般社団法人データサイエンティスト協会が2023年に実施した調査によると、日本の職場におけるAI導入率は13.3%で、アメリカの30.2%の半分以下となっている 。上にご紹介したアメリカのレストラン経営者が、自ら生成AIを使って顧客とやり取りをしたり、新規メニューの開発などを積極的に行っている一方で、日本の中小企業経営者の多くはAIに触れもせず、その将来性や可能性について実感することもできない旧態依然の状態に置かれている。
アメリカ国内においては、「AIを知り、活用する」経営者のグループと、「AIを知らず、活用しない」経営者のグループとに二分される構図が出来上がりつつあるが、その国際バージョンのようなものが日米間で発生しないとも限らない。日本の中小企業経営者においては、ぜひとも自らAIに触れ、試してみて、自社のビジネスに積極的に取り入れていただきたい。AIを筆頭とするテクノロジー導入における日米の差は確かに存在しており、それが今後さらに広がらないとは誰も保証できない。
参考文献
https://www.uschamber.com/assets/documents/Impact-of-Technology-on-Small-Business-Report-2024.pdf
https://www.uschamber.com/small-business/state-of-small-business-now
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2023FY/000356.pdf
https://www.datascientist.or.jp/dssjournal/dssjournal-1903/

前田 健二
経営コンサルタント・ライター
事業再生・アメリカ市場進出のコンサルティングを提供する一方、経済・ビジネス関連のライターとして活動している。特にアメリカのビジネス事情に詳しい。