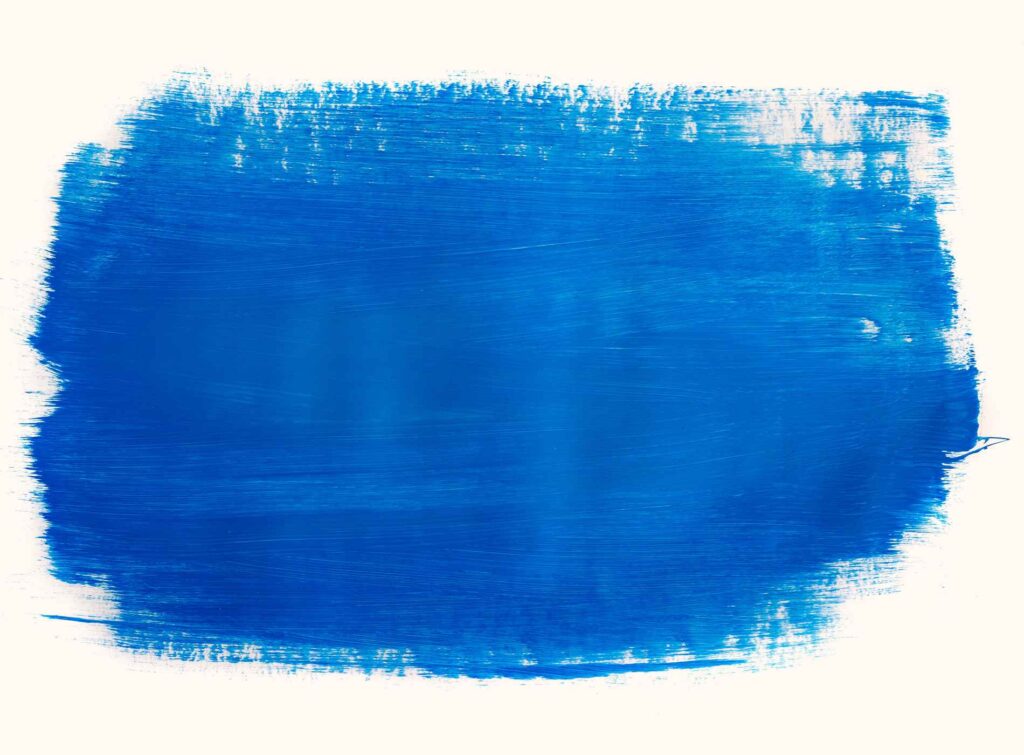PICK UP
批判から一転、大活況の裏側で。一個人から見た「大阪・関西万博」

目次
「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに、2025年4月13日から開幕した『2025年日本国際博覧会 大阪・関西万博(以下、大阪・関西万博)』。開幕前の不評を一掃して、現在は活況を呈しているという。
そんな大阪・関西万博に、筆者も一般来場者として訪れた。主にメディアを通じて発信される大阪・関西万博の実情を、今回は一般来場者である「一個人」の筆者の目線からお伝えしよう。
批判から一転。来場者が増え続ける大阪・関西万博

開幕前、関係者以外に誰がここまで伸びると思っていただろうか。大阪・関西万博は逆風のスタートだった。
開幕当初は目標としている「1日15万人」とはかけ離れた5万人程度の来場者数で推移していた。オペレーションもおぼつかないようで、メディアを通じて不安も囁かれていた。
しかし、現在では15万人を突破する日もちらほら見られ、6月28日にはなんと一般来場者だけで17万人を突破。明らかに潮目が変わってきた。
筆者が妻と万博に行こうと話していたのは、まだ来場者も少ない4月中旬だった。賛否はあるものの、結局行ってみなければわからない。妻も万博に興味があったようなので、話はすんなり進んだ。
早速チケットを購入。55年前の大阪万博はチケット売り場に長蛇の列ができていたようだが、現代はスマホで買える。そして、QRコードでピッと入場できて「並ばない」(のはず)だ。
チケットを購入した前後から、徐々に大阪・関西万博のパビリオンに関する情報が出回り始めた。
「やっぱりアメリカ館はすごいらしい」
「イタリア館の展示が素晴らしい」
こういうポジティブな情報に触れて、徐々に気持ちも高まっていった。
「並ばない万博」は何処へ

私たち夫婦は、5月16日(金)の夕方から夜、5月17日(土)のお昼に万博を訪れた。
事前にチケットを購入して、QRコードもある。東京のターミナル駅の自動改札のように、人が流れるようにゲートを通れることを想像していた……が、なんと並ぶはめになったのだ。
その原因は「手荷物検査」であった。なるほど、テロなどが会場で起きたら一大事だ。それゆえ、手荷物検査が必須になるのはわからなくもない。しかし、「並ばない万博」のコンセプトは何処へ?と疑問が湧いてきた(これは、きっと筆者だけではないだろう)。
今回の万博に精通している方ならきっとこう思うだろう。「あなたは東ゲートから入場しようとしたんでしょ?なぜ混んでいるほうから入場しようとするの?』」と。
しかし、地下鉄・中央線で容易にアクセスできる東ゲートに人が集中するのは目に見えている。だったら、もっと工夫できることもあったのではと、大阪の地理に詳しくない関東人は思わなくもない。
並ぶのは、入場ゲートだけではない。万博の目玉であるパビリオンも当然のごとく並ぶ。
30分待ちなら御の字、大人気のパビリオンは2時間待ちがザラだ。事前に抽選で選ばれて、予約していないと入れないと覚悟したほうがいいだろう(もしくは、開演直後に入場して一目散にパビリオンに並ぶか)。
筆者が訪れた時期は1日10万人ほどの来場者で、メディアから入場者が少ないと批判が上がっていた時期だった。しかし、現在は先述したとおり1日17万人ほど来場するほどだ。あれから1.5倍以上の人が集まって、果たしてまともにパビリオンを観覧できる状態なのだろうか。
さらに、コンビニやお土産屋さんでも並ぶことを念頭に置くべきだろう。筆者が訪れた日はせいぜい5分ほどだったが、現在はどうなのか。皆目見当がつかない。
多くの国々が掲げる「デジタル活用」と「サステナビリティ」

一個人にとっては「並ぶ万博」だが、そんな中、筆者はいくつかの国のパビリオンに入場できた。
これから訪れる方々のために、ネタバレしない程度にお伝えするが、私が見た範囲で共通していたのは多くの国々で「サステナビリティ」と「デジタル活用」が掲げられていたことだ。これは、2020年代らしいといえよう。
特にデジタル活用は、いわゆる先進国だけでなく成長国のパビリオンでもアピールされていた。サステナビリティとデジタル活用を掛け合わせて、「スマートシティ構想」を提示するケースも散見されるほどだった。
サステナビリティとデジタル、この2大要素はこれから世界において欠かせないのだと、改めて痛感させられた。一方で、どこの国も同じようなビジョンを描いていることに、国ごとの個性が埋没しているのではないかと懸念も抱いてしまう。
大阪・関西万博でしか「見れないもの」や「気づき」もある

少し大阪・関西万博に対して後ろ向きな内容が中心になってしまったが、万博に行ったからこそ体感できることもある。
その1つが、意匠を凝らした「建造物」だ。各国が威信をかけて建てたパビリオンは「並ばず」とも目にすることができる。建築の素人の目からは、まさに建築技術の粋を集めたように見える。東京のガラス張りの超高層ビルばかり見ている筆者にとっては、別世界を歩いているようだ。
建築とは、こんなに自由なものなのか。建築関係の仕事に携わっている方や建築学部の学生は、入場ゲートでどれだけ並んでも大阪・関西万博を楽しめるだろう。
建造物といえば、大阪・関西万博の目玉は「木造リング」だ。メディアでも頻繁に取り上げられ、多くの人がその存在を認知しているが、画面を通して見るのと実物を見るのではやはり違う。日本人は昔から「木」の力を信じてきた。その集大成があの木造リングなのかもしれない。
木造リングから見る、夜の大阪・関西万博の会場は、この世のものなのかと目を疑うほど美しい。万博に訪れた際は、ぜひ夜の木造リングも堪能してほしい(ただし、強風になると上がれなくなってしまう)。
もう1つ、万博の醍醐味は「世界を身近に感じられる」ことだ。大阪・関西万博には、160を超える国や地域が参加し、歴史や文化、産業、技術、そしてこの先のビジョンを紹介。私たちが知らない一面を知ることもできる。
例えば「オーストリア」。日本人なら多くの人が「芸術の都・ウィーン」を思い浮かべるだろう。しかし、これはあくまでオーストリアの一面にすぎない。詳細はネタバレになってしまうのでここでは伏せるが、オーストリアパビリオンを訪れたら並びながら学べるだろう。
命をつないで、言ってみたい

ここまで一個人が周った大阪・関西万博についてお伝えしたが、そもそも万博とはどのようなイベントなのか――。その意義に触れて、本稿を締めたい。
大阪・関西万博の公式ガイドブックを紐解くと、6〜7ページにかけて万博が残した偉業が簡潔にまとめられている。具体的には、象徴的な建造物(ロンドンの水晶宮『クリスタル・パレス』やパリのエッフェル塔)や「未来の日常」を映し出す出展品が紹介されている。
その中でも、日本人の目に止まるのはやはり1970年の大阪万博だろう。このページでは、日本電信電話公社(現NTT)が出展した「携帯電話」が掲載されている。おそらく黒電話がまだ主流だったのだろう。携帯電話を操作している女の子は、なんとも不思議そうな顔をしている。
ちなみに、この携帯電話はただの携帯電話ではない。調べてみると、なんと電卓(計算機)も搭載されているのだ。計算機(コンピューター)付きの携帯電話、そう「スマートフォン」だ。現代の私たちの日常にもっとも欠かせないツールは、なんと55年前の大阪万博でそのコンセプトは示されていたのだ。
スマートフォンだけではない。大阪万博では、なんと電気自動車の構想も掲げられていたという。「月の石」がフィーチャーされがちな大阪万博だが、そこには55年後の未来がはっきりと示されていたのだ。
そして、未来を示してきたのは大阪万博だけではない。過去に行われてきた万博を振り返ると、そこでは50年後の未来が体感できたのだ。
翻って、大阪・関西万博では、一体どんな未来が示されているのだろうか。一個人では、それを窺い知れないのは、冒頭から読み進めていただいた読者ならご理解いただけるだろう。木造リングと、開催前の不評が一気に吹き飛んで大人気になった『ミャクミャク』しか残らないなんてことにはならないでほしい。
大阪・関西万博には、子どもたちも多く来場しており、平日には修学旅行生も訪れているという。彼らが、55年前に携帯電話を操作していた女の子のような表情をしながら見て触って体験したことが、55年後の未来では当たり前になっていてほしい。そして、もしまた日本で万博が開催されたときに、こう振り返ってほしい。
「55年前の大阪・関西万博では、確かに未来が示されていた」と――。
そして、あわよくば95歳まで命をつないで、筆者もそう言ってみたいものだ。
画像提供:筆者
参考文献
2025年日本国際博覧会 大阪・関西万博 公式ガイドブック
【速報】万博きのう28日(土)の一般入場者数は「過去最多」17万7000人、今日のイベントは?
https://news.yahoo.co.jp/articles/2a4b306d706399c98e4de52865d101524aadcbe8

狩野 晴樹
ライター
都内のスタートアップに勤めるビジネスパーソン。副業でたまに執筆活動を行う。趣味は野球&サッカー観戦。アラフォーになったものの、「不惑」は遠いと日々感じている。