TECHNOLOGY
【2025年最新】生成AIソフトおすすめ15選!無料・有料別に選び方や使い方を徹底比較

目次
急増する生成AIソフトの中から「どれを選べば良いかわからない」と悩んでいませんか?本記事では、2025年最新のおすすめ生成AIソフトを無料・有料、目的別に15選ご紹介します。
ChatGPTやMidjourneyなどの人気ツールを徹底比較し、失敗しない選び方のポイントからビジネスでの活用法、著作権の注意点まで網羅的に解説。この記事を読めば、あなたに最適な生成AIソフトが必ず見つかります。
▼更にAIについて詳しく知るには?
AI(人工知能)とは?導入するメリットと活用例やおすすめのツールを紹介
▼社内のデータをAI化するには?
ノーコードAIツールUMWELT紹介ページ(活用事例あり)
1. 生成AIソフトとは?まずは基本を解説

近年、ChatGPTやMidjourneyといったサービスの登場により、「生成AI(Generative AI)」という言葉を耳にする機会が急増しました。
生成AIソフトは、専門的な知識がない人でも、まるで人間と対話するように、あるいは簡単な指示を出すだけで、新しいコンテンツを創り出せる画期的なツールです。まずは、この生成AIソフトが一体何なのか、その基本から詳しく見ていきましょう。
生成AIソフトとは、大量のテキスト、画像、音声などのデータを事前に学習したAIモデルを利用して、ユーザーの指示に基づき、オリジナルのコンテンツを自動で生成するソフトウェアのことです。基盤となっているのは、ディープラーニング(深層学習)と呼ばれる技術であり、特に文章生成では「大規模言語モデル(LLM: Large Language Model)」が中核を担っています。
これにより、単なるデータの処理や分析に留まらず、創造的なアウトプットを生み出すことが可能になりました。
1.1 生成AIソフトでできることとは?
生成AIソフトの最大の魅力は、その多様な活用範囲にあります。これまで時間と手間がかかっていた様々な作業を効率化し、新たなアイデア創出のきっかけを提供します。具体的にどのようなことができるのか、代表的な例をご紹介します。
- 文章の作成・編集:ブログ記事、メールの文面、SNSの投稿、企画書、レポートなどを自動で作成します。また、既存の文章の要約、翻訳、校正、表現のリライト(書き換え)も可能です。
- アイデア出し・情報収集:新しい企画のブレインストーミングや、複雑なテーマに関する情報整理、専門的な内容の分かりやすい解説など、思考のパートナーとして活用できます。
- クリエイティブ制作:キーワードや簡単な説明文(プロンプト)から、広告用のバナー画像、イラスト、ロゴデザイン、プレゼンテーション資料などを生成します。
- プログラミング支援:PythonやJavaScriptといったプログラミング言語のコードを生成したり、既存のコードのバグを発見・修正したり、仕様書を作成したりできます。
- 音楽・音声の生成:動画のBGMや効果音を作曲したり、テキストを人間のような自然な音声で読み上げるナレーションを作成したりすることが可能です。
このように、生成AIソフトはビジネスの現場から個人の創作活動まで、幅広いシーンで活躍するポテンシャルを秘めています。
1.2 従来のAI開発ソフトとの違い
「AIソフト」と一括りにされがちですが、「生成AIソフト」と、これまで主流だった「従来のAI開発ソフト」には、その目的と役割に明確な違いがあります。従来のAIは、主にデータの中から特定のパターンを見つけ出し、「予測」や「分類」、「識別」を行うことを得意としてきました。
両者の違いを理解することで、自社の課題解決にどちらが適しているかを判断しやすくなります。以下の表で具体的な違いを確認してみましょう。
| 比較項目 | 生成AIソフト | 従来のAI開発ソフト(予測・識別系) |
|---|---|---|
| 主な目的 | 新しいコンテンツの「生成・創造」 | 既存データに基づく「予測・分類・識別」 |
| アウトプット例 | ブログ記事、広告画像、プログラムコード、作曲された音楽など | 将来の売上予測数値、製品が不良品かどうかの判定結果、顧客のグループ分けなど |
| ビジネスでの活用シーン | コンテンツマーケティング、デザイン業務の効率化、企画立案のサポート、社内文書作成の自動化 | 需要予測による在庫管理の最適化、工場の検品自動化、顧客データ分析によるマーケティング戦略立案 |
| 主なユーザー層 | マーケター、ライター、デザイナー、企画担当者など、幅広い職種のビジネスパーソン | データサイエンティスト、AIエンジニアなど、専門的な知識を持つ技術者 |
特に大きな違いは、ユーザー層にあります。従来のAI開発ソフトは、AIモデルを構築するためにプログラミングやデータサイエンスの専門知識が不可欠なものが多くありました。
一方、生成AIソフトの多くは、直感的に操作できるGUI(グラフィカル・ユーザー・インターフェース)を備えており、専門家でなくてもチャット形式や簡単なキーワード入力で手軽に利用できる点が画期的です。
2. 【目的別】生成AIソフトの種類と代表的なツール
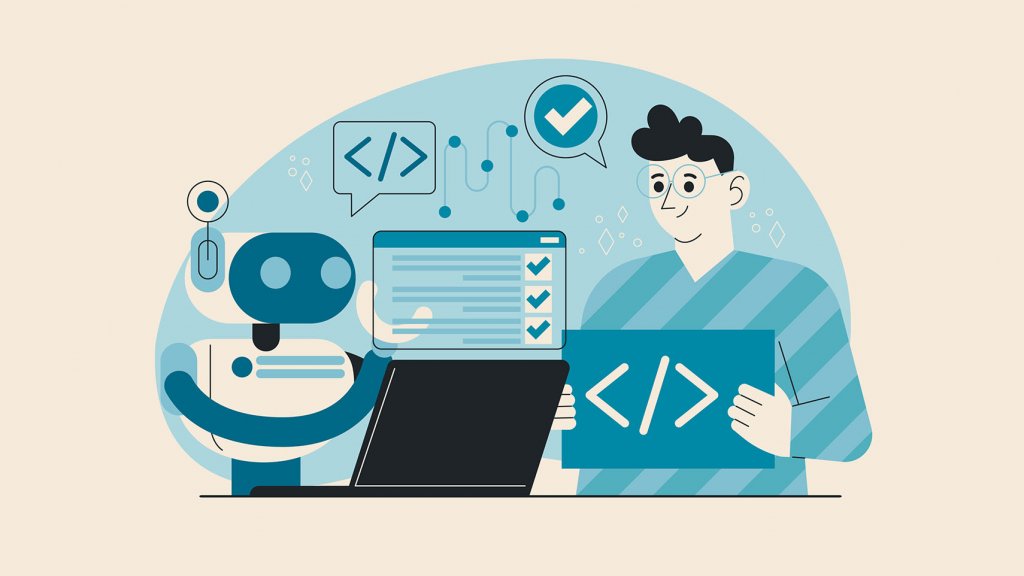
生成AIソフトと一言でいっても、文章を作るもの、美しい画像を生成するもの、さらには動画や音楽を生み出すものまで、その種類は多岐にわたります。自分の目的や用途に合ったソフトを選ぶことが、生成AIを最大限に活用するための第一歩です。
ここでは、代表的な生成AIソフトを「文章」「画像」「動画」「音楽・音声」の4つの目的に分類し、それぞれの特徴と代表的なツールを紹介します。
2.1 文章生成AIソフト
文章生成AIソフトは、自然言語処理技術を用いて、人間が書いたような自然なテキストを生成するツールです。ブログ記事やメールの作成、企画書のアイデア出し、文章の要約・翻訳、プログラミングコードの生成など、ビジネスからプライベートまで幅広いシーンで活用できます。対話形式で手軽に利用できるものが多く、業務効率化の切り札として注目されています。
2.1.1 ChatGPT
ChatGPTは、米国のOpenAI社が開発した、世界で最も有名な対話型AIの一つです。非常に汎用性が高く、自然な会話はもちろん、専門的な文章の作成、アイデアの壁打ち、データ分析、翻訳、コーディング補助まで、あらゆるタスクを高いレベルでこなします。
無料プランでも十分に高性能ですが、有料プランはさらに高度な推論能力と精度を誇り、プラグインやGPTsによる機能拡張も魅力です。
2.1.2 Google Gemini (旧Bard)
Google Geminiは、Googleが開発した生成AIです。最大の強みは、Google検索と連携した最新情報へのアクセシビリティです。リアルタイムの情報を反映した回答を生成できるため、最新のニュースやトレンドに関する文章作成に適しています。
また、GmailやGoogleドキュメントといったGoogleの各種サービスとの連携もスムーズで、Googleエコシステム内で作業を完結させたいユーザーにとって非常に便利です。無料で利用できる範囲が広いのも特徴です。
2.1.3 Claude
Claudeは、元OpenAIのメンバーが設立したAnthropic社が開発した生成AIです。特に長文の読解・要約・生成能力に定評があり、一度に大量のテキスト(最大で約15万ワード)を処理できます。研究論文の分析や契約書のレビュー、長編レポートの作成など、専門的で大量のドキュメントを扱う業務で真価を発揮します。安全性や倫理性を重視した設計で、より丁寧で信頼性の高い回答を生成する傾向があります。
| ツール名 | 開発元 | 主な特徴 | 料金プラン |
|---|---|---|---|
| ChatGPT | OpenAI | 汎用性が非常に高く、機能拡張も豊富。自然な対話と高度な文章生成能力が魅力。 | 無料版あり / 有料版(Plus, Team, Enterprise) |
| Google Gemini | Google検索と連携し、最新情報に基づいた回答が得意。Googleサービスとの連携が強力。 | 無料版あり / 有料版(Gemini Advanced) | |
| Claude 3 | Anthropic | 長文の処理能力が非常に高い。安全性と倫理性を重視した丁寧な回答を生成。 | 無料版あり / 有料版(Pro, API利用) |
2.2 画像生成AIソフト
画像生成AIソフトは、「プロンプト」と呼ばれるテキストの指示に基づき、オリジナルの高画質画像を生成するツールです。Webサイトのアイキャッチ画像、広告バナー、プレゼンテーション資料の挿絵、SNS投稿用の画像、ゲームやデザインのコンセプトアートなど、クリエイティブな分野で幅広く活用されています。
これまで専門的なスキルが必要だった画像制作のハードルを大きく下げ、誰でもアイデアを視覚化できるようになりました。
2.2.1 Midjourney
Midjourneyは、高品質で芸術的な画像の生成に特化したAIツールです。特に、幻想的で美しい、絵画のような作風を得意としており、多くのクリエイターから高い評価を得ています。コミュニケーションツールであるDiscord上で、チャット形式でプロンプトを入力して画像を生成するという独特のインターフェースが特徴です。現在は有料プランのみの提供ですが、そのクオリティの高さから根強い人気を誇ります。
2.2.2 Stable Diffusion
Stable Diffusionは、オープンソースで公開されている画像生成AIモデルです。最大の魅力は、その自由度の高さとカスタマイズ性です。モデルが無料公開されているため、自身のPC環境に導入して無制限に画像を生成したり、特定の画風を追加学習させたモデル(LoRAなど)を利用したりできます。
専門知識は必要ですが、思い通りの画像を追求したい上級者や開発者にとって最適な選択肢です。また、このモデルを利用した多くのWebサービスも存在します。
2.2.3 DALL-E
DALL-Eは、ChatGPTと同じOpenAI社が開発した画像生成AIです。ChatGPT PlusやMicrosoft Copilotに統合されており、対話形式で直感的に画像を生成できる手軽さが魅力です。プロンプトの解釈能力が非常に高く、複雑で長い指示でも忠実に再現しようとします。また、画像内に正確なテキストを描画する能力にも優れており、ポスターや広告デザインなどにも活用しやすいのが特徴です。
| ツール名 | 提供元 | 主な特徴 | 料金プラン |
|---|---|---|---|
| Midjourney | Midjourney, Inc. | 芸術的で高品質な画像の生成が得意。Discord上で操作する。 | 有料プランのみ |
| Stable Diffusion | Stability AI (モデル) | オープンソースでカスタマイズ性が高い。無料で利用できる環境も多い。 | モデル自体は無料 / 各種サービスによる |
| DALL-E | OpenAI | プロンプトへの忠実度が高い。ChatGPTやCopilotから対話形式で利用可能。 | ChatGPT PlusやCopilot Proなどの有料プラン内で利用 |
2.3 動画生成AIソフト
動画生成AIは、テキストや画像からオリジナルの動画コンテンツを生成する、今最も注目されている分野の一つです。プロンプトを入力するだけで、実写さながらの映像やアニメーションを数分で作成できます。まだ発展途上の技術ですが、SNS用のショート動画、広告映像、製品紹介ビデオ、映像制作のプリビジュアライゼーションなど、その活用範囲は無限大です。代表的なツールとして、OpenAIの「Sora」、Runway社の「Runway」、Pika Labs社の「Pika」などがあり、今後の技術進化が非常に期待されています。
2.4 音楽・音声生成AIソフト
音楽・音声生成AIは、作曲やナレーション作成といった音に関するクリエイティブ作業を自動化するツールです。テキストで曲の雰囲気やジャンルを指定するだけで、ボーカル付きのオリジナル楽曲を生成する「Suno AI」のようなサービスが登場し、大きな話題を呼んでいます。
また、入力したテキストを自然な人間の声で読み上げる音声合成ツールも進化しており、「CoeFont」のように自分の声をAIに学習させてオリジナルのAIボイスを作成するサービスも人気です。動画のBGMやナレーション作成、オーディオブック制作、ポッドキャスト配信など、幅広い用途で活用が始まっています。
3. 失敗しない!生成AIソフトの選び方5つのポイント

生成AIソフトは、文章作成から画像生成、動画編集まで、その種類は多岐にわたります。しかし、選択肢が豊富なあまり「どのソフトを選べば良いかわからない」と悩む方も少なくありません。せっかく導入しても、目的を果たせなかったり、使いこなせなかったりしては意味がありません。ここでは、あなたのニーズに最適な生成AIソフトを見つけるための5つの重要なポイントを解説します。
3.1 目的・用途で選ぶ
生成AIソフトを選ぶ上で最も重要なのは、「何のために使いたいのか」という目的を明確にすることです。目的によって、選ぶべきソフトの種類は大きく異なります。まずは、自分が生成AIを使って実現したいことを具体的にイメージしてみましょう。
例えば、「ブログ記事の執筆を効率化したい」のであれば文章生成AIが、「SNS投稿用のユニークな画像が欲しい」のであれば画像生成AIが必要です。以下の表を参考に、ご自身の目的に合ったソフトのジャンルを見つけてください。
| 目的・用途の例 | 選ぶべきソフトの種類 | 代表的なソフト例 |
|---|---|---|
| ブログ記事、メール、企画書の作成 | 文章生成AI | ChatGPT, Google Gemini, Claude 3 |
| Webサイトのアイキャッチ画像、SNS投稿画像の作成 | 画像生成AI | Midjourney, Stable Diffusion, DALL-E 3 |
| 広告動画、YouTube動画、プレゼン用動画の作成 | 動画生成AI | Sora, Runway, Pika |
| BGM、効果音、ナレーション音声の作成 | 音楽・音声生成AI | Suno AI, Udio, VALL-E X |
このように、まずは大まかなジャンルを絞り込むことで、ソフト選びが格段にスムーズになります。
3.2 無料か有料かで選ぶ
生成AIソフトには、無料で利用できるものと、月額料金などが発生する有料のものがあります。どちらを選ぶかは、利用頻度や求める機能のレベルによって決まります。それぞれのメリット・デメリットを理解し、自身の予算や使い方に合ったプランを選びましょう。
まずは無料プランで基本的な機能や操作感を試し、より高度な機能や多くの生成回数が必要になった場合に有料プランへ移行するのがおすすめです。
| 項目 | 無料プラン | 有料プラン |
|---|---|---|
| メリット | ・コストがかからない ・気軽に試せる |
・高機能、高精度 ・生成回数や速度の制限が緩やか ・商用利用が可能な場合が多い ・サポートが充実している |
| デメリット | ・機能や生成回数に制限がある ・生成速度が遅い場合がある ・商用利用が許可されていないことが多い |
・月額料金などのコストがかかる |
| おすすめのユーザー | ・生成AIを初めて使う方 ・個人的な趣味で利用したい方 |
・ビジネスで本格的に活用したい方 ・高品質なコンテンツを大量に生成したいクリエイター |
有料プランの料金体系も、毎月定額のサブスクリプション型、生成回数に応じて課金されるクレジット(トークン)型など様々です。利用頻度に合わせて無駄のないプランを選びましょう。
3.3 操作のしやすさで選ぶ(専門知識は必要?)
「AIソフトは専門知識がないと難しそう」というイメージがあるかもしれませんが、近年の生成AIソフトの多くは、誰でも直感的に操作できるよう設計されています。特にWebブラウザで利用できるサービスの多くは、チャット形式で指示(プロンプト)を入力するだけで、簡単にコンテンツを生成できます。
しかし、一部のソフトウェア、特にStable Diffusionなどを自分のPC環境で動かす場合は、ある程度の専門知識や環境構築のスキルが求められます。操作性を確認する際は、以下の点をチェックすると良いでしょう。
- インターフェースの分かりやすさ:チャット形式か、メニュー項目は整理されているかなど、直感的に操作できるUIかを確認しましょう。
- 日本語への対応:メニューや説明が日本語に対応していると、スムーズに利用できます。海外製のソフトでも、多くの人気ツールは日本語に対応しています。
- チュートリアルやガイドの充実度:公式のチュートリアルや使い方ガイドが充実しているソフトは、初心者でも安心して始められます。
多くのソフトには無料体験期間やフリープランが用意されているため、本格的に導入する前に、実際に触ってみて操作性を確かめることが失敗しないための鍵となります。
3.4 商用利用の可否を確認する
生成AIソフトで作成したコンテンツをビジネス目的で利用する(例:ブログに掲載して収益を得る、商品デザインに使用する、広告として配信する)場合は、「商用利用が可能か」を必ず確認する必要があります。この確認を怠ると、後々ライセンス違反などのトラブルに発展する可能性があります。
商用利用の可否は、各ソフトの利用規約に明記されています。一般的に、無料プランでは商用利用が制限され、有料プランでは許可されているケースが多く見られます。
また、生成したコンテンツの著作権が誰に帰属するのかも、ツールによって扱いが異なります。ビジネスでの活用を考えている方は、登録前に必ず利用規約に目を通し、商用利用の範囲や条件を正確に把握しておきましょう。
3.5 対応デバイスや動作環境で選ぶ
生成AIソフトを「いつ、どこで、どのデバイスで使いたいか」も重要な選択基準です。ソフトの提供形態は主に以下の3つに分けられます。
- Webブラウザ型:PCやスマートフォンのブラウザからアクセスして利用するタイプです。ソフトウェアのインストールが不要で、デバイスを問わず手軽に始められるのが最大のメリットです。ChatGPTやGeminiなど、多くの人気ソフトがこの形式を採用しています。
- ソフトウェアインストール型:PC(Windows/Mac)にソフトウェアをインストールして利用するタイプです。オフラインで作業できたり、より高度なカスタマイズが可能だったりする場合があります。特に画像生成AIや動画生成AIの中には、高性能なグラフィックボード(GPU)を搭載したPCでないと快適に動作しないものもあるため、推奨される動作環境(スペック)を事前に確認することが不可欠です。
- スマートフォンアプリ型:iOSやAndroidの専用アプリとして提供されるタイプです。スマートフォンならではの手軽さが魅力で、外出先でも気軽にコンテンツを生成できます。ただし、PC版に比べて機能が一部制限されている場合もあります。
自分のワークスタイルや利用シーンを想定し、最適な提供形態のソフトを選びましょう。複数のデバイスでデータを同期できるかどうかも、合わせて確認しておくと便利です。
4. 【無料】今すぐ試せる!おすすめ生成AIソフト

生成AIソフトに興味はあるものの、「いきなり有料プランを契約するのはハードルが高い」と感じる方は多いのではないでしょうか。近年、無料で利用できる生成AIソフトが続々と登場しており、その多くは有料版に匹敵するほどの高い性能を備えています。
まずは無料のソフトを試すことで、生成AIで何ができるのか、どのように業務や創作活動に活かせるのかを具体的に体験できます。
この章では、アカウント登録だけですぐに利用を開始できる、おすすめの無料生成AIソフトを「文章生成」「画像生成」のカテゴリに分けてご紹介します。それぞれのツールの特徴や無料プランでできることを比較し、あなたに最適なソフトを見つける手助けをします。
4.1 無料で使える文章生成AIソフト
メール作成やブログ記事の執筆、アイデア出しなど、テキストに関わる様々なタスクを効率化できるのが文章生成AIです。無料で使える代表的なソフトにはそれぞれ特徴があり、用途に応じて使い分けることで、その能力を最大限に引き出すことができます。
4.1.1 ChatGPT(無料版)
OpenAI社が開発した、世界で最も有名な対話型AIです。自然な対話形式で、質問応答、文章の要約、翻訳、アイデアの壁打ちなど、幅広い用途に対応できます。無料版ではGPT-3.5モデルが利用でき、日常的なタスクであれば十分な性能を発揮します。まずは生成AIの基本を体験したいという初心者に最適です。
4.1.2 Google Gemini(無料版)
Googleが開発した生成AIで、最新のWeb情報に基づいた回答を生成できるのが大きな強みです。リアルタイム性の高い情報収集や、トレンドを踏まえたコンテンツ作成で力を発揮します。また、GoogleドキュメントやGmailといった他のGoogleサービスとの連携機能も充実しており、普段からGoogleのサービスを利用しているユーザーにとっては特に便利なツールです。
4.1.3 Claude(無料版)
Anthropic社が開発した生成AIで、特に長文の読解や生成、要約能力に定評があります。他のAIよりも丁寧で、より人間らしい自然な文章を生成する傾向があります。PDFやテキストファイルなどをアップロードして、その内容について質問したり要約させたりする機能も無料で利用できるため、資料の読み込みや分析といった用途にも適しています。
| ツール名 | 開発元 | 特徴 | 無料版の主な機能・制限 |
|---|---|---|---|
| ChatGPT | OpenAI | 自然な対話形式で汎用性が高い。生成AIの基本操作を学ぶのに最適。 | GPT-3.5モデルを利用可能。利用回数に制限はないが、アクセス集中時は待機が発生する場合がある。最新情報へのアクセスは限定的。 |
| Google Gemini | Google検索と連携し、最新情報に基づいた回答が得意。Googleサービスとの連携も強力。 | 標準モデルであるGemini Proを利用可能。一部機能(拡張機能など)も無料で使える。 | |
| Claude 3 Sonnet | Anthropic | 長文の処理能力が高く、自然で丁寧な文章を生成。ファイルのアップロード機能が便利。 | 高性能モデルファミリー「Claude 3」の中間モデルであるSonnetを利用可能。利用量に応じて一時的な制限がかかる場合がある。 |
4.2 無料で使える画像生成AIソフト
簡単なキーワードや文章(プロンプト)を入力するだけで、オリジナルのイラストや写真を生成できるのが画像生成AIです。無料で利用できるサービスも多く、ブログのアイキャッチ画像作成やSNS投稿、プレゼン資料の挿絵など、クリエイティブな作業を手軽にサポートしてくれます。
4.2.1 Bing Image Creator
Microsoftが提供する画像生成AIで、ChatGPTと同じOpenAI社の高精度モデル「DALL-E 3」を無料で利用できるのが最大の特徴です。Microsoftアカウントがあれば誰でもすぐに使え、日本語の指示にも高い精度で応えてくれます。生成速度を上げるための「ブースト」クレジットが毎日付与され、クレジットを使い切っても低速で生成が可能です。
4.2.2 SeaArt.ai
アニメ風やイラスト風の画像生成に特に強いサービスです。無料で利用できるクレジット(スタミナ)が多く、毎日ログインするだけで補充されるため、気軽に多くの画像を試せます。コミュニティで共有されている他のユーザーのプロンプトや、特定の画風を再現する「LoRA」モデルを参考にできるため、初心者でも高品質な画像を生成しやすいのが魅力です。
4.2.3 Leonardo.Ai
ゲームのキャラクターや背景、アイテムといったアセット制作に特化したモデルが豊富な画像生成AIです。ファンタジーやサイバーパンクなど、特定のテーマに沿った高品質な画像を生成するのに長けています。毎日一定数の無料クレジットが付与され、生成した画像のアップスケール(高画質化)や背景透過といった編集機能も利用できます。
| ツール名 | 開発元 | 特徴 | 無料範囲・制限 |
|---|---|---|---|
| Bing Image Creator | Microsoft | 高性能なDALL-E 3を無料で利用可能。日本語の指示(プロンプト)に強い。 | 毎日付与されるクレジット(ブースト)で高速生成。クレジット消費後も低速で生成可能。 |
| SeaArt.ai | STAR CLUSTER PTE. LTD. | アニメ・イラスト風の生成が得意。無料クレジットが多く、初心者でも使いやすい。 | 毎日・毎時付与されるクレジット(スタミナ)の範囲内で利用可能。タスク完了で追加クレジットも獲得できる。 |
| Leonardo.Ai | Leonardo.Ai | ゲームアセットやファンタジー系の高品質な画像生成に特化。多様な学習済みモデルが利用可能。 | 毎日リセットされるクレジットの範囲内で利用可能。生成画像のプライベート設定は有料プランのみ。 |
無料の生成AIソフトは、機能制限や利用規約が変更されることがあります。特に、生成したコンテンツを商用利用する場合は、各サービスの公式サイトで最新の利用規約を必ず確認するようにしてください。
5. 【有料】本格的ならこれ!高機能な生成AIソフト
無料の生成AIソフトは手軽に試せる一方で、機能制限や商用利用の制約がある場合が少なくありません。ビジネスでの本格的な活用や、クオリティを追求するクリエイティブ制作には、有料の高機能な生成AIソフトが不可欠です。
有料プランでは、生成精度や速度の向上、API連携による業務システムへの組み込み、チームでの共同編集機能、手厚いカスタマーサポートなど、無料版にはない多くのメリットを享受できます。ここでは、特定の分野に特化したプロフェッショナル向けの生成AIソフトを「文章生成」と「画像・動画生成」に分けてご紹介します。
5.1 ビジネス利用に強い文章生成AIソフト
マーケティングコンテンツの作成、長文レポートの要約、顧客対応メールの自動生成など、ビジネスシーンでは文章生成AIの活用が急速に進んでいます。有料の文章生成AIソフトは、単に文章を作るだけでなく、SEO対策、ブランドイメージに沿ったトーンの統一、多言語対応といった、より高度な要求に応える機能を搭載しています。
5.1.1 ChatGPT (Plus / Team / Enterprise)
OpenAI社が開発した、最も有名な対話型AIです。有料プランにアップグレードすることで、無料版よりも高性能な最新モデル(GPT-4oなど)を優先的に利用できます。ファイルのアップロードによるデータ分析、DALL-E 3を用いた画像生成、Webブラウジング機能など、文章生成にとどまらない多彩な機能が魅力です。
特に法人向けのTeamプランやEnterpriseプランでは、管理コンソールによるメンバー管理や、入力したデータがAIの学習に使われないといった高度なセキュリティが保証されており、安心して業務に導入できます。
| プラン名 | 主な対象 | 特徴 | 料金(目安) |
|---|---|---|---|
| Plus | 個人・小規模利用者 | 最新モデルへの優先アクセス、画像生成、データ分析機能 | 月額20ドル |
| Team | 中小企業・チーム | Plusの全機能に加え、管理コンソール、より大きなコンテキストウィンドウ、データが学習に使われない保証 | 月額25ドル/ユーザー (年間払い) |
| Enterprise | 大企業 | Teamの全機能に加え、無制限の高速アクセス、エンタープライズレベルのセキュリティとコンプライアンス、APIクレジット | 要問い合わせ |
5.1.2 Jasper (ジャスパー)
マーケティングやコンテンツ制作に特化した文章生成AIとして、海外で高い評価を得ています。ブログ記事、広告コピー、SNS投稿など、50種類以上の豊富なテンプレートが用意されており、目的に合わせて高品質な文章を効率的に作成できます。
さらに「ブランドボイス機能」を使えば、自社の製品情報やスタイルガイドを学習させ、一貫性のあるトーンで文章を生成することが可能です。SEO対策機能も充実しており、コンテンツマーケティングを強化したい企業に最適です。インターフェースは英語が中心ですが、日本語を含む多言語に対応しています。
5.1.3 Catchy (キャッチー)
株式会社デジタルレシピが提供する、日本国内最大級の文章生成AIツールです。日本のビジネス環境や文化に合わせた100種類以上の生成ツール(テンプレート)が用意されており、キャッチコピー、メール文、Webサイトの文章、新規事業のアイデア出しまで幅広く対応します。特に、日本語の自然さや表現の豊かさに定評があり、国内ユーザーにとって直感的に使いやすい点が大きな強みです。無料プランから始められ、必要に応じて有料プランにアップグレードできます。
5.2 クリエイター向けの画像・動画生成AIソフト
広告ビジュアル、Webサイトの挿絵、映像作品の素材など、クリエイティブ分野では生成AIが新たな表現の可能性を切り拓いています。有料の画像・動画生成ソフトは、生成されるコンテンツの品質、解像度、カスタマイズ性、そして商用利用の権利といった面で、無料ツールを大きく凌駕します。
5.2.1 Midjourney (ミッドジャーニー)
アーティスティックで独創的な画像の生成に非常に強いAIソフトです。特に、イラスト、ファンタジー、風景画などの分野で、他の追随を許さない美しいビジュアルを生成することで知られています。
チャットアプリ「Discord」上でテキストコマンド(プロンプト)を入力して画像を生成する独特のインターフェースですが、慣れれば高速かつ高品質なアウトプットが可能です。
有料プランに加入することで、生成枚数の制限が緩和され、生成した画像の商用利用権が得られます。多くのクリエイターやデザイナーから絶大な支持を集めています。
5.2.2 Adobe Firefly (アドビ ファイアフライ)
クリエイティブソフトの最大手であるAdobe社が開発した画像生成AIです。最大の特徴は、PhotoshopやIllustratorといった同社の主要アプリケーションに機能が統合されている点です。「生成塗りつぶし」や「生成拡張」といった機能を使えば、既存の画像の一部を違和感なく変更したり、画像の範囲を自然に広げたりすることができ、デザイン作業の効率を劇的に向上させます。
また、学習データにAdobe Stockの画像や著作権がクリアな素材のみを使用しているため、商用利用時の権利侵害リスクが極めて低いことも、ビジネスで利用する上で大きな安心材料となります。
5.2.3 Runway (ランウェイ)
テキストや画像から高品質な動画を生成できる、動画生成AIの代表格です。最新モデルの「Gen-2」は、短いテキストを入力するだけで、数秒から十数秒程度の写実的な動画やアニメーションを生成できます。既存の動画のスタイルを別のものに変換する「Video to Video」機能や、動画の一部だけを動かす「モーションブラシ」など、プロの映像クリエイター向けの高度な機能も多数搭載しています。Webブラウザ上で直感的に操作できるため、専門的な映像編集ソフトの経験がなくても、手軽にAIによる動画制作を始めることができます。
6. 生成AIソフトを利用する際の注意点

生成AIソフトは、業務効率化やクリエイティブ作業のサポートなど、計り知れない可能性を秘めた便利なツールです。しかし、その手軽さの裏には、知らずに利用すると大きな問題に発展しかねない注意点も存在します。
特にビジネスで活用する際は、法務、セキュリティ、倫理の観点からリスクを正しく理解し、適切な対策を講じることが不可欠です。ここでは、生成AIソフトを安全かつ効果的に利用するために、必ず押さえておくべき3つの重要な注意点を詳しく解説します。
6.1 著作権・商用利用のルール
生成AIソフトで作成した文章や画像(生成物)を手軽に利用できる一方、その著作権の扱いは非常に複雑で、注意が必要です。安易な利用は、意図せず他者の権利を侵害してしまうリスクを伴います。利用規約の確認を怠ると、トラブルに発展する可能性もあるため、特に商用利用を考えている場合は慎重な判断が求められます。
6.1.1 生成物の著作権は誰のもの?
生成AIによって作られたコンテンツの著作権が誰に帰属するかは、国や地域の法律、そして各サービスの利用規約によって解釈が異なります。
日本では、文化庁が「AIによって生成されたものに人の思想又は感情の創作的寄与が認められれば著作物として認められる」という見解を示しています。つまり、単にキーワードを入力して出力されただけでは著作物とは認められにくく、プロンプトの工夫や生成後の加工・修正といった人間の創作的な関与があって初めて、その人に著作権が認められる可能性があるということです
。現状では法整備が追いついていない部分も多く、今後の判例や法改正の動向を注視する必要があります。
6.1.2 商用利用の可否は利用規約を確認
生成物をブログ記事やSNS投稿、広告、商品デザインなどに利用する「商用利用」が可能かどうかは、使用する生成AIソフトの利用規約で定められています。無料プランでは商用利用を禁止し、有料プランでのみ許可しているサービスも少なくありません。
また、商用利用が可能な場合でも、「クレジット表記(AIサービス名などを記載すること)が必須」といった条件が課されていることもあります。利用を開始する前に必ず公式ウェブサイトで最新の利用規約を確認し、ルールを遵守することが重要です。以下に代表的な生成AIソフトの著作権と商用利用に関する一般的な方針をまとめましたが、必ずご自身で最新の規約をご確認ください。
| 生成AIソフト | 生成物の著作権 | 商用利用の可否 | 注意点(クレジット表記など) |
|---|---|---|---|
| ChatGPT (OpenAI) | 利用規約上、ユーザーに譲渡される | 可能(無料版・有料版問わず) | 他者の権利を侵害するコンテンツの生成は禁止。出力内容が既存の著作物に類似しないか注意が必要。 |
| Midjourney | 有料プランユーザーに所有権が付与される(無料版は除く) | 有料プランのみ可能 | 無料版で生成した画像は商用利用不可。生成画像はMidjourney側が利用する権利を持つ。 |
| Stable Diffusion | ユーザーに帰属(モデルによる) | 可能(モデルのライセンスによる) | 利用する学習モデルのライセンス(例: CreativeML Open RAIL-M)を遵守する必要がある。 |
6.2 情報の正確性とファクトチェック
生成AIソフトは、インターネット上の膨大な情報から学習し、もっともらしい文章を生成することを得意としています。しかし、その情報が必ずしも正確であるとは限りません。AIが事実に基づかない情報を、あたかも真実であるかのように生成してしまう現象は「ハルシネーション(幻覚)」と呼ばれ、生成AIを利用する上で最も注意すべき点の一つです。
6.2.1 なぜ不正確な情報が生成されるのか
生成AIは、情報の真偽を判断しているわけではありません。学習データに基づいて、文脈上最も確率の高い単語や文章を予測して繋ぎ合わせることで回答を生成しています。そのため、学習データに誤った情報が含まれていたり、複数の情報を不適切に組み合わせてしまったりすると、結果として事実と異なる内容が出力されることがあります。
特に、最新の情報や専門性の高い分野、統計データ、固有名詞などに関しては、誤りが含まれる可能性が高まります。
6.2.2 ファクトチェックが不可欠な理由と対策
生成AIからの出力を、そのままレポートや記事、ビジネス文書に利用することは非常に危険です。誤った情報に基づいて重要な意思決定を行ったり、外部に発信してしまったりすれば、個人の信頼だけでなく、企業の信用を大きく損なうことになりかねません。
このリスクを回避するためには、以下の対策が不可欠です。
- 必ず一次情報を確認する: 生成された情報については、必ず公的機関の発表や信頼できる報道機関、専門家の論文など、元の情報源(一次情報)にあたって裏付けを取りましょう。
- 思考の補助ツールとして活用する: 生成AIを「答えを教えてくれる賢者」ではなく、「アイデア出しや文章構成のたたき台を作るアシスタント」と位置づけ、最終的な判断や仕上げは人間が行うという意識を持つことが重要です。
- 具体的な数値や固有名詞は特に注意する: 統計データ、法律、歴史的な事実、人物名などの固有名詞は、特に間違いやすいため、入念なファクトチェックが必要です。
6.3 機密情報の入力リスク
業務効率化のために生成AIソフトを利用する際、最も警戒すべきなのが情報漏洩のリスクです。チャットの入力欄に顧客の個人情報や社外秘のプロジェクト情報などを安易に入力してしまうと、重大なセキュリティインシデントにつながる可能性があります。
6.3.1 入力した情報が学習に使われる可能性
多くの生成AIサービスでは、ユーザーが入力したデータ(プロンプト)を、サービスの品質向上やAIモデルの再学習のために利用することが利用規約に明記されています。つまり、入力した機密情報がAIの学習データとして取り込まれ、他のユーザーへの回答として意図せず出力されてしまう可能性がゼロではないのです。また、サービス提供企業の従業員がデータにアクセスしたり、サイバー攻撃によって情報が外部に流出したりするリスクも考慮しなければなりません。
6.3.2 安全に利用するための対策
機密情報の漏洩リスクを防ぎ、ビジネスで安全に生成AIソフトを活用するためには、以下の対策を徹底する必要があります。
- 機密情報・個人情報を入力しない: 顧客情報、従業員の個人情報、未公開の財務情報、新製品の開発情報、ソースコードなど、社外秘にあたる情報は絶対に入力しないことを基本ルールとします。
- オプトアウト設定を活用する: サービスによっては、入力したデータをAIの学習に利用させないようにする「オプトアウト」の設定が可能です。利用前に設定を確認し、必ず有効にしておきましょう。
- 法人向けプランを検討する: ChatGPT Enterpriseのように、セキュリティを強化し、入力データを学習に利用しないことを保証した法人向けの有料プランも提供されています。本格的なビジネス利用を検討する場合は、こうしたプランの導入が推奨されます。
- 社内ガイドラインを策定する: どこまでの情報を入力して良いか、どのような業務に利用できるかといったルールを明確にした社内向けのガイドラインを作成し、全従業員に周知徹底することが、組織的なリスク管理において非常に重要です。
7. まとめ
本記事では、最新のおすすめ生成AIソフトを無料・有料別に15選ご紹介しました。ChatGPTのような文章生成からMidjourneyなどの画像生成まで、用途は多岐にわたります。
最適なソフトを選ぶ結論として、まずは「目的」を明確にし、「料金」や「商用利用の可否」を確認することが失敗しないための重要なポイントです。本記事を参考に、まずは無料ツールから試して、業務効率化や新たな創作活動に役立ててください。
product関連するプロダクト
-

UMWELTウムベルト
UMWELTは、プログラミング不要でかんたんに分析や自動化ができるノーコードツールです。需要予測から生産計画を最適化、人材の最適配置まで課題を解決できます。日々変化する生産数や生産計画、人員配置を自動立案し属人化や作業時間を大幅に削減します。
MWELT

TRYETING
公式
TRYETING公式です。
お知らせやIR情報などを発信します。










