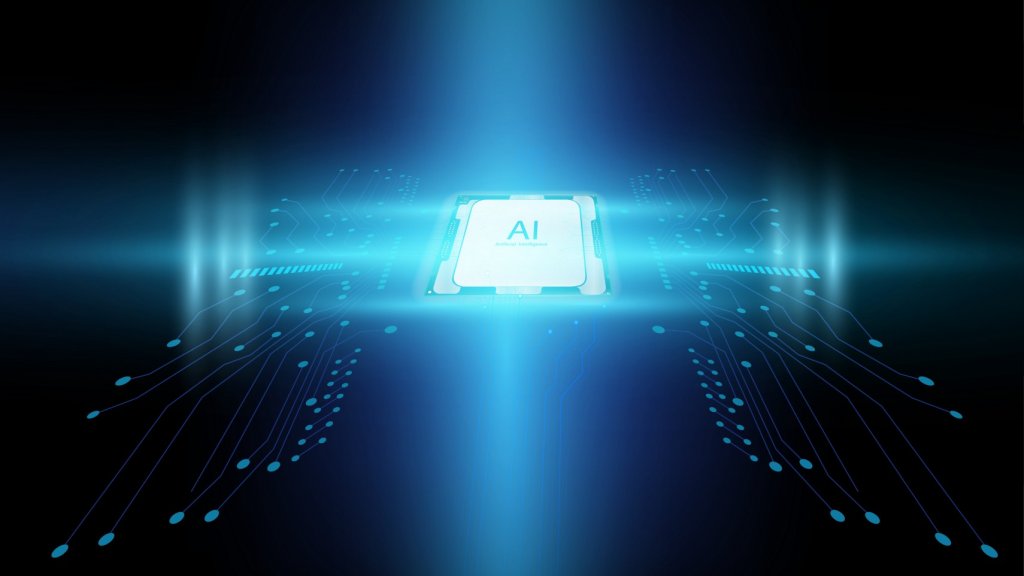BUSINESS
アメリカでついに始まった、AI普及による「新卒就職氷河期」

目次
アメリカの今年2025年度の大学新卒者の失業率が近年最悪レベルを記録している。
新卒者の失業率悪化の最大の原因とされているのが企業におけるAIの普及だ。特にこれまで新卒者が主に担当してきた「エントリーレベルジョブ」とされる仕事の多くがAIに奪われ、雇用機会が大きく減少している。
AIは、具体的にどのような仕事を代替し、今後どのような方向へ進む可能性があるのか。AI時代の新卒者のキャリアビルディングや日本への波及の可能性なども含めて考察する。
AI普及による「新卒就職氷河期」の到来

公共放送PBSが、アメリカで始まったAI普及による「新卒就職氷河期」の現状を報じている。アメリカの今年2025年度の大学新卒者の失業率は5.8%に上昇し、近年最悪レベルに達したという。ジェネレーションZと呼ばれる若い世代が職探しに苦労している現状が現れているわけだが、実際に全世代労働者の失業率4.2%を大きく上回っている。
労働市場の流動性が高いアメリカでは、失業率は景気の波に影響されやすく、日本などと比べてボラティリティ(変動幅)が比較的高いとされており、これまでは特定の産業の盛衰の影響を受けることが一般的だった。
例えば、2008年の世界金融危機や2020年のコロナのパンデミックなどの影響を受けて失業者が増加し、当時の失業率を大きく押し上げてきた。前者においては銀行、証券、投資などの金融関連の雇用が大きく失われ、後者においては外食などのホスピタリティ産業や小売業界などにおいて大量の失業者が発生、失業率を押し上げた。
しかし、今回発生している「新卒就職氷河期」では、これまでに新卒者に多くの雇用を提供してきた主な産業が軒並み採用意欲を減らし、ほぼ全業種に渡って求人数を落としているのが大きな特徴だ。
具体的にどのような仕事が減少しているのか?
では、具体的にどのような仕事が減少しているのだろうか。企業の採用担当者が口を揃えるのが「エントリーレベルジョブ」と呼ばれる仕事の減少だ。「エントリーレベルジョブ」(Entry level jobs)とは、労働経験の無いルーキー社会人に充てられる「見習い仕事」のことだ。
例えば、法律事務所では新卒者を採用すると「リーガルリサーチ」と呼ばれる判例調査や「ドキュメント・リトリーバル」と呼ばれる書類校正などの仕事をやらせるのが一般的だ。またソフトウェアやアプリケーション開発などのIT企業では「デバッグ」と呼ばれる「プログラムのバグ探し」やアプリケーションの「テスト」などを、サービス企業であれば「カスタマーサポート」や「セールスサポート」などの仕事を、それぞれ新人に割り当てるのがこれまでのスタンダードだった。
新卒者は、それぞれの職場で与えられた「エントリーレベルジョブ」からキャリアをスタートさせ、それをベースに知識と経験を積み上げてゆくのがキャリアビルディングの基本だった。ところが、そうした仕事の多くがAIに代替され、「エントリーレベルジョブ」そのものがなくなり始めているというのだ。
AI時代の新たな「新卒者のキャリアパス」とは?
アメリカの多くの職場で「エントリーレベルジョブ」が失われつつあるということは、「エントリーレベルジョブ」をキャリアビルディングの出発点とするはずだった、多くの新卒者のキャリアビルディングの機会そのものがなくなりつつあるということを意味する。これまでの新卒者は、それぞれの職場で水の中に突然突き落とされ、各種の見習い仕事を与えられてそれらをこなすようになり、毎日もがきながら徐々に仕事のノウハウを積み上げ、何とか泳げるようになっていった。
では、本格的なAI時代においては、新卒者はどのようなキャリアパスを構築すべきなのだろうか。共通して言えることは、これからの新卒者は、今まで与えられていた「エントリーレベルジョブ」はすでに無くなったという認識を持ち、エントリーレベルジョブを超越した、より専門性の高いスキルをもってキャリアパスの構築を始めるべきだということだ。
例えば、ある法律事務所では新卒者にエントリーレベルジョブを与えるのを止めて、入社してすぐに紛争調停などの専門性が高い仕事を与えるようにし始めたという。また、ある大手監査法人も新卒者に職務歴三年程度を要するような仕事を最初から与え、即戦力として活用しているという。
いずれもエントリーレベルジョブはAIにまかせて、AIのアウトプットをベースにして仕事をしている形だ。そうしたルーキーたちは、AIをアシスタントとして使いこなしつつ自らのキャリアビルディングを始めているのだ。
新卒者に求められる「AIフルーエンシー」

ある企業人事担当者は新卒者に対し、これまでのように5年から10年程度の「中長期」のスパンでキャリアプランを作ることをやめて、より短いスパンでよりフレキシブルなキャリアプランを策定するようアドバイスしている。そして何よりも、自分の仕事のためにAIを使いこなす「AIフルーエンシー」(AI fluency)を磨くことの重要性を強く訴えている。
「AIフルーエンシー」とは、GoogleのAI「Gemini」によると、「AIを十分にかつ効率的に理解して対話し、みずからのゴール達成や他者とのコラボレーション完遂、またはリアル世界での問題解決のために活用するための一連の能力」のことだ。そのためのスキルとして「コンセプトの理解、倫理的な自覚、プロンプト・エンジニアリング(AIに正しくアウトプットさせるための一連の技術)などの実務能力、AIアウトプットに対するクリティカルな評価能力」などが求められるとしている。
要するに、AIそのものを十分に理解し、AIのアウトプットを自分の責任と判断で正しく評価し、適切に活用するための一連の能力がAIフルーエンシーなのだろう。これからの新卒者は、どのような業界・業種でキャリアビルディングを始めるにせよ、この「AIフルーエンシー」が必須の能力として求められている。
これまでの人類の半世紀の歴史においても、例えば職場におけるパソコンやインターネットの登場と普及が、それまで人間に与えられていた仕事の多くを代替していった。労働環境が変化する局面においては、それぞれ歴史を転換させるニューテクノロジーをいち早く取り入れ、使いこなせる労働者に対する需要が拡大してきた。
現在始まったAIによるパラダイムシフトにおいても同様に、AIを使いこなし、それをベースに新たな価値を生み出す労働者が重宝されることになるのだろう。これからキャリア構築をゼロベースでスタートするという意味では、新卒者は総じてキャリアが白紙である分有利であり、すでに染まってしまったベテラン労働者より大きな可能性を持っているとも言える。
日本への波及の可能性
ところで、アメリカで進行中のこのトレンドは、いずれは日本へも波及するだろうか。筆者の答えは間違いなく「イエス」だ。AI革命による新卒者の雇用市場の激変は、必ず日本でも起きる。いや、すでに起きている。
一般的にアメリカほど新卒者の専門性が高くない日本においては、アメリカ並みに劇的に新卒者の雇用市場が変化しないとも思われるが、「新卒一括採用」を基本とする多くの日本企業においても、新卒者に「AIフルーエンシー」を求めてくるようになることは間違いない。
「新卒一括採用」で採用された新卒者が、「パソコン研修」や「インターネット研修」といった感じで「AI研修」を受けさせられ、AIに関する一般的な知識やスキルを学習させられるといったケースが少なくないかもしれない。一方で、AIの能力やエコシステムを深く理解し、AIを使ってこれまでになかった価値を新たに作り出す「AI使い」とも呼ぶべきタレントが出現し、それぞれの企業で突出した存在となってゆく未来像が想像できなくはない。
AIによる世界的な企業間競争が激化する中、多くの日本の企業経営者が新たなタレントの登場を期待していることは間違いないだろう。日本の若者には、そうした可能性を持つ者が少なくないと筆者は考えている。
参考文献
https://www.pbs.org/newshour/show/how-ai-may-be-robbing-new-college-graduates-of-traditional-entry-level-jobs
https://www.cbsnews.com/news/ai-jobs-unemployment-college-graduate/
https://theconversation.com/will-ai-pull-the-career-ladder-up-out-of-reach-or-just-change-what-it-looks-like-262866

前田 健二
経営コンサルタント・ライター
事業再生・アメリカ市場進出のコンサルティングを提供する一方、経済・ビジネス関連のライターとして活動している。特にアメリカのビジネス事情に詳しい。