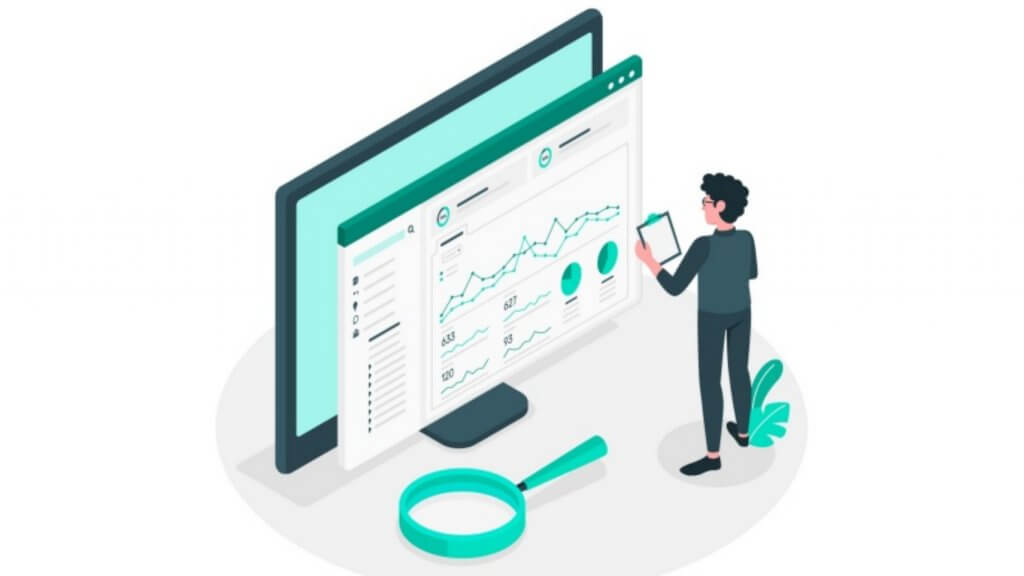WORK
春から初夏にかけて心が疲れる──。「5月病」と「6月病」の対策とは
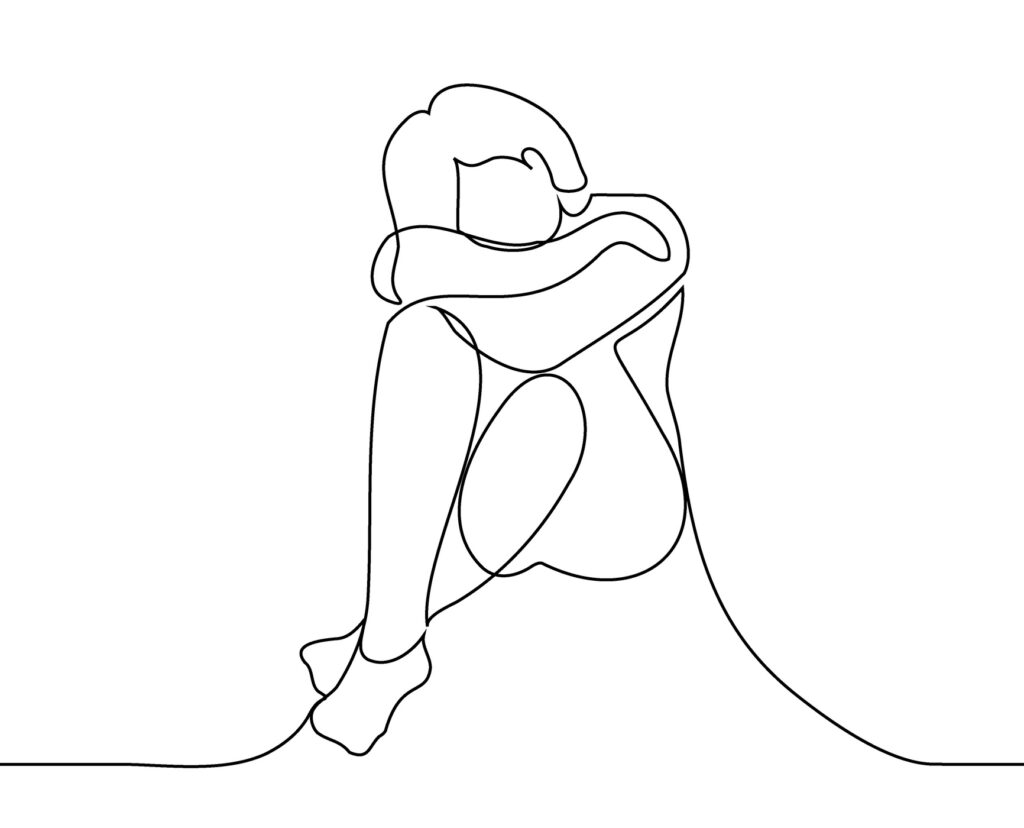
目次
連休明けのオフィス。十分に休んだはずなのに、身体は重く、思考は曇っている。浅かった眠りのせいかで疲れも抜けず、体も鈍い。そして、休み前は前向きに受け取っていたはずの転職や昇進ですら、なぜか心に影を落とす──。
それは単なる「休みボケ」ではなく、「5月病」や「6月病」という心身の不調の入り口に差しかかっているのかもしれない。
今回は、私たちの心はなぜ、春の終わりに「不具合」を起こしやすいのかを考察していく。春から初夏にかけて起こりがちな心と体の不調が、この季節に集中する理由を掘り下げるとともに、変化とうまく付き合う心身のチューニングのコツを探っていこう。
新年度文化が生み出す病「5月病」
5月の大型連休明けに発症しやすい「5月病」は、心身になんらかの不調が現れる状態を指す。医学的な正式名称ではないが、抑うつ気分、不眠、食欲不振などの症状が見られる。
もともとは、受験競争が厳しかった1960年代後半から1970年代にかけて、激しい受験競争を終えた大学生が、いわゆる燃え尽き症候群のような虚脱感や抑うつ気分を訴えたことから「5月病」という言葉が使われ始めたとされる(※1)。
現代では、新年度の4月から新しい環境に置かれる人に起きやすい。慣れない環境で必死に頑張ろうとし、気づかないうちに必要以上にエネルギーを使ってしまうためだ。連休で体も心もリフレッシュされるはずなのに、実際には思ったほどに回復を感じられず、その焦りから焦燥感や戸惑いが強まることも少なくない。
5月病の原因は、単純に語れるものではない。例えば、大学卒業後に慣れない土地で一人暮らしを始め、社会のプレッシャーに晒されるといった、「頑張らないと」「自分は社会に適応できるのか」などの葛藤や不安が影響することもある。さらに、新しい環境での人間関係の構築や理想とのギャップなど、さまざまな要因が複雑に絡み合うことで発生すると考えられている。
“慣れ”の先に待つ「6月病」という第二の不調
最近では、さらに「6月病」という言葉を耳にすることも増えてきた。5月病が新しい環境へのストレス反応として起きるのに対し、6月病は「新しい環境にある程度慣れたタイミング」で発症することが多いとされる。「5月病を乗り越えたと思ったら、6月になって不調が……」という具合だ。
背景にあるのは、不調を我慢して頑張ってしまうことが一因とされる。慣れない環境で心身が疲れている中、「5月病になりたくない」と気を引き締める。すると、5月はなんとか持ちこたえたものの、目を瞑ってきた不調が5月病よりも深刻な症状として出やすくなる。
ここで注意したいのは、たとえ自分が慣れ親しんだ環境に身を置いていたとしても、周囲の環境が変化することで、5月病や6月病が起きる可能性が十分あること。あまり知られていないが、ライフイベント法とストレス度測定をまとめた論文(※2)では、「抜擢に伴う配置転換」「昇進」など一見ポジティブな出来事でも、高いストレスがかかる要因とされる。
環境変化に伴うストレスは無意識に蓄積され、年齢や性別、社会的立場にかかわらず、さまざまな不調の引き金になるわけだ。
ポストコロナが春先の不調に与える影響

リモートワークや外出制限で、対人ストレスが一時的に減少していたコロナ禍。新しい働き方やインターネット上でのやりとりが広がったが、現在はオフィス出社回帰やオフラインが急速に進みつつある。
それにより、人との関わりが再開し、人間関係によるストレスが起こりやすくなっている。通勤の切り替えや、リモートワークとの生活リズムの違いに戸惑いながら、知らず知らずのうちにストレスを溜め込んでいる人も少なくない。
会社の決定には従わざるを得なくても、心の中で生まれた違和感を放っておくと、あっという間に影を落とす。一部の企業では、体調が悪いまま働くプレゼンティーズムによる損失が見直されるようになり、メンタル不調への理解が広まりつつあるものの、社会全体で見れば一握りに過ぎない。
「適応しない自由」が許されない現代の社会構造では、“適応できないこと”が即座に自責の念や自己否定感につながりやすくなり、心を蝕んでいく。
では、どのようにして春先の不調とうまく付き合っていくべきなのだろうか。
頑張らないという選択肢を
新しい環境で、内外からの期待に応えること、結果を出すことがデフォルトである社会では、それから逃れることはできないかもしれない。ただ、心の片隅に「頑張らなくてもいい」「逃げ道を作ってもいい」という視点をぜひ持ってほしい。
実は、5月病や6月病は、完璧主義の傾向がある人がかかりやすいとされる。外からの期待に応えようと、自分に厳しい結果を課すことで、気がつくとたくさんの重圧がかかり、それが心身の不調として現れてしまう。
また、春先は特に気温の変化が大きく、ただでさえ自律神経が乱れがちだ。すると、睡眠の質が下がったり、疲れが取れにくくなったりと、いつも以上に不調が出やすい。エネルギーが枯渇しがちな中、新しい環境で結果を出すために肩に力が入ってしまうことでエネルギーをどんどん消耗し続け、心身の限界が近づいてしまうのだ。
「頑張らない」というのは手を抜くという意味ではなく、自分の身体と心をきちんと観察した上で、今できる最善策を行うこと。春先は変化が生まれやすいからこそ、100%できない自分がいたとしても、その自分を受け入れることが、不調を回避する一歩になる。
「眠り」と「余白」が揺らぎがちな春の心を守る
5月病や6月病から心身を守るための第一歩は、しっかりと眠ることだ。さまざまなところで聞き飽きているかもしれないが、睡眠は百薬の長といっても過言ではない。
厚生労働省が行った、職場環境とメンタルヘルスに関する研究(※3)では、ベッドに入って6時間未満もしくは、実睡眠が6時間に満たない場合は、うつ病のリスクが高まることが明らかになった。また、睡眠の質も重要で、途中覚醒・寝つきの悪さも、リスクと強く関連するという。
調子がすぐれないと感じたら、まず眠る。この時、スマートフォンやSNSからはできるだけ距離を置こう。スマートフォンを利用することで、交感神経が活発になり、眠りの質が下がるおそれがある。
そうはいっても、高いストレス下では、考えれば考えるほど眠ることが難しい人も多い。そこで、眠りの質改善と並行して、「余白」を意識することも重要だ。
余白とは、仕事や学校、家庭であなたの頭を悩ませることから、距離を置くこと。抑うつ状態になると、私たちの意識は過去や未来への不安にとらわれやすくなり、その結果、無力感や自尊心の低下を招く。湧き上がってくるさまざまな心配事を止めようとすればするほど、止まらない。そんな時こそ、「今ここ」に意識を向ける練習を試してほしい。
マインドフルネスで、「今この瞬間に意識を向ける」練習を繰り返したり、リトリートに参加して日常から離れた環境に身を置いたりすることで、過去や未来の心配を手放し、心の「余白」を作り出すことができる。実際にマインドフルネスは、科学的にストレス軽減やレジリエンス(回復力)の向上、睡眠の質改善が証明されており、5月病や6月病で出やすい不調への対処法として期待できる。
春の不調は、頑張り過ぎを手放すことから

新しい環境に適応し、結果を出さなければいけないという新年度特有のプレッシャーに加え、気候の変化によるエネルギーの消耗が起きる春先。
抑うつ状態に陥ると、ついつい「頑張りが足りない」と自分をジャッジしがちになる。しかし、そのジャッジこそが5月病や6月病のきっかけになり得るのだ。
まずはうんざりするほど聞かされている、睡眠・適度な運動・健康な食事を意識しよう。さらに、「今ここ」に意識を向け、目の前に余白を作ることが、この季節を駆け抜けるために欠かせないチューニング法になるだろう。
ついつい頑張り過ぎている自分をきちんと認めてあげながら、自分の限界を見極める。新緑のまぶしいこの季節を、自分らしいペースで穏やかに過ごしてほしい。
参考文献
※1 「五月病」という言葉がいつ頃から使われ始めたか知りたい。|国立国会図書館
https://crd.ndl.go.jp/reference/entry/index.php?page=ref_view&id=1000217467※2 夏目誠・村田弘(1993).ライフイベント法とストレス度測定.『日本公衆衛生雑誌』42巻3号,402–412.
https://www.niph.go.jp/journal/data/42-3/199342030005.pdf3 川上憲人・渡邊健・津田賢一(2013).職場環境とメンタルヘルスに関する研究報告書(平成25年度 厚生労働科学研究).厚生労働省.
https://mhlw-grants.niph.go.jp/system/files/2013/133061/201315046A_upload/201315046A0012.pdf
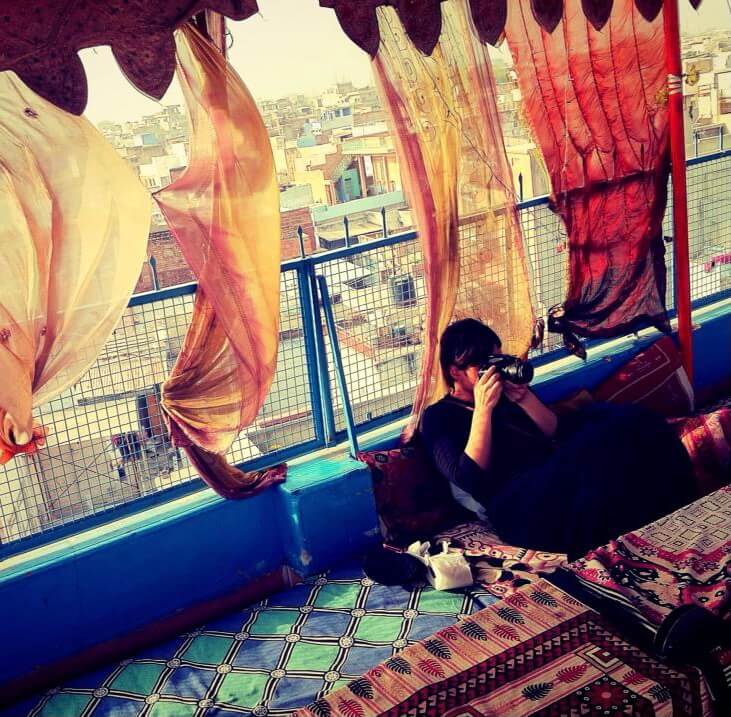
Ayaka Toba
編集者・ライター
新聞記者、雑誌編集者を経て、フリーの編集者・ライターとして活動。北欧の持続可能性を学ぶため、デンマークのフォルケホイスコーレに留学し、タイでPermaculture Design Certificateを取得。サステナブルな生き方や気候変動に関するトピックスに強い関心がある。