PICK UP
2,500年の歴史に潜む、「仏教」と「テクノロジー」の深遠なる関係

目次
宗教の発展とテクノロジーの進化。そこには、切っても切り離せない関係がある。グーテンベルクが活版印刷を発明して聖書を広げたのはその典型とも言える。そして、このような例は、日本人にとっても馴染み深い「仏教」にもある。
仏教はどのようにテクノロジーを活用して発展したのか?仏教とテクノロジーの深遠なる関係を紐解きながら、仏教のデジタルトランスフォーメーションの可能性を模索する。
旋律と抑揚のテクノロジー

お香がたちこめたお寺の本堂。薄目をあけて瞑想する仏像の前で、衣をまとった僧侶たちがお経に節をつけて唱えている。その独特の旋律と抑揚が非日常の空間を演出している。
僧侶たちが唱えるお経のメロディや「間」の取り方には、実は詳細に決められた作法があることをご存じだろうか。寺に入門した修行僧たちは、仏教の理論と修行だけでなく、経文に旋律と抑揚をつけて唱える声楽技術を徹底的に学ぶ。「声明(しょうみょう)」と呼ばれるこの仏教声楽は、2,500年の歴史の中で編み出された仏教経典の保存と伝達のためのテクノロジーなのである。
口伝と暗誦のテクノロジー
仏教経典は今でこそ文字で保存されているが、古代インドにおいては、釈迦の教えはもっぱら暗誦と口伝によって保持されていた。現存する最古の経典である『スッタニパータ』[1] にも、その痕跡を見ることができる。
『スッタニパータ』は詩の形式で書かれ、定型句がわずかに変化しながら展開する構成をとっている。韻を踏むように一連の詩が同じフレーズで終わる形式は、暗誦の便をはかったものだといわれている [2]。釈迦やその弟子たちは、仏教の教説を短い詩にまとめ、それを詠むことを楽しんだという。
釈迦が没すると、仏教の教えが失われないよう、残された弟子たちは釈迦が説いた多様な教説を整理するための会議を開いたと伝えられている。「結集(けつじゅう)」と呼ばれる経典の編纂会議は、釈迦の没後すぐに開かれたものから、1954年にミャンマーで開かれたものまで、計6回に渡って行われた記録がある [3]。驚くべきことに、はじめて経典が文字に書写されたのは、釈迦の没後450年も経過した第4回目の結集の時であったという [3, 4]。
数百年の長きに渡って、仏教者たちは文字に頼らず口伝だけで教えを伝達していたことになる。経文に旋律と抑揚をつけて唱える「声明」が生まれた背景には、口伝を重んじる仏教の性格が反映されているのだろう。
声明テクノロジーの殉教者
声明が仏教の布教においていかに強力なテクノロジーであったかを物語る事件がある。平安時代の末期、天台宗の教学をおさめた法然(ほうねん)は、新たに念仏の教えを広め、浄土宗をひらいて日本仏教の変革運動を生み出していた。その弟子であった住蓮(じゅうれん)と安楽(あんらく)は、美声と音楽的才能に恵まれ、経文に美しい旋律と抑揚をつけた「六時礼讃(ろくじらいさん)」[5] を発明したことで知られる。
この六時礼讃に心打たれた人々の中には、当時、後鳥羽上皇の寵愛を受けていた2人の女官の姿があった。彼女たちは、声明を聞くために住蓮と安楽の元に足繁く通い、ついには上皇が留守の隙に出家してしまったという。これが上皇の逆鱗に触れ、さらに旧仏教からの反発も相まって、住蓮と安楽は死罪。法然とその門下であった親鸞らは僧籍を剥奪され流罪とされた。声明はそれほど強力な布教のテクノロジーだったのである。
声明のアップグレード:テクノ法要
そんな仏教の声明テクノロジーが、現代でアップグレードされつつある。
元DJで浄土真宗の僧侶である朝倉行宣氏は「テクノ法要」と呼ばれる新たな法要スタイルを発明している [6]。テクノサウンドに乗せてお経が唱えられ、お寺の本堂と仏像はプロジェクションマッピングで装飾される。経典に説かれる「浄土」の姿が、幻想的な音と光によって寺の本堂に再現される法要だ。
現代的でアーティスティックな音と光のテクノロジーが、仏教の伝統的な声明に新たな命を吹き込んでいる。こうした新たな仏教表現は、かつて流行した六時礼讃のように、新しい仏教運動を生み出す足場となるかもしれない。
メタバースの浄土とアバターの仏

バーチャルリアリティもまた、実は仏教と縁の深いテクノロジーである。仮想空間をメタバースと呼び、仮想空間に配置されたパーソナリティをアバターと呼ぶならば、寺院は仏教世界におけるメタバースであり、仏像はアバターであると言えるだろう。
平安中期に建てられた「平等院鳳凰堂」は、経典の中に出てくる浄土の景色と仏の姿を現世に再現した寺院として知られている。平等院が建てられた当時、僧侶たちの間では、瞑想によって浄土と仏の姿を思い浮かべる「観想念仏」という修行が行われており、その修行のためのメタバースとして平等院鳳凰堂は建てられた。
現代では、バーチャルリアリティでメタバースを出現させ、そこにリアリティのあるアバターを配置することはそう難しいことではない。浄土のVRや、そこに現れるアバター仏やホログラムが寺に実装される日もそう遠くはないかもしれない。やがて寺院に行かなくても法要に参加でき、VRゴーグルをつけた修行僧が家にいながら修行する未来が訪れるかもしれない。さらには、感覚シェアリングのテクノロジーが発達すれば、僧侶が実践する修行を他者と共有することも可能になるかもしれない。
宗教とテクノロジーの出会いが生み出す「隙」
このような仏教のデジタルトランスフォーメーションは、2,500年の仏教の歴史の中でもとりわけ大きな宗教的シンギュラリティになるに違いない。
しかしながら、テクノロジーと宗教が出会うところには、必ず「隙」が生まれる。かつてオウム真理教というカルトは、仏教の教義を表面上利用して、マインドコントロールと洗脳で信者を操り、地下鉄サリン事件などの組織的なテロと殺人を起こした。オウム真理教は、ヨーガ・瞑想・催眠などを利用して信者に幻覚を見せ、その宗教体験を現実と錯誤させるテクノロジーに長けていたという。誰しもが簡単にVR技術を使えるようになり、メタバースを作り出して教祖や仏や神のアバターを配置できるようになれば、オウム真理教のようなカルトが容易に生まれ、急速に広がる危険性がある。
魔境のセキュリティ
社会は、新たなテクノロジーの発達によってカルトの危険性に直面するかもしれない。だとすれば仏教は何ができるだろうか?宗教とテクノロジーが接触するときに生じる隙を悪意ある者に突かせないための砦は、他でもない「教義」である。
仏教(特に禅宗)においては、瞑想などのある種の身体的操作によって幻覚を見たり、特殊な知覚世界に陥ったりすることを「魔境」と呼び、これを「さとり」や「現実」と誤認してはいけないという教義的なセキュリティを持ち続けてきた。臨済宗の禅僧であった大森曹玄氏は次のように語っている [7]:
“禅定中には、仏が現れても、光明を見ても、六尺もさきの線香の灰の落ちる音が聞こえても、絶対の無が現れても、善境悪境ともにひっくるめてこれを魔境と心得、そういう境に直面したときは一層心身を引きしめ、勇気をふるい起こして一才とり合わないばかりでなく、断固としてそれらをことごとく木ッ端微塵に粉砕してしまうがいいのである。”
修行者が道をはずれて反社会的なカルトに魅入られないようにするには、伝統仏教が保ち続けてきた「魔境」に対する知識が必要である。宗教が時代に刺さる表現とテクノロジーだけを追い求めれば、逆に宗教は時代に刺されてしまうかもしれない。テクノロジーが廃れれば教えは失われ、教義が失われればカルトが隙をついてくる。テクノロジーと教義は、社会と宗教の共存に欠かすことのできない両輪なのである。
参考文献
[1] 中村 元(訳),『ブッダのことば スッタニパータ』,岩波書店.
[2] 中村 元(訳),『ブッダのことば スッタニパータ』,訳者解説、岩波書店.
[3] 森 祖道、『初期仏典(三蔵)の編纂(結集)と伝承(口伝と書写)- インドからスリランカ・ミャンマーへ』,国際哲学研究7号,p.57-62、シンポジウム「聖典はどのように伝えられたのか – 宗教の言葉と思想を考える」報告 (2018).
[4] 真言宗泉涌寺派大本山 法楽寺 「結集 – 仏滅後の僧伽 -」http://www.horakuji.com/lecture/samgha/sangiti.htm
[5] 浄土宗大辞典「六時礼讃」「住蓮」「安楽」
http://jodoshuzensho.jp/daijiten/index.php/メインページ
[6] 浄土真宗本願寺派 一乗山 照恩寺
https://www.show-on-g.com/techno-hoyo
[7] 大森曹玄,『参禅入門』,春秋社,新版第一刷 (2009)
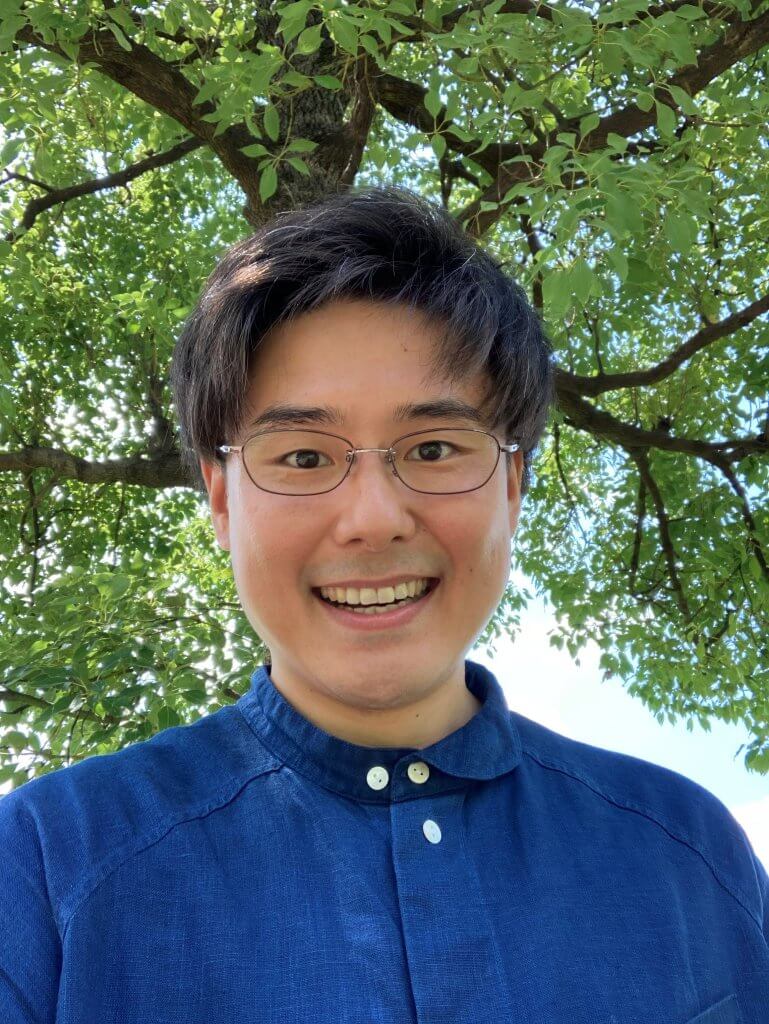
四万十川ミドリムシ
ライター
青森県生まれ、千葉県育ち。博士(理学)。大学院で非線形物理学を専攻し、現在は、複雑系物理の観点から生き物の行動と脳のしくみを研究している。浄土宗の僧侶。好きなSF映画は『ブレードランナー』と『平成狸合戦ぽんぽこ』。





