SCIENCE
【世界の酷暑2025】暑くなり続ける地球で、私たちがやるべきこととは?

目次
私たちがいま「異常気象」と呼んでいる現象が、じわじわと「普通」になっていくとしたら──。
連日40度を超える日が続き、日中は屋外を歩くのが危険なため、自宅での待機を促す“猛暑警報”が発令される。夏の風物詩だった蝉の声はもちろん、夏ならではの日常のちょっとした光景や小さな楽しみが、いつの間にか失われていく日々は、「遠い未来」ではなく、もうそこまで迫っているかもしれない。
今回は、世界各地で進行している異常気象の現実に目を向けながら、気候変動の現在地を探る。さらに、ワーストシナリオを現実にさせないために、私たちが「ニューノーマル」にどう賢く適応し、健やかな暮らしを守れるのかを考えていこう。
世界各地に押し寄せる気候変動の波

2025年も、例に漏れず世界各地で深刻な自然災害が発生している。異なる地域・異なる形で現れたさまざまな現象には、いずれも気候変動の影が色濃く映る。
干ばつが国家の基盤を揺るがすレバノン
レバノンでは、史上最悪ともいわれる干ばつが発生。ロイター通信の報道によると(※1)、レバノン最大の貯水池であるカラウン湖への流入量は、例年の約13%だったという。
過去の干ばつと比較しても類をみないレベルだといい、農業・電力供給・生態系への影響によって、社会・経済的な影響を引き起こし、国の社会基盤全体に広範なダメージをもたらす懸念が高まっている。
命を奪う熱波がヨーロッパを襲う
イギリスやフランスなど北ヨーロッパ・西ヨーロッパの多くの地域は、日本の夏と比べると比較的涼しい地域とされている。しかし近年、熱波の影響で熱中症をはじめとした関連死が増加している。
Imperial College Londonの研究によると、2025年6月23日から7月2日までの10日間で、ヨーロッパ12都市における熱中症死亡者数は約2,300人と推定された(※2)。そのうち約1,500人は気候変動による気温上昇(1~4℃)が原因とされ、これにより熱中症死亡者数は気候変動がなかった場合の約3倍に増加したと報告されている。
つまり、もともと発生していた熱波による死者が約800人であるのに対し、気候変動による追加の温暖化で約1,500人がさらに亡くなった計算だ。化石燃料の燃焼による気温上昇が、熱波による死者数を大幅に押し上げており、気温の上昇が続くことで、死者数もさらに増えると警告している。
映画の都ロサンゼルスを焼き尽くした森林火災
ハリウッドのあるアメリカ西部・ロサンゼルスは、華やかな映画の都という印象が強い。しかし、2025年1月、高級住宅街を含む広い範囲で大規模な森林火災が発生し、炎が人々に恐怖をもたらした。
気候変動による極度の乾燥や、冬季としては異例の高温が燃えやすい環境をつくり、被害の拡大につながったとされる。
灼熱の夏、日本が記録を塗り替えた7月
日本も例外ではなく、酷暑に加え、豪雨などの異常気象が増え、それに伴う熱中症や災害被害も拡大している。また、農作物の被害や水不足が続くことで、物価の高騰も社会に影響を与えている。
気象庁によると(※3)、2025年7月の日本の平均気温は、例年より+2.89℃で、これまでの記録であった2024年7月の+2.16℃を0.73℃上回り、統計を開始してから最も暑い7月だった。10月まで残暑が続くとみられている。
地球温暖化の次に待ち受けるのは、未知の災害
世界中で起きている気候変動の影響は、単なる気温上昇にとどまらない。干ばつ、熱波、森林火災、豪雨や洪水など、複数の災害が連鎖的・同時多発的に発生し、被害を拡大させている。
異常な高温は水資源を奪い、森林を炎上させ、都市を機能不全に追い込む。2025年に起きたレバノンの大干ばつ、ヨーロッパを襲った熱波、ロサンゼルスの森林火災などは、その現実を突きつけた。
地球温暖化の影響は、海面上昇、生物多様性の喪失など多方面にも広がっている。さらに近年では、森林や土壌といった自然の炭素吸収源が干ばつや火災などの影響で不安定化し、期待されたほど二酸化炭素を吸収できない研究(※4)も報告されている。
こうした変化に翻弄されるのは自然界だけではなく、人間社会そのものを脅かす規模に達している。例えば熱波は、特に高齢者や基礎疾患を抱える人々が被害を受けやすいことが、Imperial College Londonの研究(※2)でも明らかになっている。実際、2025年のヨーロッパでの熱波による死亡者のうち、約88%が65歳以上だった。
被害は生命だけでなく、社会システムの危機にまで及ぶ。熱波や干ばつによる農作物の減少は、食料価格の高騰を招き、自然災害による住宅やインフラの損壊は復旧費用の増大をもたらす。さらに停電や交通遮断は企業活動に打撃を与え、経済全体の停滞を引き起こす。こうした負の連鎖は特に経済的に困窮している層に大きな打撃を与え、被害の格差を広げている要因にもなっている。
「臨界点」と「point of no return」を迎えないために

決してポジティブな状況ではないが、まだ希望がないわけではない。ここで重要になる一つの指標が「臨界点」だ。
臨界点(tipping point、ティッピング・ポイント)とは、変化が積み重なってある値に達した時に、システム全体に影響を及ぼすポイントを意味する。気候変動に関する政府間パネル(IPCC)が導入した概念で、気候変動の文脈では、気温上昇や生態系の変化が一定の値を超えると、元に戻せない大規模な変化が起きる現象を指す。
例えば、グリーンランドの氷床の融解やアマゾン熱帯雨林の砂漠化、海流の変化など、一度進行すると自然には回復しない変化が挙げられる。
また、気温の上昇には「point of no return(引き返せない点)」と呼ばれる概念もある。地球温暖化を2℃以内に抑えたい場合、1.5℃を超えてしまうと地球の熱慣性によって2℃超えが避けられなくなる(※5)。そのため、パリ協定では「世界的な平均気温上昇を産業革命以前に比べて2℃より十分低く保つとともに、1.5℃に抑える努力を追求する」とされた。
しかし、2024年には産業革命前比で世界平均気温が単年で1.6℃上昇し、単年としてはパリ協定の1.5℃目標を初めて超えた。すぐに地球の暴走が始まるわけではないが、環境は互いに影響し合っているため、このまま放置すれば“最初のドミノ”が倒れてしまう可能性がある。だからこそ、気温上昇を1.5℃に抑える取り組みが欠かせないのだ。
気候変動に備える、暮らしと社会の新しい選択

そのために私たちが最優先で取り組まなければならないのは、一人ひとりが日常生活の中で二酸化炭素の排出を減らし、社会全体の構造を変えていくこと。とりわけ最大の二酸化炭素排出源であるエネルギーのあり方を変えない限り、1.5℃目標の達成は望めない。日本の電力は約7割が火力発電で環境負荷が大きいため、再生可能エネルギーへの転換こそが未来を左右する。
最近では、料金を抑えつつ再生可能エネルギーに切り替えられる市民向けの電力会社も増えている。さらに、電力の選択にとどまらず、再生可能エネルギーを使った商品やサービスを選ぶことも、私たち消費者にできる身近な一歩だ。
しかし、地球温暖化の影響はすでに日常生活に及んでいる。真夏の活動時間をずらしたり、災害リスクが高まる時期には暮らし方を柔軟に変えるなど、社会システム自体もこの変化に適応することが求められる。再生可能エネルギーの導入だけでなく、こうした適応策を組み合わせることで、私たちは命を守り、健やかな暮らしを維持できるはずだ。
地球温暖化は、自然に改善されることはないし、神頼みで解決できるものでもない。いま必要なのは、恐れから目をそむけるのではなく、現実と向き合い、柔軟で賢い適応と変化を受け入れる勇気なのかもしれない。
「いつもの夏」を守るために、あなたはどんな行動を選ぶだろうか。
参考文献
※1 Lebanon’s worst drought on record drains largest reservoir|Reuters
https://www.reuters.com/sustainability/boards-policy-regulation/lebanons-worst-drought-record-drains-largest-reservoir-2025-07-15/※2 Climate change tripled heat-related deaths in early summer European heatwave|Imperial College London
https://www.imperial.ac.uk/grantham/publications/all-publications/climate-change-tripled-heat-related-deaths-in-early-summer-european-heatwave.php※3 日本の7月の平均気温|気象庁
https://www.jma.go.jp/jma/press/2508/01a/betten.pdf※4 World’s Forest Carbon Sink Shrank to its Lowest Point in at Least 2 Decades, Due to Fires and Persistent Deforestation|World Resources Institute
https://www.wri.org/insights/forest-carbon-sink-shrinking-fires-deforestation※5 温暖化は暴走する?|地球環境研究センター
https://www.cger.nies.go.jp/ja/library/qa/20/20-2/qa_20-2-j.html
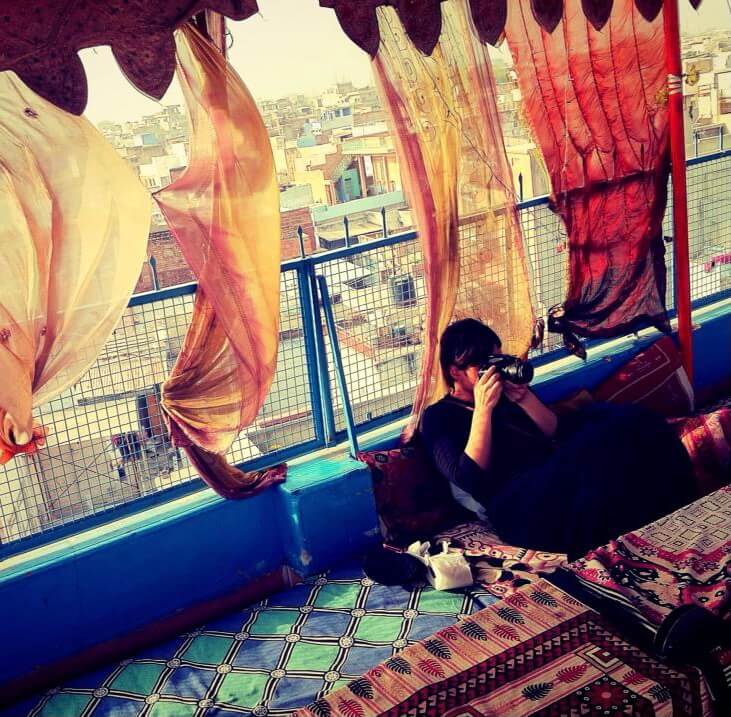
Ayaka Toba
編集者・ライター
新聞記者、雑誌編集者を経て、フリーの編集者・ライターとして活動。北欧の持続可能性を学ぶため、デンマークのフォルケホイスコーレに留学し、タイでPermaculture Design Certificateを取得。サステナブルな生き方や気候変動に関するトピックスに強い関心がある。





