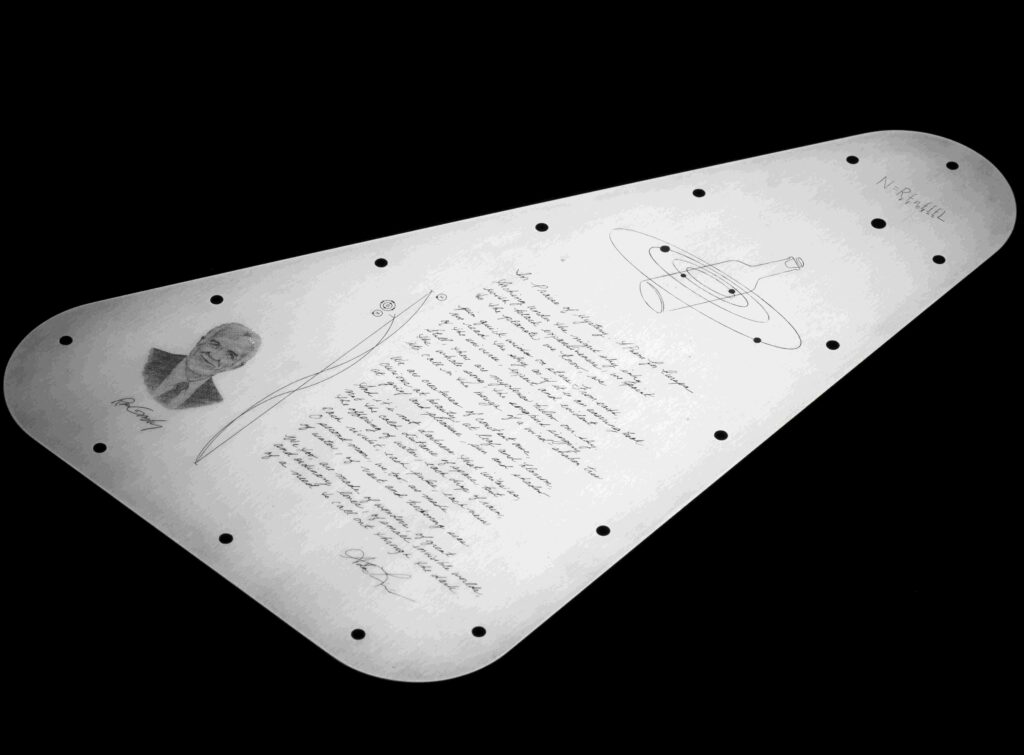SCIENCE
量子力学はなぜ生まれたのか?―後編―

目次
量子力学とは何か?という、多くの人が持つ疑問に対して応えることは決して容易ではない。しかし「なぜ量子力学が必要か」に注目をすれば、表面的なテクスチャーを超えて量子力学の存在感を感じてもらうことができるのではと考え、前半では光に注目をした解説を試みた。
そこで紹介したように、光と物質の関係を詳細に紐解くには量子という魔法のような根拠のない概念を理論に組み込まざるを得なかった訳だが、実は光についてだけではなく世界を構成する物質を詳しく理解する上でも、量子性は欠かすことのできないアイデアであった。後半では「物質」に注目することで「なぜ」量子力学が生まれたのかを紹介したい。
原子のナカミ
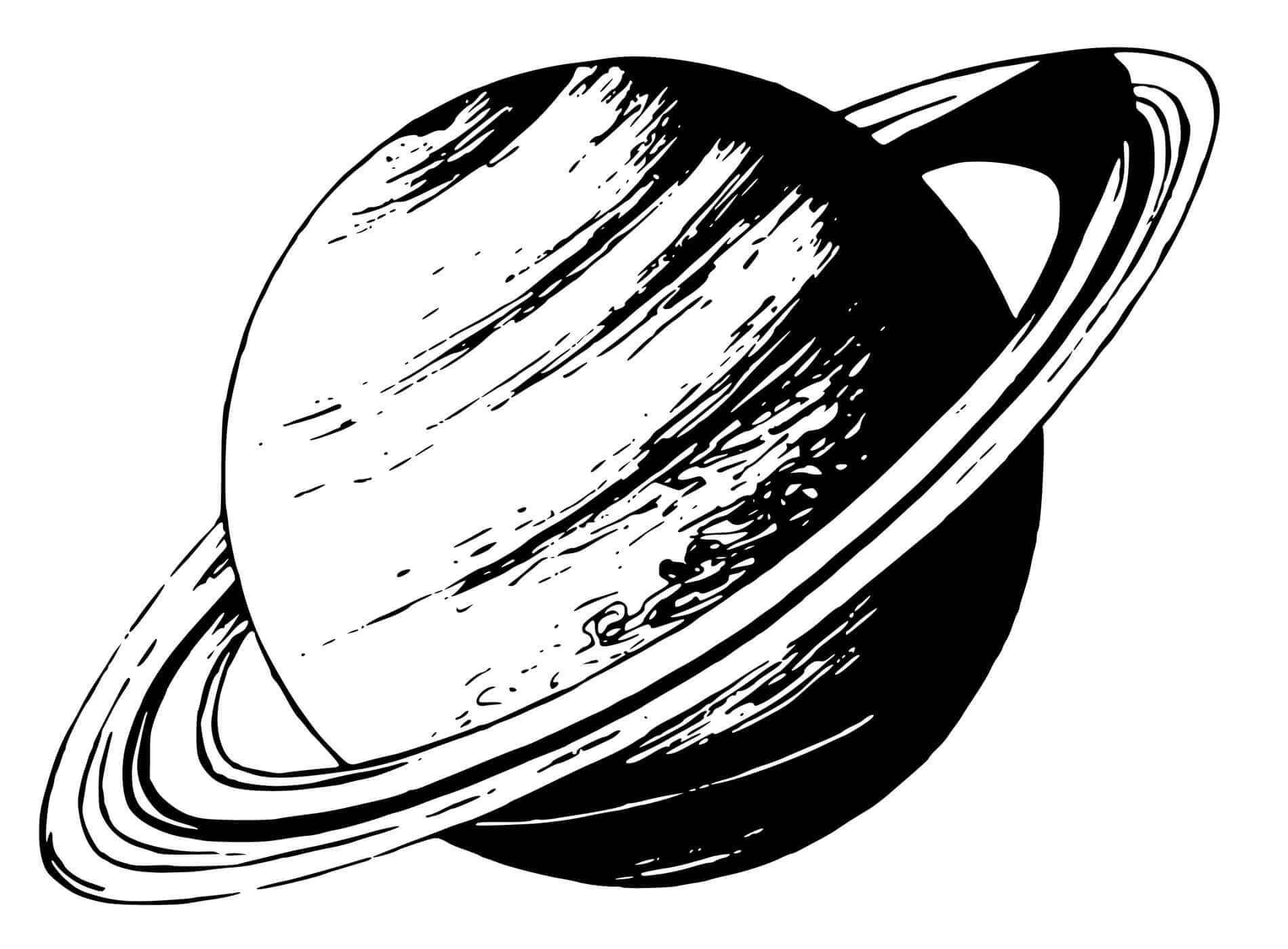
19世紀当時、物質は連続的に無限に細かく分割することができる、というアイデアと原子・分子という物質の最小単位の存在を仮定するアイデアが対立していた。純粋なガラスはどれだけ砕いでも「ガラス」であると考える方が自然であり、有限サイズの最小単位が必要な必然性がなかったのだ。
物質は元素という基本要素から成り立っていることはすでに知られていたが、遺伝子の実態がDNAという特別な分子であったように、元素の実態が連続的な何かではなく原子という特定のサイズを持った粒子であると証明されるには、ジャン・ペランの実験とアルバート・アインシュタインの理論によるブラウン運動に関する1905年の論文を待たなければならなかった。
原子の実在は曖昧であったものの、1897年のジョゼフ・ジョン・トムソンによる電子の存在の予言やアンリ・ベクレルによってウランが出す放射線に電子が含まれていることが示されたことにより、物質は負の電荷と正の電荷が組み合わさることで中性を保っている、という物質の内部構造の存在は示唆されていた。
そうなると当然生まれる疑問が「原子のナカミはどうなっているのか?」である。見えない以上、わかっている情報からそれらしいモデルを立てるほかない。トムソンは正電荷のプリンのようなものの中に負の電荷を持つプラムのような何かが散りばめられたような、プラムプディングモデルを提唱し、また長岡半太郎は土星とその輪のように、正電荷を持つ中心体とその周りを負の電荷体がリング状に回っている土星型モデルを提唱した。目には見えない原子のナカミを必死に想像し、研究者たちはそのモデルの正しさを理論・実験双方から検証した。
その後、アーネスト・ラザフォードにより、正電荷をもつ原子核が中心にありその周辺に広がって電子が分布していることが実験的に検証されたために原子のナカミはプラムプラムプディング的ではなく土星型モデルが近そうだとわかってきた。
しかし、それでも問題は山積みであった。土星型モデルは理論的には瞬く間に壊れてしまうのだ。太陽系はその誕生以来、数十億年という規模で壊れることなく存在できているが、それは天体が電気を帯びていないためである。電気を帯びた粒子は、電磁気学によると回転運動に伴いエネルギーをどんどん失い、瞬きほども耐えることなくブラックホールに吸い込まれるかのように原子核とぶつかって壊れてしまうと結論づけられた。「実験的に認められたナカミをもつ原子はなぜ安定に存在できるのか?」はマクスウェルの理論に基づいただけでは全く説明がつかなかったのである。
分子のカタチ

中心に原子核を持っているはずの原子がなぜ安定に存在できるのかも説明できなかったが、その原子同士がくっついてできているとされる分子についてもわからないことだらけであった。原子同様、分子という極微の世界の存在を認識することが難しいことを示す興味深い論文が1926年にディビッド・M・デニソンによって発表されている。それは水の赤外線吸収分光実験から水分子の形状を求める試みである。当時の論文には以下のように書かれている。
この研究では、分子形状を保つ力の起源に関する問題に立ち入ることは試みられていないが、平衡位置の近傍における原子核の挙動は、それらの間に働く中心的な力によって記述することができるという仮定はなされている。
なぜ分子が形状を保てるのかはわからないながらも、想像力と過去の知見を組み合わせることで、分子のカタチの理解を試みたのだった。
分子のカタチは原子同士のつながり方を決めればよく、デニソンは原子同士を”何かしらのバネ”が繋ぎ止めている、と仮定した。バネを仮定することで分子が光を吸収する仕組みを説明できたからだ。これは、地震災害などの事例で、建築物は、固有周波数と呼ばれる特定の振動のエネルギーをよく吸収してしまいエネルギーに耐えきれず壊れてしまうことの説明と同様である。
しかし単純なバネモデルも実験結果と合わせるには、どこに・どんなバネを入れるべきか?という問題を解かなくてならない。それは何桁かもわからない鍵の番号を当てるような難しさである。実際、デニソンの論文での仮定は現在では実験結果を説明できないことがわかっている。当時の専門家であっても、極微の世界を実験事実と照らしながら認識することは困難であったことが窺える。なお現代では、実験による観測結果を説明できるような分子のカタチをコンピュータによって容易に計算することができる。量子力学があれば、先人たちが行ったモデリングという想像力を必要としなくても、分子のカタチを導き出してくれるのだ。
物質波という奇想天外なアイデア
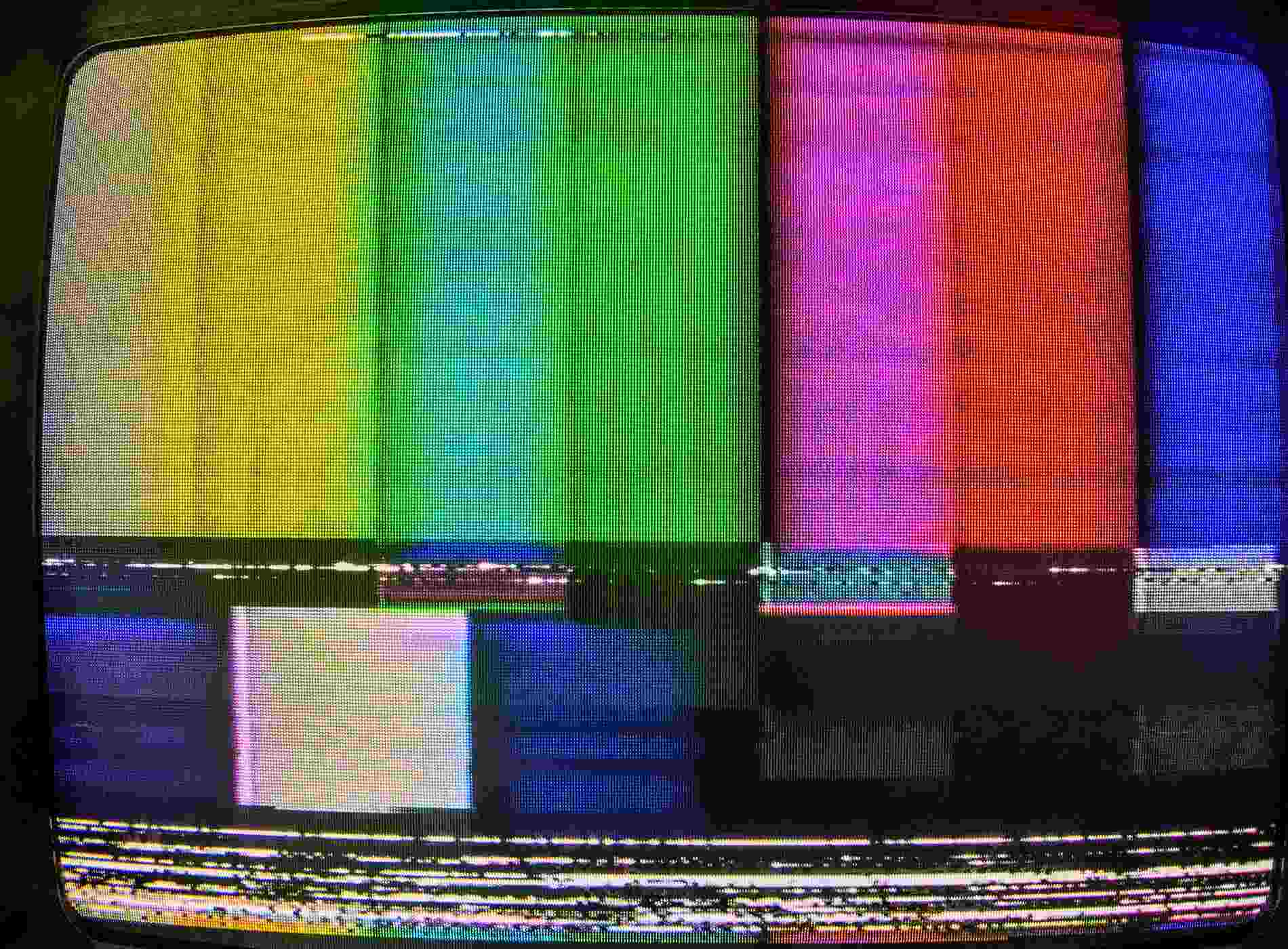
「なぜ物質が安定に存在できるのか?」という問いに対する理解は、物質波という突拍子もない概念の登場で状況が劇的に変化した。ルイ・ヴィクトル・ド・ブロイはアインシュタインの光量子仮説に現れる関係式に着想を経て「光と同様に全ての物質はこの関係式に支配される」という大胆な仮説を立てた。光が特定のカタチを持たないように、物質も特定のカタチを持たなくて良い、と言わんばかりのこの仮説は当然、私たちの直観に反するように、多くの研究者には理解できない戯言だったに違いない。しかし、光がもつ量子性を物質も持つとして生まれた物質波というアイデアは、当時最もうまくいっていたニールス・ボーアの原子模型の曖昧な部分を綺麗に説明することができた。
この研究を知ったエルヴィン・シュレーディンガーは直ちにアインシュタインの関係式を電子の性質の説明へと展開すると、電子を光と同じようなカタチのない「波」として捉えることができ、その満たすべき方程式を導き出した。
これは現在ではシュレーディンガー方程式という量子力学の基本方程式として知られている。シュレーディンガー方程式に基づくことで、原子のナカミも分子のカタチも今では説明することができる。しかし、当然のことながら、量子というアイデアを持ち込まれたが故に生まれた物質の波動性は、私たちの直観に合うものでは全くなく、到底認識できるものではなかった。光の時と同様に、魔法か何かのようなこのアイデアが何であるかは、さらに数十年にわたる研究成果を待たなくてはならなかった。
あらゆる物質が内包する電子を操る

これまで述べたように物質と光という私たちの世界を満たしている存在の関係性を「なぜ?」という疑問を追い求めた数十年に及ぶ数多くの研究者たちの成果により「光の量子性と物質の波動性というアイデアに基づくと物質と光にまつわる謎を説明できる」という量子力学の基礎となる概念・理論の骨格が形作られた。
重要なのは「量子とは何か?」という疑問に先立って、極微の実験事実を説明するには「量子という概念が必要だった」ことである。本記事で述べたとおり、量子力学の基礎概念は、実験を説明できはしても当時の常識に反する多くのアイデアが発端となっていることが多く、広く受け入れられるには相当の検証・実験的裏付け・そして次のアイデアが必要であった。
人間の感覚に寄り添いすでに研究者の間で常識となっていた古典力学に比べて、量子力学はかつての第一線の研究者にとっても現代人同様に難解極まりない代物だったのだ。「量子力学とは何か」を知るには、当時の研究者同様、客観的な観測事実を受け入れ、その過程で生まれた数多くの「なぜ?」に挑み続け、現実とその理論のギャップを埋めていく努力が、現在の我々にも必要なのかもしれない。
さて、すべての物質は電子を内包しているのだから、物質中の電子の振る舞いを手がかりにすれば金属がなぜ電気を流すのか? ガラスはなぜ透明なのか?という新たな「なぜ?」に一層深く切り込むことができるステージにも学問は到達し、現在のエレクトロニクスを支える半導体テクノロジー・トランジスタの発明へとつながる。しかし実際に様々な物質に対して、内部の電子の振る舞いを理論的に計算できるようになるにはコンピュータによる登場と密度汎関数理論と呼ばれる強力かつ厳密な多体電子状態の計算方法の登場を待たなければならない。自然界の理解から、物質中の電子を自在に操る情報テクノロジーの発展に向かうのだが、それはまた別の機会に。
参考文献
・David M. Dennison Ph.D. (1926) XII. On the analysis of certain molecular spectra , The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science, 1:1, 195-218 https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14786442608633620
・素粒子物理学をつくった人びと(上)(下), ロバート・P・クリース, チャールズ・C・マン, (訳: 鎮目 恭夫, 林 一, 小原 洋二, 岡村 浩)ハヤカワ・ノンフィクション文庫, 早川書房
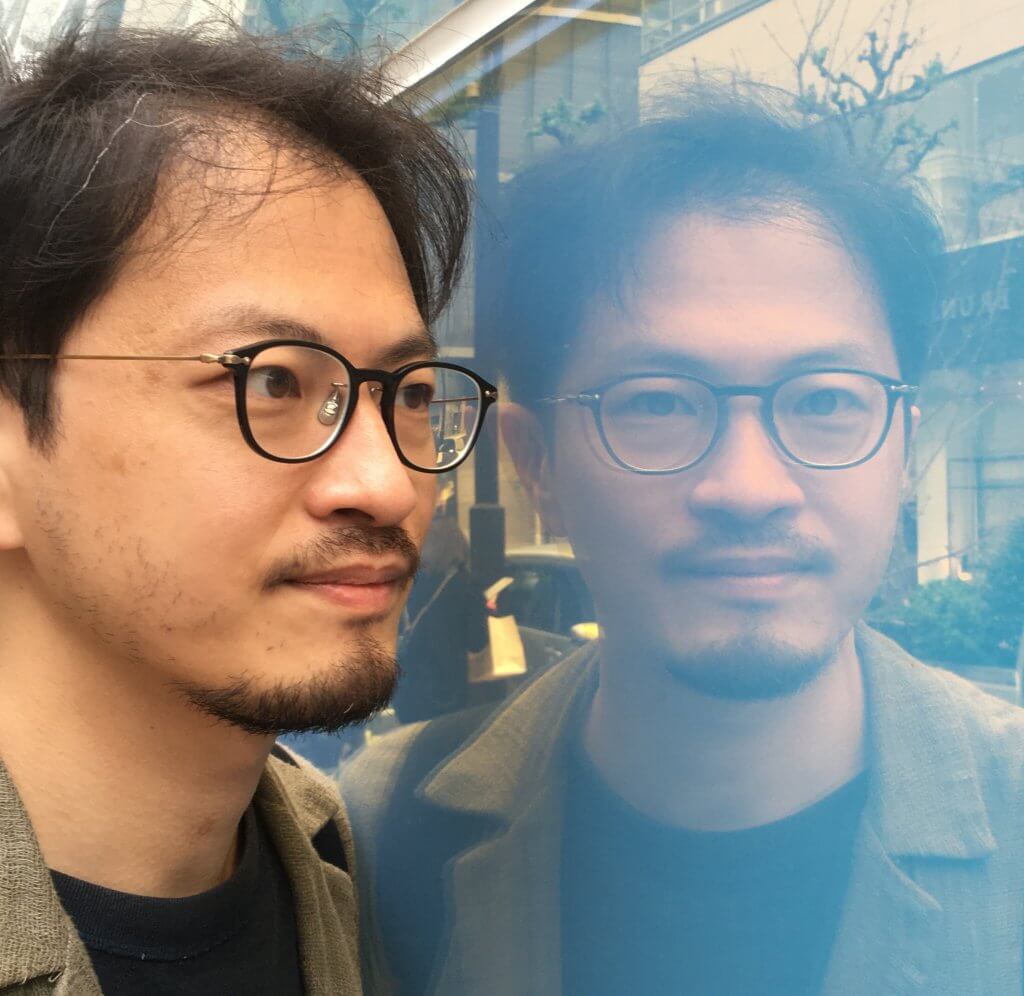
安藤 康伸
ライター
博士(理学)。国立研究開発法人にて機械学習や計算シミュレーションを材料開発に活用する研究に従事。企業向け技術セミナーや学生向け出張授業に加え,趣味でサルサダンス・ミュージカル・インプロなどのステージにも立つ。好きなお酒は無冠帝・ポルフィディオ・アネホ若しくはブッカーズ。