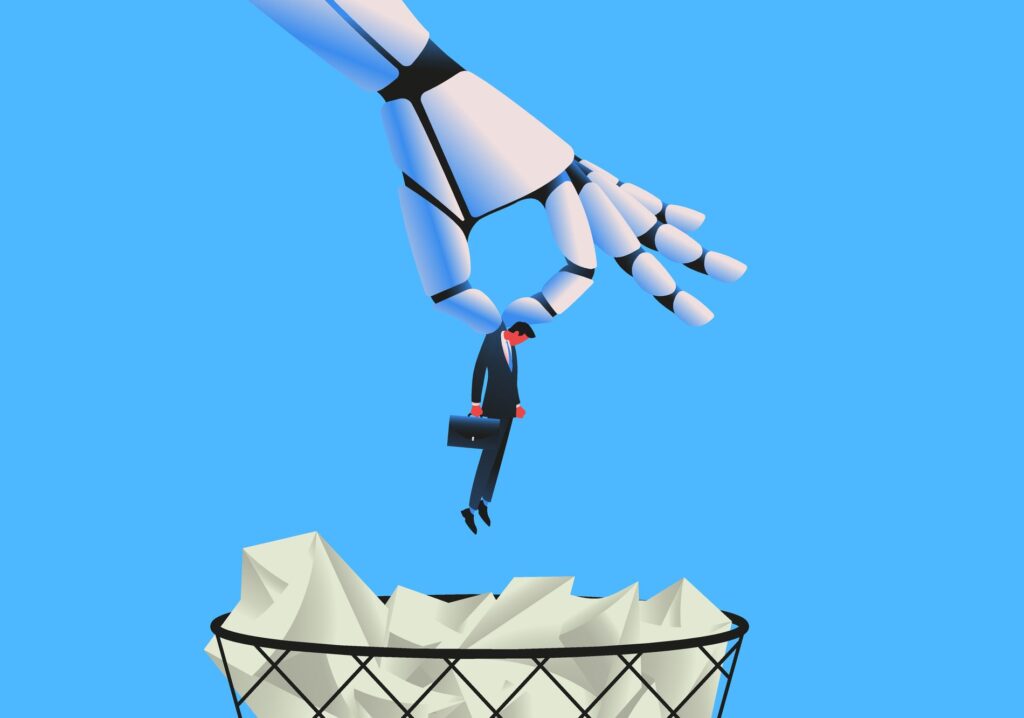BUSINESS
公的介護保険制度がないアメリカ。シニアケアはどうなっているのか?

目次
国民皆医療保険制度がないアメリカ。当然ながら日本のような国民の強制加入を前提とした公的介護保険制度も存在しない。
しかし、アメリカも他の先進諸国と同様に高齢化が進み、2030年には国民の21%が65歳以上の高齢者になると予測されている。
公的介護保険制度がなく、今後も導入される可能性がほぼゼロのアメリカでは、高齢者の介護事情はどうなっているのだろうか。AIの現場での活用などを含めたアメリカのシニアケアの現状をお伝えする。
アメリカでも増加を続ける高齢者人口

アメリカでも高齢者人口が増加している。アメリカ合衆国国勢調査局(US Census Bureau)によると、2020年時点で5610万人だったアメリカの65歳以上の高齢者人口は今後も増加を続け、2030年に7310万人、人口比率で21%になると予想されている。 日本の高齢者人口比率は2025年度で既に29.4%に達しており、日本よりも高齢化のスピードは遅めに見えるものの、それでも高齢者人口は確実に増加している。
2030年は、特にブーマー(Boomer)と呼ばれるアメリカのベビーブーム生まれ世代が全員65歳以上の高齢者になる年でもあり、アメリカ人口史における歴史的な年になるとされている。同時に、増加するアメリカの高齢者のケアをどうするかという問題が、如実に現実のものとなってきている。
公的介護保険制度がないアメリカ
ところで、国民皆医療保険制度がないアメリカでは、日本のような公的介護保険制度も存在しない。65歳以上の高齢者を対象とした公的医療保険制度メディケア(Medicare)が高齢者の医療を担ってはいるが、日本のようにジェネラルに介護サービスを提供するものではない。
メディケアはあくまでも医療保険制度であり、高齢者の病気や怪我などには対応するものの、各種の介助などの介護サービスの提供は原則していない。日本で高齢者に提供されている類の在宅介護サービスは、通常は民間の介護保険で提供されている。
一般的には、民間の長期介護保険(Long-Term Care Insurance, LTC保険)が、日本の介護保険に近いものとされている。大手メディアCNBCによると 、アメリカの一般的なLTC保険は、加入者に入浴介助、着替え、食事介助、排泄介助、トイレへの付き添い、ベッドから椅子への移動などのサービスを訪問または在宅ベースで提供している。
しかし、LTC保険の多くは単体で提供されておらず、生命保険のオプションなどとして提供されている。そのためもあってか、サービス利用条件のハードルが不必要に高く、保険料も相応に高く設定されている。介護コストが総じて高いアメリカでは、LTC保険単体でサービス提供サイクルを実現させるほど市場の需給バランスが成立していないのだろう。
多くのアメリカ人は自宅で身内が介護

医療コストと同様に介護コストも高いアメリカでは、シニアケアを誰がどのように行っているのだろうか。アメリカでは、高齢者を在宅で身内が介護するのが一般的となっているようだ。ガーディアンの報道によると、アメリカで介護を必要としている65歳以上の高齢者の65%は、在宅で身内が介護しているという。介護をする人(Caregiver)の多くは45歳から64歳の女性で、高齢の両親や配偶者などの食事、入浴、排泄などの世話をしている。そのほとんどが無給ケアギバー(Unpaid caregiver)とされている。
アメリカ保険福祉省の推計によると、アメリカには現在6300万人もの無給ケアギバーが存在し、身内に各種の介護サービスを提供しているという。また、無給ケアギバーが提供しているサービスのコストは、年間1兆ドル(約150兆円)相当に及ぶとされている。
身内による介護のほかに、日本と同様に訪問介護、介護付き住宅、老人ホームなどの介護サービスや施設も利用されてはいる。しかし、いずれも高額で多くの高齢者にとっては高嶺の花だ。
老人ホーム(Nursing home)は特に利用料金が高く、介護サービス情報サイトケアスカウトによると、2024年時点のアメリカの老人ホームの平均月額利用料は、複数人部屋が9,277ドル(約139万円)、個室が10,646ドル(約159万6900円)となっている。いずれも一日あたり300ドル(約4万5000円)以上の費用が必要であり、「一般的なアメリカの高齢者」にとっては負担が困難な水準だ。
実際のところ、老人ホームで暮らす高齢者の割合は高齢者全体の5%程度に過ぎず、極めて少数派となっている。また、老人ホーム利用者の半数は85歳以上の超高齢者で、一人暮らしが困難な人がほとんどとされる。アメリカの老人ホームは、機能的には日本の特別養護老人ホームに近く、比較的経済的に余裕がある超高齢者が終末期を過ごすための施設として使われているようである。
アメリカの「老後の生活」にはいくら必要?
そんなアメリカにおいては、高齢者の「老後の生活」には実際にいくら必要なのだろうか。日本では、老後を安心して暮らすために最低2000万円が必要という「老後必要資金2000万円説」がまことしやかに流布され、一般に広く浸透した感があるが、日本より所得格差が大きいと思われるアメリカではどうなのだろうか。
アメリカの大手資産運用会社フィデリティ・インベストメンツは、仕事から完全に引退する年齢に応じて老後資金を確保するようアドバイスしている。一般的には、60歳で引退する場合は年収の8倍、67歳以上で引退する場合は年収の10倍を用意することを勧めている。例えば、年収10万ドル(約1500万円)の人が60歳で引退する場合は80万ドル(約1億2000万円)、67歳で引退する場合は100万ドル(約1億5000万円)という感じだ。引退する年齢が高くなるほど「投資収益が見込めなくなる」「稼ぐ機会と能力が低下する」ため、必要な老後資金が増加するというロジックだ。
アメリカの大手金融機関メリルリンチも、老後の生活に必要な資金をオンラインで計算できるウェブアプリを提供している。例えば、60歳で年収8万ドル(約1200万円)の人が67歳で引退し、引退後に「比較的アグレッシブな投資」を継続すると仮定した場合、必要な老後資金は177万ドル(約2億6550万円)という結果が出た。
なお、アメリカでは、全国民の60%が緊急支出用の1000ドル(約15万円)の貯金が無いとされている。普段の生活を送る上で1000ドルの貯金ができない人達が、100万ドル単位の高額な老後生活資金を貯蓄できると考えるのは、非現実的だと言わざるを得ないだろう。
AIの利用が徐々に進むアメリカのシニアケア
一方、そんなアメリカのシニアケアの現場でもAIの利用が徐々に進んでいる。
アメリカAI研究所(The United States Artificial Intelligence Institute)によると、アメリカのシニアケアの現場では、特に「高齢者の孤独」が広く問題になっており、AIを使ったソリューションが開発・提供され始めている。カリフォルニア大学サンフランシスコ校が実施した調査によると、独居などで孤独の状態に置かれた高齢者は、そうでない高齢者よりも早期に死亡するリスクが45%も高まるとされている。高齢者を孤独にしないために対話型AIが活用され、高齢者それぞれにパーソナライズされたコミュニケーションがAI搭載ロボットによって実現されている。
また、高齢者の見守りなどのモニタリングにもAIが活用され始めている。ケアプレディクト(CarePredict)が開発したモニタリングシステムは、高齢者の生活パターンを映像でトラックし、転倒や体調急変などの異常事態を検知してレスキュースタッフへ通知するシステムだ。アメリカのシニアケアの現場でも人手不足が慢性化しており、特に在宅で身内が介護するケースなどでは高齢者の見守りが手薄になりがちだ。AIモニタリングシステムを導入することでモニタリングの質を高め、非常時の対応を迅速に行うことを可能にしている。
アメリカの介護は、既に「超高齢化社会」へ突入した日本と比べると、まだ本格的な夜明け前のような感を呈してはいる。しかし、そんなアメリカもそぞろに高齢化社会に突入しつつある。
アメリカでは、医療の現場でAIがプレゼンスを大きく広げてきているが、介護の現場でも同様にプレゼンスを拡げてゆくことになるのは間違いないだろう。巨額の介護コスト負担の問題などのいくつもの課題を負ったアメリカのシニアケアの現場で、AIがどう活躍してゆくのか注目してゆきたい。
参考文献
https://www.census.gov/content/dam/Census/library/publications/2020/demo/p25-1144.pdf
https://www.cnbc.com/select/best-long-term-care-insurance/
https://www.theguardian.com/society/ng-interactive/2025/may/01/nursing-home-assisted-living-costs-care
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/books/NBK604136/
https://www.carescout.com/cost-of-care
https://www.fidelity.com/viewpoints/retirement/how-much-do-i-need-to-retire
https://www.merrilledge.com/retirement/personal-retirement-calculator
https://www.cbsnews.com/news/saving-money-emergency-expenses-2025/

前田 健二
経営コンサルタント・ライター
事業再生・アメリカ市場進出のコンサルティングを提供する一方、経済・ビジネス関連のライターとして活動している。特にアメリカのビジネス事情に詳しい。