SCIENCE
森に匹敵する海の力で、気候危機に立ち向かう。「ブルーカーボン」の可能性とは?

目次
気候変動の加速が現実味を増すいま、温室効果ガスを効率的に吸収し、地球の沸騰化を食い止める鍵として注目を集めるのが「ブルーカーボン」だ。
ブルーカーボンとは、「海の植物たちが吸収し、海に貯めこまれる炭素」のこと。陸上の森と同じように、海中の植物たちも地球のバランスを支える生命線のひとつだ。
地球全体が高温になることで、地上の植物が二酸化炭素を十分に吸収しなくなる可能性が示唆されるなか、海の力を活かすブルーカーボンの取り組みは今後よりその重要度を増す。
今回は、最新のAI技術も取り入れながら進化する「ブルーカーボンの最前線」に迫る。”海の森”に息づく力が私たちの未来に何を示すのか探ってみよう。
海が二酸化炭素を閉じ込める「ブルーカーボン」とは
気候変動の文脈において、森だけでなく海も温室効果ガスの吸収源としてなくてはならない存在だ。
ブルーカーボンは、海岸や沿岸の生態系によって吸収・貯留される炭素のことを指す。たとえば、海草藻場、マングローブ林、塩性湿地などは「海の森」「ブルーカーボン生態系」とも呼ばれ、光合成によって二酸化炭素を吸収し、海底の土壌に長い時間をかけて炭素を固定する。つまり、陸の森が地上で二酸化炭素を吸収するなら、海の森はそれを“地中に閉じ込める”というわけだ。
沿岸のブルーカーボンは、長期的に安定した炭素貯蔵庫として、気候変動の緩和に欠かせない。熱帯の森は、1ヘクタールあたり年間およそ2〜3トンの炭素を吸収しているという(※1)。
それに対し、マングローブや塩性湿地などの沿岸生態系は、成熟した熱帯林の約2〜4倍の炭素吸収力を持つとされる。特に、海草藻場に代表される沿岸生態系では、海底堆積物中の有機炭素は酸素が届かない環境下で分解が極めて遅く、数百年から千年単位にわたって炭素固定されることを証明した研究結果もある(※2)。
ということは、沿岸の小さな生態系を守りもしくは回復させるだけで、気候変動緩和に大きく貢献できるポテンシャルがあるというわけだ。
ブルーカーボンの未来と可能性をAIで可視化

ブルーカーボンには大きな可能性がある一方で、解決すべき課題も指摘されている。ブルーカーボンは、2009年に国連環境計画(UNEP)が初めて定義したが、グリーンカーボンと比較すると、研究やデータはまだ発展途上だ。
その理由のひとつに、観測や評価の不確実性が挙げられる。海中では、炭素量の地域差は大きく、正確な評価が難しい。またブルーカーボンと一言に言っても、それぞれの生態系では特徴や固定できる炭素の量が異なるため、正しい情報を集めるためには、綿密な観測と時間をかけた検証が欠かせない。
そこで注目されているのが、AIをはじめとする最新技術の活用だ。たとえば、衛星画像解析とディープラーニングを組み合わせることで、現地調査が困難な場所でも炭素貯蔵量をより高精度に把握できるようになりつつある。それにより観測地点ごとに保全や回復の優先順位をつけやすくなり、より効果的で効率的な対策につながる。
さらに、危機管理の面でもテクノロジーの貢献は大きい。ブルーカーボン生態系は単位面積あたりの炭素蓄積量が高いため、植生が壊れると、これまで海や泥の中にため込まれていた炭素が一気に空気中に出てしまう。その結果、二酸化炭素として大気に戻り、地球温暖化を加速させるリスクがある。
だからこそ、最新技術と科学的知見を活用して、海洋の炭素貯蔵能力を正確に把握し、守り、活かすことで、ブルーカーボンの潜在力を“見える化”し、最大限に引き出せるようになる。
企業の新たな投資先“海の炭素”が動かす未来
世界各地で、ブルーカーボンを軸にした海の保全の取り組みが進んでいる。
国連開発計画(UNDP)は2025年、日本政府の支援を受けて「ASEANブルーカーボン・ファイナンス・プロジェクト」をスタートさせた。ASEAN地域は、世界の海草藻場の約3分の1、熱帯泥炭地の約40%を有するブルーカーボンでも重要な地域だ(※3)。
プロジェクトでは、持続可能な保全・回復に向けた体制を通じて、海を守る活動を一時的な環境保護で終わらせず、持続的な経済の循環に組み込むための仕組みを構築している。
この挑戦の中心にあるのが「ブルーカーボンクレジット(BCC)」だ。
カーボンクレジットとは、温室効果ガスの排出削減量(排出権)を取引する仕組み。日本でも、環境省などが主導する「Jブルーカーボン」プロジェクトを通じて、吸収量の見える化やクレジット化が進められている。
BCCは、NGOや自治体、企業などが、藻場やマングローブの再生・保全やプロジェクトに資金を提供し、プロジェクト開発者がこれを実施する。第三者認証機関が、取り組みによって実際に固定された炭素量を定量的に算出し、1トンの二酸化炭素削減または吸収量を1クレジットとして発行。
企業や自治体は、このクレジットを購入することで、自らの二酸化炭素排出量を埋め合わせる(オフセットする)ことができる仕組みだ。
しかし、BCCの市場はまだ十分に活発とはいえないのが現状だ。2014年から2025年までに約696万BCCが発行され、そのうち取引されたのは365万BCC(※4)。つまり、発行されたクレジットの半分以上はまだ市場で売買されておらず、実際に使用されたのは全体の約半分にとどまっている。
ブルーカーボンの潜在力を引き出すには、企業による積極的な参画と資金投入が欠かせない。2050年のカーボンニュートラル達成に向けて、各企業により厳しい削減目標が求められる中、クレジット購入は排出量のオフセットにとどまらず、自然資本への投資という意味を持つ。
クレジット市場の活性化とプロジェクトの拡大が進めば、ブルーカーボンの持つ可能性は、理想から現実に変わる。海の森を守る一歩は、今まさに踏み出されているのだ。
私たちの手の中にあるブルーカーボンの未来

そうは言いながらも、私たちには悠長な時間が残されているわけではない。ブルーカーボンも陸の緑と同じように、気候変動の影響を受け、急速に消滅しつつある。
記録的な高温を記録した2023年、森林や土壌などの陸上生態系が一時的に機能しなくなり、二酸化炭素の吸収能力が著しく低下したことが報告されている(※5)。2025年も、これまでにない異常な高温が観測され、陸上だけでなく海洋生態系にも未知の影響が出ることが懸念されている。もはや、自然の力だけに頼る時代は終わりつつあるのだ。
さらに、海から発せられる“アラート”も無視できない。海水温の上昇、海水の酸性化、生態系の崩壊、それによる漁獲量の減少や漁業コミュニティへの影響など、自然環境が相互に作用し合い支え合う関係だからこそ、こうした変化に目を向け、私たちができることから行動を起こすことが必要だ。
それでも、希望はまだ失われていない。私たち人間は、より良い地球をつくるリジェネラティブな存在だ。気候変動は単なる自然現象ではなく、人間の活動と気候変動が複雑に絡み合った結果。だからこそ、私たちの手のなかには、未来を変える選択がまだ残されている。
参考文献
※1 Grace, J., Mitchard, E., & Gloor, E. (2014).Perturbations in the carbon budget of the tropics.Global Change Biology, 20(10), 3238–3255.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/gcb.12600※2Duarte, C. M., Middelburg, J. J., & Caraco, N.(2005)「Major role of marine vegetation on the oceanic carbon cycle」 Biogeosciences 2:1-8.
https://bg.copernicus.org/articles/2/1/2005/※3 ASEAN, Japan, and UNDP Launch Blue Carbon and Finance Profiling Project To Accelerate Sustainable Blue Economy In Southeast Asia|UNDP
https://www.undp.org/indonesia/press-releases/asean-japan-and-undp-launch-blue-carbon-and-finance-profiling-project-accelerate-sustainable-blue-economy-southeast-asia?utm_source=chatgpt.com※4 Farahmand, S., Hilmi, N., & Duarte, C. M.(2025)『The rise and flows of blue carbon credits advance global climate and biodiversity goals』 npj Ocean Sustainability 4:39.
https://www.nature.com/articles/s44183-025-00141-6※5 Trees and land absorbed almost no CO2 last year. Is nature’s carbon sink failing?|The Guardian
https://www.theguardian.com/environment/2024/oct/14/nature-carbon-sink-collapse-global-heating-models-emissions-targets-evidence-aoe
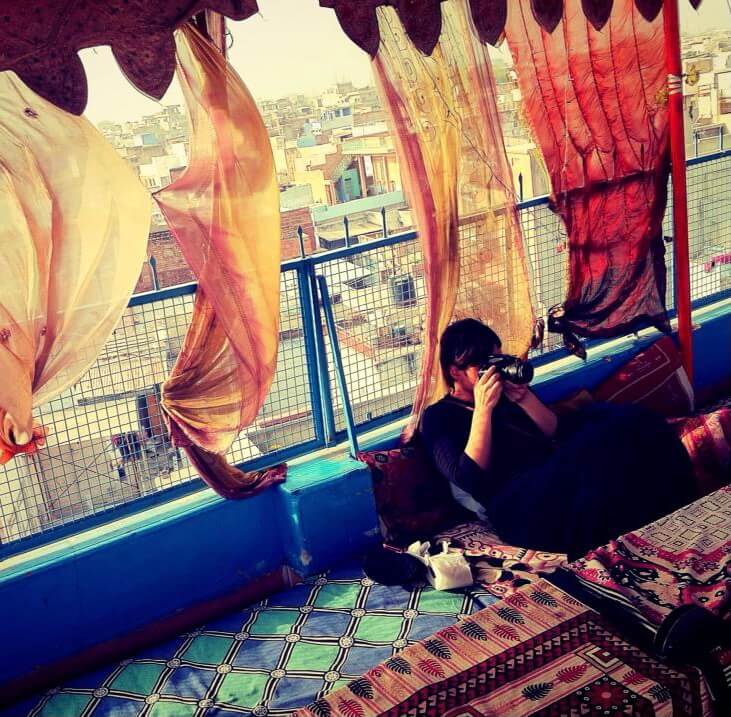
Ayaka Toba
編集者・ライター
新聞記者、雑誌編集者を経て、フリーの編集者・ライターとして活動。北欧の持続可能性を学ぶため、デンマークのフォルケホイスコーレに留学し、タイでPermaculture Design Certificateを取得。サステナブルな生き方や気候変動に関するトピックスに強い関心がある。





